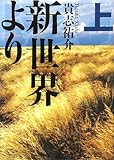- 有頂天家族/森見 登美彦

- ¥1,575
- Amazon.co.jp
古来より、日本には3種類の存在がいた――
弱っちいけど頭の働く人間、傲慢な天狗、阿呆の血を持つのんき狸。
おとぼけ狸4兄弟と、酒乱天狗の赤玉先生、半天狗美女の弁天の織り成す群像劇。
死ぬほど面白かった。
今年ナンバーワン。
たぶん。絶対。
全てが素晴らしいので文句のひとつもございません。
”面白ければ良いのだ”という、気持ちのよい明るさが一貫したテーマと描かれてるのがいい。
明るいメッセージが一貫しているっていうのは貴重。
だけど、切なさ、やるせなさも散りばめられ、魅力的なキャラクターが所狭しと飛び回る。
狸御殿、平成たぬき合戦ぽんぽこなど、狸モノは数あれど、
文句なしにその最高峰。
要はレトロなジャパニーズドラマをファンタジックに描いた物語。
サザエさんとか、ドラえもんみたいな。
今まで、森見さんと万城目さんと見分けがつかなかったけど(笑)、
これ読んで森見さん一歩リード。
描きたいものがハッキリしているから。
物語のまったり感もいいんだけど、まずは何をおいてもキャラクター。
キャラクターがとにかく魅力的。
主役の狸が可愛すぎて死ぬ。
本当は切れ者なのに、享楽的で、阿呆で、家族や隣人をすごく愛している。
きちんと主人公している、いい存在。ヒロインに食われてないし。
”夜は短し~”は、ヒロインがあまりに可愛すぎて、主人公食われてたからね。
でも今回もヒロインはすこぶるキュートです!
森見さんは可愛い女の子を書かせたら天下一品。
”夜は短し~”の純粋系天然娘とはまた違って、
わがまま放題、ファム・ファタールな大人少女がなんともいえない存在感。
しっとりとした大人美女なんだけども、奔放で自分に素直な、こどもっぽい面も持っていて、愛らしい。
だけど、それだけじゃなくって、チリッとしたスパイスも効いている。
ぎらついた悪意はないものの、お気に入りの狸を食べてしまうような、
悪ではないけど、なんだかわからない切なさを持っているのが、一筋縄でいかなくていい。
この存在感は 永遠のジャパニーズ悪女、不二子ちゃんに匹敵すると勝手に思ってる。
赤玉先生もまた最高。
ていうか、このキャラがいるからこそ、出色の物語だと思う。
威張り散らすし、お風呂には入らないし、言うこと聞かないだめだめ天狗なんだけど、
こういう、どうしようもないひとを排除するんじゃなく、ただイエスマンとして受け入れるのでもなく、
絶妙な距離感で、一員として受け入れてるのがとにかくいい。
最近の話って、若人の仲良しググループだけ、あとは敵、っての多いからね。
たとえば、うる星やつらのチェリーとか、どらえもんのジャイアンとか、
ながーく続き、誰からも愛される王道物語には、
はた迷惑な人なんだけど、何故か憎めない人物、ってのが出てくる。
こういうキャラを作れるのは、よっぽど力量がないと無理らしく、相当出来のいい物語じゃないとみかけない存在。
かつ、古き良き日本な存在。
役に立たない、いるだけで問題を起こす人なんだけど、周りがそれを同等の存在としてきちんと受け入れている。
口うるさい近所のじいちゃんとか、ガキ大将とか、まさにそんな存在。
だけど、最近の物語じゃまず見かけない存在。
森見さんも現代っこだから、身近にそういう存在がいて、こういうキャラクターが書けたのか、
それとも、レトロ趣味な人だから、好きな昔の本に元ネタがあったのかわからないけど、
こういうキャラクターまで書ける人なんだ、っていうのはもの凄く貴重な存在。
他のキャラもまたかわゆし。
長男はテンパリ生真面目男なんだけども、その几帳面さ、真面目さもきちんと受け入れられている。
次男は蛙。
蛙に変化したら戻れなくなった、というネタとしてかなり笑える存在なんだけども、
その理由を含めてなかなか深くていい存在。
井戸の中から出てこない蛙だから、みんながグチやらなにやら零しにくるってのもいい感じ。
近所の無職のおじさんなんだけど、なんだか接しやすくて、
みんな積極的に口には出さないけど、好いているってとこだろか。
こうやってみると、ほら。
古き良きジャパニーズドラマを、森見ワールドで表現したかったのがハッキリと分かる。
ご近所、ご家族で、いがみ合いながらも仲良く支えあうホームドラマ。
ひたすら気弱な弟も可愛いし、お母さんは偉大だし。
一点気に入らないとすれば、母親が息子に慕われすぎて、マザコンか!?
と勘ぐってしまう点だけども、
まぁ、これは裏読みしすぎというか、若干底意地の悪い見方なので問題なっすぃんぐ
物語も面白い。
牧歌的で、のんびり狸たんや、お役に立たない天狗さん、わがまま人間が、縦横無尽に駆け抜ける。
ファンシーなんだけども、のんびりまったりしていて素敵。
だけども、それだけでなく、牧歌的→切ない話に展開していくのがスゴ技。
”父親は鍋になった”なんて、ネタとして思わず笑ってしまったんだけど、
読み勧めていくうちに、これが結構へヴィかつ、重要な要素に。
金閣、銀閣っていう悪ガキも、はじめはろくでもない、可愛らしい悪戯ばかり仕かけていたのに、
段々洒落にならない展開になっていくのも、
ただ牧歌的なだけでなく、物語の深みを与える存在として、すごくいい展開だと思う。
で、こういう展開でありがちな、シリアスに持っていこうとしてやりすぎて失敗、違和感てのがないのがすごい。
当初ののんびりとした雰囲気をぶち壊すことなく、上手に使ってる。
でも結局、狸鍋は出るにしろ、”悪いやつは殺して成敗”な激しい展開は出てこず、
安心して読める。
てか、最近流行の話を、本でも漫画でもざっとみると、
こういう、ちょっと駄目な人が主人公で感情移入しやすく、
全体的にハッピーで朗らかな物語、ってのが好まれてると思う。
昨日テレビでやってたからエヴァとかたとえに出しちゃうけど、あれが社会現象になってしまった時代って、
相当病んでたんだと思う(笑)
今はこういう、だめなんだけども、それが受け入れられて、ちょっと不思議で穏やかな物語が好まれる時代なんだろうな。
どうしようもない不況が、一応、表面的にしろ一段落したのもあるだろうし、
徹底的に不安定で先行きの読めない時代だからこそ、牧歌的で穏やかな物語が好まれる、
ってのもあるだろし。
最後に、好みの別れそうな要素が、今回は上手に処理してあるのもポイント加算です。
森見さんの特徴であり、かつ、好き嫌いも生んでいた、レトロで硬派な文体ね。
この本ではなんともいえない、絶妙の味をかもし出している重要な要素。
文学的な言い回しだけど、センテンス切りにものすごく気を遣っていて、テンポ良く読める。
背伸び感は払拭され、完全に自分のものになっていて、
「ぷうぷう」
「ふうふう」
「ぎうぎう」
「かわゆい」
など、頻繁に差し挟まれる独特のオトマノペやら、死語な言い回しやらが、ものすごく可愛い。
こういう、軽くて可愛らしい言い回しが意図的に、頻繁に差し挟まれるからこそ、
固い文体なのに、読みやすい、軽妙さをかもし出している。
嬉しいことに、有頂天家族は続きが出るそうな。
気の早い話ですが、是非これをライフワークとして何冊も書き連ねていただきたい所存。