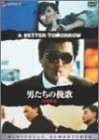- となり町戦争 (集英社文庫)/三崎 亜記

- ¥500
- Amazon.co.jp
となり町戦争 三崎亜記第1作目 小説すばる新人賞受賞作品
平凡な男の元へ、ある日一通の通知が届いた。
それはとなり町との戦争を告げ、協力を仰ぐもの。
目に見える争いも、理由も判然としないまま、”戦争”という事実だけが日常を侵食していく。
これ大好き。
タイトルの絶妙さがすべてを表していると思う。
そのへんに転がっている平凡な言葉が組み合わさって、非凡で奇妙な世界が現れる。
これこそ三崎節ではないかと。
理由も理屈も分からないまま、奇妙な世界に突如放り込まれる主人公の置いてけぼり感、
兵隊も武器も見えない、誰も騒がないのに、着実に進む”戦争”状態。
異常な状況をさらりと、当たり前のように描く、ひょうひょうとした筆致。
大好きだ。
三崎作品は既刊全部読んでるけど、やっぱこれが一番好きだなぁ。
気になるところがないでもない。
主にキャラクターで。
発想や言動の怖い若い男の人物像とか。
このキャラで、戦争の異様さに、ある程度の形が与えられてるんだけど、
物語上必要な存在、ていう記号的存在以上でも以下でもないのが、もにょもにょする。
喋り方のムカつき度、それによる、異様さの強調は理解できるんだけど、
きっと、三崎さん、想像だけで書いたんだろうな、現代っ子、だめ若者イメージ先行で
作りあげたんじゃないだろうか、という印象が付きまとってしまっていかん。
あと、香西さん。
大好きだし、このひとの存在が、この話が絶妙に成立する要因だとも分かっている。
だけども、セックス義務とか、最後は政略結婚を突然させられてしまうところとか、
なんか違和感。
サービス要因&、政略結婚のレトロさが唐突過ぎて。
それに、木のエピソードのウェットさも、このクール&乾燥した雰囲気に馴染まないように思えた。
でもそんくらいかな。
なんで戦争するのか、説明されて無いから意味不明とか、戦争してないじゃんとか、
そういうのは感じなかった。
むしろ、そんな野暮なことをしない、正体不明の空気がいいんじゃないか。
こっから褒めまくるぞ。
「となり町」と戦争をする。
この奇妙なワンアイディアがたまらなく好きだ。
言ってみれば、80年代学園漫画の、学園内闘争のポップさに近いものをイメージさせつつ、
その中身は奇妙なリアリティを伴った不気味さが溢れているところがいい。
狭い範囲の日常に、非日常の最たる”戦争”を持ち込むことによって、鮮明に浮かび上がる非日常感。
なのに、その肝心の”戦争”が全く目に見えない不安感。
更に、主人公には意味不明なのに、周囲は当然のものとして納得しているようで、
知らないのは自分だけ、という、疎外感。
物語の仕組みとしても面白いし、
現実の様々なことの暗喩なのでは?と当てはめて考えていくことも面白い。
たとえば、良く言われるように、
現代日本人にとって、最もリアルな戦争を描き出した
ということ。テレビやネットの先の戦争、闘争、紛争。
最も最近で言えばチベット紛争。
我がことのように憤慨するフリーチベットの活動者、それを覚めた目で見る無関心な人たち。
の、関係性とかね。
もしくは、日常嗜好品のチョコ、その生産をしている人々はチョコを食べたことが無く、
劣悪な環境で搾取され続けているけど、それを知っている日本人は極僅か、ということ。
または、後期高齢者制度。
施行されてから知った人が大多数で騒いでいるけども、そのうち忘れられるだろうこと。
防衛庁が防衛省にいつのまにか格上げされてたみたいにね。
ひとりひとりの生活に深く関わることなのに、
感心を持たない、知らない間に物事が進んでいる、
現実にいくらでもある、自分だけが知らないで、物事が進んでいること、複雑化していること。
そんな様々のことの暗喩に取れるのが、この物語の普遍性と魅力だと思う。
それから、キャラクター。
特に香西さん。
上でちょっぴり批判したけども、やっぱり、香西さんあってのとなり町戦争かと。
三崎作品で(今のとこ)最も成功したキャラクターだと思うなぁ。
非常に事務的で物事を淡々とこなしつつ、
常に丁寧で、言葉にしない先の感情を色々と想像させるところが好きだ。
本当はどう思っているんだろう?何を考えているんだろう?主人公にどんな感情を抱いているんだろう?
とにかく、描かれていないところに対して想像力が膨らむキャラ。
やっている仕事と、淡々とした中に読み取ってしまう、もしくは期待してしまう女らしさ。
三崎キャラは妙に機械的というか、感情のリアルさが感じられないことが多いんだけど、
香西さんに関しては、それが逆作用して、とても魅力的。
主人公との淡い恋模様だって、れっきとした恋なのか、主人公の思い込みなのか、
あと一歩で判然としないし。
香西さんがいなかったら、この作品の好き度も確実に下がったな(笑)
あともうひとり。
上司のひと。
彼の普通のおっちゃん→凄腕戦争やの豹変は、普通に怖かった。
ストーリーの静かな起伏も好き。
書面でのみ変化していく情勢と、
いぶかしみつつも行う、最後の突入劇。
「本当に危ないのかな?しゃれじゃないのかな?」と、直前までリアリティを持てないのに、
そしてやっぱり、銃弾の雨だの、戦車だの、なんて分かりやすいものは出ないのに、
もの凄くハラハラして恐ろしい、緊張感。
そこが一番好きだ。
そして何より、淡々とした筆致が好き。
これだけ妙な物語を、リアリティを持って、普通に描けるってのは特異な才能だと思う。
戦争面を強調することも無く、日常面をフォーカスしすぎてぐだぐだになることもなく。
星新一がまだ生きていたころ、彼が監修するショート・ショートコンテストってのがあった。
その中のひとつに、夜中に男がラーメンを食べたいんだけど、即席めんがどうしても見つからない。
その奮闘を淡々と描いた作品があった。
こうあらすじを書いても何気ないし、ドラマ性も感じられないのに、
その作品は奇妙な存在感を放っていた。
それを思い出す。
もしかして、あれを書いたのは三崎さんじゃないかと今でも思う。
本が手元にないから確かめられないけど、日常の中の非日常感を、筆致だけで描き出す能力が
とてもよく似ていると思う。
確かめられたらいいのにな。


追記。
自分の考えだけがーっと書きたいから、
普段は他のレビュとか読まない。
書いたあとで初めて読む。
すると、これ評価低いのね…
好きだから構わないんだけどさ。
でも気になるので考えてみたら、
自分は三崎さんを「純粋なSF者、しかもハード。なのに、一般に馴染みやすい文が書けちゃう異能力者」
って思ってるんだな。
反対派の多くは、宮部みゆきさんとか、貴志祐介とか、全部説明してくれるミステリ、エンタ小説と較べるから
フラストレーションが溜まるんだと思う。
なんも説明してくれないし。
SFなのに、SF色を感じさせず一般受けするなんて、なんて素晴らしいんだ!
とか思ってたけど、逆に、それが悪作用するってこともあるのね。
これが、戦争の理由だの、生き生きとした、汗や涙溢れる人物造詣だの入っちゃったら、全く別物になっちゃうのになぁ。