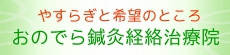「レナードの朝」という映画をご覧になったことがあるだろうか。
自分は「主人公が眠ったままの病気からよみがえった話」程度しか覚えていなかったが、今回この病気を取り上げようと思って調べてみたら、あの主人公の病気がこれだったようだ。
原作はアメリカのマウントカーメル病院に入院している20名の嗜眠性脳炎患者に、パーキンソン病向けの新藥を使った記録を綴ったものだが、映画ではその20名の中のレナード(ロバートデ・ニーロ)に焦点を当てた事実に基づくフィクションとなっている。
嗜眠性脳炎とは第一次大戦(1914年~1918年)終末ごろから10年ほど世界的に流行し、500万人が罹患し、50万人が死亡した病気で、エコノモ脳炎とも呼ばれる。
1926年頃に急速に収束し、現在は幻の病気とも言われるが、時折散発し現在でも同病名診断を受けている人たちはいる。
つまり、「レナードの朝」は幸いにも生き残った患者の後遺症との闘いのはなしなのだ。
嗜眠性脳炎は感染症であり、インフルエンザとの深い関連が指摘されながらもその実態は解明されておらず、急速に収束した経緯もまた不明のままである。
病原菌も明らかになっておらず、一説にはアスピリンの大量投与による副作用ではないかとも指摘されているが定かではない。
具体的な病症は、ウィーンのエコノモ医師の報告によると、
「この睡眠病の患者は昼も夜も眠り続ける。目を覚まさせることは可能で、質問にも答えるし、命令にも従うが、まるで夢遊病者のようだ。放っておくとすぐに朦朧とした状態に戻る。数週間で死亡する患者もいれば、何ヶ月も深い眠りの状態が続き、中には昏睡状態に陥る患者もいた。命をとりとめても完全に回復することはなく、じっと動かずに座っているだけ。周囲のことは分かっても、凍りついたように動くことも返事をすることもできなかった。彼らは無気力で、鈍感で、まるで死火山のようだ」
とされている。
現在、同病名の診断を受けた方の闘病記録のサイトを覗かせていただくと、Drからは以下のように説明されるようだ。
○興奮や強迫症などの精神障害
○不眠あるいは傾眠傾向などの睡眠障害
○不随運動やパーキンソニズムなどを起こす錐体外路障害
○開眼しているけれども反応がない意識障害
以上のような症状を起こす脳炎と。
その中でも抗NMDAーR抗体が有るか無いかで症状が変わるとのこと。
陽性であれば不随意運動、興奮、痙攣、不眠など、いわゆる活動性の高い症状があらわれる。
陰性であればパーキンソニズム、傾眠傾向が強くなる。
欧米では小児を中心に報告されている。
小児の発症はあまり予後が良くないが、大人の発症では殆ど後遺症は残らないとかで、この闘病記録を書かれているご家族の方もおっしゃっているが、当時とはだいぶ重症度が違うようだ。
さて、「レナードの朝」のストーリーだが・・・。
レナード少年はどこにでもいる普通の少年だったが、あるときから右手が震えるようになる。
そしてその震えは徐々に進行していき、テストの記述もできなくなり、友達と遊ぶこともできなくなっていく。
そんな場面から映画は始まる。
舞台は変わり、1969年。
マルコム医師はベインブリッジ病院の求人に応募したが、ベインブリッジ病院は精神科だった。
それまで研究畑を歩み、人との接触が苦手なマルコム医師は断ろうとした。
しかし、病院側の強い求めに応じて働くことにした。
病院側は適任者というより医者の資格を持った人間が欲しかったのだ。
怒号と絶叫と意味不明の言動の渦巻きに当初は戸惑うマルコム医師だったが、徐々に研究者らしい観察眼と人間らしい優しさと情熱で患者たちを診るようになる。
そんなある日、生活反応の全く見られない患者が、マルコム医師が落としたメガネを瞬間的にキャッチすることを発見した。
同僚の医師たちは単なる反射行動として相手にしなかったが、マルコム医師は同様の患者15名の観察を続けるうちに、過去に嗜眠性脳炎にかかっていたことや、音楽やトランプなど、それぞれの患者が固有の刺激に対して反応を示すことを発見し、一見生活反応の見られない患者たちが、内部の奥底に正常な精神活動を有すると確信するのである。
ちょうどその頃パーキンソン氏病の治療藥としてL-ドーパが効果を上げていた時期で、それを知ったマルコム医師は
「嗜眠性脳炎の患者が眠ったように生活反応を示さないのは、痙攣が極度に進行した結果ではないか。もしそうならば、パーキンソン氏病の痙攣を抑えられるL-ドーパは嗜眠性脳炎の患者にも有効かもしれない」
と考え、病院側を説得し、嗜眠性脳炎の患者レナード・ロウにL-ドーパを投与することになったのである。
投与開始して数日後、脇で寝ていたはずのレナードが食堂のテーブルで自分の名前を書いている奇跡の姿をマルコム医師は目にすることになる。
こうしてレナードは30年の眠りから目覚め、自分の時を取り戻すのである。
レナードは、変わった街並みやファッション、飛行機など見るものすべてが新鮮に映る。
自然を感じ、恋もして生きている喜びを満喫する。
そして高額な薬であるL-ドーパは、多くの支援者のおかげで15名全員に投与され、それぞれが自分の時間を取り戻す。
その姿はまさに感動的である。
ちなみに、「目覚めた」彼らが言うのには「眠っていた」期間のことは覚えていないとか、夢を見ていたと表現する。
しかし、彼らのその喜びは長くは続かない。
徐々にドーパミンは効かなくなり、再び痙攣が始まるのであった。
レナードはこの先に何が待っているかを知っている。
同じ病院の入院中の父親を見舞う美しい女性に恋をしたレナードは、彼女との会話を楽しみにしていたが、進行していく症状に「もう会わない」と告げる。
そして、レナードは再び自分だけの世界に入っていく・・・。
再び動けなくなっていく道を歩む彼らの苦悩はいかばかりであっただろうか。
「人間らしさ」の定義の一つには、「コミュニケーションが取れること」ということがあるかもしれない。
しかし、改めてこの映画を見てみると、コミュニケーションが取れ無くなっても一度つながった絆は断ち切れることはないということも教わった気がする。
マルコム医師は以前にレナードから言われた言葉を思い出し、それに促され、苦手だった恋に踏み出す。
自分だけの世界に入ってしまったレナードの元を訪れる女性の姿もあった。
また、これまで全く生活反応を示さない彼らをまるで「もの」のように扱っていた職員たちも、それ以降また彼らが生活反応を示さなくなっても、人間的な対応をやめることはなかった。
この病気の重篤性、患者本人の苦悩、家族の思い、病気に挑む病院スタッフの情熱、「人間らしさ」とは何か、様々な思いがめぐる映画である。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
刺さない鍼で痛みなく、眠っちゃうほど気持ちイイ
盛岡・若園町の おのでら鍼灸経絡治療院
URL: http://www.onodera-shinkyu.com/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆