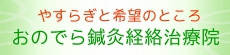AKBの秋元才加が故郷のフィリピンを訪ねた際に、バロット(フィリピン名、ベトナム名ではホビロン)をおいしそうに食べている映像を見た。
「あーやっぱり普通に食べているんだ」
と思い、ちょっとだけ食べてみたい気持ちが生まれてきた。
ホビロンという名でその存在を知ってはいた。
それは孵化しかけたアヒルの卵のゆでたものである。
孵化しかけているから、当然ヒナの姿もその中には見える。
その話を聞いて、嫌いなものは何もない自分でも「うわっ強烈!ムリっ!」っと思ったものだ。
だが、フィリピンやベトナムでは生活の中に密着し、当たり前に食されているという。
結局自分も食わず嫌いなだけなのだ。
欧米人の目には、そんなホビロンは残酷には映らないのだろうか。
欧米人が捕鯨やイルカ漁に対し、非常にセンシティブになっている。
それはクジラやイルカが非常に高い知能を持っており、特にイルカは人間と友人とも言える関係にあるからだという。
知能が高いから残酷、低いから残酷ではない。
そういった考えは感覚的に分からなくもないが、やはりいびつであろう。
オーストラリアではカンガルーが食されているようだが、あの愛くるしさを見ると「あーあれを食するのかあ」と思ってしまう。
しかし、アジア人は驚くことがあっても抗議することなど決してないだろう。
それは、人間には豊富な食文化があることを知っているからだ。
いわゆるゲテモノ食いと呼ばれる昆虫類から始まり、犬の焼肉や、サルの脳ミソ、動物の腸内にあるフンすらも料理に使う文化もある。
そして、人肉を食べる対象とする部族もかつては存在していたのである。
さすがに人肉は人権だけでなく、健康上の問題もあり禁止もされ、すたれていったが、これほどまでに多種多様な食文化を持つのが人間なのである。
そんな中で、食していいもの、いけないものを、知能が高い、低いで線引きするのならばその基準はどこにあるのか。
牛も子供を産めば愛おしむように舐め、常に寄り添う。
また、屠殺場に送られるときにはそれと察知し、激しく抵抗するという。
そこに知性は感じられないのか。
自分は、その民族が培ってきた食文化をどのようにするのかは、その民族が決めるべきものと思う。
例えばケネディ駐日大使がイルカ漁に不快感を覚えたとしても、なぜアメリカ人はイルカ漁をしないのか、その理由や文化を述べることはしても、批判するのは間違いだと思う。
ましてやシー・シェパードによる実力行使の妨害活動などもっての他である。
いつも思うのであるが、イルカ漁や捕鯨を批判する人たちは、どこかしらネット上ですぐに他人を口汚く批判するような人たちに似ている。
その事象に対して深く解釈しようという気がなく、薄っぺらな正義感をひけらかし、自分の主張だけが絶対的に正しいと勘違いしているような人たちである。
よく引き合いに出される話であるが、日本人がクジラをとるとまったく捨てるところなく、そのすべてを利用するが、かつてアメリカではクジラの油をとるためだけに捕鯨し、それ以外のものはすべて捨てていたという。
人は他の命を取り込むことでしか生きてはいけない。
植物もまたその命のひとつである。
そうであるならば、いただく命に敬意を払い、使い切る文化の方がよほどその命を大切にしていると言えるのではないだろうか。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
刺さない鍼で痛みなく、眠っちゃうほど気持ちイイ
盛岡・若園町の おのでら鍼灸経絡治療院
URL: http://www.onodera-shinkyu.com/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆