こんにちは。和久田ミカです。
今日は、思考力についてです。
たまにはまじめに 話をしようかなと思います。
山田ズーニーさんの本を初めて読んだとき、これって コーチングじゃん!と思いました。
たとえば、こちら。
 |
伝わる・揺さぶる!文章を書く (PHP新書)
Amazon |
内容は「どうしたら文章が機能するのか」「結果が出せるのか」ということについて、さまざまな観点から書いてあります。
 |
あなたの話はなぜ「通じない」のか (ちくま文庫)
Amazon |
読んだとき、
そうだよねー、
コーチングって別に学ばなくても、センスがある人はできちゃうんだよねー、ちくしょー
と思いました。ちょっとすねた感じで。
コーチングって、できない人は 学んでもいまいち身につかない。
向き不向きがある職業だと感じます。
私はあんまり勘がよくないので、すごくいっぱい勉強してコーチングを身に着けました。
そして、10年たった今も、勉強してます。
この本も、すごくいい本で、コーチングと共通している点がたくさんあります。
あえてひとつだけ挙げると、「話を聞くことは、クライアントと同じ絵を見ること」。
話を聞く作業って、単に情報を聞くのではありません(というか、あまり情報は聞いてない)
相手が思い描いていることを 共通理解すること、が最初にやること。
それを「同じ絵を見る」という表現で学びました。
ズーニーさんの本の中でも、
![]() 論理的であること=共通の事柄の認識が一致すること
論理的であること=共通の事柄の認識が一致すること
![]() 共感とは=相手の感情に対して同調し、お互いの理解が深まること
共感とは=相手の感情に対して同調し、お互いの理解が深まること
のような感じで、書いてあります。
相手との間にかけ橋を作っていくからこそ、説得力のある文章が書けるのだなあと 思いました。
話を聞く、ということもそう。
単に聞くのではなく、相手との間に かけ橋を作ることが大事。
じゃないと、相手の言葉を誤解して受け取っちゃうから。
たとえば、クライアントが
「自分軸がある人になりたいんです」
といったときに、勝手に「しっかりした人」のように解釈して話を始めたら、どんどん話がずれていきます。
最初に、
「あなたにとって『自分軸がある人ってどんな人?』」
と聞いて 共通認識をしてすり合わせること。
「自分軸って、どんな絵なの?」
と聞きながら、クライアントの心の中の絵をいっしょに見ていくんです。
だから、逆からいうと
話が通じない人は、相手の言葉を勝手に解釈している人とも言えますね。
人の話を、自分のフィルターで勝手に変換していることに 気づかない人と話すと、ほんと疲れますもん。
では、子どもの思考力を高めるためには 何ができるでしょうか?
上に書いたことは、子どもに実践するのは ちょっと高度ですよね。
私がお勧めしたいのは、ふだんから さまざまなことに、問いを持ち続けて行くことかなーと思います。
子どもも。大人も。
質問をする力や 質問に答える力は、すぐには つきません。
私も コーチングを学び、自分自身がセッション受け続けてきて、質問力がついてきました。
娘に対しては、ふだんの会話から 娘の考えを引き出す質問をしようと努めています。
娘が小さいときだったら、
「そのとき どう思ったの?」
と思ったことを言語化させたり、
「他にはどんな方法があるかな?」
と選択肢を多く持たせたり、
「それを選ぶことで、よいことと悪いことがあるね。何だと思う?」
とメリット・デメリットを考えさせたり。
今はもう、中学生になったので
「その目的(や意図)は何かな」
「もう少し詳しく教えて」(説明をさせ、私が整理していく)
「その2つの(概念や価値観の)ちがいは、何?」
「一言でいうと、どういうこと?」
みたいな抽象的な質問に代わってきています。
テストの成績を見せに来たら、
「へー。で、今回はどう思ったの?」
「今後の課題は?」
と聞きます。
(ただし、見せに来ないときは、成績や通知表も見ません)
テスト前だったら、
「目標は?」
「(前回の結果を踏まえて)今回はどんな計画を立てているの?」
「いつから(テスト勉強を)始めるの?」
「(計画を進める上で)障害になりそうなことは?」
「何か手伝ってほしいことある?」
そんな感じ。
必要があれば、「ママの意見を言ってもいい?」と助言します。
でも、お子さんによっては何を聞いても
「わか~んな~い」
って 言う場合もあるかもね。
わからない、というよりは、言葉にできない、って いう感じかな。
そんなときは、
・言いたそうなことを言語化して代弁する
・選択肢を示して選ばせる
・親としての考えや思いを話す
など、いろんな方法で 種をまくことができますね。
言葉を、子どもの中に入れていく作業です。
また、子どもがとんちんかんなことをいっても、とりあえず
「へー」 「なるほど!」 「そうなんだね~」
と聞くことも大事かな。
否定されたら、しゃべらなくなるから。
答えが正しいか、よい考えかどうか、よりも
「”自分で考えられた”ということ」
を ほめていくと、だんだんと 話せるようになるの。
今、学校では、話したり、聞いたり、話し合ったりすることが重視されています。
答えがない質問に対して、自分の考えを書くような問題も多くなっています。
日本人って、わからないと思うと 何も書かない傾向があるそうです。
(逆に、アメリカ人などは とりあえず なんでもいいから回答する傾向があるそう)
まちがったらどうしよう、と思うと、とりあえず「わかんない」にしちゃえ、って思うみたい。
正しい、正しくない、にとらわれず、自分の考えを持つことは、会話で伸ばしていけるんじゃないかな。
大学受験の方法も変わっていくみたいだしねん。
あー、まとまらないけど、最後に一言。
ただし、
「大学に合格させるために、思考力をつける」
なんて 邪道だからねん。
コミュニケーションは「相手との間にかけ橋を作ること」。
親が先生になっちゃったら、家庭が息苦しくなる。
あくまでも根っこは
「あなたのこともっと知りたい」
という気もちだと思います。
んで、二次的に 思考力もついてくる、という感じかなー。
尻切れトンボだけど終わり(←なんだかんだで、論理的な文章を書くのは苦手)
募集中・募集予定の講座
![]() すまいるママ塾 vol.5 HSC(The Highly Sensitive Child)。「ひといちばい敏感な子」
すまいるママ塾 vol.5 HSC(The Highly Sensitive Child)。「ひといちばい敏感な子」
会場は、定員100名を超えて締め切りました。
ライブ配信か録画配信は、20日まで募集しています。
・・・・・
日本ではまだまだ知られていない「HSC」。
明橋大二先生をお招きして、お話をお聞きします。
私も対談をしますよ。
 |
ひといちばい敏感な子
Amazon |
![]() 無料メルマガ 「ママを楽にする魔法の言葉」
無料メルマガ 「ママを楽にする魔法の言葉」
↓タイプ別診断を加筆して、文庫本になりました
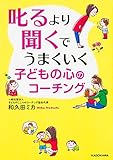 |
叱るより聞くでうまくいく 子どもの心のコーチング (中経の文庫)
648円 Amazon |
↓フルカラー・大きな文字でご覧になりたい方は、こちらがおすすめ!
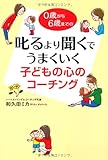 |
1,296円 Amazon |

