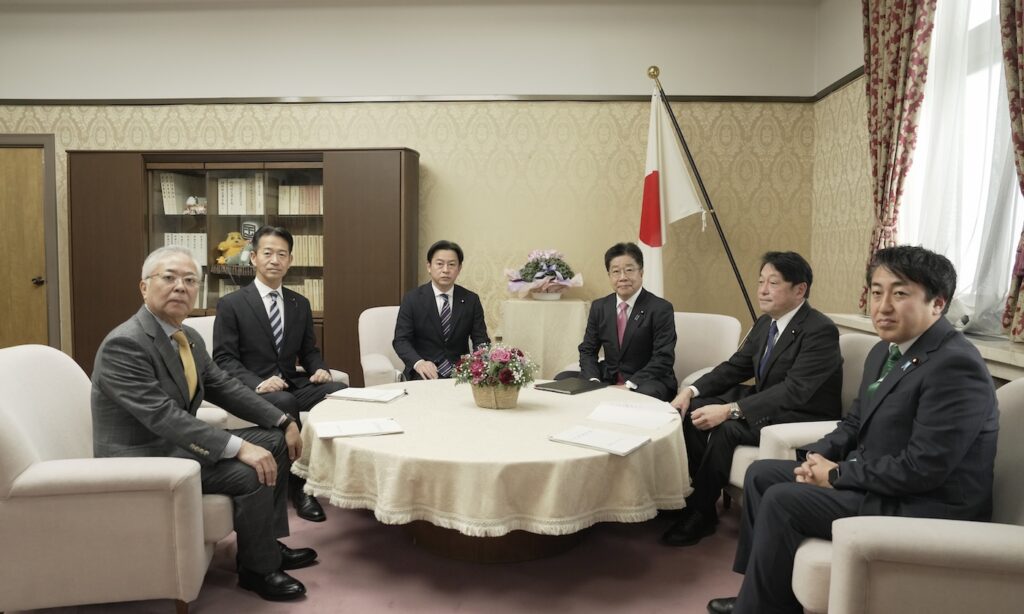(1)2025年が始まった。
さて、2025年はいわゆる団塊の世代が後期高齢者になる年。ずっと前から言われていたX年である。
介護保険制度がスタートして四半世紀になろうとしており、その総括はどうなっているのかは分からないが、これからも要介護者を現役世代が支えるという構造は変わらないし、世代間の軋轢は消えないだろうと思う。
おそらく介護問題は大なり小なり存在するし、万人が納得いくような制度にはならない。もし相当の納得が欲しいのであれば、自分で勉強して介護保険のできる範囲や自費で出来ることを学び、さらには自分がどう生きていきたいかという、ケアマネ的に言えばACP(アドバンスケアプラン)という自分自身を見つめ直すという事も面倒くさがらずにやる事なのだろうと思う。
介護や老後の生き方を学ぶ機会というのはあるようでなかなか無いし、実感としても薄いものだろうが、目に着いたら考えるべきことなのだろうと思う。
(2)財務省の執念
さて年末に出た記事であるが、財務省の執念というか①二割自己負担者の増加②ケアプランの有料化③軽度者の地域支援事業への移行は、何度潰してもゾンビのように復活する。
政治や行政にとって抵抗のほとんどない介護業界は、格好の餌食になる。
ケアマネの立場で言えば、ケアプランの有料化には反対である。しかし、もしケアプラン作成料が有料となった場合どうするか?私としては、まずはその案内をすると思う。そもそもケアマネなんて、要するに予定表を作って毎月来る人でしょ?という認識の人は一定数いるのは事実である。そして、ヘルパーに来てさえもらえばいいんだ、とかデイサービスに行きさえすりゃいいんだというサービスありきの人ならケアマネの存在意義は小さい。それであれば今のプランのままで継続している人は、ケアマネのテクニックが必要な時まで使わなくても良い。そして担当から外れるわけだから、相談がある時は地域包括に行ってくださいという方法が取れる。
ケアプラン有料化の反対意見として多いのは、「ケアマネジメントの利用が抑制されることで早期発見・対応が困難になる」「利用者や家族から不要なサービス利用などの要求がエスカレートする」「介護支援専門員の本来業務以外への要求が強まる」が多かった。(福祉新聞より)
さもありなんという事と、おそらく本格的に議論が必要なのは、高齢者や家族がケアマネに求める事が明確でないという事なのだろうと思う。
(3)必要とされる仕事と認められるまで
確かにケアマネがいることで、介護サービスの利用が促進され、高齢者の在宅生活の支援につながってきたというのは実績としてある。逆にケアマネがいなかったら、介護サービスの利用が促進されなかったかといえば、それは分からない。
つまりは身近なソーシャルワーカーとしての役割としての評価だが、これは費用対効果を含めて評価しづらい面でもある。
私自身、長い事この福祉業界にいる。多くの人を見送ってきた。その人たちが私と関わって良かったかどうかという事は分からない。しかしその経験が次の利用者への糧になっているし、変わりゆく情勢の中で一定の道筋を示せているのではないかと思っている。
それを有料化することによってやりにくくなるという事はあるだろう。しかしそれはケアマネが主張する事で、利用者が主張してくれるかは分からない。月数百円なら負担しても良いというかもしれないし、ケアマネを利用しなかったからといって相談窓口はどこかにあるわけだから、特別困らないという事にもなるかもしれない。
もしそれを逆手に取るのであれば、利用料の支払いを拒否するような利用者に対しては、利用料を払ってくれるまでサービスの利用を中止するという事が現実的に可能かどうかという事。
ケアマネは各事業所のサービスを統括するので、サービス全部が止まることになる。
でもそれはケアマネの対応が悪いとしてケアマネのせいにさせられるんだろうなという事も容易に予想できるけどね。
いずれにしても、この国の介護が役に立つ制度であり続けるために、我々は尽力するしかないのだ。
2029年4月からは居宅介護支援事業所の管理者は全員、主任ケアマネになる。私はその資格を取るつもりは無いので、そこで廃業する。それまでは全力で走るという事だ。
仕事としてだが、ケアマネとして必要じゃなくなる日まで、自分は頑張るつもりだ。