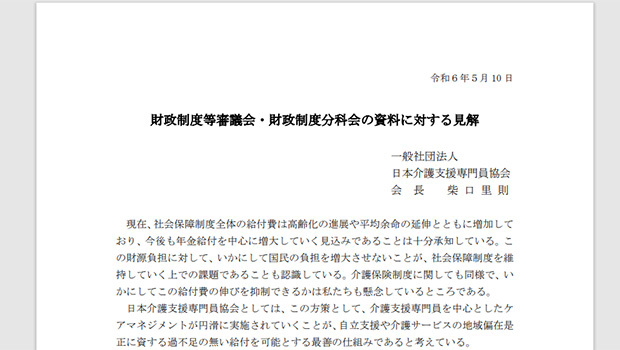(1)「セルフプラン」という方法
「介護を受けるのにケアマネって絶対に必要なの?」と聞かれれば答えは「NO」である。
介護サービスの受けるにはケアマネが役所に届け出をして行う「居宅介護支援」の他に利用者や家族が行う「自己作成」も認められているからだ。
その方が家族や利用者が必要書類を役所に提出したり、担当者会議を開催したりすることによって介護について学ぶこともできると前向きにとらえるこという見方もなくはない。
(2)セルフプランのやり方
しかしこれはケアマネが行う業務を家族が行うという事である。
大まかな流れで言えば
①利用者に対しアセスメントを行い
②ケアプラン原案を作成し
③サービス事業所を選定、確保して
④担当者会議を開き
⑤ケアプランを確定し
⑥利用票を本人、提供表をサービス事業所に交付し
⑦月々のモニタリングを行い
⑧実績が来たら国保連に請求し
という作業を毎月行う事になる。
これが出来るという事であれば、自己作成で行えばよいと思う。
(3)制度としての自己作成
ただ、制度設計・執行の立場から考えればセルフプランは疑問符が付くのだろう。
例えばヘルパーに来てほしいとする。内容的にも週2回で良いと思われるものを週5回とされたとする。仕事量が確保できるから事業所としては特に問題は無い。場合によっては仕事をしたことにして話し相手で時間が終わる事もあるだろう。家族にしてもそんなに費用もかからないからそれで構わない。
しかし、制度としては有資格者をそのような形で使うのは不適当という事になる。しかし適当か不適当化を判断し、家族に話しても、家族としてもそれなりに理由があるから改まる事もない。
そうすると昨今言われているヘルパー不足は更に加速することになる。
(4)ケアマネは活用すべき
ケアマネは利用者や家族との信頼関係が全てと言っても過言ではない。介護サービスを利用して家族がどれだけ助かるかを可視化、数値化する事は難しいが、介護という難題を目の前にした人たちにとって必要な業であることは間違いない所だ。
ケアプランを有料化するかどうかの議論だが、「信頼関係があるなら、多少の費用負担もしてもらえるはずだ」という見方はあるだろう。しかしそれによりケアマネが利用者や家族に対して言えない事が出てきたりすれば、制度の崩壊にもつながりかねない。おそらくそんなことは無いし、そうなったらその時に考えれば良いという見方は出来ないでもないだろう。
今後AIが発達し、ちょっと情報を入れればケアプランが作成できるようになると、自己作成が増えてケアマネは必要なくなるのではという見方もあるが、そうなって失ったものを考えれば良いのではないかと思う。