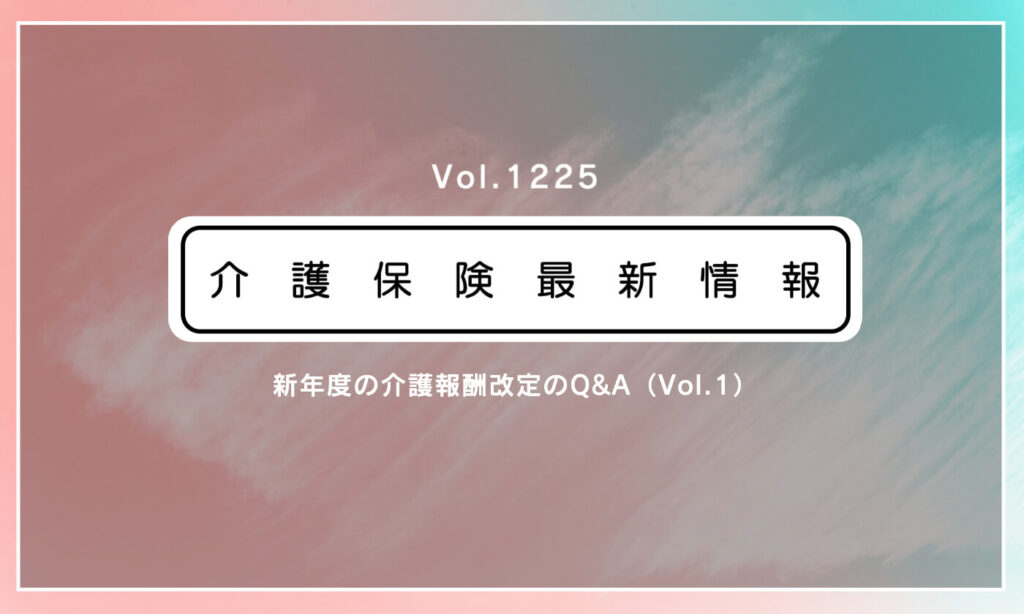(1)そもそもモニタリングって何?
今回の改定で、ケアマネのモニタリングがオンラインでも出来るようになった。モニタリングというのは要介護であれば月1回、要支援であれば3か月に1回、利用者宅を訪問し、本人と面会するというもの。
意義で言えば、ケアマネが作成したプランの方向性に沿ってサービスが行われているかを確認し、必要であればプランの見直しを行うというものである。
しかし大体においてプランは変更なく行われるので、モニタリングは利用票に印鑑をもらう(以前は印鑑をもらっていた)「スタンプラリー」と揶揄されていた。
ケアマネの中には全く訪問しないで、しかも三文判を買って自分で印鑑を押していた人もいたくらいだ。ケアマネにとってみれば、状態もサービス内容も変わらないのに、雑談しに行くくらいなので無駄だと思う人もいたと思う。
利用者にしても、ご家族と話をするだけで、自分の話は聞いてもらえないという不満もあった。
(2)そんなに訪問するのが億劫なのか
ケアマネってそんなに忙しいの?と言われれば、対応しなければならない事が重なった時は忙しい。
大まかなスケジュールで行くと、まず要支援の報告を地域包括に行う締め切りが大体毎月5日くらい。国保連への請求が10日。それから予定を作って利用者宅を回る。1日何件回るかは分からないが、トラブルの発生や余裕をもってとなると、実質回れる日数は11~12日となる。これを持っている件数から割ると、毎日3~4件回るという計算になる。
またケアマネがい忙しいと言われる所以は、何かあればすぐにケアマネに報告するという習慣もある。極端な話、訪問介護の訪問時間が30分ずれただけで事業所に交付する提供表の訂正を求めるところもあったくらいだ。
そこをどのようにして業務効率化するかというのがポイントであった。
(3)オンラインモニタリングというトラップ
モニタリングのオンライン可能というのは、そうした業務効率の一環として厚労省が認めたものだろうと思う。今後、逓減制で担当件数が増えるケアマネがいることを見越しての事だろうと思う。
まあ、そこは評価する所だが、まずオンラインモニタリングを同意するか云々については、それなりのハードルがある。これがふわっとしたものだから、実地指導の担当者次第で運営基準減算になり得る。実際行おうとする人は注意すべし、だな。