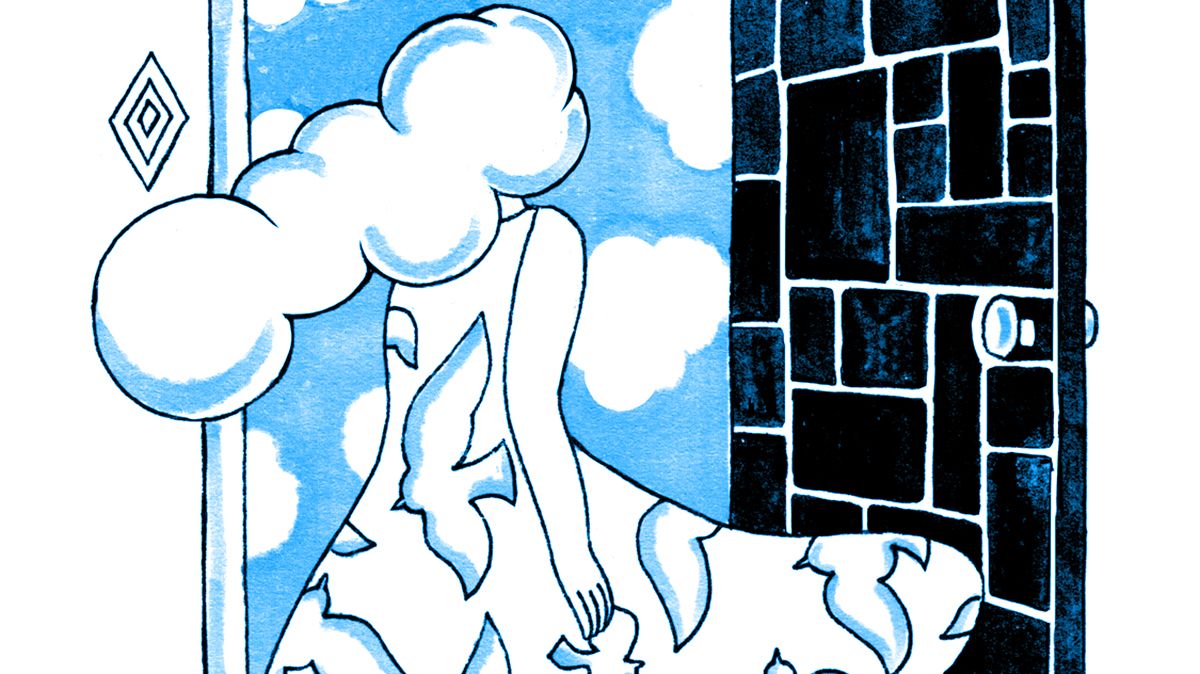日本人の特徴なのか、殆どの人が終活を行わない。というよりその現実が近づいている事は恐ろしい事のようだ。
それでもいわゆる終活と言われるもので、遺言を残すとかエンディングノートを書くとか言う事はやっておいてもらわないと後で遺族が困るという事にはなる。
しかし本人の立場で言えば、そんなことは言っていられないというのも現実だろう。
死に向かう時に4つの痛みがあるという。
①身体的苦痛・・・身体の痛み
②精神的苦痛・・・ネガティブなことを想像してしまい不安になる、イライラしてしまう、そわそわして何も手につかない、気分が落ち込んで憂鬱になる、見放された気持ちになり孤独を感じるといった精神的な負担。
③社会的苦痛・・・病気の治療や症状が仕事に影響を与えてしまったり、病気について職場にどのように伝えるべきか悩んでしまったりする「仕事上の問題」から生じる苦痛があります。そのほか、いつものように働くことができずに経済的な不安を抱えてしまう「経済的な問題」や、家事や育児に制限が生じたり、役割を果たせなかったりすることへの苦悩といった「家庭内の問題」によって生じることもある。
④霊的苦痛(スピリチュアルペイン)・・・病気に対する大きな不安や恐怖、家族や職場の人に対する申し訳なさや依存することへの負担感などから、自分という存在の意味や価値を見失ってしまったり、虚しさを覚えてしまったりもする。
特に④のスピリチュアルペインでは、なぜ自分にこの病気が来たんだろうとか、なぜこのような苦しみを経験しなければならないのか、人生にはどんな意味があるのかなどの根源的なことまで感がるようになると言われている。
そうしたものに寄り添うのが欧米では宗教の存在なのだろう。
勿論、日本でもあるのが、それをあからさまに語ると怪しいとか騙されていると思われてしまうようで話が先に進まない。
なので、ある程度の年齢になったら死を受け入れる心づもりが必要で、エンディングノートは書ける時に書いておくという余裕とは言わないけど、ちょっと書いてみようかという時に書いておいてもらいたいものだ。
おそらく本人の死の受け入れと、残された遺族の何をすればいいんだという迷いは相いれないものかもしれない。
しかし人生では必要な事で、「親は子より早く死ぬんだから」と言っているだけでなく、「自分が死んだらこうして欲しい」という事まで考えてはもらいたい。余裕が無いのは承知しているけれど。