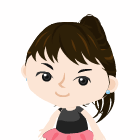*********************
Battle Day0-Day262までのあらすじ (登場人物についてはサイドバーを参照してください)
BattleDay233~ここまでのあらすじ
結局、妹・莉子からは連絡がなく、父の希望していた老人ホームは、せっかくの空いている部屋に入ることができず次の機会を待つことになった。コオはいら立ちを募らせる。莉子ばかり心配する父、同僚のソフィの事故のケア、などはコオを疲弊させ、その中で重症のアレルギー事故をを起こしたコオは、体調とともに心のバランスも大きく崩していた。そして父の誕生日がやってきて、父はケーキを持ってきたコオに、莉子は母と同じ、料理学校に通ったことがあることをとを話す。
*********************
「莉子がお菓子作ってるところなんて見たことなかったけどな。」
コオは控えめに言った。実際、料理が、はっきり言えば下手、というより、単純にやらない、というのがコオの知ってる莉子だった。1年間だけコオと二人で暮らしたことがあるが、彼女がろくなものを作っていた記憶がない。莉子が転がり込んできたとき、実は莉子がご飯でも作ってくれるのを期待していた。修士課程の最終年度で、毎日実験で忙しかったコオは、9時5時でアルバイトをしていた莉子には、そういう時間があるはずだと思っていた。
今でも少しだけだが、反省しないでもない。やってほしいならやってほしい、といえばよかった。コオは小さいときから莉子と会話するのが苦手だったから、話さなくても、居候である以上それくらいやってくれるだろう、と勝手に期待していたからだ。それにしても、彼女のつくったものは納豆ご飯、卵かけご飯。それくらいしか記憶がない。しかも指先一つ分だけ残して冷蔵庫にいれっぱなしてカビさせたりするのだから、しょっちゅうそれでコオと言い争いになったものだ。
「パン作ったりしてくれたよ。結構立派なのをな。」
「ふーん。でもやめちゃったんだ。」
何故?とはコオは聞かなかった。莉子が辞めたなのなら、その理由を父に語るはずはまずないだろうし、なんとなく理由が想像できる気もしたからだ。彼女は、母のようにコオをのように、限界を突破するためにあえて無理をする、ということをしない、とずっとコオは感じていた。そんな莉子が、あの頃の母のようにがむしゃらになれたとは思えない。母だって、好きだったからあれほどまでに無理ができた。でも莉子はお菓子作りなんてやったの見たことないもの。
莉子はいつでも言っていたではないか。《私はお姉ちゃんみたいな崖に向かって突っ込んでいくような生き方したくないから》そんな風に。
コオが昔の嫌な思い出にぼんやりしていると、父はさらに言った。
「でも、仕事はいろいろしようとはしていたみたいだぞ、ピアノの先生辞めた後に。」
「色々?また学校にでも通ったわけ?」
「なんて言ったかな、えーと匂いの・・・そうだ。アロ・・・アロマテラピーの資格、とか。」
「・・・何かは知ってはいるけど・・・」
コオは言葉を失った。
アロマテラピー?知ってる。知ってはいる。検定試験があるのも知ってはいるが・・・
コオには現実出来である、とは到底思えなかった。
「莉子ちゃんは夢見る夢子さんだからなぁ。」
そんな風にのんびりという父の言葉をコオは茫然と聞いた。