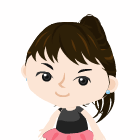*********************
Battle Day0-Day231までのあらすじ (登場人物についてはサイドバーを参照してください)
Day232-これまでのあらすじ
ある日、夜中に電話が鳴る。遼吾を待つコオだったが、期待に反して電話は、T大学病院。コオの同僚ソフィ李が事故を起こし、救急車で運ばれた連絡だった。命に別状はなかったが、翌日に病院に迎えに来るように、病院側に頼まれる。不便な場所にある病院とけが人のため、コオは別れた夫遼吾に車を借り, ソフィのもとに向かい、彼女の大けがを目の当たりにする。検査結果が出るまで4時間待たされることになり、コオは、一度職場に戻り、ソフィの着替えを購入し、上司に事故の報告をした。ソフィのところに戻るが、彼女は朝コオに会ったことを覚えていなかった。コオは記憶が抜け落ちていくソフィに不安を感じながらも退院を手伝い、車で帰路に就いた。以降、ソフィの事故後処理に忙殺されるコオは、仕事を同僚たちに少しずつ分散させるようになる。しかし父・妹莉子・遼吾との離婚というプライベートが重くのしかかった上に、ソフィの事故後処理は、コオの精神を限界に近づかせていた。
そんな時にコオは父に頼まれて探した老人ホームを、最終的に父に見学してもらうことにした。コオが気に入った1件目より、父は2件目が気に入ったように見えた。この施設でコオは再び、支払いなどの説明を受け、自分はキーパーソンではないことの説明もする。
*********************
コオは、父を再び施設に送り届けた後、藤堂を北寿老健の父の担当ケースワーカー浅見に紹介をした。今後どう事を進めていくかの相談つまりは作戦会議をするためだ。
父の老人ホームの見学も終わり、コオが一番気に入った施設ではなかったが、2番めの施設は父も概ね気に入ってくれた、これで後は、莉子次第ということになる。
莉子がイエスといえば、すぐにでも施設に入れる。でもすぐ返事がなかった場合、埋まってしまって待つことになってしまうかもしれない。なんといっても今空きはたった一室なのだ。その場合は順番待ちに入れてもらい、北寿老健で秋を待つことになる・・・
「その待ちになった場合、その間に北寿老健の期限の入所期限、3ヶ月が過ぎてしまったらどうなってしまうんでしょう。」
コオは尋ねた。
「ええ、原則的には3ヶ月期限ですが、いきなり行き先もないのに、さぁ、でてください、ってならないから大丈夫ですよ。お父様が以前一度自宅に戻られた後、具合が悪くなったということが実際にあったわけですから。もう、移られる先を考えておられるわけですし、大丈夫ですよ。」
浅見ケースワーカーが言った。
「それは、助かります。ただ、前もお話しした通り、私と妹は折り合いがよくありません。私が探した、というだけで彼女は拒否反応を示すでしょう。ですから、できれば浅見さんが父から頼まれて、業者に、つまり藤堂さんに頼んで探してもらった、という形にしてもらえませんか?それで、このパンフレットを渡してほしいんです。」
「・・・。パンフレットをお渡しするだけでいいんですかね?」
「ええ、必要な情報は藤堂さんが入れてくださってますから・・・私の名前は基本的に出さないでほしい、というのが私の希望です。」
「私の名刺を入れておきます。ご連絡いただけるように、一筆書いて。」
藤堂がそういって言ってくれた。
「そして、見学もさせてもらえる、ということを一言浅見さんから添えていただけると助かります。」
浅見はうなずき、コオは、これでいったんこの件は私の手を離れるな、と考えていた。
次は、支払いについて詰めていくときが自分がまた出るときになるだろう。その際は莉子はコオに連絡を取らざるを得ないはずだ。前金はコオが払うことになってるのだから。そこさえクリアすれば・・・父の件はある意味解決だ。
「いずれにしても、妹さんにご連絡しなければいけないですねぇ。」
「いま、どんな感じですか?連絡は。」
「お父様のお洗濯ものを取りに来るときと…支払いの時はいらしてるみたいですが、電話での連絡はあまりとってないんです。」
「え?支払い?口座引き落としじゃないんですか?」
この半年、莉子は、父の事を基本なにもやりたがらない、としかコオは思わなかったのに。わざわざ支払いをしに来る?洗濯物でさえ、きちんと週に1回来ているわけではない。そもそも、いつもそれで父は軽く文句を言っていた。先に入院していた紅病院でも、時折コオは看護師に、『もう2週間きていなくて、今週こなかったらお姉さんお願いします』と言われてたことさえあった。その莉子がわざわざ、支払いを窓口にくる?
「ええ、現金払いされるんです。窓口で。引き落としでもいいって言ったんですけど。ですからいらっしゃるときに、うまくタイミングが合えば一番いいんですけどねぇ。」
浅見ののんびりとした口調とは逆に、コオはなぜかふっと冷たいものが背中を走っていったような気がしていた。
そして、この件は自分の手を離れる、と思ったのとは逆に、コオは父との穏やかだった時間も徐々に失っていくことになる、このとき感じた悪寒は直感のようなものだったのかもしれなかった。