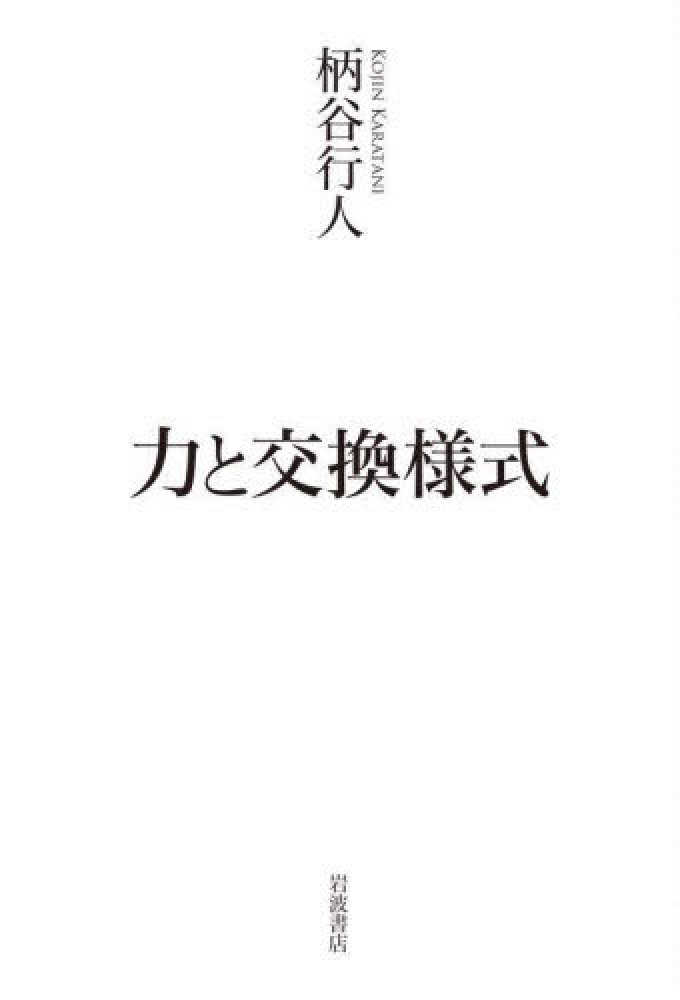ウィーンのカフェ ©CAFÉ LANDTMANN, Wien.
【38】 ジーグムント・フロイト――
「超自我」:外的権威の内面化か?「自律性」か?
前回、フロイトの考察の歩みをたどりながら考えたのは、「自律」とは何か? ということです。
「自律」はしばしば「自立」と書かれたりもします。「自律」と「自立」――イメージとしては、なんとなくつながりますが、突き詰めて考えると、矛盾してくるようにも思えます。「自らを律する」と言うが、何によって、あるいは何をモノサシにして律するのか? 自分をモノサシにできるほど、「自己」は確固としたものだろうか?
フロイトを参照するまでもなく、人間の「自己」とは、じつにあやふやなものです。日々行動し生きている当の「自己」の大部分は、本人には意識されていません。人を行動に駆り立てている動因の大部分を、本人は知らないのです。しかも、人の行動も考え方も、外部の社会や隣人、家族などの影響をつねに濃厚に受けています。「自らを律する」とは言っても、そこで「律する」主体となるべき「自己」は、けっしてそう頼りになるものではないのです。
中学校や高等学校は生徒に対して、「自律せよ」「自律心を持て」ということを、しばしば求めます。しかし、その「自律」の内容が、校則を守るとか、与えられた道徳律を遵守するといったことにのみ集中されるなら、はたしてそれは「自律」なのか? ロボットがプログラムに従って動くのと、どこが違うのか? そうではない、自分で考えて従うのだ――としても、じっさいのところ、与えられた外部の「権威」を内面化しているにすぎないのではないか? つまり「権威」による他律ではないか、という疑問が生じます。
しかし、フロイトは、「どうあるべきか」ではなく、じっさいに現在あるがままの人びとが、どんなふうに生きているのか?‥常に、そこから出発します。人びとが外部の権威に支配され、権力に操られて互いに争いを繰り返している実情があるとしても、それによって重篤な神経症を患い自己を失う場合があるとしても、それらを心のメカニズムとして、まずはありのままに理解しようとするのです。
『しかし、超自我はエスが最初に対象を選択したさいのたんなる残存物ではなくて、その〔…〕反動形成の意味をもっている。その自我との関係は、「お前は父のようであらねばならない」という勧告に尽きるものではなく、「お前が父のようであることは許されない」すなわち、父のなすことのすべてを行なってはならない、多くのことが父の特権になっている、という禁制をふくんでいる。〔…〕両親、ことに父がエディプス願望の実現の妨害者として認められるので、幼い自我は、これと同じ妨害者を自分の内に設けることによって、この〔ギトン註――外部からの〕抑圧行為に対して自分を強力にした。
子供は、これを行なうための力をある程度まで父から借りたのであるが、この借りは、とくに重大な結果をもたらすのである。超自我は、父の性格を保持するであろう。そして、エディプス・コンプレクスが強ければ強いほど、またその抑圧が加速度的(権威、宗教教育、授業、講義の影響を受けて)に行なわれれば行なわれるほど、のちになって、超自我は良心として、おそらく無意識的罪悪感として、自我を厳格に支配するであろう。』
フロイト,小此木啓吾・訳「自我とエス」, in:『フロイト著作集』,新装版第6巻,2023,人文書院,p.292.
「幼い自我は、これ〔父〕と同じ妨害者を自分の内に設けることによって、この抑圧行為に対して自分を強力にした」という部分は、戦争神経症による「反復強迫」が、将来のショックに備えて、それに耐えられるように「自我」を鍛錬する・という『快感原則の彼岸』の考察を想起させます。つまり、「超自我」の形成は、単なる外的権威の内面化ではなく、むしろ個人の《自律性の獲得・強化》の側面を持っているという・後期フロイトの発展方向が、ここに垣間見えています。
『この反復強迫は、たんに受動的な症状ではなく、能動的な自己治癒の企てなのだ。ただし、能動的ではあるが、意識的なものではない。〔…〕
『自我とエス』〔…〕で明確にされた「超自我」は、』初期フロイトの「夢の検閲官」や、社会的規範の内面化である他律的「現実原則」『とは異質であった。「検閲官」が他律的であるのに対して、「超自我」はいわば自律的、自己規制的なのである。タヒの欲動を持ち出すことによって、フロイトは、むしろ社会的規範=現実原則を超える「自律性」の根拠を見いだしたのだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.90-91.
もっとも、それに続いてフロイトは、「超自我」の自我に対する峻厳な支配を、父の権威によるエディプス・コンプレクスの抑圧によって説明しています↑。「超自我」は、その力を父から借りたことによって、父の権威的性格を保持することになる。その上に、成長につれて「宗教教育」などの外部的権威の作用が加速度的に加えられ、「超自我」の権威的道徳性を強化する、と述べるのです。
とはいえ、それでもなお、「超自我」の心的機構における位置・役割は、外界からの影響を直かに受ける・他律的な「意識」に従うのではなく、内的な「エス」と・より強く結びついています。フロイトは、このような「超自我」の自律的な面を強調してもいるのです:
『エディプス・コンプレクス〔…〕は、人間に固有の特質と思われるが、それを精神分析の仮説は、氷河時代を通じて強制された文化への発展の遺産であるとみなした。〔…〕
自我理想〔=超自我――ギトン註〕とは、エディプス・コンプレクスの遺産であり、したがってエスのきわめて強力な興奮と、もっとも重要なリビドーの運命を表現するものである。自我理想を形成することによって、自我はエディプス・コンプレクスを支配し、同時にみずからエスに服従する。自我が本来、外界現実の代表者であるのに対して、超自我は内的世界、つまりエスの代理人として自我に対立する。〔…〕生物の法則と人間種族の運命がエスのうちにつくり、伝えたものは、自我理想の形成によって受け継がれ、自我の中で個人的に体験される。自我理想は、その形成の歴史によって、個人の中の系統発生的獲得物、古代の遺産ときわめてゆたかに結合している。個人の精神生活の中でその最深層に属していたものは、理想形成によって、〔…〕人間精神の最高のものになる。〔…〕
父への憧憬にたいする代償形成としての自我理想は、あらゆる宗教がそこから生成した萌芽をふくんでいる。自我と自我理想とを比較して、おのれの不肖の身を批判することは、憧憬を抱く信者がよりどころにする謙譲な宗教感情をうむ。〔…〕
社会的感情は、共通の自我理想に基く他人との同一視の上に立っている。〔…〕社会的感情は、若い世代の仲間に起こる競争〔女をめぐる争い――ギトン註〕をなくす必要によって得られた。〔…〕敵意は満足されえないので、最初の敵〔兄弟や最初の競争相手――ギトン註〕と〔ギトン註――自分と〕の同一視が行なわれる。穏和な同性愛者を観察した結果は、この同一視も愛情の対象選択の代償〔愛情の対象を、女から競争相手である男に向け変えた――ギトン註〕であり、この対象選択が攻撃的な敵対的態度を切り離した〔抑圧した――ギトン註〕という推測を裏づけている。〔…〕
エスは、自分のそばで外界を代表している自我によることなしには、外界の運命を体験することも経験することもけっしてできない。〔…〕自我の体験は一見すると継承されない〔…〕ように見える。しかし、もしその体験が、しばしば〔…〕世代を追ってつづく多くの個人に繰り返されるならば、それはいわばエスの体験に変わり〔自我の記憶がエスに沈降し――ギトン註〕、その印象は遺伝によって保存される。したがって遺伝性のエスは、その中に数えきれないほど多くの〔ギトン註――過去の〕自我存在の残余を隠しており、〔ギトン註――現在の〕自我がその超自我をエスから作るとき、おそらくただ古くなった自我の像を出現させ、復活させるのであろう。』
小此木啓吾・訳「自我とエス」, in:『フロイト著作集』,pp.292-295.
「自我理想(超自我)は‥‥古代の遺産ときわめてゆたかに結合している。」「遺伝性のエスは‥‥数えきれないほど多くの」過去の「自我‥‥を隠しており、」それらは、超自我となってよみがえる。これらの現象は、「超自我」の復古的性格、先史・古代人の心性を保存し「反復」する性質を示すものです。
同様のことは、『蕪気味なもの』論文〔⇒:(10)【34】〕でも言及されていました:「われわれはみな個人としての発達の過程で、原始人のアニミズム‥‥を経てき」ている。「古い確信はわれわれのうちに今なお生き続けて」いるので、それは何かきっかけがあると浮上し、人は呪いの「欲望を抱くだけで他人を刹すことができるとか、タヒ者たちは生き続けて」いるといった「撫気味な」確信を抱くことになるのだ、と。
ジーグムント・フロイト(1926年) ©Wikimedia.
【39】 ジーグムント・フロイト――
「生の欲動」と「タヒの欲動」「破壊衝動」
先行する『快感原則の彼岸』とは異なって、『自我とエス』論文では、自己保存本能が、「タヒの欲動」ではなく「生/性の欲動」のほうに入れられています。そのほうが、論理的に無理がないでしょう。しかし、この変更に伴って、「タヒの欲動」の性格が変わってきたようにも思われます。「自己保存」がなくなったぶんだけ、『自我とエス』論文での「タヒの欲動」は、生命体を破壊し生命の動きを静止させる傾向を、より強く持つことになります。また、「性の欲動」のほうは、「自己保存」を合併したぶんだけ、保守的傾向を帯びることになります。
『本能には、2種類が区別されねばならない。その1つは性本能あるいはエロスで、〔…〕それは、〔…〕自己保存本能をもふくむ。
第2の種類の本能を示すことは〔…〕もっと困難なことである。〔…〕生物学に根拠をおいて理論的に考察したあげく、われわれはタヒの本能を仮定した。このタヒの本能に負わされた課題は、有機的生物を生命のない状態にひきもどすことである。〔⇒:(9)【28】――ギトン註〕
これに反して、エロスは、分解されて分子の状態になっている生ける物質を、ますますひろく集合させて生命を複雑化し、そのさい、もちろん生命を保持しようという目標を追っている。
この2つの本能は、そのとき、厳密な意味で保守的にふるまう。生命の発生によって混乱した状態を復旧しようと努めるからである。それゆえ、生命の発生は生き続けることの原因であると同時に、タヒにむかって努力することの原因でもあるにちがいない。生命それ自体は、この2つの傾向の闘争であり妥協なのであろう。〔…〕
どのような方法でこの2種の本能がたがいに結合し、混合しているかは、まだまったく想像できないと言ってよい。単細胞の要素的な有機体が多細胞の生物に結合する結果、単細胞のタヒの本能を中和し、破壊的興奮を、特別な器官を媒介にして外界に向け換えることができたのであろう。この器官は筋肉系統であり、タヒの本能は〔…〕外界あるいは他の生物を破壊する衝動として現れる』
小此木啓吾・訳「自我とエス」, in:『フロイト著作集』,pp.297-300.
「タヒの欲動」から「破壊衝動」が生まれる機序を、1924年の別の論文で、より詳しく見ておきます:
『生物体中に働いている〔…〕2種類の欲動〔「性の欲動」と「タヒの欲動」――ギトン註〕という仮説にまで立ち戻ると、〔…〕(多細胞)生物においてリビドーは、細胞中に支配するタヒあるいは破壊の欲動にぶつかる。この欲動は、細胞体を破壊し、個々一切の有機体単位を無機的静止状態〔…〕へ還元してしまおうとする。リビドー〔「性の欲動」――ギトン註〕は、この破壊欲動を無害なものとし、その大部分を、〔…〕ある特殊な器官系すなわち筋肉・の活動の援助のもとに、外部に放射し、外界の諸対象へと〔ギトン註――打撃力として〕向かわせる。それが、破壊欲動とか、征服欲動とか、権力への意志とかいうものなのであろう。
この欲動の一部が直接性愛機能に奉仕させられ〔…〕重要な役割を演』ずるの『が本来のサディズムである。タヒの欲動の別の一部分は、外部へ振り向けられることなく、有機体内部に残りとどまって、〔…〕随伴的性愛興奮作用によってリビドーに奉仕する。これが本来の性愛的マゾヒズムである。』
青木宏之・訳「マゾヒズムの経済的問題」, in:『フロイト著作集』第6巻,p.318.
原始的な生物の体内で、生きようとする「生の欲動(エロス)」は、生命体自身を無機物質に戻してしまおうとする「タヒの欲動」の妨害にあうので、この「タヒの欲動」の矛先を外部に向けさせて生命体を守ろうとする。こうして、動物は「破壊衝動」ないし「攻撃欲動」をますます強力に発揮するようになる。その後、氷河時代の人類に、この「破壊衝動」の向きの再度の転換が起こって、「超自我」が形成された、というのです。
しかし、もともと「タヒの欲動」は、原初の単細胞生物の時代には、攻撃的な性質ではなく、生命を、単に静かに静止させる傾向を持っていたはずです。「タヒの欲動」の再帰転換によって誕生した「超自我」にも、それは受け継がれていないのだろうか? 「超自我」の「自我」に対する攻撃性は、本来の性格ではないのではないか?――という疑問が、ここで生じます。
Gregory Crewdson: untitled, 1998-2002.
『自我は、大部分、放棄されたエスの対象備給〔断念された性愛の対象――ギトン註〕の代わりになる同一化から形成されている。この同一化の最初の時期に属するものは、きまって自我の中で特別の機関としてふるまい、超自我として自我に対立する〔…〕
超自我が自我の中で、あるいは自我に対して、特別な位置を占めるのは、〔…〕第1に、それは自我がまだ弱いあいだに起こった最初の同一化であったこと、第2に、それはエディプス・コンプレクスの遺産であり強大な対象を自我に導入したこと』が要因『である。超自我の起源が父コンプレクスにあることに由来する性格、すなわち、自我に対立しそれを支配する能力を、超自我は〔ギトン註――「最初の同一化」であったがゆえに〕生涯にわたって保持するのである。超自我は、かつての自我の弱体と依存性の記念碑であり、成熟した自我に対してもその支配を続ける。子どもがその両親に従うように強制されているように、自我はその超自我の至上命令に服従するのである。〔…〕
エスの最初の対象備給、つまりエディプス・コンプレクスに由来することは、超自我にとって、それ以上の意味がある。〔…〕超自我は、この由来によって、エスの系統発生的獲得〔人類史的な「エス」の発達史――ギトン註〕に関係づけられ、エスのうちに残渣を残した過去の自我形成の再現とみなされる。したがって、超自我は不断にエスと密接な関係を保ち、自我にたいしてエスの代表としてふるまう。超自我はエスのうちに深く入り込み、そのために自我に比べて意識から遠く離れている。〔…〕
これらの状態〔意識的/無意識的な罪悪感が心内で働いている状態――ギトン註〕では、超自我は、意識的自我からの独立と無意識的なエスとの親密な関係を示している。〔…〕
超自我は本来罪悪感として〔…〕現れ、そのさい自我にたいして異常な苛酷さと厳格さを示す』ことがある。メランコリー(鬱病)の場合を見ると、『意識を占有した非常に強い超自我が、自我にむかって激怒』する。この場合、『超自我の中で支配しているものは、タヒの本能の純粋培養のようなものであって、自我が躁病に転変することによって予めその暴君をふせがないと、しばしば本当に自我をタヒに駆り立てることがある。〔…〕
衝動抑制、つまり道徳の見地から見ると、〔…〕エスはまったく無道徳であり、自我は道徳的であるように努力し、超自我は過度に道徳的で、エスに似て非常に残酷になる可能性がある。人間が外部に向かう攻撃性を抑制すればするほど、その自我理想の中では、ますます厳格になり、攻撃になるということは注目に値する。〔…〕人間がその攻撃を統御すればするだけ、その自我理想の自我に対する攻撃傾向は昂進する。〔…〕
超自我は、父という模範との同一視によって生じたものであり、これらの同一視は、どれも非性化あるいは昇華の性格をもっている。このような変化が起こるときには、衝動の分解が起こるように思われる。エロス的成分は、昇華されたのちには、それに加わる破壊性のすべてを拘束する力をもはや失ってしまう。そして、破壊性は、攻撃傾向や破壊傾向として解放される。この分解のために、一般に自我理想は、厳格で残忍な命令の様相をおびることになるのである。』
小此木啓吾・訳「自我とエス」, in:『フロイト著作集』,pp.303,306-308.
本来、エディプス・コンプレクスは、幼児期における両親に対する「性の欲動」つまり「快感原則」にしたがう衝動を機縁とするもので、超自我には、この「性の欲動」と、「タヒの欲動」によるその反動形成に基く4重のアンビヴァレントな「同一化」の結合が入りこんでいました。したがって、超自我は、必ずしもつねに「攻撃衝動」の対自化のみに占められて峻厳に自我を責めるわけではないと思われます。しかしフロイトは、超自我に含まれる「性的衝動」は昇華して力を失うので、「攻撃衝動」が前面に出て「自我」の断罪に向かうのだ、と言うのです。
ミツバチの社会:女王蜂と働き蜂。©あきた森づくり活動サポートセンター
「ミツバチやアリ,シロアリなどは、年十万年にもわたる格闘のはてに、
我々が見とれる国家制度や分業、個の制限を実現してきた」(p.135)
【40】 ジーグムント・フロイト――
文化と「攻撃性」と「超自我」
『文化とは、たがいにばらばらだった複数の個人を、後には複数の家族を、さらには部族や民族、国をひとつの大きな単位へ、人類へと包括していこうとするエロース〔=「リビドー」=「性/生の欲動」――ギトン註〕に従属する過程だ、と言っておこう。〔…〕われわれに〔…〕分かるのは、これがまさにエロースの働きだということである。こうした人間集団をリビードによって互いに結びつけようというのである。労働共同体の利点といった必要性だけでは、人間集団を束ねておくことはできまい。しかし、文化のこうしたプログラムに逆らうのが人間の自然な攻撃欲動、すなわち一人が万人に、万人が一人に対して抱く敵意である。この攻撃欲動は、エロースと並び立ち、』エロスとともに世界を支配する『タヒの欲動から派生した蘖 ひこばえ であり、その主たる代理者である。〔…〕文化とは、人間という種において演じられるエロースとタヒとのあいだ、生の欲動と破壊の欲動とのあいだの闘いをわれわれに示しているにちがいない。この闘いは生一般の本質的内実であり、それゆえ文化の発展は、端的に人間という種による生死の闘いと呼ぶことができる。〔…〕
他の動物種では、環境の影響と、その動物のなかで互いに覇を競いあう欲動とのあいだに一時的な和解が成立し、発展が静止するにいたったのかもしれない。原始人では、リビードの新たな進撃を開始したせいで、破壊欲動のほうもあらためてこれに対抗するように焚きつけられたのかもしれない。〔…〕文化は、自分に向けられる〔ギトン註――人間の欲動からの〕攻撃を抑え、無害化し、ひいては一掃するのにどんな方策をもってするのか。〔…〕個人の発達史を辿ることで、その方法を見ていきたい。個人の攻撃欲を無害化するために、どういうことが行なわれているのだろうか。〔…〕
攻撃性を内に取り込み、内面化するのだ。それは本来、攻撃性をそれが由来する元の場所に送り返すこと、要するに自らの自我に向けることである。帰ってきた攻撃性を自我の一部が引き受け、これが超自我となって自我の残りの部分と対峙し、さらに良心となって、ちょうど自我が別の疎遠な個人に向けて満足させたかったであろう同じ厳しい攻撃性を、自我に対して行使するのである。厳格な超自我とそれに服属する自我とのあいだの緊張は、罪の意識と呼ばれ、懲罰欲求として現れる。このように、文化は、個人を弱体化、武装解除し、占領した町で占領軍にさせるように、内部のひとつの審級に監視させることによって、個人の危険な攻撃欲を取り押さえるのである。』
フロイト,嶺秀樹・他訳「文化の中の居心地悪さ」, in:『フロイト全集』20,2011,岩波書店,pp.134-136.
『われわれが攻撃欲動を満足させないと、そのいちいちが超自我によって引き受けられ、(自我に対する)超自我の攻撃性が増大する、〔…〕自分にとって最初の、しかも最も重要ないくつかの満足〔欲動の充足――ギトン註〕を権威によって阻止される子供は、この権威に対して、少なからず攻撃性向をつのらせたにちがいない。〔…〕子供がこうした困難な経済状況から脱け出す方法は、よく知られたメカニズムである。〔…〕権威を自分と一心同体と見なし、自分の中に取り込む。こうして権威は超自我となり、子供がこの権威に向けたかったはずの攻撃性をすべて保有することになる。
子供の自我は、屈服した父としての権威という悲しい役割に甘んじなければならない。〔…〕「もしもぼくが父さんで、父さんが子供だったら、ぼくは父さんをひどい目にあわせてやる……。」超自我と自我との関係は、いまだ未分化の自我と外の対象とのあいだにあった現実の関係が、欲望によって歪められた上で回帰したものなのである。
超自我のもともとの厳しさは、一概に、外の対象としての父から経験した厳しさ、あるいは父に備わっていると思われた厳しさというわけではなく、むしろ自分が父親に対して抱いた攻撃性の厳しさの代理だ、〔…〕良心は、初めにひとつの攻撃性が抑え込まれることによって生じ、その後の経過の中でそうした抑え込みが繰り返されることによって強化されるのだ。
〔…〕経験から知られるところでは、子供が発達させる超自我の厳しさは、彼自身が被った取扱いの厳しさをけっして再現するものではない。〔…〕いたって穏和な中で育てられた子供でも、きわめて厳格な良心を獲得することもある。』
嶺秀樹・他訳「文化の中の居心地悪さ」, in:『フロイト全集』,pp.143-144.
注意したいのは↑2番目の段落です。ここからわかるように、「攻撃欲動」が自分(自我,わたし)のほうに向けられて「超自我」となる、という図式にあっては、「自我」=父(の代わりのもの)、「超自我」=内面化された攻撃性、なのです。正確に言えば、外部の「権威が内面化する」のではなく、「攻撃性が内面化する」。ここに、後期フロイト特有の考え方があります。「超自我」は、権威の内面化ではなく、もともと個人のエスが持っていた無意識の攻撃欲動が内面に(「わたし」に)向けられたものなのです。
「自我」を中心に、「自我」のほうから見ると、「超自我」は父の権威の内面化ですが、逆に、「エス」と「超自我」のほうから見ると、「自我」は、攻撃対象であった父の身代わりであり、父と戦ってきた攻撃欲動は、「超自我」となっても相変わらず「自我」を相手に戦いを続けているのです。「超自我」の「自我」に対する峻厳さ・残忍さも、そこから生じています。それは、父に対する「復讐」の残忍さです:「父さん(自我=わたし)をひどい目にあわせてやる」
『「超自我」は、〔…〕いわば自律的、自己規制的なのである。タヒの欲動を持ち出すことによって、フロイトは、むしろ社会的規範=現実原則を超える「自律性」の根拠を見いだしたのだ。〔…〕
一般に、「超自我」というと、〔…〕両親を通した社会の規範の内面化であると見なされてしまう。それなら、』初期フロイトの「夢の検閲官」や、他律的『「現実原則」と違わないことになる。しかし、たとえば、厳格な両親のもとで育った子供が厳格な超自我をもつとは決まっていない。むしろその逆のケースが少なくない。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.90-91.
『「過度に柔和で寛大な」父親は、子供に過度に厳格な超自我を形成させる誘因となるだろう。というのも、子供は、自分に愛が強く注がれているのを感じて、自らの攻撃性の捌け口としてそれを内に向けるほかないからである。〔…〕厳格な良心は、欲動の断念と愛の経験という、生〔生/性の欲動――ギトン註〕に影響する2つの要因の協働から生じる。前者は攻撃性を解き放ち、後者〔愛の経験――ギトン註〕はこの攻撃性を内に向け、さらに超自我にそれを委ねる、と言えよう。』
嶺秀樹・他訳「文化の中の居心地悪さ」, in:『フロイト全集』,p.145(原注28).
つまり、攻撃欲動が対象を自分に向け換えること自体、父との戦いの敗北によってではなく、「愛の経験」を要因として生じるというのです。
「超自我」がこのように、もともと父(または母)に向いていた「攻撃(復讐)欲動」が、向け先を変えたものだとすると、この欲動は、アンビヴァレントな性格を帯びています。攻撃しながら憧 あこが れ(慈 いつく しみ)、憎みながら愛するのです。この二重性は、相手が「自我」になっても残るはずです。
フロイトは先行論文『自我とエス』では、エロス的な「愛」のほうは昇華してしまうので、「超自我」は攻撃性ばかりで占められてしまう、と書いていました。ところが、この『文化の中の居心地悪さ』になると、アンビヴァレンツの存続――「超自我」は「自我」に対して厳格一方にふるまうわけではなく、「自我」は「超自我」に対して絶対服従するわけではないこと――を認める叙述をしている部分↓があるのです。
この部分↓でフロイトは、れいの「原父刹し」(⇒:(11)【35】)を再説しているのですが、「原父」刹害ののちに、または刹害を断念したのちに、「愛が前面に現れ、この愛が‥‥超自我を樹立し、」罪責感情を存続させ良心を成立させると述べています。
『この後悔〔刹害後または刹害断念後の後悔――ギトン註〕は、父にたいする原初的な感情の両価性 アンビヴァレンツ の結果であった。〔…〕憎しみが攻撃性によって満足させられると、行為にたいする後悔というかたちで愛が前面に現れ、この愛が父との同一化を通して超自我を樹立し、あたかも父に向けてなされた攻撃の行ないに対する懲罰のためとでも言うように、超自我に父の権力を与え〔…〕たのだった。良心の成立には愛が関与しており、罪責感は宿命的なものであって避けることはできない〔…〕父親を刹したのか、それとも〔…〕差し控えたのかは、〔…〕決定的ではない。いずれの場合とも、人は自分に罪があると感じる。というのも罪責感は〔…〕エロースと破壊ないしタヒの欲動とのあいだの永遠の闘い〔愛/憎のアンビヴァレンツ――ギトン註〕の表現だからである。〔…〕
文化というのが家族から人類に至る必然的な発展の歩みであるなら、この文化には、〔…〕愛と死の追求との永遠の争いの結果として、個々人が耐えがたいと感じるほどの罪責感の増進が切り離しがたく結びついている。〔…〕
人間の共同生活は、人間自身の攻撃欲動や自己破壊欲動によって攪乱されている。人類は、これを自らの文化の発展によって抑制できるのか。どの程度までそれが可能なのか。私には、その成否が人間という種の運命を左右する懸案ではないかと思われる。〔…〕人間は今や、こと自然の諸力の支配に関しては目覚ましい進歩を遂げ、それを援用すれば人類自身が最後のひとりに至るまで根絶しあえるまでになった。〔…〕〔ギトン註――攻撃欲動すなわち「タヒの欲動」とならぶ〕「天上の力」のもう一方、永遠のエロースには、ひとつ奮起して意地を見せてくれることを期待しようではないか。だが、その成否や結末は、いったい誰に予見できよう。』
嶺秀樹・他訳「文化の中の居心地悪さ」, in:『フロイト全集』,pp.146-147,162.
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!