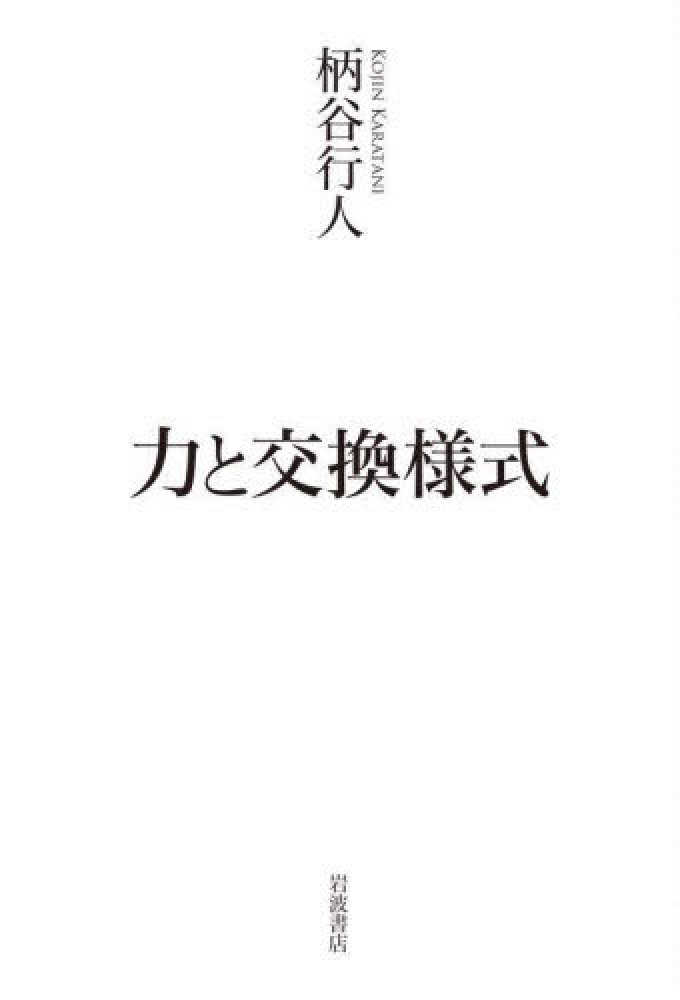地下鉄サリン事件(1995年3月20日): 「霞ヶ関」周辺の地下鉄駅から
救出された乗客は口々に「眼が痛い」「息ができない」と訴えた。©読売新聞
【30】 ジーグムント・フロイト――
災害神経症と生体の防御システム
柄谷氏が「交換様式」との関係で『快感原則の彼岸』に注目する接点は、フロイトにとって考察のきっかけとなった「戦争神経症」、すなわち「反復強迫」という深層心理現象の発見です。
この一群の心理現象は、現代の私たちにはむしろ、より身近になっています。「外傷性神経症」「トラウマ」「PTSD」――そうした術語を、だれもが多かれ少なかれ聞き知っているのではないでしょうか。
これらの現象が日本でクローズアップされたのは、おそらく「地下鉄サリン事件」〔1995年〕をきっかけにしてだったと思います。そのため、現代の私たちの関心は、これらの心的外傷を引き起こす犯罪や社会的原因のほうに向けられがちです。
しかし、フロイトがこれらの考察に向ったのは、第1次大戦の戦傷や被害によって神経症を発症した人びとの治療がきかっけでした。したがって、大戦終結後の彼の考察は、もっぱらこれらを発症する心的過程の解明に向ったのです。
『外部から来て、刺激保護を突破するほど強力な興奮を、われわれは外傷性のものと呼ぶ。〔…〕外部から来る外傷のような出来事は、たしかに有機体のエネルギーの運営に大規模な障碍を惹き起し、あらゆる防衛手段を活動させるであろう。しかし、そのさい快感原則は無力にされている。他方、心的装置に充満した巨大な刺激量は、押し戻すことができない。むしろ刺激をとらえて料理し、侵入した刺激量を心理的に拘束し、そのうえでそれを除去するという別個の課題が生まれるのである。
おそらく、肉体的苦痛に特有な不快は、制限された範囲内で刺激保護が破られた結果であろう。このようにしてこの末梢部位から、さもなければ装置の内部からのみ来るはずの不断の興奮が、心の中枢装置〔意識的な表面部分――ギトン註〕に向って流れこむのである。この侵入にたいする精神生活の反応として何が起こるのであろうか? 突破箇所の周辺に、それに相応した高度のエネルギー集中が行なわれるために、あらゆる側面から備給エネルギーが召集される。そのために他のすべての心理的体系が貧困におちいるような大規模な「逆備給」が行なわれ、その結果他の精神活動が広い範囲で麻痺したり低下したりする。
われわれは、このような事情から、それ自体高度のエネルギー備給をもった体系は、あらたに流入するエネルギーを受け入れ、それを静止した備給状態に変化させること、つまり心理的に「拘束する」ことができるという結論を引き出すのである。固有の静止せる備給エネルギーが高度であればあるほど、その拘束の力も大きくなるであろう。それゆえ逆に、備給が低いほど、その体系は流入するエネルギーを受け入れることができなくなり、それだけ刺激保護〔刺激から生体を保護する機構――ギトン註〕の破綻の結果は、強烈なものであるにちがいない。〔…〕おそらく、心的装置に流入するエネルギーの「拘束」は、自由に流動する状態から静止した状態への移行のなかで行なわれる、と推測してよいだろう。
ふつうの外傷性神経症を、刺激保護のはなはだしい破綻の結果、と解してみてもよいだろうと思う。〔…〕ショック理論が、ショックの本質を〔…〕神経要素の組織学的構造の損傷とさえみるのにたいし、われわれはその作用を、精神の器官・にたいする刺激保護の破綻と、そこから発生する課題から理解しようと試みるのである。
驚愕〔…〕の条件は、刺激を最初に受けとる体系の、過剰な備給をもつ不安・という準備状態が欠けていることである。そのとき、この低量の備給のために、体系は来襲する興奮量をうまく拘束することができなくて、それだけに刺激保護の破綻の結末が、はるかに容易に現れるのである。』
フロイト,小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,新装版第6巻,2023,人文書院,pp.172-173.
生体に外部から急激なエネルギーの侵入があると、物理的損傷が生じるだけでなく、生理化学的・心的システムにも大きな混乱が起きます。混乱を放置すれば、侵入したエネルギーは、心的装置の中をかけめぐって、あちこちに混乱を拡大させていきます。そこで、これに対する生体の心的防衛機能として、異常なエネルギーの高まりを、侵入点――表面に近い場所、つまり「意識」活動の場――の付近で「拘束」し、他へ拡大させない、ということが行なわれるわけです。
この「拘束」を、生体がどのようにして行なうかといえば、生体内部の「エネルギー備給」によって行なうのです。たとえば外部から毒物質が侵入した場合、そこに大量の水を供給して薄めれば、毒物質が及ぼす効果を低めることができます。それと同じように、生体内部の心的エネルギーを侵入点に集中させて、外部から来た影響を薄め、全体を静止させて動きを止めるわけです。量的にはエネルギー水準は高いままですが、増減がなく静止したエネルギーは、急激に動くエネルギーよりも、生体ははるかに容易に持ちこたえることができます。
フロイトは、↑このようなモデルで考えています。外傷性ショックに限らず、たとえば、性的興奮が急激に高まった場合にも、生体の自己防衛機能が働いて、まず興奮を高水準で「拘束」し、次いでこれを放出して、一気にエネルギー水準を低めるのです。この(危険な)エネルギーの・低下が、性行為の「快感」として感じられます。「快感原則」は、エネルギー水準を低めまたは低く保つ原理です。
「外傷性」のエネルギー侵入の場合にも、同様にして、心理的ショックのエネルギーを「拘束」するわけです。「拘束」が成功するためには、あらかじめ心的装置の内部にエネルギーを溜めておかねばなりません。このエネルギー蓄積の過程が、災害に見舞われる直前に起きる「不安」という心理状態です。
出陣学徒壮行会(1943年) © NHK
【31】 ジーグムント・フロイト
――「トラウマ」の発症メカニズム
ところが、何の予兆もなく災害が起きた場合、また、前線に向かう兵士のように、「不安」が起きないよう人為的に抑圧されてしまった場合には、内部エネルギー水準が低いままショックを受けることになります。この場合、心の自己防衛機構は破綻し、「拘束」は打ち破られてしまいます。その結果、心的システムは、外傷そのものが治癒した後も、長きにわたって「外傷性神経症」ないし「戦争神経症」を病むことになるのです。
『外傷性神経症の夢は、患者を災害の場面に繰りかえし引きもどすという性格をもっていて、患者はそのたびに驚愕をあらたにして目ざめる。〔…〕
災害神経症者の夢が、患者を規則的に災害の場面につれもどすとき、それは願望実現に役立ちはしない。〔…〕われわれは、災害神経症者の夢は、〔…〕解決されねばならない別の課題に役立つものと仮定してよいであろう。生命の目標〔…〕それは、生物がかつて棄て去った状態であり、しかも発展のあらゆる迂路をへてそれに復帰しようと努める古い出発点の状態であるに相違ない。』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,pp.161,173-174.
前期フロイトによれば、睡眠中の「夢」は、願望を実現する機能を持っています。たとえば放尿する夢は、放尿を脳内で予行することによって、睡眠中の体内に高まった尿意を満足させ、睡眠を継続させる効果があります。「夢」は、心内に蓄積された願望を仮想において実現することによって、願望実現に向けて高まったエネルギーを低下させ、睡眠の障碍を取り除くのです。このような「夢」の機能は、「快感原則」によってうまく説明することができます。
ところが、「災害神経症」「戦争神経症」患者の見る夢は、「快感原則」では説明できないのです。「快感原則」とは真逆の原理に支配されているように見えます。彼らは、災害の影響がなくなり、戦争が終結した後でも、毎晩のように爆撃や建物崩壊に見舞われた場面を夢に見て飛び起きるのです。彼らの夢は、快感ではなく著しい「不快」を反復体験してエネルギーを異常に高め、睡眠を妨げるために見られているとしか思えません。その結果、災害・戦争神経症者は、現実的対象を欠いた・いちじるしい「不安」にかられることになります。
『不安の発生がとだえたことが、外傷性神経症の原因になったのだから、これらの夢は、不安を発展させつつ、刺激の統制を回復しようとするのである。』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,p.174.
つまり、外傷性神経症となった原因は、戦争や災害の際に、「不安」という準備過程をおかずに、またはそれが不十分なままに、災害ショックを受けたために、「刺激統制」の心的機構が破綻したことにありました。そこで、生体は、戦争・災害の恐れがやんだあとも、ショックの記憶を繰り返し呼び戻して、「刺激統制」を鍛錬して能力を高め、将来のショックの来襲に備えようとする。そういうことが考えられます。なぜなら、ショックは、実際に見舞われる場合よりも、「夢」によって仮想される場合のほうがずっと御しやすく、予行練習の意味をもつからです。
ただ、そこで生ずる疑問は、このような “自己鍛錬” を導く心内の(無意識の)原理ないし本能は何か、ということです。それは「快感原則」ではないとしたら、何なのか?
【32】 ジーグムント・フロイト
――「反復強迫」:トラウマと子供の遊び
いま、フロイトの考察は、次のように進んでいます:
①外傷(ショック)による心的損傷のメカニズム
↓
②「外傷性神経症」の発症メカニズム
↓
③「反復強迫」
↓
④根底的原理としての「タヒの欲動」
考察は、②を経て、③の入口まで来ています。しかし、③の考察は、「外傷性神経症」のみならず、より広い実例を集めて行われる必要があるので、フロイトの叙述は遠心的に広がってしまいます。そこで私たちも、フロイトの他の論文にまで眼を広げて関係個所を見ていく必要があります。とくに、③と④のつながりが、この『快感原則の彼岸』論文では明確に述べられていません。引用者としては苦労する部分ですが、柄谷氏の説明も参照しながらがんばってみましょう。
『このような〔ギトン註――戦争・災害神経症者の〕夢によって、われわれは心的装置の一つの機能について見通しをもつことができる。その機能は、快感原則〔…〕からは独立しており、快の獲得や不快の回避の企て以上に根源的なものと思われる。
災害神経症者の夢は、もはや願望実現の観点から見ることはできないし、小児期の精神的外傷の記憶をよみがえらす精神分析の際に起こる夢もまた同様である。これらの夢はむしろ反復強迫にしたがうものであり、この反復強迫は分析の際には、当然のことながら、〔ギトン註――医師の〕「暗示」によって促進される〔ギトン註――患者の〕願望、すなわち忘却されたものと抑圧されたものを呼び出そうという願望に支えられる。』
a.a.O.
精神分析治療で、幼児期に被った心的外傷体験――たとえば、エディプス・コンプレックス体験――を無意識領域の記憶から呼び戻すカウンセリングがしばしば行われます。繰り返し呼び戻すことによって、被験者の心的装置は、その記憶に耐えられるようになり、神経症を克服します。これは、災害・戦争神経症者の「夢」と同じ「反復強迫」の過程を、人為的に医師の管理下で起こさせていることになります。
災害・戦争神経症者の自発的な「夢」の場合と違うのは、被験者が「呼び戻し」の夢を願望するように、医師が被験者を「暗示」にかけて夢を惹き起す点にあります。ですからこの場合は、「夢は願望の実現である」という原理が部分的に働いていることになります。
しかし、精神分析治療の際に呼び出される幼児期の記憶だけでなく、幼児・小児そのものの心的行動のなかにも、「反復強迫」の実例を見出すことができます。小児の行動は、「高度な衝動性」を特徴としており、また、快感を与えるものだけでなく、「気味の悪い」「デモーニッシュ(魔的)なもの」にも惹かれるという特質をもっています。快/不快の別なく同じことの「繰り返し」「反復」を好むのも、小児に顕著な性向です。
『反復強迫は、高度に衝動的な、そして快感原則に対立するところではデモーニッシュな性格を示している。小児の遊戯にさいして、われわれは、小児が、かつて強い印象を受けた体験を能動的に行なうことによって、たんに受け身の体験のさいよりも、ずっと充分な程度に支配できるという理由で、不快な体験をも反復するということを理解できるように思う。事あたらしく反復されるごとに、この目標となる支配が改善されるものと思われるが、快適な体験でも小児は反復に倦むことを知らず、かたくなに同一の印象に固執するであろう。このような特性は後になって〔大人になると――ギトン註〕かならず消滅する。〔…〕小児は見聞きした遊びや、お相手をしてもらった遊びを、大人が疲れきって拒絶するまで繰り返し要求して倦むことがないであろう。またおもしろい話をして聞かせれば、小児は新しい話を聞く代わりに、繰り返しその話を聞きたがって、頑固に同じままに反復することを求める。そして、話し手が間違えて喋ったり、なにか新味を出そうとして加えた変更さえも、ことごとく訂正するのである。』
フロイト,小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,新装版第6巻,2023,人文書院,p.176.
しかし、幼児の「繰り返し」遊びは、つねに「快感原則」に合致するとは限りません。「繰り返し」じたいが快感になっているとしても、なぜそうなのか、という疑問はつきまといます。大人の場合には、そのようなことはないからです。大人の場合には、異常に多い回数の繰り返しは、むしろ不快を与えます。
子どもの場合には、大人とは違って、数多くの心的規制機能によって保護された「意識」の部分がまだ柔らかく、“心” の内部にある無意識的な「本能」ないし「衝動」の影響を受けやすいからだ、と考えることができるかもしれません。私たちの「意識」は、大脳皮質のような・心的機構の最外殻、外部と接触する表皮のすぐ下の層に定位するものと仮定すると、このことは、より真実らしく思われてきます。外部からの “体験” の影響を最も受けにくい脳の最内奥部分に、原始の生命から受け継がれてきた「タヒの本能」――もっとも保守的な現状維持ないし原状回帰の衝動――が眠っています。最外殻にある「意識」が体験によって受けた刺激のなかで、もっとも強い印象や衝撃を与えたものだけが、順に内部へ沈降していき、半意識~無意識の「記憶」を形成します。
子どもの「意識」はまだ、“心” の内部に対する防衛機能が完全ではないので、最奥の保守的本能の命ずるままに浮上してきた過去の印象に容易に揺さぶられ、それを反復します。
大人の「意識」は、上がってきた印象の再現を「拘束」――ブロック――しようとするので、そこで不快感が生じます。子どもの「意識」では、そのようなことはない。むしろ、意識は内部の無意識と一様になり一体化するので、システムの複雑な稼働はやみ、エネルギー準位は低下して「快」が生じます。
しかし、子どもの「繰り返し」遊びのすべてが、「繰り返し」の快感によって説明できるわけではありません。たとえば、フロイトの挙げている例では、生後1年半で、「母親が何時間もそばにいないことがあっても、けっして泣いたりはしなかった」幼児であるが、その児が母親の不在の時に何をしているかを観察したところ、長い糸の付いた糸巻きを、覆いをかけた小児ベッドの中に落としては、「オーオーオーオ」という叫びをあげた。ついで、糸を繰って外に引っ張り出し「Da! いた!」と嬉し気に叫ぶ遊戯を何度も繰り返していた。つまり、母親の不在と再会を想像上で繰り返す遊戯をしていたのです。
生後1年半の幼児にとって、母親の不在が繰り返される事態が楽しいはずはなく、この遊戯は、「不快」をこそあえて繰り返していると言わざるをえないのです。
『子供が苦痛な体験を遊戯として繰り返すことは、どうして快感原則に一致するであろうか。〔…〕偏見なしに観察すれば、子供は〔ギトン註――快感とは〕別な動機から、自分の体験を遊戯にしたてたのだ〔…〕子供はこの場合、〔ギトン註――母親が立ち去った時には〕受け身であって、いわば体験にとらえられたのであるが、ついで能動的な役割に移り、体験が不快であったにもかかわらず、これを遊戯として繰り返したのである。〔…〕
子供たちは、生活のうちにあって強い印象をあたえたものを、すべて遊戯のなかで反復すること、それによって印象の強さを鎮めて、いわばその場面の支配者になることは、明らかである。しかし、この反面、彼らの遊戯のすべてが、この彼らの年代を支配している願望、つまり大きくなりたい、大人のようにふるまいたいという願望の影響下にあることも充分に明白である。たとえば医者が子供の喉の中を覗き込んだり、ちょっとした手術を加えたりすると、この恐ろしい体験は確実にそのすぐあとの遊戯の内容になるであろうが、そのさい〔ギトン註――支配衝動以外の〕他の理由から快感を獲得することも見落とすわけにはいかない。子どもは体験の受動性から遊戯の能動性に移行することによって、遊び仲間に自分の体験した不快を加え、そして、この代理のものに復讐する〔医者に復讐する代わりに、遊び仲間に不快を負わせる――ギトン註〕のである。』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,pp.162-164.
【33】 ジーグムント・フロイト
――「反復強迫」と人生の「繰り返し」
しかしながら、こうした・事態をよりよく支配したいという衝動、訓練による自己強化の願望、受けた不快を他に転嫁するといった、快感獲得につながるような動機では、まったく説明できないような「反復強迫」も存在するのです。たとえば、人生における「運命」という幻想です。
人生の中で、同じ失敗を何度も繰り返す人がいるものです。というより、本人が、自分はどうしてこうも同じ悪い運命に何度も巡り合うのだろうと思って悩むのです。たとえば、何度も離婚する人は、そういう悩みを抱えやすい。じっさいには、偶然もあろうし、本人が思うほどには、新旧の “悪い運命” は似ていなかったりします。にもかかわらず、本人にはどうしても、「同じことの繰り返し」だと思えてしまう。これは、多くの場合に「反復強迫」という心理作用のためです。過去の不幸を頭の中で「反復」して、新しい事態の上に投影してしまうのです。
さらに悪い場合には、新しい相手の上に「投影」が起こって、じっさいに過去と同じ不幸を繰り返してしまう場合もあります。離婚した前配偶者を、再婚した配偶者の上に投影して、新しい相手とも不仲になってしまうなど。この場合を「転移」と言います。
『われわれが、いま述べなければならないあらたな注目すべき事実は、反復強迫がなんら快感の見込みのない過去の体験、すなわち、その当時にも満足ではありえなかったし、ひきつづき、抑圧された衝動興奮〔やりとげたかったこと――ギトン註〕でさえありえなかった過去の体験を再現するということである。〔…〕
当時、不快しかもたらさなかったこれらの活動の過去の経験からは、何も学ばれはしないはずである。しかし、それにもかかわらず、この経験は反復される。ある種の強迫が、そう駆り立てるのである。〔…〕それは、彼らの身につきまとった宿命、彼らの体験におけるデモーニッシュな性格〔魔的な運命の廻り合わせ――ギトン註〕といった印象を与えるものである。〔…〕あらゆる人間関係が、つねに同一の結果に終るような人がいるものである。かばって助けた者から、やがては必ず見捨てられて怒る慈善家たちがいる。〔…〕どんな友人を持っても、裏切られて友情を失う男たち。誰か他人を、自分や世間にたいする大きな権威にかつぎあげ、それでいて一定の期間が過ぎ去ると、この権威をみずからつきくずし、新しい権威に鞍替えする男たち。また、女性にたいする恋愛関係が、みな同じ経過をたどって、いつも同じ結末に終る愛人たち、等々。〔…〕
以上のような、転移のさいの態度や、人間の運命についての観察に直面すると、精神生活には、実際に快感原則の埒外にある反復強迫が存在する、と仮定する勇気がわいてくるにちがいない。また、災害神経症者の夢と、子供の遊戯本能を、この強迫に関係させたくもなるであろう。〔…〕
反復強迫は快感原則をしのいで、より以上に根源的、一次的、かつ衝動的であるように思われる。』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,pp.166-168.
Sarah Lloyd
【34】 ジーグムント・フロイト
――「反復強迫」と「不気味なもの」
フロイトはあるときイタリアの田舎町で、あてもなく歩き回っているうちに、娼窟のような家が集まった・いかがわしい街路に迷い込んでしまった。急いでそこを立ち去ろうと歩いていると、また同じ角 かど に出てしまった。それが何度か繰り返された時、「部気味としか表現しようのない感情」に襲われたのです。あたかも、魔物か悪霊が彼をとらえて封じ込めているかのような。。。
しかし、似たような体験は、冬山の登山者やスキーヤーにもしばしば起きます。濃い霧がたちこめてホワイトアウトしてしまった雪原で、次の山小屋をめざして歩いていると、着いた山小屋は、今朝出た山小屋で、同じ小屋番と目と目を見交して仰天してしまう…。人間は、方向感覚を失ってさまようと、直進しているつもりで、少し逸 そ れて歩く習性があるようなのです。そのために、無意識に円環を描いて歩いてしまう。おそらく、太古の狩猟時代に身についた本能なのでしょう。狩猟中に路に迷っても、自分のテリトリーから離れないようになっているわけです。
『同じ事態の反復というこの契機〔…〕は、一定の条件のもと一定の状況と結びつくと、疑いの余地なく部気味な感情をひき起こす。〔…〕意図せざる回帰という性格を』もつ同様の体験が、『寄る辺なさと不気味さというこの同じ感情を結果として伴うのである。例えば、〔…〕暗い部屋の中で、扉や電灯のスイッチを探してうろうろするのに、何度も何度も同じ家具にぶつかってしまうといった場合である。〔…〕
意図せざる反復というこの契機のみが、さもなければどうということもないものを蕪気味にし、〔…〕単に「偶然だ」と語ってすまされる〔…〕場合に、宿命的なもの、免れがたいものという想念を押しつけてくるのである。〔…〕
心の無意識の中には、欲動の蠢 うごめ きから発生する反復強迫の支配を認めることができるのである。この強迫はおそらく、欲動の最も内的な本性そのものに依存しており、快原理を超え出るほどにも〔快感原則に優越するほど――ギトン註〕強く、心の生活の特定の側面に魔的 デモーニッシュ な性格を帯びさせるものであって、小さな子供がさまざまに追求することのうちにはいまだにとてもはっきり表明されており、部分的には神経症患者の精神分析の経過を支配している。ここまでに述べられた究明の全体を通して、われわれは、内的反復強迫を思い起こさせうるものはすべて、部気味なものと感じとられるだろうと考える用意が整ったのである。』
藤野寛・訳「✕気味なもの」, in:『フロイト全集』17,2006,岩波書店,pp.30-31.
フロイトは、この論文ではまだ、「反復強迫」は「おそらく、欲動の最も内的な本性そのものに依存して」いるにちがいない――という見通しを述べるにとどめています。しかし、『快感原則の彼岸』を読んできた私たちには、その「最も内的な本性」とは、あらゆる生命体の内奥に潜む・生命誕生以来の本能――「タヒの欲動」――であることが解ります。
静止状態、旧い状態に戻ろうとする「タヒの欲動」こそが、「快」「不快」の別なく体験を「反復」し、外界に「反復」を投射しようとする「意識」の傾向を促しているのです。
宮沢賢治『狼森と笊森、盗森』中央公論社刊、司修画。
賢治童話はアニミズムの世界だ。
『部気味なものの実例を分析した結果、われわれはアニミズムという古 いにしえ の世界観に連れ戻されたのだ。この世界観は次のような特徴によって際立つ。すなわち、世界が人間の霊魂によって満たされること、自らの心の過程をナルシス的に過大評価すること、思考の万能とその上に築かれる呪術という技法、〔…〕どうやらわれわれはみな、個人としての発達の過程で、原始人のこのアニミズムに対応する段階を経てきたのであり、この段階が〔…〕痕跡を残すことなく経過し去ることは誰にも決してないのであり、今日われわれに「侮気味」と思えるものはすべて、アニミズム的な心の活動の残渣に触れ、それが表現されるよう促すという条件を満たしているようなのだ。〔…〕
この上なく撫気味に思われるものとは、多くの人々にとって、タヒと、タヒ体、タヒ者の回帰、霊魂や幽霊と関わりのあるものである。〔…〕
神経症の男性が、女性の性器は自分にとって何かしら不気味だと断言する、ということがしばしば起こる。この不気味なものは、しかし、人の子にとって古の故郷への入口、誰もがかつて最初に滞在した場所への入口なのだ。〔…〕ある場所や風景を夢に見ている人が、「これは私には見覚えがある。私はここにすでに一度いたことがある」と夢の中で考えるとすれば、それを解釈するために、母親の性器や母胎をもちだすことが許されるだろう。つまり、不気味な(unheimlich)ものとは、この事例にあっても、かつて慣れ親しんだ(heimisch)もの、古くからなじみのあるものである。そして、この言葉に付いている前綴り「un-」は、抑圧の目印なのだ。』
藤野寛・訳「✕気味なもの」, in:『フロイト全集』,pp.35-36,41-42.
「反復」は、多くの場合に「部気味なもの」という感情を伴なってあらわれる。子どもの遊びのように自ら能動的に「反復」する場合を除けば、「つねに」武気味感情を伴なうと言ってよいかもしれません。
しかし、「反復」はなぜ「葡気味」なのでしょうか? フロイトは、それを「抑圧」によって説明します。「反復」は、心の無意識の最奥から浮上してきた傾向です。それは、原始的な心性や、母胎に在った時の胎児の記憶、幼児期の性感情の記憶と同様に、成長した大人にとっては「抑圧」されるべきものなのです。「抑圧」の葛藤が、不安を掻き立て、迫りくる危機に備えてエネルギー水準を高めておこうとするので、正体不明の「不気味なもの」を嫌悪し、自我を防衛しようとする衝動が働くのです。
もちろん、↓下で述べられているように、今日では「克服」したはずの原始的な心性の復活に対して、これを「抑圧」しようとする衝動も働いています。
『蕪気味なものの感情がそこで生まれてくる条件は、見誤りようがない。われわれは――もしくは、われわれの原始の祖先は――かつて、それらの可能性〔事物が人間に対して邪悪な/好意的な意志をもつこと――ギトン註〕を現実のものと見なし、それらの出来事〔事物のアニミズム的なふるまい――ギトン註〕の現実性を確信していた。今日われわれは、そんなことをもはや信じていない。〔…〕とはいえ、これらの新しい〔ギトン註――アニミズムは迷信だという〕確信についてわれわれが完全に自信があるわけではない。古い確信はわれわれの内に今なお生きつづけており、〔…〕捨て去られたこの古い確信に裏付けを与えるかに見える何事かが』起こると『たちまち、われわれは蕪気味なものの感情を抱くことになる。その感情には「なるほど、ただ欲望を抱くだけで他人を刹すことができるとか、タヒ者たちは生き続けており、かつての活動の場では目に見える〔…〕というのは、やっぱり本当なのだ!」などという判断が〔…〕付け加えられることもありうるのだ。〔…〕
体験において舞気味なものが生じるのは、抑圧された幼児期コンプレクスが何らかの印象によって再び生命を与えられ活性化された場合か、あるいは、克服されていた原始的確信が改めて裏付けられように見える場合である。』
藤野寛・訳「✕気味なもの」, in:『フロイト全集』,pp.45-46.
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!