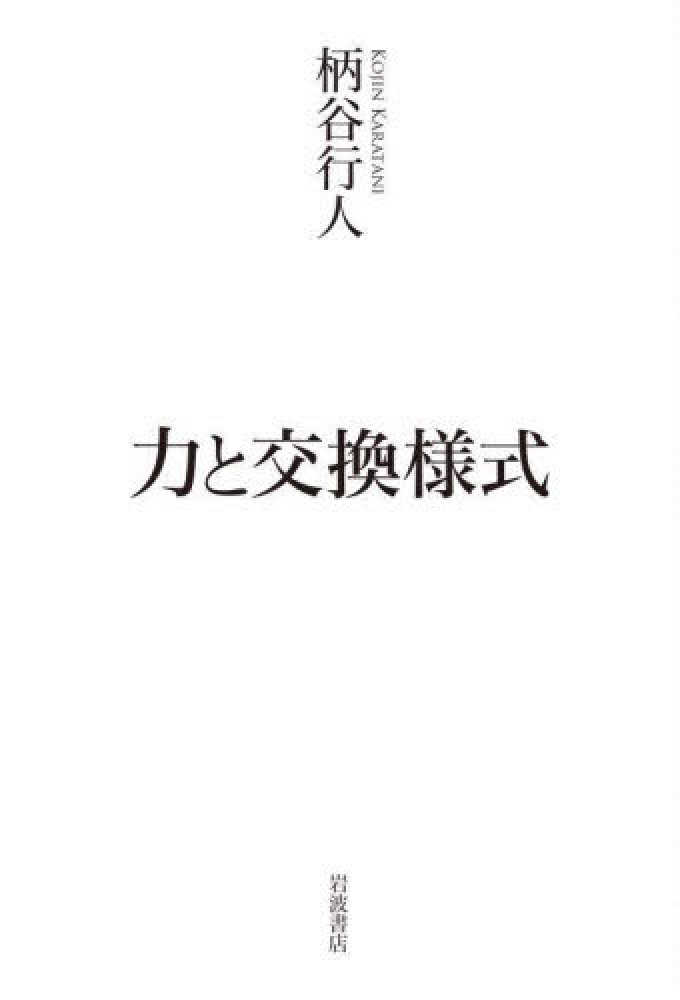ブッシュマン(サン人)の家族 ナミビア、エトスハ自然公園 ©Wikimedia.
【35】 ジーグムント・フロイト――
「トーテムとタブー」
これまでの2回((9) (10))で、私たちは、フロイトの論文に直かに接して、その質実な科学者的探究姿勢に触れてきました。飛躍のない論理によって、当代の人びとの常識的通念から思弁的に仮説を構築し、それを、精神分析治療の実践から得られた経験的事実によって検証してゆく誠実な、しかし目新しい理論を求める読者には限りなく退屈に感じられる歩み。。。
ブロッホ、ベンヤミンをはじめとする “フロイト以後” の多くの文芸批評、社会分析は、フロイトの構築した理論の上に立ってそれぞれの思想を展開しましたが、ブロッホらの考察方法は、フロイトとは対照的に飛躍にみちた絢爛たる闇と光の絵巻です。フロイトがあくまで人間の生理的~心理的構造機能として論じたものの上で、彼らは、世界と社会の哲学を構築しようとしました。そこに、比喩、アナロジーなどのあいまいな方法で橋渡しがなされるのは避けられません。いきおい、彼らの結論は「謎めいて見える」こととなります。そのような「謎めい」た言説を、むしろポジティヴに受け止め、より堅実な社会構造論で裏づけようとしているのが、柄谷行人の「交換様式論」だと言えるでしょう。
私たちにとって、このレヴューの課題は、柄谷氏の「交換様式論」、なかんづく4つの「交換様式」のなかで最も難解な「交換様式D」を解明することにあります。
そこでまず、フロイトの発見した「反復強迫」という心理現象(とブロッホによるその “応用”)を、柄谷氏はどう理解しているのか、この点から始めたいと思います。
『ブロッホがいう “希望”〔…〕とは、「中断され、おしとどめられている未来の道」であり、それを「反復」させるのが交換様式Dから生じる力にほかならない。〔…〕
ブロッホは『ユートピアの精神』〔1918年〕で、フロイトの「無意識」概念に対して、「いまだ意識されないもの」という概念を立てた。そして、この「未意識」こそ、「未来の道」としての社会主義をもたらす、と考えたのである。つまり、共産主義は、人が理想化する〔理想と思う――ギトン註〕社会を意識的に実現することではない。それは、いわば「〔ギトン註――太古の時代に〕中断され、おしとどめられている未来の道」が、おのずと回復されることだ。つまり、未意識とは「反復」にほかならない。
しかし、そのように述べたとき、ブロッホは、ちょうどその頃、フロイトの考えが大きく変ったことを知らなかった。〔『快楽原則の彼岸』の公刊は 1920年――ギトン註〕』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.385-387.
ここには、柄谷氏の読み違えがちょっとあります。ブロッホは『ユートピアの精神』で、フロイトの「タヒの欲動」についても書いています。しかも、彼が『ユートピアの精神』に「いまだ意識されないもの」概念を導入したのは、1921年の第2版からなのです。ブロッホは、後期フロイトの「反復強迫」現象と「タヒの欲動」について知ったうえで、それに基づいて「いまだ意識されないもの」概念を立てた――というのが事実です。
ケニアの遊牧民 マーサイ族 ©Wikimedia.
『前期フロイトでは、父刹し(原父刹し)が最初に置かれる。それは、交換様式でいえばBから出発して考えることに等しい。
しかし、後期フロイトの場合、定住以前の遊動的状態、つまり無機的な状態(U)から出発している。それは定住化とともに失われる。このとき、無機的な状態に戻ろうとする「欲動」が生じた。フロイトはそれを「タヒの欲動」と呼び、快を求める欲動(快感原則)と区別したのである。《反復強迫は快感原則をしのいで、より以上に根源的、一次的、かつ衝動的であるように思われる》〔『快感原則の彼岸』〕
つまり、フロイトがそこに見いだした「反復」強迫とは、〔…〕ブロッホがいう「未意識」に相当するものであった。〔…〕私の考えでは、この問題は、交換様式の観点から見ることによってのみ解明される。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.386-387.
まず、前期フロイトの「原父刹し」ですが、これは、先史時代におけるインセスト・タブー(近親相姦の禁止)とトーテミズムの発生を同時に説明する仮説です。
『ダーウィンは高等猿類の生活習慣から、人間ももともとはかなり小さな群族をなして生活していて、その中ではもっとも年長でもっとも強い男の嫉妬が性的な乱婚状態を阻止していたと推測した。〔…〕青年男性が成人すると、支配権をめぐって戦いが起こり、一番強い者が、他の男たちを刹すか追放するかして、その共同体の首長と認められる』
門脇健・訳「トーテムとタブー」, in:『フロイト全集』12,2009,岩波書店,pp.161-162.
「群族」の支配者である「原父」は、息子たちに、族内の女との性交渉を禁じ、逆らう者は追放する。追放された男も、もし女(たち)を獲得できれば、それぞれが新たな「群族」の「原父」となって支配する。こうして、族内ではインセスト・タブーが支配し、族外婚が制度化されるが、のちに「群族」が血縁家族に分化すると、インセストの範囲も近親間に制限される。
狩猟技術を実演するブッシュマン(サン人)
ナミビア、イントゥ・カラハリ狩猟場
フロイトは、この構想にトーテミズムの起源を重ねます。フロイトの考えるトーテミズムは、「トーテムの供犠」を中心とするものです。部族員は、自分たちの始祖であり神聖な動物であるトーテム(たとえば、熊)を、ふだんはみだりに傷つけてはならないタブーを守っていますが、何年かに一度、饗宴を催して、捕獲したトーテム動物を残酷なしかたで刹し、全員で喰い尽くす。アイヌのイヨマンテに似ていますが、この饗宴は、部族員全員に参加義務があります。
「原父」の支配する群族で『ある日のこと、追放されていた兄弟たちが共謀して、父を殴り刹し食べ尽くし、そうしてこの父の群族に終焉をもたらした。〔…〕そこで彼らは、食べ尽くすという行動によって父との同一化をなしとげ、それぞれが父の強さの一部を自分のものにしたのであった。』
門脇健・訳「トーテムとタブー」, in:『フロイト全集』,p.182.
ところが、「徒党を組んだ兄弟」たちは、「父」に対する矛盾したアンビヴァレンツな感情に支配されていた。彼らは父を憎んでいたが、同時に、父の強大な力を賛嘆してもいた。そのため、憎悪が満足された後は、やりとげた凶行に対する強い「罪責感情が発生した。」そこで、兄弟たちは、父の課していたインセスト・タブーを継続するとともに、父を象徴する動物を「トーテム」と観念して、その刹害を禁止したのです。
こうして、族内では平和が保たれるようになった。そして、一定期間ごとに「原父」を象徴するトーテム動物を全員で刹し食い尽くす供犠を行なって、部族の結束を確認するようになった、と云うのです。
『トーテム宗教とは、息子たちの罪責意識から、この感情を鎮め、侮辱した父を事後的な服従によって宥めようとして出現した試みなのである。これ以降のあらゆる宗教が同じ問題の解決の試みであることは明らかである。〔…〕
精神分析は、トーテム動物が実際には父親の代替物であることを明らかにした。この事実にみごとに合致するのが、トーテムを刹すことはふだんは禁じられているのに、その刹害が祝典となるという矛盾〔…〕である。この両価的 アンビヴァレント な感情的態度は、今日でもなお幼児の父親コンプレクスを特徴づけ、成人の生活でもしばしば続いていくものである』
門脇健・訳「トーテムとタブー」, in:『フロイト全集』,pp.186,181.
カメルーンの音楽狩猟民バカ族の村 © NHK.
このフロイトの仮説は、人間社会の発生を、「一人の強者」の支配から・多数者の相互支配への移行によって説明する発想であり、近代の民主化の歴史を先史に投射したものとも言えます。しかし、その思想的帰結として、「一人の強者」の支配――柄谷氏の「交換様式B」――を、人類にとって根源的なものと見なすことになる点は、見逃せません。
フロイト自身は、後期(1920-30年代)になっても、「原父刹し」のようなエディプス・コンプレクスから社会の発生を説明する『トーテムとタブー』の発想を捨てておらず、後期の「タヒの欲動」をも取り入れながら、人間「文化」の成立と「文化」の問題性を展望しています(『自我とエス』〔1923年〕,『文化の中の居心地悪さ』〔1930年〕)。
しかし、柄谷氏は、後期フロイトの「タヒの欲動」「反復強迫」から、フロイト自身の文明論を超えて、「交換様式D」による社会構造論・変革論を構築してゆくこととなります。そこにおいて柄谷氏が採り上げるキー概念が、後期フロイトの提起した「超自我」なのです。
【36】 ジーグムント・フロイト――
前意識的「自我」と無意識的「エス」
ここで、柄谷氏の主張を、もう一度見ておきましょう:
『後期フロイトの場合、定住以前の遊動的状態、つまり無機的な状態(U)から出発している。それは定住化とともに失われる。このとき、無機的な状態に戻ろうとする「欲動」が生じた。フロイトはそれを「タヒの欲動」と呼び、快を求める欲動(快感原則)と区別したのである。《反復強迫は快感原則をしのいで、より以上に根源的、一次的、かつ衝動的であるように思われる》〔『快感原則の彼岸』〕
つまり、フロイトがそこに見いだした「反復」強迫とは、〔…〕ブロッホがいう「未意識」に相当するものであった。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.386-387.
この部分は、第1部で、原始社会の「交換様式A」について述べた議論の、細部をはしょって再説しているので、飛躍が多くてわかりにくい。第1部第1章「交換様式Aと力」を参照することにしましょう。
『“前期フロイト” の考えには、快感原則と現実原則の二元論がある。快感原則〔…〕は自ら〔ギトン註――生物体〕を危うくするので、それを抑制し断念させる必要がある。それが現実原則である。現実原則とはいわば社会が個人に課す原則である。一方、快感原則は個人の無意識の欲望にある。それは通常、現実原則によって抑制されているが、一定の状況では解放される。たとえば、夢、祭式、戦争などにおいて。〔…〕
フロイトは、〔…〕快感原則および現実原則よりも根源的なものとして反復強迫を見いだした。それをもたらすのは「タヒの欲動」である。フロイトの考えでは、タヒの欲動とは、生物(有機体)が無機質に戻ろうとする欲動である。そして、それが外に向けられたとき、攻撃欲動となる。〔…〕
第1次世界大戦の場合も、〔…〕今日ならPTSDと呼ばれるような戦争後遺症が顕著になっていたのだ。しかし、フロイトがこの戦争神経症者のケースに注目したのは、タヒの欲動が能動的な役割を果たすという側面を見たからだ。つまり、毎日戦争の夢を見てとび起きることが、むしろショックを再現してそれを乗り超えようとする意味をもつ、ということである。〔…〕
それが〔…〕外傷体験を能動的に克服する行為であると考えた。すなわち、この反復強迫はたんに受動的な症状ではなく、能動的な自己治癒の企てなのだ。ただし、能動的ではあるが、意識的なものではない。
このことは、フロイトが『自我とエス』〔1923年〕で超自我という概念を提起したことにつながっている。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.88-90.
↑引用文のなかで、いまひとつしっくりしないのは、第2段落にある「タヒの欲動〔…〕が外に向けられたとき、攻撃欲動となる」という部分と、最後の段落の「超自我」が、それとどういう関係にあるのか、ということです。これらについては、『快感原則の彼岸』ではあまり言及がありませんでした。
自らの生命を否定する傾向が、外部の他の生命体に向かった時に「攻撃欲動」になる、というのは、常識的イメージとしてはわかりますが、ここは通り過ごせない重要な部分です。まず、「超自我」について、上の引用につづく柄谷氏の説明を見てみましょう:
『それに対する概念〔後期の「超自我」に対応する前期の概念――ギトン註〕は初期からあった。たとえば、『夢判断』における「夢の検閲官」〔無意識の性的欲動を摘発して、意識への浮上を阻止する心のしくみ――ギトン註〕である。それは、親を通して子供に内面化される社会的な規範のようなものであった。それは〔ギトン註――「快感原則」とは対立する〕「現実原則」である。
しかし、『自我とエス』〔…〕で明確にされた「超自我」は、それとは異質であった。「検閲官」が他律的であるのに対して、「超自我」はいわば自律的、自己規制的なのである。タヒの欲動を持ち出すことによって、フロイトは、むしろ社会的規範=現実原則を超える「自律性」の根拠を見いだしたのだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.90-91.
人間の心の中に「自律性」があるとしても、それが、たんなる「社会の規範の内面化」であるとしたら、「現実原則」の「検閲官」と異ならないことになります。たしかに、後期のフロイトも、「超自我」にそういう面があることは認めています。しかし、「超自我」は、外部から与えられた規範の「内面化」にとどまるものではない。「超自我」の形成は、人間に、より単純な生命体の生から――生命誕生の時から――受け継がれてきた無意識の衝動に影響を受けている。さらに言うと、社会という広がりを視野に入れて見れば、「超自我」に内面化される「社会の規範」そのものが、社会を構成する人間たちの心奥の無意識の衝動と、何らかの関係をもって成立していないだろうか? この点を少し突っこんでおくことが、柄谷氏の以後の議論を消化するために必要です。
そこで、やや回り路になりますが、『自我とエス』から、フロイト自身の論理を直かに見ておきたいと思います。
まず、↑この図を見ていただきましょう。前回、『快感原則の彼岸』で掲げたモデルとは異なって、「意識」と「無意識」のあいだで、人間の大脳の心的機構は、いくつかの部分に分かれています。下部の無意識的領域には「エス」と書かれています。
この「エス〔Es〕」というのは、ドイツ語の三人称単数中性の人称代名詞で、英語で言えば「非人称の it」です。しかし、英語よりも使用範囲がはるかに広い。たとえば、
Es friert mich.〔It freezes me.〕――私は凍えている。
Es fürchtet mich.〔It frightens me.〕――私は怖い。
のような感情表現があります。「エスが私を凍えさせる」「エスが私を怖がらせる」。あたかも、「エス」という・人間の感情や感覚を支配する巨大な力が存在するかのようです。(〔 〕内は逐語訳で、英文としては誤りです)
この語法に由来して「エス」と呼ばれる心的装置は、人の思想や感情をおおもとで支配する完全に無意識な部分、ということになります。
しかし、「エス」は、単一の原理で成り立っているわけではありません。「タヒの欲動」と、「生の欲動」ないし「性の欲動(エロス,リビドー)」は、「エス」が人の心を支配する2大原理です。
「エス」と「意識」のあいだには「自我(das Ich)」があります。つまり、後期のフロイトによれば、私たちにとっての「じぶん」=「わたし」は、なかば無意識の領域に座しているのです。
「自我」の一部、下よりの位置に「超自我」があり、これは、「自我」の一部が「エス」の影響を受けて分化した部分。いわば、「わたし」を監視し叱責する「わたし」です。
なお、フロイトの原図(『自我とエス』所載)には、「超自我」の場所は描かれていません。のちの『続精神分析入門』〔1933年〕では、上図の「聴覚帽」の位置に描かれます。おそらく、「超自我」の言語表象との結びつきを重視した結果でしょう。しかし、『自我とエス』〔1923年〕の段階では、無意識の「エス」との関係をより強く見ているので、↑上図のように描いてみました。
「自我」と「抑圧されたもの」のあいだにある赤い二重線は、抑圧のブロックです。つまり、「自我」が忘れてしまいたい記憶が、出て来ないように封印しています。「抑圧されたもの」は、「自我」――「わたし」――から完全に分離されているわけです。しかし、「抑圧されたもの」は「エス」の一部になっていて、「エスを通して自我と連絡することができ」ます。(小此木啓吾・訳「自我とエス」, in:『フロイト著作集』,新装版第6巻,2023,p.285.)
フロイトによると、「前意識」(自我)は、「言語」と結合しているという点が、「無意識」(エス)との大きな相違です。
『無意識的表象と前意識的表象(思考)との本質的〔…〕相違は、前者が認識されないままの、なんらかの〔ギトン註――非言語的〕材料によって成就されるのにたいして、後者(前意識的表象)が、言語表象との結合が加わっているという点にある、〔…〕なにか〔ギトン註――外部からの知覚、内部無意識からの感情、など〕が、いかにして意識されるかという問題は、〔…〕なにかが、いかにして前意識的になるかということである。その答えは、それに対応する言語表象〔言語のかたちをとったアイデア――ギトン註〕との結合によって、となるであろう。
これらの言語表象は、記憶の残存物である。言語の残存物は本来、聴覚から生じたもので、このために Vbw 体系〔「前意識」体系すなわち「自我」――ギトン註〕は、ある特定の感覚的源泉〔音声言語?――ギトン註〕に恵まれている。〔…〕
言語表象の役割は、いまや完全に明らかになった。その仲介によって、内部の思考過程は知覚になる。思考が過重な備給をおびるさいには、思考は実際――外部から由来するように――知覚され、そのために真実と〔つまり「自分が考えたこと」だと――ギトン註〕みなされる。
〔…〕われわれは、自我が・その核心である知覚体系 W から由来しているのを知り、記憶の残存物に依存している前意識 Vbw を第1にふくんでいるのを知る。しかし自我もまた、われわれが経験したように、それ自身は意識されない。
〔…〕われわれが自我〔「わたし」――ギトン註〕とよぶものは、人生において本来受動的にふるまうものであり、〔…〕未知の統御しえない力によって「生活させられ」ている。〔…〕われわれは、知覚体系 W に由来する本質――それはまず前意識的である――を自我と名づけ、自我がその中で存続する他の心理的なもの――それは無意識的であるようにふるまう――を〔…〕エスと名づけるよう提案する。
〔…〕個人とはわれわれにとって心理的なエス――未知で無意識的な――であり、自我がその表面に乗っていて、その自我から知覚体系 W が核心として発展する。〔…〕
自我が、知覚―意識 W-Bw の仲介のもとで外界の直接の影響によって変化するエスの部分であり、〔…〕また、自我はエスに対する外界の影響とエスの意図を有効に発揮させるよう努力し〔…〕ている。自我は、われわれが理性または分別と名づけるものを代表し、情熱をふくむエスに対立している。〔…〕
自我の〔…〕エスに対する関係は、奔馬を統御する騎手に比較される。〔…〕騎手が馬から落ちたくなければ、しばしば馬の行こうとするほうに進むしかないように、自我も、エスの意志を、あたかもそれが自分の意志ででもあるかのように、実行に移すことがよくある。』
フロイト,小此木啓吾・訳「自我とエス」, in:『フロイト著作集』,新装版第6巻,2023,人文書院,pp.281-282,284-286.
【37】 ジーグムント・フロイト――
「エス」⇔「自我」対立と、「超自我」の形成
以上が、「エス」(無意識)>「自我」(前意識)>「知覚」(意識)にかんするフロイトの説明です。つぎに、この構造から、「超自我」がどうやって生み出されてくるかが述べられます。
『自我が、知覚体系の影響によって変化したエスの部分であり、精神における現実外界の代表者にすぎないならば、われわれの扱う事態は単純にちがいない。ところが実際には、もっとほかのことがある。
自我の中の1段階、自我理想、あるいは超自我とよばれるべき自我の内部の分化を、〔…〕他の箇所ですでに論じた。〔…〕さらに自我のこの部分が、意識とそれほどしっかりした関係をむすばないという新しい事実が解明されなければならない。』
フロイト,小此木啓吾・訳「自我とエス」, in:『フロイト著作集』,新装版第6巻,2023,人文書院,p.288.
進化の早い段階、つまり生物に「意識」が発生する前の段階では、生物の「こころ」とは、「エス」がそのすべてだったと考えることができます。やがて、動物のある段階で、外界からの影響を綜合してとらえる「知覚」体系が確立すると、「エス」の一部が変化して、「自我」が形成されます。「自我」は、フロイトの比喩で言えば、「エス」という卵黄の上に乗った胚のようなものです。
しかし、人間の場合には、「自我」の中がさらに分化して「超自我(自我理想)」が形成されます。この分化は、人類史のなかでは氷河期(洪積世)に起こり、個人史においては、小児期にエディプス・コンプレクスの放棄とともに起きます。「超自我(自我理想)」は、外界と意識の作用によって形成されるのではなく、むしろ、内部の「エス」(無意識)からの影響を受けて、「自我」(前意識)の中に形成されるのです。
『われわれはメランコリー(鬱病)の苦悩を、失われた対象を自我の中に再現し、したがって対象備給を同一視によって代償する、という仮定から説明することに成功した。〔…〕われわれはそれ以来、このような代償が自我の形成に大きな関係を持っていて、性格とよばれるものをつくる上で重大な貢献をしていることを理解した。』
a.a.O.
近親者や親友、恋人との死別によって「うつ」にふさがれるとき、私たちの心は、失われた人を自分の中に再現し、自分の心の一部を対象と「同一視」することによって、悲しみを埋め合わせようとします。この過程は、無意識に起きる場合もあります。何の悲しみも感じないかのようであり、涙一滴流そうともせず葬儀や財産整理に専心する遺族の行動に、亡き人に生き写しのものを認めたことはないでしょうか? 人の心は無意識のうちに、失われた対象を自分の中に作り上げるのです。
同じことは、小児がエディプス・コンプレクスを断念するときにも起きると、フロイトは言います。父または母への性的欲求の断念は、自分の中に対象を取り入れて欲求を自分に向かわせる自己愛の形成によって容易になります。同時に、(たとえば)母への性的欲求を邪魔する父をも取り入れて、父の権威を自己内化する「同一視」も行なわれます。いずれにせよ、対象への欲求はアンビヴァレンツであり、つぎつぎにさまざまな対象が愛かつ憎の感情に彩られて「自我」の中に沈殿していきます。この混合沈殿が、「性格」を形づくるというのです。
『この同一視は、一般にエスがその対象を棄てる条件なのであろう。ともかく、〔…〕自我の〔ギトン註――「わたし」の〕性格が、棄てられた対象備給の沈殿であり、対象選択の歴史をふくんでいることを理解する助けになる。〔…〕多くの恋愛経験をもつ女性にあっては、彼女の性格の中に対象備給〔過去の恋人――ギトン註〕の残渣を容易に指摘することができる〔…〕
自我が対象の性状を身につけるとき、自我は、いわばエスに対してさえ、愛の対象として関係をむすぶことを強いる。そして「見たまえ。お前は私をも愛することができる、私は対象にそれほど似ているのだ」と言って、対象の喪失を代償することを求める。
このように、対象リビドー〔外部の対象に向かう性的衝動――ギトン註〕が、自己愛的リビドーに変わることは、明らかに〔ギトン註――外部の〕性的目標の放棄をもたらし、非性化、すなわち一種の昇華をもたらす。〔…〕
自我の対象同一視が優勢になり、あまりに多くなり、強くなりすぎて、たがいに不調和になると、病的な結果〔…〕自我に分裂が生じる可能性がある。〔…〕
最初の非常に幼い時代に起こった同一視の効果は、一般的であり、かつ永続的であるにちがいない。〔…〕自我理想〔超自我――ギトン註〕の背後には、個人の最初の最も重要な同一視が隠されているからであり、その同一視は個人の原始時代、すなわち幼年時代における父との同一視である。これは、〔…〕どの対象備給よりも早期のものである。
〔…〕父に対するアンビヴァレントな態度と、母を単なる愛情の対象として得ようとする努力が、男児のもつ単純で積極的なエディプス・コンプレクスの内容になるのである。
エディプス・コンプレクスが崩壊するときには、母の対象備給が放棄されなければならない。そしてそうなるにためは2通りの道がありうる。すなわち、母と〔ギトン註――自分〕の同一視か、父と〔ギトン註――自分と〕の同一視の強化かのいずれかである。後者の結末』で『エディプス・コンプレクスが消滅することによって、男児の性格の男らしさは堅固なものになるであろう。これとまったく同じように、女児のエディプス状況は、母との同一性の強化に〔…〕終ることになり、それが女らしい性格を与える。〔…〕
子供の根源的な両性的素質にもとづいて〔…〕男児は〔…〕、同時に女児のようにふるまい、父に対して愛情ある女性的態度を、母に対しては女性的な嫉妬ぶかい敵対的態度を示す。この両性的素質がたがいに干渉する〔…〕
エディプス・コンプレクスが崩壊するときには、その中にふくまれる4つの傾向があつまって、そこから、父との同一視と母との同一視が生ずる。〔そのそれぞれが、自分を父(母)と同一視して母(父)を愛する/父(母)と同一視された自分を愛する、という二重の「同一視」。――ギトン註〕〔…〕
エディプス・コンプレクスに支配される性的段階の最も一般的な結果として、自我の中の沈殿がおこる〔…〕この沈殿とは、ある仕方で互いに結合した2つの同一視の設立にほかならない。この自我変化は〔…〕、自我理想あるいは超自我として、自我の他の内容に対立することになる。』
小此木啓吾・訳「自我とエス」, in:『フロイト著作集』,pp.288-291.
「自我」における個人の「性格」を形づくる「代償・同一視」のなかで、もっとも発達早期に形成されて強力な力を発揮するのが、エディプス・コンプレクスによる「超自我(自我理想)」の形成だと言うのです。
フロイトは、この論文『自我とエス』では、柄谷氏の期待とは異なって、「原父刹し」(エディプス・コンプレクス)という前期フロイトの枠組みから、あまり隔たっていないようにも見えます。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!