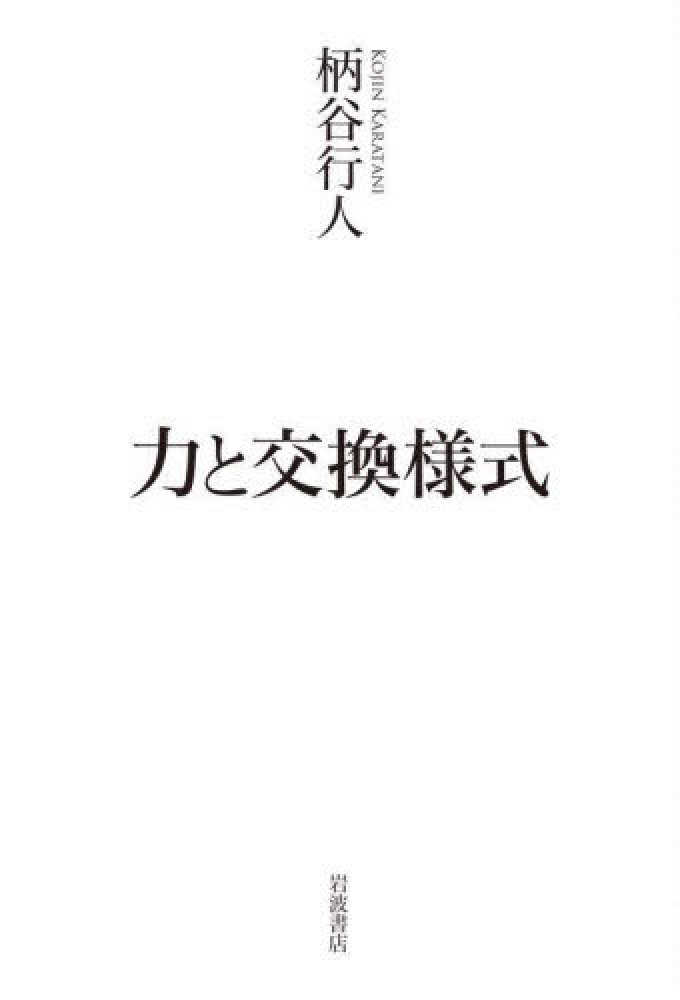イロコイ連邦。東岸インディアン5部族は、1570年頃
連邦国家を結成した。© kg-images / Science Source
【1】 柄谷行人 “畢生の大著” か?――
エンゲルス『ドイツ農民戦争』について
柄谷行人氏の『力と交換様式』については、この大著を読むための入門書まで出ていて、入門書のほうは、すでにこちらでレヴューしました。柄谷行人は読んだことがないという方は、まずそちらを読んでいただきたいと思います。「交換様式A,B,C,D」の説明など、ここではいまさら書きませんので、何それ? と思う方は、迷わず ☞そちら へ。
読書メーター↑を見ても、『世界史の構造』あたりから続けて読んでいるファン読者は、「柄谷もカドが取れたな。こんな読みやすい本を書くなんて…」と言っている。に対し、だいぶ昔の『探究Ⅰ』で挫折した読者は、あいかわらず何のことやらわからない、という感想です。かんたんな用語の約束ごと(ホントにカンタン)くらいは頭に入っていないとチンプンカンプンになります。「わからない奴はサルだ」と(柄谷氏に)言われたくなかったら、まずこちら へ。
さて、この間に私は、マルクス『ザスーリチ草稿』とエンゲルス『ドイツ農民戦争』をレヴューしましたが、じつは、これらは『力と交換様式』を読むための準備でした。
てっとりばやく結論を知りたい読者のために、『力と交換様式』最終の「第4部」からレヴューを始めたいと思います。といっても、「第4部」だけでまた 10回近くかかるかもしれません。
切り口を『ザスーリチ草稿』に置いて、ここから入って行きたいと思います。と、その前に‥
『ドイツ農民戦争』のほうですが、私はちょっと期待外れでした。エンゲルスのこの著作自体はたいへんおもしろいのですが、柄谷さんが言っているようなことは、あまり読みとれなかったからです。
そのことにちょっと触れておきますと、現代のブリックレまでの研究史通覧に付き合ってくださった方にはわかるとおもいますが、「ドイツ農民戦争」という事件の全体像は、エンゲルスが考えていたような「挫折した市民革命」とはかなり異なっているのです。ミュンツァーの「革命神学」が現れて紆余曲折したけれども、全体として見れば、この事件は、平民も参加するような議会制民主主義と地方自治を導入する改革運動だった、それによって、当時の社会つまり封建制を、建て直す運動だった、――そう考えたほうがよいのです。
ところが、エンゲルスはミュンツァーの「革命家」力量を過大評価していて、ミュンツァーが「革命神学」を説いて同志を集め、計画的に引き起こした反乱蜂起が「ドイツ農民戦争」だった。かんたんに言えば、そういうイメージをテーゼにしてぶち上げているのです。もっとも、それは必ずしもエンゲルスを批判する理由にはなりません。何といっても、当時(19世紀半ば)はまだ、十分な史料が発掘されていなかったのですから。
ライプチヒ近郊ヘルドルンゲンのミュンツァー記念像 © mapio.net.
むしろ重要なのは、エンゲルスがなぜそのような歴史把握を志向したか、ということです。エンゲルスは、ミュンツァーの「革命神学」を近代思想に引き寄せて解釈しています。「革命神学」は、ほとんど無神論だ、とまで言っています。ミュンツァーの神学がまとった宗教という「外被」を剥ぎ取ると、そこには、フランス革命を導いた科学的合理主義、自由主義(つまり啓蒙思想)、…それどころかユートピア的社会主義思想までが見いだせます。「農民戦争」当時のドイツには、近代的なプロレタリアートはおろか、市民階級(ブルジョワジー)さえまだいなかったのに、エンゲルスは、近代的啓蒙思想とユートピア社会主義が「革命」を指導したと言うのです。
これは、エンゲルスが『空想から科学へ』で主張したような「科学的社会主義」とは大きく異なるものです。「史的唯物論」にも反しています。しかし、エンゲルスは大まじめです。柄谷氏が注目するのは、そこなのです。
ひとことで言えば、ユートピア思想、ユートピア社会主義、千年王国思想、‥‥そうしたものを否定しては、「社会主義」も「共産主義」もありえない、ということです。ユートピア思想は、柄谷氏の図式で言えば「交換様式D」です。「D」は、「A・B・C」のように自然にそうなるようなものではないが、(「社会主義革命」「社会主義建設」‥によって)人為的・計画的に造成できるものでもない。「生産力の発展」がもたらすものでもない。ある時、思わぬほうから突然やってくる、というのです。
考えてみれば、「ドイツ農民戦争」の勃発は、まさにそういうものでした。ミュンツァーは、たまたま西南ドイツに旅行して「農民戦争」に遭遇し、驚いているのです。フランス革命の「バスチーユ襲撃」、ロシア革命の発端、みな、そういう予想できない突発事件でした。(スイスに亡命していたレーニンは、革命のニュースを知って、あわててドイツ帝国軍部と結託し、封印列車を仕立ててもらってサンクトペテルブルクに乗り込み、革命を簒奪するのです。)ユートピア思想にしても、黙示録のヨハネ、トマス・モアやウィリアム・モリスが最初に得た閃きは、本人も予期しない異様な観念だったにちがいありません。
柄谷氏の考えを私なりに敷衍して言いますと、重要なのは、この最初の突発的な「発端」であって、それこそが「D」です。そのあとに起きる一連の政治的事件は、この「発端」を手前勝手に乗っ取るクーデターであったり(レーニンのように)、「発端」に刺激されたブルジョワジーの改革行動(つまり「交換様式C」)であったりします。
「D」は、人類史のさまざまな時点で、このようにして到来しました。到来によってただちに社会全体を塗り替えたことはありませんでしたが、「D」が到来するたび、人類とその社会は、そこから何がしかのものを受け取り、変化に、あるいは進歩に、役立ててきたのです。
「D」の到来が、いっきょに社会を変革してユートピアを実現するようなことが、将来にあるかどうかはわかりません。未来永劫ないかもしれません。しかし、いつか突然「D」は到来する。しかも一度ではなく、何度でも到来する。そのことだけは間違えないと言えます。
もちろん、このような見方は、「科学的社会主義」に正面から反するものです。「D」の到来は計画できないし、「指導」不可能だからです。しかし、柄谷行人氏によれば、「交換様式D」の解明こそが「社会主義の科学」です。そして、『ドイツ農民戦争』を書いた時のエンゲルスも、おそらくそう考えていました。(すぐあとで『空想から科学へ』を書いて真逆を向いてしまいますが)
イロコイ族の村
【2】 原始社会における「個人の自由」
――『ザスーリチ草稿』を切り口に
『マルクスはザスーリチへの返事を書いたころ、まだ共同体について十分に考えていなかった。
以後、彼はモーガンの『古代社会』を考察するなかで、それを考えた。彼はすでに『資本論』で、資本主義経済の鍵を、生産様式でなく交換様式において見ようとしたのだが、氏族社会を見るとき、それと類似するやり方をした。つまり、『資本論』において交換様式Cに焦点を当てたように、『古代社会』の考察では交換様式Aに焦点を当てたのである。〔…〕
マルクスが、〔…〕真に称賛に値するものとして〔ギトン註――氏族社会に〕見出したのは、成員個人の対等性と独立性という側面であった。
イロクォイ族の氏族のすべての成員は、人格的に自由であり、相互に自由を守りあう義務を負っていた。特権と人的権利においては平等で、サケマ(族長)や首長たちはなんらの優越も主張しなかった。それは、血族の紐帯で結ばれた兄弟団体だった。自由、平等、友愛は、かつて定式化されたことはなかったとはいえ、氏族の根本原理であった。(マルクス「モーガン『古代社会』摘要」, in:『マルクス・エンゲルス全集』,補巻4,1977,大月書店,pp.257-474.)
つまり、マルクスが重視したのは、氏族社会における諸個人の平等や相互扶助のみならず、諸個人の自由(独立性)であった。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.348-349.
個人間の関係が平等かそうでないかということは、考古学でも文献史学でも比較的に確認可能なことですが、「個人の自由」「独立性」ということになると、なかなか客観的評価は難しくなります。現存の未開種族の人類学的なフィールドワークならば、観察による評価ができるかもしれませんが、他の種族、あるいは文明社会の個人と比較するとなると、やはり客観的な結論は出にくいと思います。
しかし、だからといって、未開社会における「個人の自由」「独立性」がどうであったかという重要な問題を、分からないとしてすますわけにもいきません。
また、一般的には、古い時代ほど、また未開な社会ほど、共同体への成員のきづなは強く、個人の独立性は弱い――と考えられています。ところが、柄谷氏は、また、マルクス,モーガンも、国家成立以前の未開社会のほうが、成立後の文明社会よりも個人の自立度が高く、人間は自由であった――と考えているようです。
“共同体の拘束が強い・古い時代ほど、個人の独立性は弱く、成員は不自由だった” ――という歴史の見方は、現在では社会科学の常識かもしれません。しかし、そのような常識が広まったのは、それほど古いことではないのです。テンニース『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』〔1887年〕あたりが画期だったのでしょう。
「ゲマインシャフト(共同社会,共同体※)」は、地縁,血縁,友情などで自然発生した社会集団。親族の集団や、ひとつの町、ムラ、国家、といった集団です。人間は「ゲマインシャフト」を選べない。生まれると同時に「ゲマインシャフト」の成員となる。あるいは気づかないうちに、仲良しグループなどの「ゲマインシャフト」の成員となっています。
「ゲゼルシャフト(利益社会)」は、意識的に組織したり加入して成員となる集団です。典型的なのは「会社」。テンニースは、大都市も「ゲゼルシャフト」に分類しました。移入・転出が自由ですし、成員の行動が利害・打算に基いているからです。「ゲゼルシャフト」は近代的な社会類型です。
註※「共同体」: 「共同体」と訳されるドイツ語は、じつは2つあります。「ゲマインシャフト」と「ゲマインデ」です。「ゲマインデ」のほうは、実際に存在する部落,地区,市町村のような団体です。「住民団体」「地域団体」と訳したほうが適切かもしれません。対して、「ゲマインシャフト」のほうは、学者が「この集団はゲマインシャフトだ」と指称する分類概念,タイプ概念です。『ドイツ農民戦争』レヴューでは、諸著者の引用文でも私のト書きでも、「共同体」は「ゲマインデ」の訳語でした。「ゲマインシャフト」と「ゲマインデ」は、かなり意味が違うのに、日本の翻訳者は、区別せずに「共同体」と書いていることが多いので、注意が必要です。
テンニース『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』が述べる: 古代・中世→近代/ 共同体→利益社会 という図式が通説化するにつれて、個人は、近代で初めて自立し、自由になった※。近代以前には、中世,古代,原始時代‥と古くなればなるほど非自立で不自由だった――という “常識” が形成されたのでしょう。
註※「近代化と個人の自立」: この図式(じつは疑わしい)は、日本史学でも常識化しています。この常識化を押し進めたのは、桃山・江戸時代に関する安良城盛昭氏の「小経営自立説」です。太閤検地によって農民は自有耕地を確保したので「自立」した、「自立」したから、江戸時代の高率の年貢を負担できた、と言うのです。これに対して、網野善彦氏ら中世史家は頑強に抵抗しました。江戸時代の農民よりも、戦国時代までの農民・遊動民のほうが、自由で自立的であったからです。とくに女性の自立が顕著でした。ここでは日本史に深入りしませんが、注意したいのは、安良城氏は、唯物論というより偏狭な物質主義で歴史を見ていることです。
しかし、マルクスとエンゲルスが著作活動や抄録研究をしたのは、テンニースより以前だったのです。“前近代=共同体/近代=自由・自立” という常識を、彼らは持っていません。彼らは、モーガン『古代社会』から、未開社会では「個人が自立し、自由だった」という論証を読み取って、すなおに受け入れたのです。
『この原理〔未開氏族社会における諸個人の自由(独立性)――ギトン註〕は、かならずしも生産手段の共同所有ということから来るものではない。むしろ、その逆である。
たとえば、「アジア的」な農耕共同体でも、生産手段は共有されているけれども、そこに氏族社会※のような個人の独立性はない。〔…〕下位にある集団は上位の権力に従う。
一方、生産力から見てより未開である氏族社会※では、下位にある個々の集団が上位に対して半ば独立している。それをもたらすのが互酬交換、つまり、交換様式Aである。それが「兄弟同盟」をもたらすとともに、集権的な国家の成立を妨げるのだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.349.
註※「氏族社会」: 柄谷氏がモーガンとマルクスにしたがって「氏族社会」と呼んでいるのは、北米インディアン・イロクォイ族の社会、ギリシャ人・ローマ人・ゲルマン人の(都市)国家形成期までの社会です。つまり、「未開社会」とほぼ同義と考えられます。日本史で言えば、弥生・古墳時代(縄文は「氏族」以前!)、地域によっては飛鳥・奈良時代の「首長制」社会まで含むでしょう。そうすると、「アジア的な農耕共同体」は、奈良ないし平安時代以降、中国では秦漢以降、となるでしょうか。
つまり、人間は生産力の発展とともに自由(自立的)になったのではない。「アジア的」専制国家のもとでは、それ以前の「氏族社会」にはあった「個人の自立」が奪い去られ、人は不自由になった。いささか図式的なイメージで言いますと、「アジア的」専制皇帝は、人びとを動員して大規模な灌漑工事を行ない、砂漠を沃野に変えた。それによって生産力は飛躍的に発展した。しかし、強制動員の過程で人びとは、「氏族社会」で持っていた「個人の自立性」を失い、発展した農業生産力に満足し、収穫の大部分を貢租として奪われても、専制皇帝を讃えながら喜んで上納した。自立性を失った農民たちは、収税を効率的に行なえるように耕作地・居住地に緊縛され、「自由」を失った。このようになるでしょうか。
もちろんこれは、図式的マンガです。一口に水利灌漑工事と言っても、農民たちが自発的に灌漑・治水を行なって、集団的な自立性を発揮した自国の多くの例を、私たちは知っています。それらの史実を留保しつつも、柄谷氏とマルクスの・このテーゼを、とりあえず受け入れたいと思います。「原始社会のほうが個人は自立し自由だった。アジアの(日本も!)古代・中世専制国家のもとで、自由と自立を奪われた」というテーゼは、否定してしまうにはあまりにも魅力的だからです。
『たとえば、マルクスが注目したのは、モーガンが氏族社会の議会について述べた所である。《氏族はその首長たちによって代表され、部族は諸氏族の首長たちの評議会によって代表されていた。――イロクォイ族にあっては、全員一致が評議会の決定の根本法則であった。軍事作戦は、通常は志願の原理による行動にゆだねられていた》(同前)
ここから見ると、アテネのデモクラシーが、アジア的国家を脱する文明の産物ではなく、氏族社会を受け継ぐ「未開」の産物であることがよくわかる。〔…〕その意味で、未来の共産主義を考える鍵はギリシャではなく、それ以前の氏族社会にある、といわねばならない。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.350.
このイロクォイ族の議会も、「個人の自立」の現れかというと、議論の余地はあると思います。「首長」の下の氏族内については、どのように意見がまとめられるかは各氏族にゆだねられている、つまり、「首長」の専断で決まる場合もあるということです。「全員一致」も、かならずしも民主的ではありません。「多数の圧力」がより強く働くシステムだ、とも言えるからです(日本中世の「一揆」では、無記名投票の多数決でした。これがほんとうの民主主義です)。もっとも、逆にこうも考えられます。「評議会」が「全員一致」なのは、首長が自分の氏族の意見と異なる結果を氏族に持ち帰れないからだ。それだけ「首長」の権限は弱く、氏族員の意見が優先する。そういうわけで、はじめに指摘したように、氏族社会の「個人の自立と自由」を証明するのは、なかなか難しいものがあるのです。
【3】 マルクスの共産社会プログラム
――「個人的所有」の謎
前節の引用で柄谷氏が、「未開社会の自由・自立は、生産手段の共有から来るものではない。」と言っていることも重要です。このことは、社会主義、ないし共産主義社会のプランにもかかわります。史的唯物論では、未来の共産主義は、原始共産主義社会の「高次における再現」とされます。原始共産社会では、人びとは自由で平等であり、財産は共有でした。そこで、未来の共産主義社会についても、マルクス以後の「マルクス主義」者たちは、私有財産の廃止ということを強調します。その前段階として、生産手段(土地など)を共有ないし国有にする「社会主義」を唱えます。
しかし、生産手段を共有にすれば、自由で平等な社会になるかというと、そうではない。たとえ経済的に平等であっても、「個人の自立」ないし独立性が無ければ、民主主義にも自由にもならないからです。このことを歴史的に例証しているのが「アジア的」専制国家のもとにある社会だ、と言うのです。古代・中世のアジア諸国では、土地は多かれ少なかれ共有ないし国有だった(日本古代なら、「班田収授法」があった)。にもかかわらず、そこには「個人の自立」も「自由」も無かった、というわけです。
「正倉」群の址と復元画。「武義郡衙」址。弥勒寺東遺跡。岐阜県関市。
「正倉」は、収税した「租」穀を貯蔵する倉庫。「租」穀は地方に備蓄
されたので、各地の國衙・郡衙には「正倉」が立並んで威信を示した。
『共産主義は、たんに国有化あるいは共同所有化によって成り立つのではない。それは、いわば「個人的所有」(私的所有と区別される)を確立することによって成立する。マルクスはその例を氏族社会に見出した。〔…〕
マルクスは「古代社会」(氏族社会)に関して、私的所有と個人的所有の区別を重視した。〔…〕マルクスは『資本論』でも、次のように私的所有と個人的所有を区別していたのである。
資本主義の生産様式から生じる資本主義の取得様式は、したがって資本主義的私的所有は、個人的な(individuell)・自分の労働に基づく私的所有・の第1の否定である。だが、資本主義生産は、一つの自然的過程の必然性をもって、それ自身の否定を生み出す。すなわち否定の否定である。それ〔否定の否定――ギトン註〕は、生産者の私的所有は再建しないものの、それでも※(wohl aber)資本主義時代の成果を基礎とする個人的所有(das individuelle Eigentum)を再建する:すなわち、協業、ならびに、大地・および・労働そのものによって生産された生産手段・の共同占有(Gemeinbesitz) 〔を基礎とする 個人的所有を再建するのである。〕〔『資本論』, MEW XXⅢ, S.791.〕
マルクスが晩年に『古代社会』について論じたとき、このような「個人的所有」と「私的所有」の区別が念頭にあったはずである。つまり、共産主義とは、たんに私的所有の廃棄であるだけでなく、個人的所有の実現にもとづくものである。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.350-351.
註※「~ものの、それでも」: この「wohl aber」は熟語で、「~ではあるが、しかし」「~ではあるものの」という譲歩的な強い逆接。独和辞典に書いてある初歩的知識です。大月書店版全集の「おそらく」は誤訳。
つまり、未来の「共産主義」社会において、個人は無所有になってしまうわけではない。むしろ、資本主義の “勝利” ――原始的蓄積!――によって奪い取られた「個人的所有」を取り戻すのだ。賃金奴隷に転落させられていた労働者も、小作人の境遇に落されていた農民も、自分の個人としての「所有」を取り戻す。それが共産主義だ。マルクスの考えていたことを言いかえると、そうなるでしょう。
↑『資本論』からの引用部分は、このブログでの引用は、もう3回目になるでしょうか。前回は斎藤幸平さんの『ゼロからの資本論』(3)〔9〕 で引用しました。引用するたびに、内容がすんなり頭に入るようになっています。とともに、訳文に不満を感じるようになりました。なので、今回は、柄谷さんの出している大月書店版全集を鵜呑みにするのでなく、MEWを参照して自分でかなり手を入れてみました。
かんたんに説明しておきましょう。人びとの各人が「個人的所有を取り戻す」という「共産主義」のプランを構想するにあたって、技術的問題としてどうしても避けて通れないのが、資本主義によって達成された「社会化」の成果をどう継承するかという難問です。
資本主義以前には、短い期間でしたが(社会全体に行きわたったわけでもない)、独立・小生産者の時代がありました。ひとり親方の手工業者、あるいは独立自営農のような人びとです。自らの労働によって生産し、商品交換を通じて自らの生存を維持する。誰にも搾取されないが、誰からも搾取しない。そこには、人間の本来のあり方があります。「個人的 individuell」という語は、in-dividu-ell(分断 dividu されない)と解析することができます。人間が社会的圧力で解体されることなく、全人的に自己実現する。その基盤となる経済的条件が「個人的所有」なのです。資本主義に先立つ段階で、独立小生産者たちは、これを、勤労者の「私的所有」という形で実現していました。
「ロビン・フッド」のコスチューム。ロビン・フッドは、中世末
イングランドの独立自営農(ヨーマン)が伝説化されたキャラクター
しかし、「私的所有」には競争があります。「私的所有者」は自由ですから、競争に負ければ自分の財産・生産手段を売り渡して労働者に転落していきます。これが「第1の否定」。
資本主義は、発展していけば必然的に、自分のうちに秘めた矛盾が爆発して次の生産様式――マルクスによれば社会主義――に移行します。ホントに「自然的過程」でそうなるのかどうか知りませんが、マルクスはそうなると考えていました。これが「否定の否定」。
ここで大きな困難が起きます。小生産者が競争に負けて売り渡した作業場を、勝った資本家が買い集め、労働者を派遣して働かせているだけなら、「否定の否定」はカンタンです。資本家を追放して元の状態に戻せば、作業場の持ち主各個人の「所有」が回復します。ただし、「私的所有」を再建すると、また競争になって資本主義になる。悪夢を繰り返すだけですから、この点は変えないとなりません。
しかし、じっさいには資本主義のあいだに「産業革命」が起きています。巨大な溶鉱炉や、たくさんの装置がパイプでつなげられた化学工場。こんな巨大装置を分割して労働者各自が所有する、などということはできません。装置だけではない。近代企業は、各部門が有機的に統制されて初めて動くものです。けっきょく、資本主義産業を、小生産者の群れに戻してしまうことはできないのです。
「個人的所有」を再建しなければならない。しかしそれは、「資本主義時代の成果を基礎とする」ものでなければならない。そこでマルクスの考えたプランが、「コロンすなわち」以下です。文構造が晦渋で難物なので(マルクスが苦しんでいる様子がわかります)、図示しましょう↓
上の私の訳では「共同占有」としましたが、図は斎藤さんの訳なので「コモンとしての占有」になっています。しかし、重要なのは全体としての「個人的所有」の内容です。
まず、「協業」は資本主義時代と同様になければなりません。各自が勝手に親方をやっていたのでは巨大装置は動きません。「大地」つまり人間の手が加わっていない森林や山々(鉱山)、川の水、そういったものは〈コモン〉とする。つまり、誰のものでもない。誰でもが使える代わり、誰も独り占めすることはできない。そういう利用のしくみをつくる必要があります。
「大地」も生産手段、つまり生産に無くてはならないものですが、溶鉱炉や工場装置、原料、輸送手段のように、人間が造った生産手段もあります。マルクスは、これらのものも〈コモン〉にしようと言うのです。
この点を私なりに解釈すると、日本で古くからある「入会 いりあい 権」というのが、「コモンとしての占有」の一つの可能性になると思います。「入会権」のようなものは、アジアでもヨーロッパでもどこの国にでもあります。近代的私的所有の「共有権」とは異なるものです。どこが違うかというと、「入会権者」は、自分の持ち分を処分することも払い戻すこともできません。しかし、出入りは自由です。誰か外の人間が入会権管理団体に入れば、自動的に「入会権」を取得し、転出すれば自動的に失います。もちろん、入会権管理団体が多数決で決議すれば、管理のしかたを変えたり、改修したり、また、処分して新しい工場を建てることもできます。
「小繋事件」百周年記念碑。岩手県一戸町小繋。明治の地租改正で、山林が個人の
私有地となり、住民は入会山へ入れなくなった。入れば森林法違反で逮捕された。
住民は 1917年と 46年に出訴したが、裁判所は「入会権」を認めなかった。
『私の考えでは、「個人的所有」という概念は、1840年代にマックス・シュティルナー※が唱えた「唯一者とその所有」と関連するものである。唯一者は、〔…〕個々の人間に存する人格の独自性・自律性を意味する。たとえば、通常エゴイストが他者と連合することはない。しかるに、〔…〕唯一者は、というより唯一者のみが連合しうるのだ。〔…〕
マルクスは、モーガンの『古代社会』を読んで、個人的所有に基づく共有〔正確には、「共同占有に基づく個人的所有」――ギトン註〕、つまり、共同体に従属しない「唯一者」たちの連合によって、それまでの共同体とは異質な共同体が成り立ちうることを悟った。モーガンはいう。《政治における民主主義、社会における友愛、権利と特権における平等、そしてまた普通教育は、経験、知性、および知識が着々とその方向をとっている次代の・より高度の社会を示している。それは古代氏族の自由、平等および友愛の・より高度の形態における復活であろう。》(『古代社会』下巻,岩波文庫)
マルクスがこのとき考えたのは、未来の共産主義が、“アルカイックな社会の高次元での回復” だということである。〔…〕
それは次のようなことを意味すると言ってよい。国家の揚棄は、交換様式Aを “高次元で回復する” ことによってのみ可能である。〔…〕A の “高次元で” の回復とは、D の出現にほかならない。
また、ここで重要なのは、D は人間の意志あるいは企画によって到来するものではない、ということである。それはいわば「向うから来る」。その意味で、』「向うから来る」D『の存在を明らかにすることが、「社会主義の科学」にほかならない。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.351-353.
註※「マックス・シュティルナー 1806-1856」: ヘーゲル左派の哲学者・ジャーナリスト。主著『唯一者とその所有』。エンゲルスも、「私たちはシュティルナーの到達した地点から出発しなければならない。」として、「利己主義による共産主義」を唱えている。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!