- 法律入門 判例まんが本〈4〉憲法の裁判100/辰已法律研究所
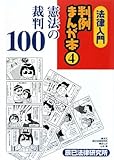
- ¥1,575
- Amazon.co.jp
重要判例を4コママンガにした教材です。
判例の事案を具体的にイメージするのは意外と難しいものです。
こういった教材で、絵の形で頭に焼き付けると印象に残りやすいと思います。
所詮はマンガなので、勉強のメインに位置付けるべき教材ではありません。
ただ、勉強の合間などにパラパラと眺めるのにはちょうど良いアイテムです。
憲法・行政法などはおすすめです。
おすすめ度⇒B
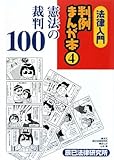
重要判例を4コママンガにした教材です。
判例の事案を具体的にイメージするのは意外と難しいものです。
こういった教材で、絵の形で頭に焼き付けると印象に残りやすいと思います。
所詮はマンガなので、勉強のメインに位置付けるべき教材ではありません。
ただ、勉強の合間などにパラパラと眺めるのにはちょうど良いアイテムです。
憲法・行政法などはおすすめです。
おすすめ度⇒B
かつて辰已 で人気講師だった人です。
現在は独立して新たな予備校を起ち上げられたようです。
辰已時代の途中の頃までは、各科目の基本原理を教えるのがとても上手な先生でした。
特に、いわゆるベテラン受験生を合格まで導く“あと一歩”の指導に定評がありました。
旧司時代の受験界には、受験年数や受験資格に制限がなかったこともあって、悪い意味で「実力者」と呼ばれる長期受験生が現在とは比較にならないほど大量に存在していました。
彼らの知識過多やハイレベルな勉強態度に戒めを与え、そういう「実力者」ほど基本が抜け落ちているという正当な事実を指摘→矯正していたのが、当時の北出講師でした。
ところが、ロースクールが設立され新司法試験が施行されたあたりから、北出講師の講義は年を追うごとにどんどんハイレベルになっていきました。
放っておくと、だいたいみな自然にそうなっていきます。
現在の司法試験制度では、受験年数や受験資格に制限があるため、旧司時代とは比較にならないほど受験生の知識レベルは落ちました。ハイレベルな勉強もほとんど不要になったはずです。
にもかかわらず、北出講師はこのとき、受験生のレベル低下とまるで反比例させるかのように、自身の講義レベルを上げていってしまったのです。
もちろん、問題の絶対的難易度、つまり、完全解を作成する難しさの点で、新司が旧司よりハイレベルになったのは事実です。しかし、司法試験は相対的評価の試験です。問題の難度が上がったからといって、即、講義(受験生に要求すべき内容)の難度まで上げるべきということにはなりません。
北出講師や羽広講師などのベテラン講師は、このとき完全に方針を誤ったと私は思っています。
彼らはおそらく、受験生のレベルに合わせるのではなく、問題の難度に合わせる形で講義レベルを上げてしまったのでしょう。
講師として、本来は受験生の相対的レベルを見なければならなかったはずなのに、新しい制度のもと、新しい試験が目の前に突然現れたことで、きっと我を忘れて浮足立ってしまったのだろうと思います。
私自身はこのとき当事者(=受験生)だったので、旧司型の論文問題さえ満足に書けないままロースクールに鞍替えしていった友人たちが、あんな大長文問題を、北出講師や羽広講師が要求するような水準で処理できるわけがないことくらい、簡単に予想できました。
当事者目線さえしっかりと持っていれば、こんなのは少しも難しい話ではなかったのです。
ともあれ、このように、司法試験受験生のレベルがかつてよりも大幅に下がったロースクール時代になって、その些か拘りぬいたハイレベルの講義内容と、受験生の実質的需要との間には、大きなズレが生じてしまったように思います。
辰已時代の終わりあたりでは、ガイダンスや講義で新司の難しさを無用なまでに強調し、新司用の特別な対策なしに合格は覚束ないと説く典型的な講師になっていました。
この認識が誤りであったことは、現在の予備試験合格者の司法試験合格率をみれば明らかです。
司法試験に合格する実力は、予備試験に合格する実力にほんのちょっとスパイスを加えるだけで十分身に付けることができます。
こんなことは別に「後だしジャンケン」でも「蓋を開けてみれば・・」という話でもなく、わたし程度の人間にすら、最初から100%の確信をもって予想できたことでした。
私には、北出先生ほどの人になぜこんな簡単なことが分からないのだろうか・・・と、当時、彼の講義を聴きながらとても不思議な思いがしたのを覚えています。
現在の受験生には、この「不思議」の感覚はもはや分からないでしょう。
新司法試験およびロースクール設立という事態は、このように多くの優秀な受験生や講師たちの判断を大きく狂わせてしまうほどの巨大なインパクトだったのです。
現在はどういうレベルで講義をされてるのか分かりません。
受講される方は、以上の経緯を参考にして慎重に判断してください。

・司法試験に興味を持った方
・これから司法試験の勉強を始める方
・なんとなく入門講座を受け始めてしまった方
・なんとなくローの未修に入学してしまった方
こういった方が、まず最初に読むべき本として一番におすすめしておきます。
司法試験という試験を、手っ取り早く網羅的に知るのに最適の本です。
すべての司法試験初心者に。
おすすめ度⇒A

刑訴の入門書です。
この「ブリッジブックシリーズ」は、科目によって出来やコンセプトがバラバラで、全体をまとめた評価はしにくい教材です。
たとえば、憲法は入門書というより一般書みたいな感じです。法学の入門書としては使えません。
民訴は入門書にするには少し高度です。
本書(刑訴)は、分かりやすい入門書としておすすめです。
知識ゼロレベルからでも十分に読めると思います。
2色刷りかつ分かりやすい記述で、初心者でも集中して読めば3日前後で終えられます。
私も初学者の時に何度も何度も読んで、刑訴の土台作りをしました。
予備校の入門講座を受けていなくても、本書を何回か読んで完全に身に付ければ、入門卒業レベルに到達できると思います。
おすすめ度⇒B

刑訴の概説書です(ギリギリ基本書にもなるかなと思います)。
福井先生は別にもっと厚い正真正銘の基本書も出しておられますが、本書が一番出来がいいテキストだと思います。
コンパクトですが、けっして無味乾燥ではなく、記述は分かりやすく読みやすいです。
定義などの確定的な概念から出発して各論点の説明に至る文章の運びが上手いです。
通読に適した教材だと思います。
人権擁護に傾いた学説っぽい学説を採られている部分も多く、通説と異なる部分もありますが、その辺に注意して読めばとても良いテキストだと思います。
おすすめ度⇒B