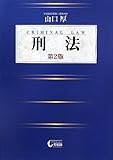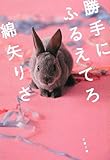今日は雑談です。
少し自分のことについて書きます。
先日、弁護士の友人に、私が正直に未修入学者であることなどの事実を書いているにもかかわらず、未だに私の属性を知りたがる人が後を絶たないことをボヤいたところ、
その友人曰く、
「その気持ちも分かる気がする」
「きっとみんな、そんなわけないだろ、って思ってるんですよ」
ということでした。
つまり、私の方法論は、未修ロー生の常識的レベルを遥かに超えており、経歴自体に嘘があると考えなければ、普通の受験生は納得できないものだということです。
よって、「お前はいったい何者なんだ」という疑問が生じるのも無理はない、とのことでした。
まあ、そう言われれば、たしかに私は少し(というか、だいぶ)アブノーマルなんでしょう。私のことを直接知っている友人たちは、そういう私の特性を時間をかけて理解してくれたので、中には合格間近の段階になっても、初学者レベルの私にアドバイスを求めてくる人もいました。私のほうも、何の疑問もなく、自分より数段上の実力者に「指導」を与えていました。
ちなみに、私自身の経験から、これは試験勉強のみならず人間存在の真実だとさえ思っていますが、属性よりも内容を重んじて、自分より遥かに格下の人間に平気でアドバイスを求められるような人は、受験生云々以前に、人間として極めて優秀です。司法試験でいえば、そういう人は100%合格します。
もちろん、人の属性が気になって仕方がない人でも、確率的には合格しますので安心してください。
ここが1000人以上も受かる試験の甘いところです。
え~と、なんの話でしたっけ・・・あぁ、私がアブノーマルだという話でした。
とにかく、そのことは自分でも自覚しています。
以前、コメント欄に、「もの凄く勉強されているのは確かだと思う」みたいなことを書かれたことがあり、こういうコメントを読むと、自分が買い被られている気恥ずかしさとともに、根本的なところから自分が誤解されていることを痛切に感じます。
正直いうと、ブログで自分語りみたいなことをするのは趣味ではないのですが、誤解されたままというのも何だか気持ち悪いですし、それ以上に皆さんに申し訳ないので、私がどんな風にアブノーマルなのかを少しだけお話しさせていただきます。
その前に、「経験」と「発言権」は有因か無因か というエントリーをご覧いただけると幸いです。
ここで私の見解に賛同できない方がこのブログを読むのは時間の無駄です。
なにせ、受かっていない人間が書いてるんですから。
でも、ここまで親切に申し上げても、やっぱり気になって読んでしまう人がいるんですよね。
なんでなんでしょう? 私自身は気に入らないブログを読むことなんてまずあり得ないのに・・・。
そういう人の精神構造は理解できませんが、まあ、やっぱり自分に自信がなくて不安なんでしょうね。
********************
私は大学卒業後、アメリカ留学をしていて時機を逸したこともあり、就活はせずに父親の経営する会社に籍を置きました。仕事は事務関係が中心でした。
どうでもいい話ですが、よく法務局に登記をもらいに行ったり、手形の受取に行ったりしてました。
年齢にそぐわないお金もらい、休みもたくさんあって、私は趣味に遊びに精を出していました。
言われるまでもなく、相当に恵まれた環境にいたと自覚しています。
ただ、当初から、いつかは独立して何か自由にできる仕事がしたいという希望がありました。
それで司法試験を始めることにしたわけです。もう10年近く前のことです。
伊藤塾の呉先生の基礎マスターを、まずは憲民刑だけとりました。
同時に、既卒者メインで構成されたゼミ(勉強会)に参加しました。
この勉強会、一人だけダブってる東大生を除けば全員が既卒者で、塾講をやっている人から専業受験生まで身分は様々でしたが、総じて優秀な人が多く、今まで6~7割くらいは合格したかなと思います。
ここで私のアブノーマルな部分に火が付きます。
生来の凝り性である私は、司法試験についても、誰よりも貪欲に情報の摂取を始めました。
私より何倍も司法試験に詳しい人がたくさんいることが、私の情報への食欲に拍車をかけました。
試験情報・教材情報・予備校情報・勉強方法etc…について、私が玄人レベルに到達するのに1年くらいしかかからなかったと思います。
このブログにアップしている教材情報なんて、1年もあれば摂取できるレベルのものです。
別に中身をほとんど読んでいなくても、この程度の内容なら書ける人はたくさんいるでしょう。
そうやって、気がつくと私は、ゼミ内でも2番目くらいの司法試験の「玄人」になっていました。
もっとも、そのこと自体はいつものことでした。
私は他人よりも些か凝り性な性格で、何か特定の分野に興味を持つと、とにもかくにも情報を摂取し、関連分野の書籍を漁りまくる行動に出るのが常でした。別に司法試験だけに詳しいわけではなく、一言でいえば「そういう奴」なだけなのです。
・・・と、ここまでは、まだまだ普通でした。
受験界には、こういう司法試験オタクは数多く存在しています。
【勉強法オタクは受かりにくいか?】
司法試験や他の試験で「勉強法オタクは受かりにくい」と言われることがよくあります。
その考え方は、大雑把にいえば次の2つに分類できます。
【1】勉強法無効説
一つ目は、勉強法は無力(無効)だという考え方です。
この説の支持者は、昔ながらの努力至上主義的な考え方をとても大事にしています。
つまり、①方法と②努力でいえば、試験の本質は努力(②)にある、というのです。
皆さんの周りにも、口を開けば「しょせん勉強は努力だよ」と言う受験生はたくさんいるはずです。
(1)無効説の支持者は、人生のどこかで努力至上主義によって成功を得た体験がある人が多いです(特に難関私大の出身者)。たった一度の成功体験によって人生の選択の柔軟性を失ってしまうことは、試験に限らずよくあることです。
(2)また、勉強法で一度痛い目をみた(と勝手に思っている)人も無効説の支持者になることが多いです。彼らは、自己の経験則によって勉強法にダメだしをします。
【2】勉強法有害説
二つ目は、勉強法を考えると努力をしなくなるため、試験に受かりにくくなる、という考え方です。
つまり、①方法と②努力を有因関係と捉え、更に、①から②への悪影響が存在すると考えるのです。
予備校講師がこの有害説を主張することが多いです。彼らは、勉強法に一定の有効性を認めながらも、勉強法に拘ると勉強しなくなるからダメだと警告します。しかし、彼らの大半は、そもそも努力中心主義で合格した勉強法の素人たちです。ゆえに、受験生の方法論的観点からの疑問・批判に対して有効な助言・反論をすることができません。彼らが勉強法の有効性を認めつつもその有害性を強調するのは、本当は、彼らが勉強法を十分に「勉強」していないからなのです。
いろいろ書きましたが、私は【1】【2】いずれの考え方も間違っていると思います。
まず第一に、そもそも勉強法オタクを自認する、あるいは周りから勉強法オタクと呼ばれる受験生のほとんどは、実際には、勉強法を突き詰めて考えているとは到底言えないレベルの人たちだからです。
彼らは彼らでずいぶん考えてきたつもりのようですが、今までこういう人を実際に目の前に引き摺り出して・・・じゃなかったお呼び立てして(←こういうことをするから嫌われる)その拘りの方法論をとくと伺ったことが何度もあります。その度に耳に入ってきたのは、およそ方法とは呼べない浅知恵ばかりでした。
ネットで一方的に叫んでいるときは、どうやらその程度の浅知恵でも通用すると錯覚してしまうようです。
しかし、現実に目の前にでてくると、無理な強弁やスルー技が使えないので、そのような浅知恵は長くて3分もちません。
残酷ですがそれが現実です。
このように、勉強法オタクと呼ばれる人たちのほとんどは、勉強法を本当の意味では極めていない、いわば「なんちゃって勉強法オタク」に過ぎないのです。
第二に、私の周りの数十人の受験生に限っていえば、本当にきちんと自分の頭を使って自らの勉強法を極めた本物の司法試験オタクが、「それでも受かりませんでした」なんて例を、私は今のところただの一例も見たことがないからです。本物の勉強法オタクは、私が知る限り、誰ひとり落ちていません。
「本物」とは、その人なりに自らの勉強法を考え抜き、鍛え抜いてきた考え方のことです。もっというと、その人なりの揺るぎない一貫した筋が、目的との関係ではっきりと確認できる考え方のことです。
このような考え方に初期段階で到達していた受験生(合格者)もいますし、まさに「勉強法オタク」と呼ばざるを得ないほどに時間をかけて到達した受験生(合格者)もいます。いずれにしても重要なのは、試験の合否と関係するのは、勉強法に費やした時間ではなく、その水準のほうだということです。
以上の理由から、勉強法をきちんと考えることが合格に役立たない、あるいは合格の妨げになるなんていう話は、少なくとも私には全く信じることができません。
そもそも、勉強法オタクは受かりにくいという認識が生じること自体、勘違いである可能性が高いです。
というのは、司法試験のような難度の高い試験では、そもそも普通の受験生だって普通に受かりにくいからです。そんな中で、勉強法オタクが普通の受験生よりも受かりにくい証拠など提出できるはずがありません。
おそらく、勉強法オタクが、普通の受験生および予備校講師にとって目障りな存在であることからくる一種の認知バイアスによって、なんとなくそんな気がする(受かりにくい気がする)だけでしょう。
高難度の試験では、勉強法オタク(⇒なんちゃって勉強法オタク)も普通の受験生も、どちらも平等に、そしてどちらも十分に受かりにくいのが実情であるはずです。
繰り返しますが、試験に受かるために必要なのは、
①方法 と ②努力
この2つだけです。
②は「本気で受かる気があるか」「本当に受かりたいと思っているか」と言い換えても構いません。
いずれにしても、この2つの組み合わせだけで結果はすべて決まります。
①と②を揃えることができれば、誰でも100%合格します。
①が欠ければ、確率的にしか受かりません。
②が欠ければ、絶対に受かりません。
↑これが今も昔もこれからも変わらない、極めてシンプルな試験の真実です。
勉強法を追求することは、その追及の仕方が正しければ、その受験生の合格の要件のうち、①を確実なものにします。これだけをみても、勉強法の追求が無駄でないことが分かります。
もちろん、①だけで合格できるわけではありません。①を揃えても、その受験生に本気で受かる気がなければ、その受験生は合格できません。これも当然のことです。しかし、そのことが、①の有用性を否定する根拠になるわけではありません。
このように話はいたって単純なのです。これ以上に話を複雑にする必要を、私は全く感じません。
話を戻します。
当時の私は、そういった司法試験オタクの頂点の一角を占める程度の存在でした。
ところが、ここから先に、私がもはや普通の受験生あるいは普通の勉強法オタクに戻れなくなってしまった最大の要因がありました。その要因とは、これは本当に偶然でしたが、同じゼミメンバーの中に、ひとり本物がいたことです。私のように、色々なことに興味があって、たまたま司法試験にも興味を持った人間とは違う、正真正銘の試験オタク、否、試験の権化みたいな人がいたのです。
彼の方法論は、当時私が憧れていたⅠ先生やS先生などの方法論をはるかに凌駕するものでした。
論理的な面で徹底されていながら、しかし極めて単純明快な方法論でした。
私がこのブログで連日偉そうに「過去問だ」とか「条文だ」とか、まるで自分が考えてきたことのように語っていますが(汗・・)、これらは全部、彼の方法論をそのままオウム返しにしているだけです。
もの凄く自分に贔屓目にいえば、私が彼の方法論を理論化した面もたしかにあるにはあります。しかし、私がやったのはせいぜい発明の商品化のレベルです。発明それ自体に私は関与していません。
「御三家→東大」のようなルートを歩んでいる人の中には、このような試験の権化みたいな人種が、常に現れては(試験の向こう側に抜けて)消えていっているのだろうと想像します。
彼の存在は、生来の病的な凝り性を持つ私にとって、またとない触媒となりました。
もう、ほとんど格好の餌食です。待ってましたと言わんばかりです。
私は、単なる司法試験オタク、つまり教材情報や予備校情報を豊富に知っているだけの存在から、司法試験をはるかに超えて、ついには試験全般の普遍的な法則を探求していく存在になっていました。
試験に役立つ知識や方法を増やすなんてレベルには飽き足らず、試験勉強全体の理論化・体系化を志向するレベルまで研究は続けられました。
読んだ勉強法にかんする書籍の数は250冊以上になります(お願いだから引かないで・・)。
ちゃんと数えていないので、もう300冊は超えているかもしれません。
同時に、広く試験勉強一般から司法試験に至るまで、勉強法のアイデアをメモした勉強法ノートを作っていたのですが、この勉強法ノートは丸々4冊になりました(文字びっしりです)。
ここまではまだそういう人もいるかもしれません(いや、さすがにもういないかも・・)。
さらに大きかったのは、件の試験の権化との、何十回にもわたる試験談義の繰り返しでした。
その頃は暇だったので、夕方にジョナサンに入って、気がついたら朝まで試験勉強の話をしていた、なんてこともしばしばありました。勉強法の討議に費やした時間は、トータルで数百時間に及びます。
こうして、いつの間にか私もまた、ほとんど試験の権化みたいな受験生になってしまったのです。
(3年くらい前には、すでに現在の水準に到達していました)
ここで申し上げたいのは、私が些かやりすぎたことは置いておくとして、私が司法試験および試験全般の方法論について揺るぎない自信を持って語っているのは、そのことについて自分が相応の努力をしてきた確信があるからに他ならない、ということです。
他の多くの受験生たちのように、「ねえ、私の司法試験観を聞いて」「私、司法試験って○○だと思うの」…といった、酔っぱらった勢いに任せたアイデンティティの発露をしているわけではありません。
私としては、単純に、やったことを、やった分だけ、正確に語っている。ただそれだけなのです。
あと、もう不要になったのでここに排泄しているのです。
私は常日頃から、試験合格に必要なのは、
①目的への正しい方向
②目的までの距離を埋める必要最小限の努力
この2つだけだと言ってきました。
そして、これまで述べてきたように、私の①は、もはや怖ろしいほどに完璧です。
①の領域において、私はもうずいぶん前から受験生でも勉強法オタクでもなくなってしまっています。
私は、別に片意地を張る必要もなく、勉強法においては既にプロの受験評論家レベル、しかも、その中でまずまず優秀な部類に属していると思っています。さすがに和田秀樹と対等な勝負ができるなどと思い上がってはいませんが、勉強法の領域においては、不勉強極まりない司法試験業界の講師のほとんどに、ダブルスコアで圧勝しているはずです。
ここで私がやった①を「やりすぎ」と評価することは簡単です。そう言いたい人は多いでしょう。
しかし、そう言うためには、司法試験の講師たちが正しい水準で①を身に付けていることが条件です。
今までこのブログでも散々述べてきたように、この業界の講師のほとんどは、法律の内容を分かりやすく教えることしか能のない、車の片輪が破損したような人ばかりです。
本当は、いやしくもプロの指導者を名乗るのであれば、①だってきちんと努力をして、他人に説くに値するだけのものを身に付けていなければならないはずです。しかるに、この業界の講師たちは、①についてまるで何も考えていません。彼らは、①についてはただの怠け者でしかありません。
私が尊敬するG先生も、①については、間違いなく私の数十分の一以下しか考えていないはずです。
本来はこの程度の努力で人に方法を説くのは、越権行為と言われなければなりません。さしずめ、②を十分に身に付けていない私が、偉そうに予備校の入門講座を担当するようなものです。
指導者になろうと思ったら、私と同程度に①をやることは、「やりすぎ」でも何でもありません。
真の意味でプロと呼びうる指導者は、皆この程度はやっています(司法試験にはほとんどいませんが)。
一方で、単に合格者になるのでいいなら、私と同程度に①をやるのはもちろん「やりすぎ」です。
なぜなら、現在はすでにこのブログがありますし、試験の権化もすでに講師になっているからです。
方法論についてはこのブログを熟読してもらえれば十分です。それであなたの①は全部おわりです。
こうして私は、①(方法論)だけが先に合格レベル・・・じゃなかった、プロレベルになってしまいました。
もはや、私の①は完璧です。本当をいえばまだまだ探求の余地はありますが、もはやこれ以上①ばかりに意識を向けるのは、さすがに逃避以外の何ものでもないというところにまで来てしまいました。
ここで、私の課題は、②(努力)を残すだけとなったわけです。
3年くらい前、方法論の探求が飽和期を迎えたことが認識されるにしたがって、私は今まで目を逸らしてきた②に、いよいよ自分が向き合わなければならなくなったことを覚悟しました。
********************
最も大きな転機は、方法論が飽和したこともありますが、何よりたくさんいた受験仲間たちが、合格したり、司法試験を諦めたり、別の道に進んだり、ローに進んだりと、皆それぞれの道に進み終わったことが大きかったです。
逆にいうと、私は皆がそれぞれの道に進み終わるまでは、このモラトリアムを満喫していてもよいのだという正当化を無意識にしていたと思います。
ともあれ、取り残された感満点になった私は、自分が本気で司法試験に受かる気があるのかどうかを、いよいよ自分自身で確認しなければならない段階になったと悟りました。
私は生来の怠け者でしたし、負けず嫌いでもなかったので、友人たちが先に合格していく姿には、焦りも何も感じませんでした。しかし、自分の年齢が大台に差し掛かろうとするいま、ここで最後の決断をしなくてはならないという別の意味での焦りは、はっきりと生じていました。
みんな、それぞれの道へ進んだ。いい加減、決断しなければ・・・。
桜蔭の女の子 でも書きましたが、それまで勉強という勉強をほとんどしてこなかった私です。
ここから人生最大の苦難が幕を開けることになります。
情報から入るのを習慣にしていた私は、まずはここでも書籍の力を借りました。
「やる気がでる○○」みたいな本を何十冊も読み、心理学や行動経済学のテキストも参照しました。
そうして、自分が、東大や司法試験に合格する人とどこが違うのか、なぜ彼らのように努力をすることができないのか、その理屈を学びました。
そうやって、できる人・できない人の「理屈」は学んだのですが、そこで次第に分かってきたことは、理屈をいくら学んでも、それを他ならぬ自分に適用するのは簡単ではない、ということです。
「こうすればあなたもできるようになる」みたいな自己啓発系の本は何冊もでていますが、頑強な正真正銘の怠け者である私には、中谷彰宏も苫米地英人も全然効きませんでした。
行動経済学を駆使して、なぜ自分に努力ができないかをどれだけ理解しても、何冊もの「やる気本」から処方箋をいくら学んでも、それで自分ができるようになるなんて奇跡は起きませんでした。
本を読む、頭で考えるだけでなく、友人にも相談しながら数々の実践にもトライしましたが、それらもすべて上手くいきませんでした。
このときの私がどれだけ焦っていたかは、文章からはあまり伝わらないかもしれません。
しかし、私だって相応の希望と覚悟をもって入ってきた司法試験受験界です。このまま何もできず不戦敗でこの世界を去らねばならないというのは、筋金入りの怠け者を自認する私にとってさえ、想像するだけで恐怖なことでした。
いよいよ追いつめられた私は、最後のカードを切るつもりで、2008年のリーマンショックに乗じて儲けた株の売却益300万円を使って、予備校がすぐ傍にある都内のマンションの最上階の一室を借りました。
そして、その部屋を、TVもPCも置かない、さしずめ牢獄のごとき禁欲部屋にしたのです。
それから数か月、その部屋にひたすら籠るという荒行に出ました。
実家にはほとんど帰らず、ケータイのアドレスも変えて無用なメールを断ち切りました。
近くには予備校がありましたから、そこから自習室にも通いました。
もうほんとにこれが最後だと思って、TV、PC等々・・普段の自堕落な生活環境を完全排除して、苦しむだけ苦しみました・・・。
そして、その結果は、なんと ・・・・・・・・・・・ ただ苦しんだだけに終わったのです。 
半年以上、マンション住まいを続けましたが、そこから唯一学んだことは、人間は変わらない生き物だということです(それはそれで貴重な経験でした)。
********************
こうして、私の手持ちのカードは全てなくなりました。
もう少し、あともう少しなのに、どうしてできないんだろう。
こんなに苦しんだのに、友人たちにできたことが、なぜ私にはできないんだろう。
もう、自分の側から出せるものは何もなくなっていました。
試せる方法は全て試しましたし、もう何より苦しむことに疲れていました。
そんなときです。
- 勝手にふるえてろ (文春文庫)/文藝春秋
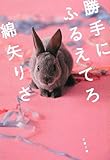
- ¥480
- Amazon.co.jp
刊行されて間もない、綿矢りさの『勝手にふるえてろ』を読んでいました(ハードカバーのほう)。
このお話というのは、簡単にいうと、①と②の二人の男性のうち、長く想いを寄せていた①ではなく、想いを寄せられていた②を主人公が選ぶというストーリーです。
この小説の一般的な解釈は差し当たりどうでもいいです。
ただ、そのときの憔悴し切っていた私には、この物語が↓こう訴えかけているように聞こえました。
「自分」を基準にして、「自分」の好き嫌い、「自分」の価値判断etc…こういった「自分」から発するものを譲らないままでいる限り、その人の世界が「自分」という枠の外に広がることは永遠にない。
その人の世界は、「自分」という枠の中に永遠に自閉し続ける。
それは、「自分」の好きなものを「自分」が選択できるという意味では、自由な生き方だといえるけれども、「自分」の中からしか選択できないという意味では、一切の可能性が消滅した世界だともいえるのではないだろうか。
「自分」にとって都合のよいもの、心地よいもの、想像可能なものだけを選択することが、果たして自由と呼べるだろうか。それは究極の不自由そのものではないか。
自分の可能性は、自分の<外>にしかないのではないか。
そうやって<外>に出ることが、自由になるということではないか。
ここでいう「自由」とは、自分が枠の「外」に出ること。
そういう変化の「可能性」が付与されることです。
・・・そのとき、私はふと、それまでの考え方から自由になりました。
実は、私の考えには、所与の枠がありました。
それまでは、あくまでもその枠内で自分を何とかしようとしてきました。
その枠を無視して考えれば、私にも勉強せざるを得なくなる状況があり得る。
そういう強制力をもたらす方法があることに、私自身、本当は薄々気づいていました。
既に友人の一人がその方向に進んでいて、彼は勉強せざるを得ない状況に追い込まれていました。
その光景を私も見ていましたし、私もまた彼と同じ環境に身を置けば、同じように勉強せざるを得なくなるに違いないという事実に、本当は気づいていたのです。
私は、気づいていないフリをしていただけでした。
私のような怠け者でも、ロースクールに入ってしまえば、嫌でも勉強するしかなくなる。
そんなことは、本当は分かっていたのです。
私のような、自分のペースでやりたいとか言っている怠け者の治療には、スパルタな環境に身を置くという劇薬しかあり得ないことくらい、私自身、とうの昔に心の底では気づいていたのです。
しかし、私はその事実に向き合うことを避けていました。
未修進学という選択肢を、無意識に封じ込めていました。
何よりロースクールが嫌いでしたし、ロースクールの正当性に疑問を感じていました。
こんなところに行かなくてはならないなら、間違いなく2年が限界だ。3年なんて絶対にヤダ。
既修に受かる実力が付くまではローに入らないという方針は、それはそれで正当な提案だと今でも思っています。しかし、こと私についてはそれは違います。私のような人間が「既修に受かる実力が付くまで」なんて言っていたら、冗談ではなく老人になるまで勉強しないでしょう。
一般論としては、既修のススメ① 既修のススメ② に書いたことは今でも正しいと考えています。
いくら自分を変えたいと願っても、自分の<内>に留まる限り、それは永遠に叶わない。
本当に自分を変えたいのなら、自分の<外>に出るしかない。
綿矢りさをきっかけにそのことに気づいた私は、ついに観念して未修への出願を決めたのです。
未修受験の話は何度か書きましたが、さすがに未修はほとんど何の対策もせずに受かりました。
それまでの人生でしてきた「無駄」が、ここでは思いっきり生きました。
入学してからは、順調にことが運びました。
あれだけ苦しんだ勉強という行為も、強制的な環境下では、意外なくらいに楽にできるものです。
さすがに根は怠け者なので1日10時間以上は無理ですが、7~8時間くらいなら大丈夫そうです。
ローに入る前は、自分なら1日3~4時間の勉強(努力)ができれば受かるだろうと踏んでいました。
そこから考えると、努力という点については、私の試みは十分に成功したようです。
私のエピソードは以上です。
ここまでの究極の怠け者は、司法試験受験生にはほとんどいないでしょう。
他資格の受験生などで、私の経験を参考にしていただける方がいたら嬉しいです。