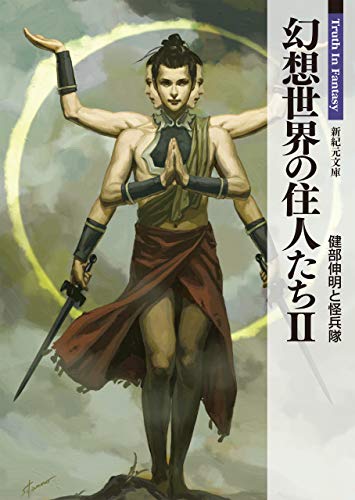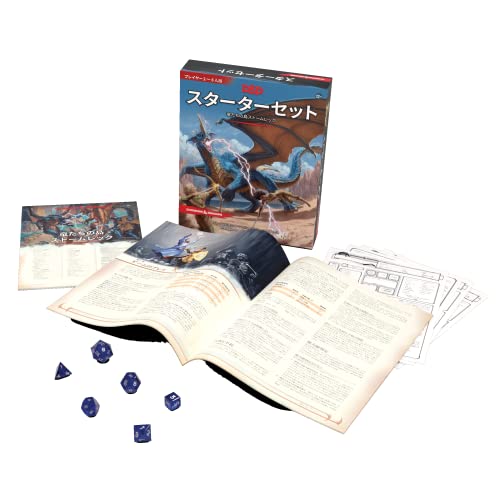『ドラクエ』をまったくやったことのない人も、とがった頭をして、愛敬のある顔で、にへら~と笑うあのキャラクターを、どこかで一度くらいは目にしたことがあるはずだ。縫いぐるみ、Tシャツ、ボールペン、消しゴム、マグカップなど、数多くのグッズも作られた。
これだけの人気者でありながら、このスライムというモンスターには、案外ナゾが多い。
中身は液体なのか、固体なのか?
どのくらいの大きさなのか?
あの体で、どうやって勇者たちに攻撃するのか?
このコーナーでは、エニックスの出した『ドラクエ』関連書籍をもとに、この不可思議な生き物の実態に迫ってみようと思う。
(初出:2002年12月1日発行『ゲイムマンの すばらしきゲームたち(1)』(本の風景社・ブッキング))
※この記事は全3回のうち第1回です。第2回、第3回はこちら。
- 『ポートピア連続殺人事件』の舞台を巡る【レトロゲーム紀行】
- 『ツインビー』合言葉はBee!へ至る道のり&アイドル化計画の顛末
- 高橋名人が『スターソルジャー』の映画で修行していた寺はここ!
- 寝台特急で『ドラゴンクエスト』クリアできるか?

▲ドラクエシリーズの人気キャラクターとなったスライム。テーブルトークRPGでは厄介な敵だが、『ウィザードリィ』や『ドルアーガの塔』など、テレビゲームでは弱いモンスターであることが多い
I.『ドラクエ』以前
スライムの起源は、どうもはっきりしない。おそらくアメーバからの連想と思われる。
映画『人食いアメーバの恐怖』(1958)のブロッブ(※)や、ラブクラフトの小説『狂気の山脈にて』(1931)に登場するショゴス(※)が、スライムの原形としては有名なところ。
※ブロッブ……スティーブ・マックイーン主演の映画『マックイーンの絶対の危機(人食いアメーバの恐怖)』(原題はそのものずばり『The Blob』)に登場する不定形生物。人間を飲み込むごとに大きくなっていく。
※ショゴス……H・P・ラブクラフトの怪奇小説『狂気の山脈にて』などに登場する不定形生物。知的生物“いにしえのもの”によって作り出され、彼らの従者として労働を行っていたが、後に反乱を起こす。「テケリ・リ! テケリ・リ!」と鳴く。
また、モンスターの解説書として有名な『幻想世界の住人たちII』(健部伸明と怪兵隊/新紀元社)では、ロバート・E・ハワードの『石碑の呪い』(1969、創元推理文庫『コナンと石碑の呪い』に収録)に出てくる不定形の怪物が、「スライムの姿を一番よく表している」としている。
この怪物は、ゼリー状の触手で生物に絡みつき、その肉体を消化する。強い磁力を持つ石柱に捕らわれたキンメリアのコナンが、この怪物に襲われたが、すんでのところで難を逃れ、火を用いて退治している。
※『石碑の呪い』は、実際にはハワードの作品ではなく、彼の死後にL・スプレイグ・ディ・キャンプとリン・カーターが、コナンを主人公として書いた作品です。そのため、21世紀に発売された創元推理文庫の『新訂版コナン全集』や、新紀元社の『愛蔵版 英雄コナン伝説』には収録されていません。
こうした流れを受けて、テーブルトークRPGの元祖『ダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)』(TSR)に登場したのが、グリーンスライムをはじめとする不定形生物群である。
『D&D』のスライムは、決して弱いモンスターではない。
グリーンスライムは普段、迷宮の天井にへばりついている。そして下を何か生き物が通ると、その上めがけて落ちてくる。
グリーンスライムは強力な同化能力を持っており、石以外のあらゆる物質を溶かすことができる。スライムに取りつかれた獲物の体は、次第に溶かされていき、やがてスライムと同一化してしまう。
不定形の生き物だから、剣やオノによる攻撃で、ダメージを受けることがない。スライムに取りつかれた人間を助ける唯一の方法は、たいまつなり魔法なりで、スライムを焼いてしまうことである。人間のほうもヤケドを負うかもしれないが、致し方ない。
しかも、倒したところで得られるものはない。宝箱や金貨を持っているはずはないのだ。スライムは金属も木も溶かしてしまうのだから。
まさにハイリスク、ノーリターン。ヤな敵である。
『D&D』にはほかにも、ブラックプティング(火以外で攻撃されると分裂する)、オーカージェリー(武器や電撃で攻撃されると分裂する。火か冷気でしかダメージを受けない)、グレイウーズ(酸で武器やよろいを溶かす。火や冷気に強いが武器攻撃に弱い)、ジェラティナスキューブ(半透明なゼリー状の立方体。部屋いっぱいに詰まっていることがある)など、数多くの不定形生物が登場する。どれも一筋縄ではいかない強敵だ。
こうしたスライムの特徴を、かなり忠実に再現したコンピューターRPGが、『ファイナルファンタジー』(スクウェア)である。このゲームのスライムは、剣で切りつけてもほとんどダメージを受けない。倒そうと思ったら、魔法を使うしかないのだ。
余談だが、『ファイナルファンタジー』シリーズ、特に『I』は、モンスターや魔法、シナリオなどで、『D&D』を強く意識しているようだ。これに関してはいずれ機会があれば取り上げてみたい。
このように、もともとスライムは、決して弱いモンスターではなかったのだ。ではいつからこんなに弱くなってしまったのだろうか?
弱いスライムの元祖は、『ウィザードリィ』(サーテック)の「バブリースライム」と考えて間違いないだろう。
ワードナの迷宮に入ってすぐ、地下1階に出現するのだが、同じ階に出てくるオークやコボルド(ともにテーブルトークRPGの定番ザコキャラ)よりはるかに弱い。剣で簡単にダメージを与えられるし、戦う相手をスライム化する能力もない。
『ドルアーガの塔』(ナムコ)のグリーンスライムも、ゲーム開始後最初に出てくるザコモンスターだった。もっともこちらのほうは、剣を突き刺されてもダメージを受けないことがあり、戦う相手を一撃で倒せるなど、『D&D』のグリーンスライムの恐ろしさの片鱗は見せている。
でも止まっているところを剣で突けば一発で消えてしまうので、やっぱり弱いことに変わりはない。
コンピューターRPG(除『ファイナルファンタジー』)のスライムは、どうしてこんなに弱いのか?
これはあくまで私の推察にすぎないが、彼らは進化の過程にある生き物なのではないだろうか。
『D&D』のスライムは、確かに戦闘では強い。しかし生物としては致命的な問題がある。液状の体を持つがゆえに、湿った所でしか生きられないのだ。
だから迷宮の中なら大丈夫だが、ひとたび陽光の下にさらされると、たちどころにひからびてしまうだろう。これでは広い範囲の土地に子孫を残すことができない。
そこで現れたのが、バブリースライムと考えられる。この生き物は、液状の体を包む薄い表皮を形成して、体が乾燥するのを防ごうとしたのではないか。
表皮は固体だから、剣で突かれればダメージを受ける。また、表皮が邪魔をして、他の物体を溶かすことができなくなっている(たぶん何か別の方法で、体内に栄養分を取り込んでいるのだろう)。バブリーなのは呼吸して吐き出された(あるいは光合成で作られた)空気が、表皮の下に潜ってしまうからかもしれない。
バブリースライムは、表皮が完全ではなかったようで、とうとう地上に出ることはできなかった(『ドルアーガの塔』のスライムの表皮は、突き刺しても死なないことがある点から推測するに、おそらくもっと不完全である)。しかしスライムはさらに進化を遂げて、『ドラゴンクエスト』の時代、ついに野外に姿を現すことができたのだ!
そう、『ドラクエ』のスライムは、スライムの究極の進化形なのである。
(「スライム研究序説2:ドラクエ公式書籍を紐解いて初期スライムの生態を探る」に続く)
- 『ポートピア連続殺人事件』の舞台を巡る【レトロゲーム紀行】
- 『ツインビー』合言葉はBee!へ至る道のり&アイドル化計画の顛末
- 高橋名人が『スターソルジャー』の映画で修行していた寺はここ!
- 寝台特急で『ドラゴンクエスト』クリアできるか?
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1986 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
※「日本縦断ゲーセン紀行」など、いろいろ書いてます。
- 北海道(日本縦断紀行第1回~第23回)
- 青森、岩手(日本縦断紀行第23回~)
- 京都(日本縦断紀行第234回~)
- Qさま優勝への道
- レトロゲーム紀行
- ゲームヒット祈願の旅:関西、岡山
- ゲームヒット祈願の旅:東京、神奈川
- ゲームブック風アドベンチャーゲーム【脱出ゲーム 香川県からの脱出】
- 愛媛県取材旅行
- 銚子電鉄関連記事
- 大井川鐵道関連記事
- テーマ別記事一覧
俳優・八名信夫氏の著書『悪役は口に苦し』(小学館)の中で、それぞれの時代背景について補足説明する文章を、少しだけ書いてます。(昭和中期のパ・リーグ、東映ヒーロー、オレたちひょうきん族など)
当ブログ内で、ゲームブック風アドベンチャーゲーム『香川県からの脱出』を公開しています。