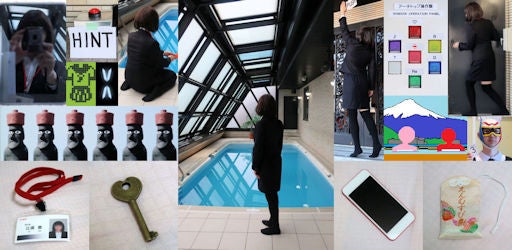小野 ('22.6.13)

引き続き、勧修寺(かじゅうじ)。
芝生越しに見る宸殿の建物が、重厚に感じられる。
正面の向拝の大きなひさしと、壁いっぱいの正方形の格子模様。
(障子だと思ったが、近づいてみたら障子じゃなかった)
それに加えて、この建物の由来を知っているから、より重厚に思える。
もとは1676年(延宝4年)に建てられた、明正天皇(上皇)の御所御対面所で、明正天皇崩御翌年の1697年(元禄10年)に下賜された。
- まずは勧修寺へ
- 水戸光圀公の石灯篭
- 恋の花咲く氷室池
- たまに行くなら西友山科店
- ラクト山科で昼ごはん
- 町ゲーセンとイオンモール

地図がないからどこを通っていいか迷ったが、宸殿の裏に回ると、こけら葺きの建物があった。
ここの前庭が特徴ある風景だったので、建物の方はあまりよく見ていなかったが、実はこの建物こそ、勧修寺の建造物の中で唯一、重要文化財に指定されている書院だった。
1673年(延宝元年)より建てられた、後西天皇(上皇・後西院)の御所が、後西天皇崩御翌年の1686年(貞享3年)に下賜されたもの、という説と、明正天皇の御常御殿(居間)を下賜されたものという説がある。
境内に説明板が2枚あり、どちらも京都市が立てたものだが、その2枚で書院に関する説明が食い違っている。
外観は何となく地味に見えたが、以前、BS11/KBS京都の番組『京都浪漫 悠久の物語』で見た内部の様子は、大きくて豪華な近江八景図や龍田川紅葉図(土佐光起・光成筆)が描かれているなど、重要文化財にふさわしい、絢爛豪華な空間だった。

書院の前庭には、独特な形の石灯篭(勧修寺型灯篭とよばれる)があり、

それを覆うように広がる、これまた独特なハイビャクシンの木。
樹齢750年の大木なのだが、「這柏槇」の名の通り、上にはほぼ伸びず、ひたすら平面に広がっている。

勧修寺型灯籠は、あの「水戸黄門」こと徳川光圀が寄進したと伝わる。

本堂へ向かう道沿いに、青くきれいな花が咲いていた。
ガクアジサイか。

本堂で参拝。
ガラス越しでよく見えないが、御本尊は千手観世音菩薩立像。
本堂の建物は、1662年(寛文2年)造営の仮皇居内侍所仮殿(この前年に内裏が火災で焼失していた)の旧材を使って、1672年(寛文12年)、灌頂道場として建てられたもの。
入口の音声案内以外に説明がほぼない上、勧修寺には公式サイトもないので、行きそびれている見どころや、解除してない実績がないか不安になる。
こういう所を気ままに散策できるような、ゆとりのある人間に成れてない。

その足元に、四国八十八ヶ所の石が、番号入りで並べられていた。
像の周りを1周すると、全ての石が踏める。
京都観光Navi(京都市観光協会) 京都府観光連盟
JRおでかけネット(JR西日本) 京都市交通局
※旅のマップはこちら。
※これ以前の「日本縦断ゲーセン紀行」はこちら。
・第241回 町ゲーセンで演ろうぜ(小野→東野→山科→京都)
・第240回 百夜後に死ぬ深草少将(醍醐→小野)
・第239回以前
スマホ用無料ゲームを作っています。
「脱出ゲーム 新入社員・江須恵(えすけい) 例のプールに閉じ込められた!」
「芸能人 真澄田竜子 - 霧笛があの娘を呼んでいる」