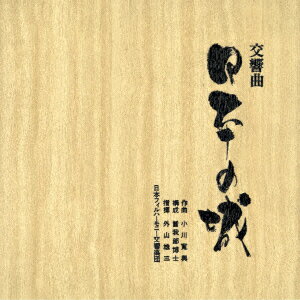前の2回のコンサートは、図書館の入り口エントランスの左側の最初のコーナーにレコード陳列させていただきました。しかし今回は図書館のスケジュールが決まってから急遽決まったイベントなので、割り込むスペースはありませんでした。そんなことで考えたのが今回の会場となるAVホールの入り口部分を使ってレコードジャケットを展示すると言う案でした。ただ1番奥まったコーナーですから、またコンサート当日の二日間しか陳列することができませんから、非常に不安はありました。コンサートの告知の方法も、このスペースだけでの勝負でしたから、いつもと認知度が低いのではないかと言う不安もありました。
そんなこともあり、今回はこのブログでも積極的にコンサートを告知し、またスメディアにも開催の案内を送って準備だけはしたつもりでした。そして開催の前日になって、地元の中日新聞が催し物の案内ということで、このコンサートを取り上げてくれることになった時は非常に嬉しかったです。
そして昨日のようなハプニングもあり、ますます不安になっていましたが、当日も時間になり、いや準備の段階でお客様がちらちらとホールにお越しになっているのを見て、これはひょっとしていけるんじゃないかなと言う気持ちにもなりました。そして開演の時間になると、続々とお客様が集まってくれて、ホールの中は予想以上のお客さんで溢れていました。何よりも嬉しかったのが、図書館の館長が休みの予定を書いて、でもこのコンサートを聞きに来てくれたことです。コンサートが終わってからもお声掛けをいただき、非常に珍しいコンサートを楽しませていただきましたと声をかけてくれました。
開演前には公式記録としての愛地球博2005年のビデオもスクリーンに上演しました。当時の雰囲気に浸って欲しかったからです。これも今回AVホールでプロジェクターがきっちりと使えるようになったからです。またコンサート中は講師の高山さんが持参して編集してくれたその日に使うレコードの演奏者たちの写真をプロジェクターで映し出してくれたことです。ただ、このAVホールはかなり古いシステムで構成されていますので、最新のパソコンには機器が対応していませんでした。そんなことで我々が所有するウィンドウズ7の古いパソコンを引っ張り出してきて、それに接続して映すと言うハプニングもありました。
名城市の講師のお話とともに次々とかけられる。音楽は参加してくれた人の心に響いたのでしょう。今回使った蓄音器はイギリスコロンビアのほとんど初期のモデルです。面白いのは蓄音機の正面に扉があり、これを開閉して音量の調整ができるモデルだったことです。
当日使用したSPレコード
まぁ、ハプニングと言えば、コンサートの途中で、小生は蓄音機のネジを巻いたりレコードの針の交換を担当していたのですが、1曲ごとに取り替える針をちょっと焦ってしまい、上下逆さまに針を取り付けてレコードをかけてしまったことです。びっくりしたのはそれでも音はちゃんと聞こえるのですが、何かおかしいなと言う音の揺れがあったので、初めて針を逆に取り付けたことに気がついた次第です。まぁ、もちろんもう一度かけ直しです。しかし蓄音機と言うのはこういうハプニングでもちゃんと音を出してくれるのにはびっくりしました。
ちょっと時間をオーバーしてしまいましたが、何とか初日のコンサートは無事に終了しました。
今日は本来のレコードプレーヤーを使ってのコンサートになりますが、曲をかけ間違いないのように最新の注意を払って対応するつもりです。どうぞよろしくお願いします。