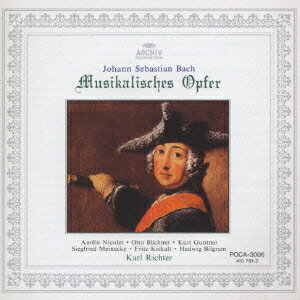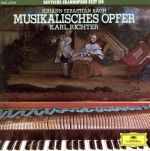カール・リヒター
「音楽の捧げ物」
曲目/J.Sバッハ
音楽の捧げ物BWV1079
1.3声のリチェルカーレ(Ricercare a 3)
2.王の主題による無限カノン(Cannons diversi super Thema Regium)
3.2声の蟹形カノン(Canon a 2 [crab canon])
4.2つのヴァイオリンによる2声の同度のカノン(Canon a 2 Violin[:/i] in Unisono)
5.2声の反行カノン(Canon a 2 per motum contrairum)
6.2声の反行の拡大によるカノン(Canon a 2 per augmentationem, contrario motu)
7.2声の螺旋カノン(Canon a 2 [circularis] per tonos)
8.5度のカノン風フーガ(Fuga canonica in Epidiapante)
9.6声のリチェルカーレ(Ricercare a 6)
10.2声の「求めよ、さらば与えられん」による謎カノン(Canon a 2 “Quaerendo invenietis”)
11.4声の謎カノン(Canon a 4 “Quaerendo invenietis”)
フルート、ヴァイオリン、通奏低音のためのトリオ・ソナタ(A Sonata sopr’il Soggetto Reale)
12.ラルゴ(Largo)
13.アレグロ(Allegro)
14.アンダンテ(Andante)
15.アレグロ(Allegro)
16.無限カノン(Canon perpetuus)
指揮、チェンバロ/カール・リヒター
フルート/ オーレル・ニコレ
ヴァイオリン/オットー・ビュヒナー、クルト・グントナー
ヴィオラ/ジークフリート・マイネッケ
チェロ/フリッツ・キスカルト
チェンバロ/ヘトヴィヒ・ビルグラム
録音/1963/01/17-21 ミュンヘン
P:ハンス・ヒックマン
E:ハラルド・パウディス
アルヒーフ 20MA 0051(410781-1)
手元にあるのは「アルヒーフ2000」と題されたシリーズで1983年に再発されたアルバムです。バッハ最晩年の作品であり、「フーガの技法」と並んで特別な地位を占める作品なのがこの「音楽の捧げもの」です。よく知られているように、この作品はプロイセンの国王であったフリードリヒ2世が示した主題(王の主題)をもとにした作品集です。王の主題は、「3声のリチェルカーレ」の冒頭に提示されています。
聴けば分かるように、非常に「現代的」な感じが漂う主題であり、バッハの時代においてはかなり異様な感じのする旋律だったはずです。あのウェーベルンがこの主題を使って曲を書いているほどですから。当然の事ながら、これを主題として処理していくのは不可能とまでは言わなくても、かなりの困難さがあることは容易に想像がつくような代物です。ですから、本当にフリードリヒ2世自身がこの主題を示したのかは疑問です。
当時、プロイセンの宮廷には息子であるフィリップ・エマヌエル(C.P.bach)が勤めていたのですが、そこへ親父であるバッハが尋ねてきたのです。おそらくは、この宮廷楽団の中でバッハ一族の力が伸びていくのを快く思わなかった一部の音楽家達が、その鼻っ柱をへし折ってやろうという「悪意」に基づいて作り出したものではないかと想像されます。(真実は分かりませんが・・・)
何故ならば、フルート奏者としても名高かったフリードリヒ2世は作曲も行っていて幾つかの作品が残されているのですが、その作風はこの主題とは似てもにつかないギャランとな性格を持っていたからです。ただ、バッハの高名はプロイセンにも届いていましたから、その実力の程を試してやろうという「悪戯心」は王も共有していたかもしれません。
しかし、王にとっては一場の座興であったとしても、バッハにしてみれば真剣勝負であったはずです。そして、「どう頑張ってもこの主題をもとにフーガに展開などできるはずがない!!」とほくそ笑んでいる反対派の音楽家を前にしてみれば、絶対に失敗などできる場面ではなかったのです。それ故に、ここではバッハという人類が持ち得た最高の音楽的才能が爆発します。バッハは王の求めに応じて、即興でこの主題をもとにした3声のフーガを演奏して見せたのです。おそらく、この時の即興演奏が「音楽の捧げもの」の中の「3声のリチェルカーレ」として収録されているはずです。
リヒターのチェンバロで始まる3声のリチェルカーレは厳粛でおごそかです。昔から名盤の誉れ高いレコードで、今回その世評を確認することができました。冒頭のリチェルカーレからバッハの世界に引き込まれてしまいます。
このアルバムにはフルートで、オーレル・ニコレ1959年にベルリンフィルを退団してフリーになっていましたし、ヴァイオリンにはミュンヘン・バッハ管弦楽団のコンマスを務めていたオットー・ビュヒナーが配されています。クルト・グントナーは当時はバイエルン国立管弦楽団のコンサートマスターの職にありました。当時のドイツの音楽界は活気がありました。
この当時ですからリヒターは現代楽器のノイペルトあたりを引いているような気がします。ピリオド楽器の繊細な音とは、ほど遠いキンキンした音色ですが、凄まじいほどの凝縮力で一気呵成に弾ききっています。こういう演奏を聴くと現代楽器とか古楽器という違いはなんぞやという感覚になります。まあ、バッハの音楽は現代でもジャズやポップスの世界で盛んに演奏されていますから、バッハの音楽は時代を超越しているということなんでしょうなぁ。
こういう曰く付きの音楽、我が家では大晦日の年越しの音楽でした。ベートーヴェンの第九ではなかったんですなぁ。そして下はウェーベルンの編曲による6声のリチェルカーレです。
今年の年末は先に取り上げた古楽器によるクイケンの演奏か、このリヒターの現代楽器による演奏かで大晦日は悩みそうです。