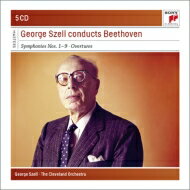Kultur Spiegelのジョージ・セル 2
曲目/
ベートーヴェン/交響曲第4番
1. Adagio - Allegro vivace 10:04
2. Adagio 9:51
3. Allegro vivace 5:57
4. Allegro ma non troppo 6:03
メンデルスゾーン/交響曲第4番「イタリア」イ短調Op.90*
1. Allegro vivace 9:53
2. Andante Con Moto 5:19
3. Con Moto Moderato 6:39
4 Saltarello (Presto) 5:26
チャイコフスキー/イタリア奇想曲Op. 45, TH 47 ** 14:47
指揮/ジョージ・セル
演奏/クリーヴランド管弦楽団
録音/ 1963/04/05
1962/10/26*
1958/02/28、3月1日 ** セヴァランス・ホール
P:トマス・フロスト
独ソニークラシカル 88697385892
前回の続きです。この2枚目も市販品では絶対ない組み合わせです。それにしても、渋い選挙区になっています。まあ、一枚のCDに収めるためには時間的制約はあるのでしょうが、ベートーヴェンは第4番が収録されています。多分このCDの肝はメンデルスゾーンの「イタリア」でしょう。
このコンビはCBSに結構な量のレコーディングを残しています。しかし、当時のCBSの中ではバーンスタイン、オーマンディに次いで3番手だったので決して恵まれた環境ではありませんでした。それが証拠に当初は看板の「COLUMBIA」からは発売されず傍系の「EPIC」レーベルからのリリースでした。今では「EPIC」はポップスの看板ブランドですが、60年代はクラシックのレーベルでもあったのです。国内盤はそういう区別はなかったんですけどね。そんな状況からかセルは客演で招かれた際にはヨーロッパの各オーケストラと録音セッションを持ち数々の名盤を各レーベルに残しています。コンセルトヘボウしかり、ベルリンフイルしかり、また、ウィーンフィルも含まれています。そして、1968年前後にCBSを離れEMIに移り、これからという時にがんで亡くなってしまいました。せめて、後5年長生きしてくれたらセルの評価ももっと上がっていただろうにと思わざるを得ません・・・
最初はベートーヴェンの交響曲第4番です。セルは1960年代前半に交響曲全集を完成させています。録音はオケとの距離も適度でホールの残響も良く感じられます。ただ、惜しむらくはティンパニの音だけがやや不明瞭で音が定位していないのが残念です。第1楽章の序奏のテンポは遅めです。繊細なタッチでかなり神経質な表情で入念です。それが主部に入ると堂々とした見得を切り、勢いを持って音楽が動き出します。明瞭なアレグロ・ヴィヴァーチェで弦楽アンサンブルの精度は流石にこのコンビらしいところでカッチリした音楽で音の粒が揃っているので聴きごたえがあります。
第2楽章は主旋律だけでなく輻輳する旋律もうまく拾い上げて立体的な響きで重厚に響きます。全体的にエッジを効かせて
リズム感を強めに感じる表現です。それに対して中間部のヴァイオリンやクラリネットの語り口は繊細さとしなやかさを感じさせるもので音の対比が鮮やかに描かれています。ただ、ここでもティンパニの音は焦点がはっきりしていないのが残念です。続く第3楽章は冒頭から弦楽は歯切れの良い表現で勢いとクッキリとしたメリハリが感じられます。弦の音が揃っているので全体の音のやりとりが聴いていて楽しくもあり、中盤での木管と弦楽の絡みも音楽をする喜びを感じさせます。
第4楽章は一昔前のゆったりとしたテンポでピリオド楽器による演奏とは違うゆったりとしたテンポでありながらアクセントを強めに効かせてメロディラインをくっきりと歌わせています。ヴァイオリンもよく歌いますが、低音部のコントラバスも十分に鳴らされているので立候補体感のある音楽が響きます。現代の演奏に比べるとややおっとりしたようなテンポですが、小生の耳にはこのテンポが懐かしく感じられます。そんなこともあり、いつもは大曲の中に埋もれてしまうこの4万ですが、ここではしっかりとその存在感を感じることができます。こういうガッチリとした構成で聴かせる演奏は久しぶりにこの曲を堪能させてくれました。
このアルバムでこの第4番がチョイスされたのはなかなかのセンスでしょう。
そんなセル/クリーヴランドの録音はCD時代になって廉価盤としてCBSブランドで大量に再発されていました。このメンデルスゾーンの「イタリア」もオリジナルでは「真夏の夜の音楽」とカップリングされていました。そして、これはセル/クリーヴランドを代表する一枚であったわけです。レコ芸のリーダースチョイス「名曲名盤100」にも両者ともベスト10に入っている。ちなみに同じくレコ芸の批評家人による「名曲名盤100」では1983年、1987年ともに交響曲第4番はベスト3に選ばれています。
小生もLP時代から聴き込んできた演奏です。SONYのCD化はハイ上がりのものが多くLP時代の音質とイメージが変わってしまうものが多いのですが、これはドイツプレスのせいか当時の日本盤よりはマシでした。最近は一枚目のシューマンとともにSACDでも発売されているようで、オリジナルに近い印象になっているのでしょうなぁ。
室内楽的なアンサンブルを目指したセルの真骨頂とでもいうべき演奏で、透き通ったクリアな弦の合奏で始まるこの曲はイタリアの青を連想させる明るい演奏です。インテンポで緻密なアンサンブルがぐいぐいとオーケストラを引っ張っていきます。第2楽章もメンデルスゾーンの陽の部分に光を当てたさわやかな演奏。ところどころでセルの息づかいが聴かれるのもご愛嬌でしょう。第3楽章はスケルツォでなくてメヌエットになっていますが、セルの演奏はあくまでも優雅に旋律を歌わせ中間部のホルンも美しく荘厳でに響き、また特徴的なクラリネットの音色も気品が感じられます。第4楽章はプレストで早い楽章ですがアンサンブルは少しも乱れていません。クリーヴランドはまさしくセルのオーケストラです。60年代はこういう指揮者とオーケストラの結びつきが多かったように思います。アンセルメ/スイス・ロマンド、オーマンディ/フィラデルフィア、カラヤン/ベルリンフィル、バルビローリ/ハレ管弦楽団など独自のサウンドで聴いてすぐ分かる特徴があったものですが、最近はグローバル化が進んで世界的に均一化されてしまいこういう個性が消えてしまって、そういう意味でもクラシック業界は面白みが消えてしまているのではないでしょうか。さて、クリーヴランドは磨かれたアンサンブルで実に見事に楽譜を音にしている。金管も突出せずバランスのいい響きで、例えて言うならおいしいイタリアワインを飲みながらゴージャスなディナーを味わっているような趣があります。あまり重厚にならず、さりとてムーディにならずと最高のシェフの料理が味わえます。
この録音のプロデューサーはトマス・フロストでCBSのクラシックのメジャー所をほとんど手がけているが音質的にはバーンスタイン、オーマンディとはかなり異なるサウンドに仕上がっています。これはやはりホールの特徴がそのまま出ているのでしょうか?。ちみにクリーヴランドはセヴァランスホールで非常にバランスの良い音がしています。