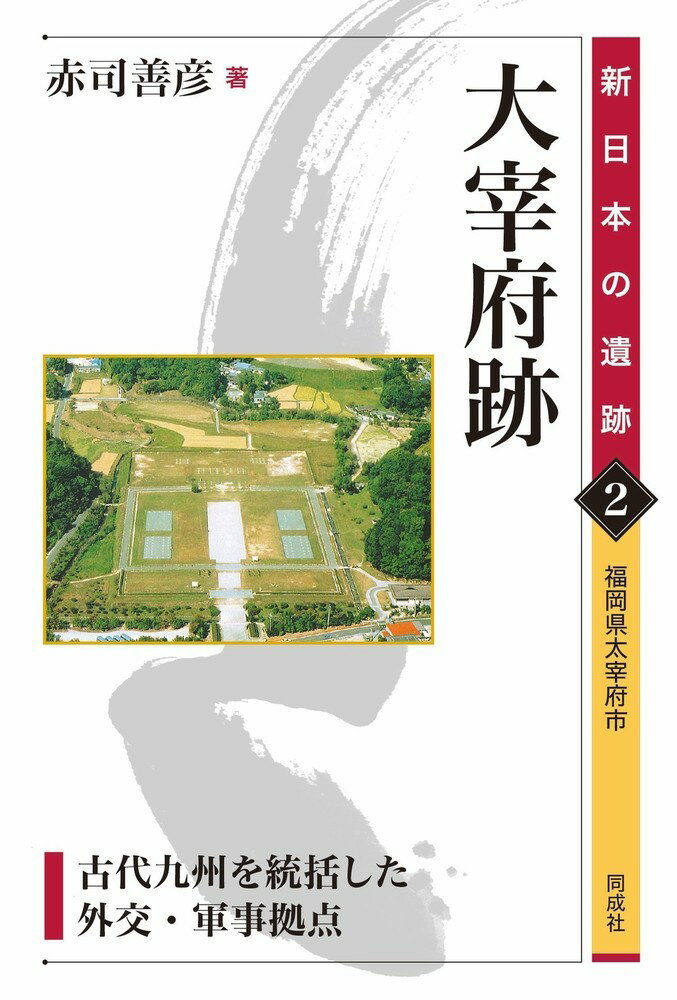大宰府跡
新日本の遺跡 2
著者:赤司善彦
出版:同成社
大宰府跡に関する著作物は多い。書店でも図書館でもよく目にする。しかし、1968(昭和43)年からはじまり半世紀以上に及ぶ計画的な発掘調査の成果を、網羅的かつ客観的にまとめたものは皆無である。なぜなら、それは単に発掘調査に留まらず、(1)長期的な発掘調査で得られた膨大な情報の把握と整理及び関連遺跡との関係性追究、(2)東アジア史・文献史学・歴史地理学・保存科学に関する多様な知識と視点、(3)文化財保護としての意識と観点、こうした多岐にわたる専門分野をバランスよく高度に分析することが不可欠だからである。筆者は大宰府跡の発掘調査に長年携わり、最新の研究成果を九州歴史資料館や九州国立博物館における展示という手法を通して、その都度わかりやすく楽しく披露してきた。この40年に及ぶ取り組みの集大成が本書であり、ついにここに筆者が求める「大宰府復元」が完成したのである。---データベース---
つい先日の2月4日に、「日本遺産」の太宰府天満宮などの文化財で構成された「古代日本の『西の都』」について、文化庁は「地域活性化の取り組みに改善が必要だ」として認定を取り消しました。日本遺産の認定が取り消されるのは、2015年に制度ができてから初めてです。
「日本遺産」は、各地に点在する文化財を歴史的な経緯や地域の特色ごとにまとめて観光振興に生かそうと、文化庁が2015年から地域を認定しています。これまでに104件が認定されていますが、このうち、太宰府天満宮など福岡県と佐賀県の一部の市と町の文化財で構成された「古代日本の『西の都』」について、文化庁は4日、地域活性化の取り組みに一層の改善が必要だなどとして、日本遺産の認定を取り消しました。一方、北海道小樽市の「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽」が新たに日本遺産に認定されました。
そのうえで日本遺産の候補地域に格下げし、2026年度以降に日本遺産に再度申請できるとしています。
丁度このタイミングでこの本を読んでいました。で、何でなのと?疑問に思い取り上げた次第です。この本の章立てです。まず初めに基本的なことですが、太宰府天満宮は「太」の字を使いますが、この大宰府は「大」の字を使うという事です。違うんですなぁ。小生をこの本を読んで初めて知りました。(^_^;)昨年の九州旅行では初日にこの太宰府天満宮を訪れていますが、殆ど太宰府市はこの大宰府跡のことを殆どPRしていませんでした。まあ、小生も大宰府のことはブラタモリで知っていた程度で、この時は「吉野ヶ里遺跡」をメインに組んだ旅行でしたからほぼ無視していました。まあ、そんな反省からこの本を手にしたわけですけどね。この本の章立てです。
はじめにー大宰府の先進性と辺境性
第1部 遺跡の概要ー大宰府跡とはー
第1章 大宰府の環境
第2章 大宰府跡の研究史と保護の歴史
第3章 大宰府の前史と機能
第2部 遺跡のあゆみー発掘調査が語るものー
第4章 大宰府跡の発掘調査
第5章 発掘調査成果からみる大宰府の3つの機能
第6章 大宰府跡の保存と活用
あとがき
大宰府と太宰府天満宮との位置関係
これまで太宰府は大和朝廷の出先機関とばかり思っていましたし、その役割は大陸との文化の交流使節ならびに防衛拠点という位置付けと思っていました。史実としては魏志倭人伝に登場する伊那国が原型なような気がします。小生は大和朝廷は九州からの東進説を採っていますから、その九州の地にこういう施設を置いておこうという考え方は分かります。
太宰府の区画
太宰府政庁部分
ところで、「大宰府」には「府」の字が使われています。「府」とは本来「蔵」「役所」「みやこ」の意味を持っています。律令制における「府」には「大宰府」の他に「衛門府」、左右の「衛士府」「兵衛府」のみです。また延喜式での「府」は「鎮守府」、左右の「近衛府」「衛門府」「兵衛府」です。これら以外の役所に「府」のつくものはありません。「大宰府」は防人司を兼ねており軍事的な役所です。 白村江の敗戦により、日本は九州「大宰府」とその周辺に防衛拠点を置かざるを得ませんでした。wikiには平城宮木簡には「筑紫大宰」、平城宮・長岡京木簡には「大宰府」と表記されており、歴史的用語としては機関名である「大宰府」という表記を用いていることが分かります。
この規模を見ると東は天満宮のすぐそばまで広がっているのが分かります。現在はただ、ただっ広い発掘現場の横に小さな資料館があるだけですが、クラウドファンディングで南門や正殿が復元出来ればもう少し政庁跡が魅力的になるのかもしれません。そうすれば、日本遺産に復活出来る道筋もつくのではないでしょうかねぇ。