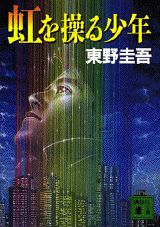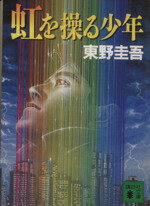虹を操る少年
著者:東野圭吾
出版:講談社 講談社文庫
「光にメロディがあるの?」「あるさ。みんな、そのことに気づいていないだけさ」。“光”を“演奏”することでメッセージを発信する天才高校生・光瑠(みつる)。彼の「光楽」に、感応し集う若者たち。しかし、その力の大きさを知った大人たちの魔の手が忍び寄る。新次元コミュニケーションをめぐる傑作長編ミステリ。---データベース---
この作品は一連の殺人がらみの推理小説ではなく、彼の別系統のファンタジー作品といっていいでしょう。1994年の作品、ということは携帯もまだそれほど普及していないし、パソコンもWindows3.11の時代です。そんな時代にあって言葉ではなく音楽をその手段とはしていますが、光を演奏してメッセージを送るコミュニケーション手段としています。このコミュニケーションのことをここでは「光楽」と呼んでいます。作者自身が最初は子供向きの作品として構想していたものを大人用に書き直したということで主人公は中学生や高校生という設定になっているところが設定や展開の荒さや若さみたいのものが感じられます。まあ、東野氏のブレイク前の作品ということで最初は実業之日本社から単行本として発売されています。
この小説の解説の井上夢人氏がカラヤンとベルリンフィルのエピソードを書いています。カラヤンは自ら飛行機を所有し操縦もしていたのですが、演奏会場に向かう時その自家用の飛行機に乗り込む時、離陸寸前で飛行機から降りてしまったのです。カラヤン曰く、左右のプロペラの回転数が違う、整備が終わってから乗ると言ったとか。まあ、ここではカラヤンの耳がオーケストラの楽器の音を聴き分けているという耳の持ち主ということを言いたかったようですが、残念ながらカラヤンの所有していたのはファルコン10という時えっ時でプロペラ期ではありませんでした。面白いエピソードがあって、1966年(昭和41年)には、日本での公演の為に来日していた時、三菱重工小牧工場を訪れ、出来たばかりのMU-2のコックピットに座り15分間の空の旅を楽しんだという出来事もありました。カラヤンのMU-2に対しての感想は上々でMU-2を気にいり発注。他にも数機持っていたようです。ただ家族やスタッフの強い薦めで必ずプロのパイロットが乗ってます。好きだったんですね。
話はそれましたが、そういう経緯があったので、冒頭には暴走族のグループが登場し、そこから派生的にニュー・タイプの「マスクド・バンダリズム」が勢力を伸ばしていきます。この組織のことはあまり詳しくは語られていませんが、彼らの乗り回すバイクにはその秘密が隠されていたようです白川光瑠少年が、自分にその能力があることを知り、若者を中心に公に向けて、光を発していきます。この光、人間の目で捉えることができるのは電磁波のうち、ヒトの目で見える波長のものです。つまり虹の範囲内ということですね。可視光線に相当する電磁波の波長は下界はおおよそ360-400 nm、上界はおおよそ760-830 nmです。可視光線より波長が短くなっても長くなっても、ヒトの目には見ることができなくなります。タイトルはそこからつけられたものでしょう。
ストーリーは、現代の社会構造に疑問を抱きそれを破壊することを究極の目標とするニュータイプの暴走族グループ「マスクド・バンダリズム」が登場します。最初はちょっと物騒な出だしです。その一員である相馬功一は、ある夜、暗闇に点滅する不思議な“光”を見つける。その“光”は、まるで「こっちへ来いよ」と囁きかけているかのようでした。同じく、優秀な医者になるために受験勉強に励む高校二年生の志野政史。最近、集中力が長続きせず、スランプに陥っていました。彼も、そんなある夜、不思議な“光”を見つけたのだです。さらには中学一年生の小塚輝美。彼女は、家庭問題を苦に自殺を考え、飛び降りようと真夜中にベランダに出ます。その時、彼女もまた不思議な“光”を見つけ、その光に吸い寄せられていきます。
現代社会の中で苦悩する若者たちを導く不思議な「光」。その不思議な“光”を操っていたのは高校二年生になる白河光瑠でした。彼は、「光」を演奏することでメッセージを発信することが出来、それを「光楽」と名付けます。彼の「光楽」に感応し、何処からともなく若者たちが集います。その影響力は少しづつ増大していきます。やがてその存在が世間に知られるようになると、その力の大きさを知った既存社会の大人たちは「光楽」阻止に動きだし、その魔の手が光瑠に忍び寄っていくことになります。
推理小説的にはその段階で犠牲者が出て爆死するのですが、この小説では警察組織は全く登場しません。ミステリーではないからです。どちらかといえばSFっぽい。主人公の光留という高校生が持つ特殊な能力が読み進めるうちに不思議に感じになります。本当に誰でも持ち合わせるチカラなんかな?と思わされます。全てにおいて先を読み取る光留の能力で結構なドキドキな展開もで新人類の誕生を思わせます。
ただ、後半の展開は個人的には、ある人物があっさり救出されてしまったり、悪役?があっさり負けてしまったり、ラストの妙に薄味な展開にはやや疑問が残ります。
内容が内容だけに映画化やドラマ化は難しいと思われますが、1998年にNHKFMの「青春アドヴェンチャー」でラジオドラマとして放送されたことがあるようです。まあ、これが限界でしょうかね。
小説の中で光楽の作品の具体例として登場するのはモーリス・ラヴェルの「ボレロ」なんですが、イメージ的には下のようなものでしょうか。