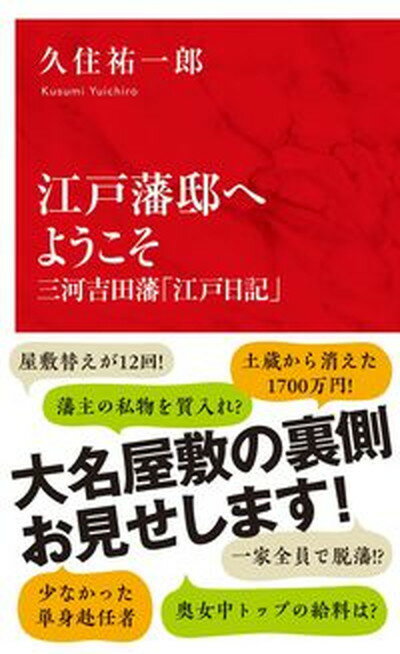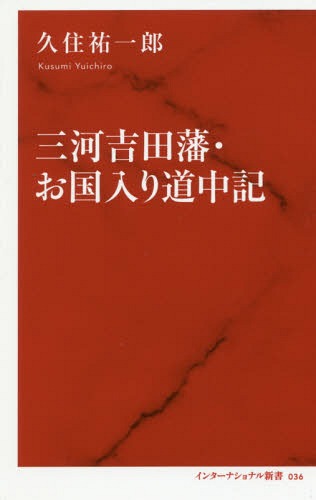三河諸藩の参勤交代と江戸藩邸
-三河吉田藩を中心に-
「三河諸藩の参勤交代と江戸藩邸 -三河吉田藩を中心に-」というちょっとディープな講演会がありましたので出掛けてきました。時代小説を読む上で武家屋敷は避けて通れない存在です。何しろ江戸の面積の70%は武家地でさらにその55%が大名屋敷だったのですから。つまり、江戸の市街地の35%も占めていたのです。大名屋敷は、参勤交代で江戸滞在中に居住する上屋敷、隠居時や世継ぎの住居となる中屋敷、そして上屋敷が火事になった時の避難場所となったり接待場所として庭園を有する下屋敷、さらに物資を収める倉庫としての蔵屋敷も存在しました。
この公演は豊橋市美術館の学芸員の久住しですから、一件は三河諸般の研究が主体で三河の諸般についての説明が主体です。愛知県の三河には六藩あり、その上屋敷は次の所に構えていました。
・吉田藩---呉服橋門内、東京駅北
・田原藩--半蔵門外、三宅坂
・岡崎藩--日比谷門内、表門は移築されて現存
・挙母藩---三田四国町、慶大東門付近
・西尾藩---大名小路、東京駅南口付近
・刈谷藩---赤坂門内、永田町メキシコ大使館
大名屋敷ですから江戸城の近くに上屋敷があるのは当然です。ちょっと見にくいかもしれませんが、御三家の尾張藩、水戸藩、紀州藩は別格として、江戸城周辺に配置されています。そして、藩財政は地元よりも江戸藩邸の方が財政支出が多かったと説明されました。
また、参勤交代については封建制の足枷という意味合いがありましたが、親藩とと外様ではかなり運用の仕方か違っていて、そもそも親藩大名は老中や幕府の養殖についていることが多く、その職にあるときは参勤交代は免除されるので外様ほど財政的には逼迫していなかったのではないでしょうか。下は文政から天保期の三河諸藩の藩主の居所を期した書類ですが、刈谷藩はほぼ江戸詰、吉田藩は最初は老中職、のちに大坂城代、次に京都所司代とほぼ地元に帰っていません。また、三河の中では誰かが地元に残り、全てが江戸に集中するということはほぼなかったようです。
こんなことで、吉田藩は江戸時代の140年間で59回は参勤交代は免除になっていたようです。そして、行われた参勤交代は江戸と吉田(豊橋)間を6泊7日で往来していたと記録されています。その規模は通常265人で内訳は詩文48人、足軽32人、中元185人で構成されていました。
この参勤交代は実際にはコーディネーターの人宿が請負い、宿泊日程や通い日雇の派遣などを請け負っていたといいます。まあね仕組みとしては今と変わりがなかったという所でしょうか。藩としては統括マネージャーとしての「目付」、宿泊地、宿割りを「宿割」、会計マネージャーの「宿払」、そして、河川を渡る際の「船割」が担当していたということです。多分映画の「超高速!参勤交代」をご覧になった方なら分かると思いますが、行列は、
・惣行列---城下町、昼休、関所
・本行列---宿場町
・引行列---郊外
に分かれて人員が調整されエキストラが雇われていたということです。まあ、こんなものがYouTUbeにアップされています。