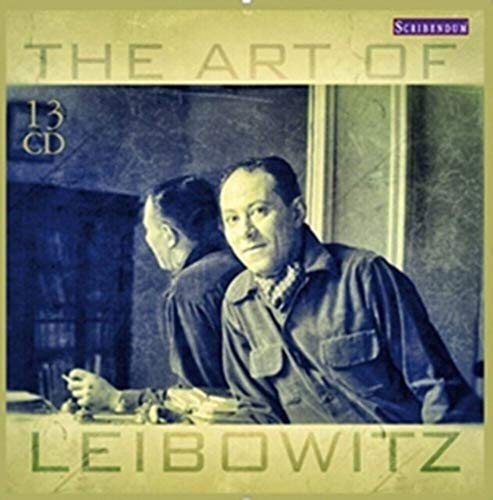レイボヴィッツの「英雄」
曲目/ベートーヴェン
Beethoven Sympnony No 3
I. Allegro Con Brio 12:53
II. Marcia Funebre 14:24
III. Scherzo: Allegro Vivace 5:13
IV. Finale: Allegro Molto 10:51
指揮/ルネ・レイボヴィッツ
演奏/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
録音/1961/04/10-12 ウォルサムストウ・タウン・ホール、ロンドン
P:チャールズ・ゲアハート
E:ケネス・ウィルキンソン
リーダース・ダイジェスト RBS1-7
マトリックス番号 M80Y−7103
捕獲して手元にあるのは国盤のレイボヴィッツ/ロイヤル・フィルのベートーヴェンの交響曲全集です。このレイボヴィッツの演奏はCDでは第3番だけ別途で所有しています。CDはアメリカのチェスキーレーベルで発売されたもので、リマスタリングもしっかりとされていました。この曲の録音データはこのCDに記載されたものを使用しています。演奏時間もレコードのデータとCDのデータでは大きな違いがありますからここはVDのデータを優先させています。
今はリーダーズ・ダイジェストなんて雑誌はほとんどの人が知らないのではないでしょうか。小生も最初はレコードの通信販売の会社だと思っていました。
リーダーズ・ダイジェストは今ではただの通販会社になってしまっています。でも、1970年代には活発に活動していて、雑誌よりもレコードの通販で売り上げを伸ばしていました。小生もいまだに手持ちでは数セット所有しています。多分このレイボヴィッツのベートーヴェンは1960年代に発売されたものではないでしょうか。のちにはビクターではなく、本家のRCAがレコードを制作しているからです。このセット、当初はモノラルでリリースされていたようですが、手元にあるのはステレオによる全集です。
下に小さくSTEREOPHONICと印刷されています。
名曲全集のような組物が多いリーダーズ・ダイジェストで、ベートーヴェン交響曲全集の企画が持ち上がった訳は、以下のようなゲルハルトの言葉が物語ってくれます:
「ベートーヴェンの9つの交響曲全曲をもう一度まとめて出そうとうい想念はパリの歩道に面したささやかなカフェーで生まれた。私はルネ・レイボヴィッツと一緒にラヴェルのラ・ヴァルスとボレロの録音をやっていた。2人はコーヒーを飲みながら音楽について議論を戦わせていた。話はベートーヴェンに移った。レイボヴィッツはこう言った。
“世界で一番演奏回数が多いベートーヴェンの第5の出だしのところで、ここのところの小節が一度も正確に演奏されたことが無い、ということに気が付いたことがあるかい? それからここのところと..ここのところ”
そして48時間後には彼はベートーヴェンの演奏のなかで一般に行なわれている約600(!)ほどの誤りを見つけ出したことは明らかになったので、録音を行なわない理由はもうどこにもなくなった」
ということで、ベートーヴェン自身のオリジナルなメトロノーム記号に出来るだけ従おうとした最初の録音とされています。ピリオド・アプローチの先駆けとも言え、60年代初めとしては斬新な試みだったようです。ただし、当初はブライトコップ版しかまともな楽譜のない時代です。
レコード会社の分野外からのリリースながら、知る人ぞ知る有名な録音といえます。カラヤンが最初のベルリンフィルとのベートーヴェン交響曲全集の録音を始めたのは1961年12月からです。ということはそれに先立ってこの録音プロジェクトがスタートしていたということになります。この当時ベートーヴェンの交響曲全集をステレオで録音していたのはブルーノ・ワルダーとアンドレ・クリュイタンスぐらいでしょう。このリーダーズ・ダイジェストでの録音制作は米RCAが依頼を受け、当時のRCAの名プロデューサー、チャールズ・ゲルハルトのもと、当時提携関係であった英DACCAの名エンジニア、ケネス・ウィルキンソンが録音を一手に引き受けて行なわれました。世界発売はRCAが担いましたが、日本は提携先のビクターがレコードを制作しています。
ここで取り上げるレイボヴィッツ/ロイヤルフィルの「英雄」は、比較すると以下のようになります、同年代の録音にピリオドのホグウッドを並べてみました。
クリュイタンス 14:27 16:07 5:24 11:33
ワルター 16:04 15:33 6:31 12:16
カラヤン 14:44 17:05 5:44 12:20
レイボヴィッツ 12:45 14:21 5:13 10:45
ホグウッド 17:46 14:57 6:07 11:01
ただ、1960年ごろはまだ提示部の繰り返しは一般的ではありませんでした。ホグウッドは提示部をすべて繰り返していますからそういう点を考慮するとメトロノーム記号に基づいた演奏ということでは多分ホグウッドと同等なのではないでしょうか。
若き日のレイボヴィッツ
マイクはメインはRCAの3チャンネル収録のようです
また、レイポヴィッツは当時一般的だった楽譜を使用していて、第1楽章のコーダ部分のトランペットは改訂版を使用していて、高らかにトランペットで歌い上げています。
第一楽章から速いテンポで清涼感のある響きの演奏です。これが本来のアレグロ・コンブリオなんでしょう、凄いスピード感です。このころはビーチャムからルドルフ・ケンペにバトンタッチされたころですが、まだまだ不安定な時期でした。それをレイポヴィッツはアンサンブルがをっちり纏めていて、とても見通しの良い演奏です。
第二楽章は静かに演奏される主要主題。一楽章ほどの速さは無く、ブライトコプフ版の伝統的な演奏に比べて僅かに速い程度です。哀しみを強調するような演奏ではありませんが、 楽譜に忠実に自然体で作品の美しさを表現しているようです。
第三楽章は早く躍動感があって生き生きとしています。オケの反応も良く瞬発力があって良く弾みます。トリオのホルンも豊かな表現で伸び伸びと歌っています。つづく第四楽章は、三楽章の勢いそのままに四楽章に突入します。デッカはこの時代まだ、本格的なベートーヴェンの降機用曲全集を手掛けていませんが、エンジニアのケネス・ウィルキンソンは残響を豊かに取り入れたホールトーンを重視した響きで音をとらえています。清涼感のある響きがとても美しいです。静寂感もあり、オケの集中力の高さが感じられます。クライマックスで朗々と吹き鳴らされるホルン。トランペットは音がスタッカート気味に短めなのが特徴といえば特徴です。コーダではさらに加速しているような勢いになっています。
ホルンセクション
時代を先取りりした録音ですが、ベートーヴェンの音楽の原点を感じることができ、60年代にこういう演奏に出会えた人はある意味幸せであったような気がします。