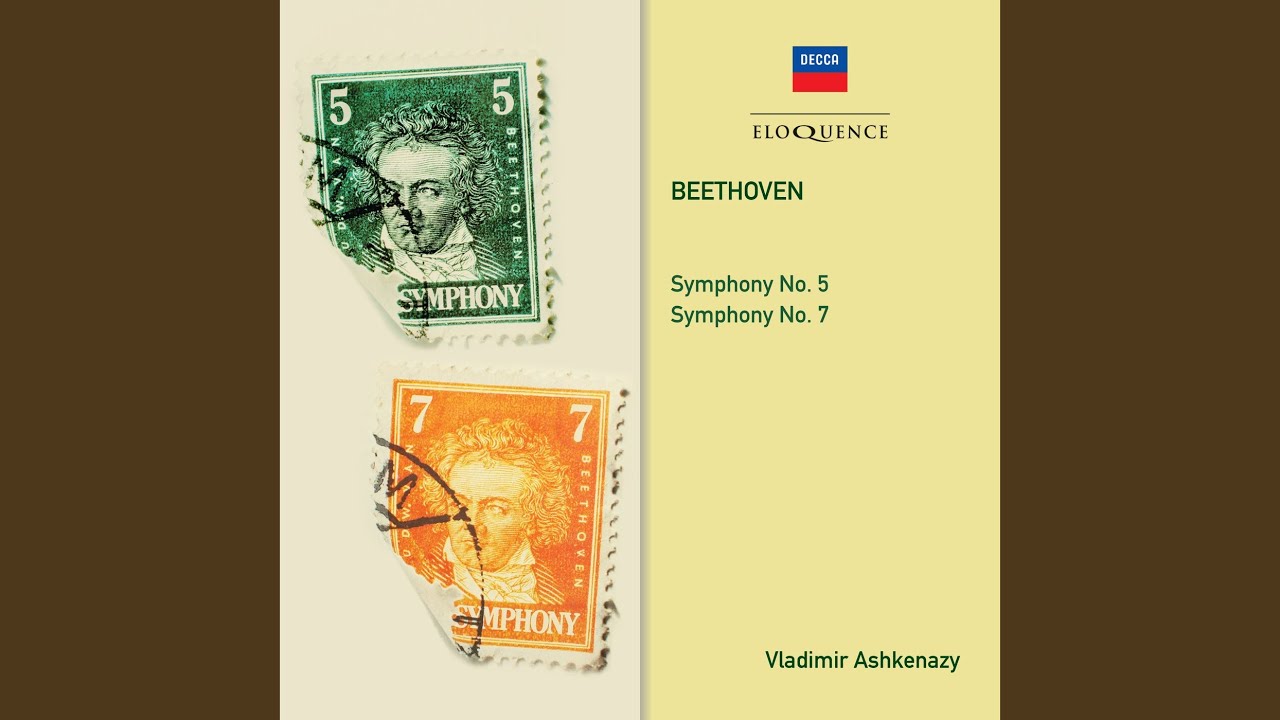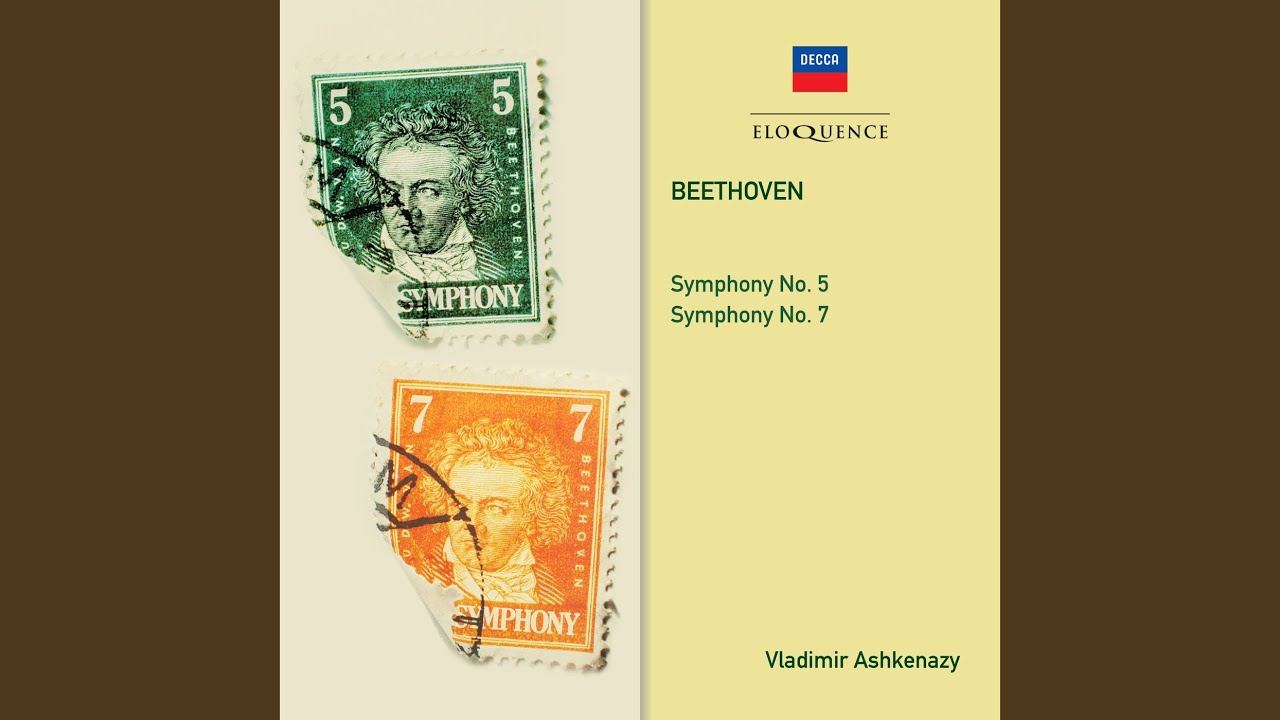アシュケナージの運命、第7番
曲目/
ベートーヴェン 交響曲 No.5 ハ短調 Op.67 (1808)
1. Allegro con brio 8:08
2. Andante con moto 10:45
3. Allegro 5:24
4. Allegro 11:23
ベートーヴェン 交響曲 No.7 イ長調 Op.92 (1812)*
1. Poco sostenuto - Vivace 15:35
2. Allegretto 10:18
3. Presto - Assai meno presto 8:27
4. Allegro con brio 7:05
録音:1981/03、1983/10*
P:アンドルー・コーナル
E:コリン・ムファット、ジョン・ダンカーリー*
DECCA 4785220
アシュケナージは晩年NHK交響楽団とベートーヴェンの交響曲全集を録音しましたが、指揮者としての初期のキャリア時代にはフィルハーモニア管と3曲を録音しています。ここに収録されている交響曲第5番はその最初の録音になるものです。最初はLPレコードとして発売され、併録はレオノーレ序曲第3番でした。その後はCDでこの5番と7番のカップリングで1990年代に再発され現在に至っていますが、すでに忘れ去られているようです。ちなみに残りは「田園」が録音されただけで終わっています。
この頃アシュケナージはフィルハーモニア管の首席客演指揮者でしたが、首席指揮者はジョゼッペ・シノーポリに決まってしまい、後が続かなかったのでしょう。また、ちょうどそのころフィルハーモニアはEMIにザンデルリンクでベートーヴェンの交響曲全集を録音しており、そちらの方が話題になったこともデッカが全集化を諦めた原因の一つではと推測します。
アシュケナージは冒頭の運命の動機を従来のオーソドックスなテンポで比較的ゆっくりと演奏しています。そこにはちよっと緊張というものが感じられません。提示部はそれほどでもないのですが、全体にリズムは軽めで音楽が流れていきます。
これに対してほぼ同時期に録音されたザンデルリンクの方は冒頭は同じようなテンポで進んでいきましが、後は音楽が地に着いた推移で、どっしりと重厚感があります。同じオーケストラなの違いは歴然としています。
|
|
第1楽章 |
第2楽章 |
第3楽章 |
第4楽章 |
合計 |
|
アシュケナージ/PO |
8:08 |
10:45 |
5:24 |
11:23 |
35:40 |
|
アシュケナージ/NHK |
7:23 |
9:38 |
4:55 |
10:57 |
33:59 |
|
ザンデルリンク/PO |
8:04 |
10:38 |
6:05 |
10:23 |
35:10 |
|
ザンデルリンク/ベルリン |
8:01 |
10:34 |
5:48 |
9:36 |
33:59 |
新旧の演奏時間を比較してみました。これからわかることはセッションとライブの違いこそあれ、アシュケナージは決して老人病にはなっていないということです。ただ、当時は状況が悪かったとは言えるでしょう。ちなみにNHKとの演奏はベーレンライター版を研究した痕跡がうかがえます。
ということで、2楽章以下も70年代の演奏スタイルを引き継いだ解釈で、ザンデルリンクとの比較ではやや部が悪いといった印象はぬぐえません。また、オーケストラのまとめ方も第二楽章のコーダではでが揃わないと言ったアンサンブルの乱れもあり、今となっては市場価値も下がっているような気がします。
全体としては下の演奏になっています。
カップリングされているのは交響曲第7番です。こちらもやはり70年代までのスタイルを引き継いだステイルによる演奏と言えるでしょう。どっしりとした構えはドイツ伝統の様式を踏まえています。しかし、どうしても指揮という行為にまだ十分慣れていなないのか音楽の流れに乗れてない危なっかしさが感じられます。当時はアシュケナージはフィルハーモニアのシェフになり損ねてプレヴィンからロイヤルフィルのポストの禅譲を持ちかけられています。この時代なかなか指揮者への転向は生易しいものではありませんでした。ウィーンフィルのコンマスから指揮者に転向したワルター・ウェラーしかり、ロンドン響のホルン奏者だったバリー・タックウェルしかりでしょう。
フィルハーモニアの大御所、クレンペラー並みのスケール感を狙ったような演奏ですが、全体の安定感は今ひとつです。テンポはクレンペラーよりも遅いのですが、全体としてのまとまりは第5番よりははるかに充実しています。この2年間で、指揮者としてのアシュケナージは格段の進歩をしているように見受けられます。前任のムーティはこのフィルハーモニアとはベートーヴェンの交響曲は録音していなかったので、チャンスと意気込んだのでしょうが、ザンデルリンクに掻っ攫われたという状況ですな。
この演奏自体はそれほど悪くはありません。アシュケナージも当時はこの楽章が一番人気があることを睨んで、じっくりしたテンポで切々到達ていきます。
第3楽章は一転、畳み掛けるようなテンポで突き進んでいきます。ここも全体のバランスから行ってなかなかいい仕上がりです。デッカとしてはアシュケナージで推していきたかったんでしょうなぁ。
この7番はブラインドテストで聴いたなら、かなりいい線を行く演奏と捉えられるのではないでしょうか。
ちなみに、ザンデルリンクのベートーヴェンはレコード時代には第3番と第6番しか発売されていません。不遇でした。しかし、本国イギリスではこのアシュケナージの録音より、ザンデルリンクとの演奏の方が好評だったんですなぁ。てなこともあり、デッカは急遽ショルティ/シカゴでデジタルによる第2回目の全集に取り組むことになります。