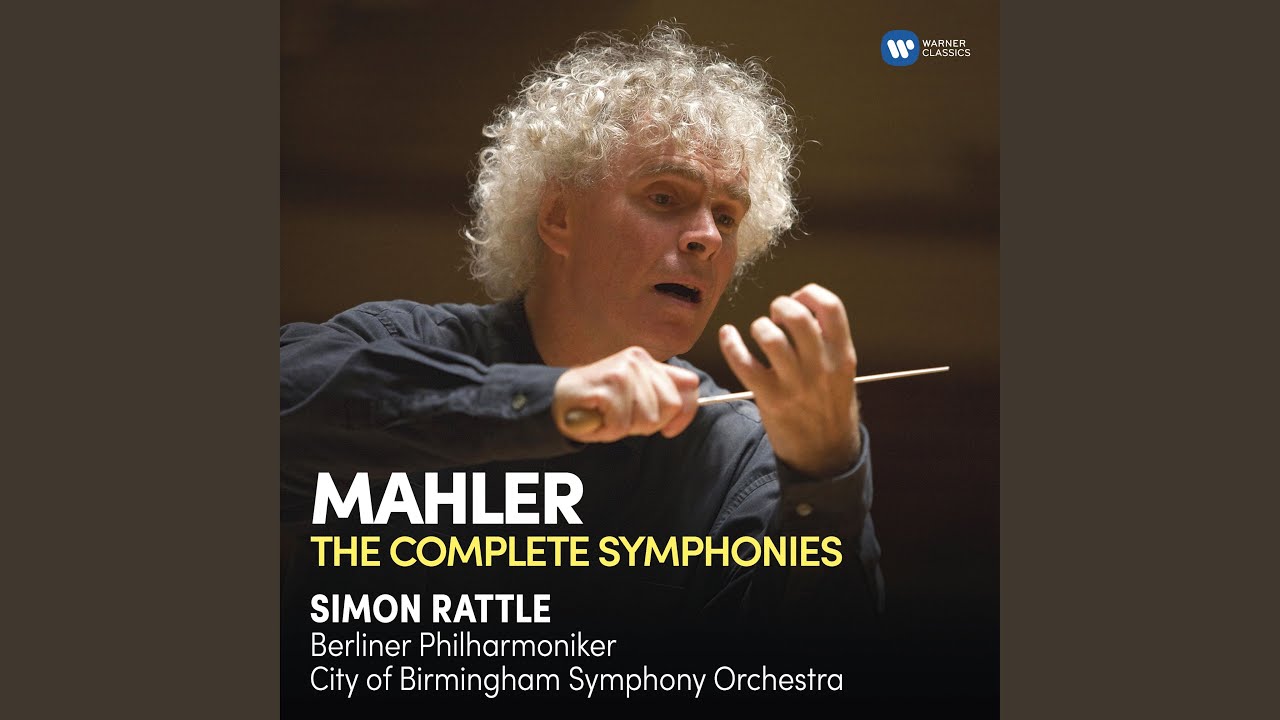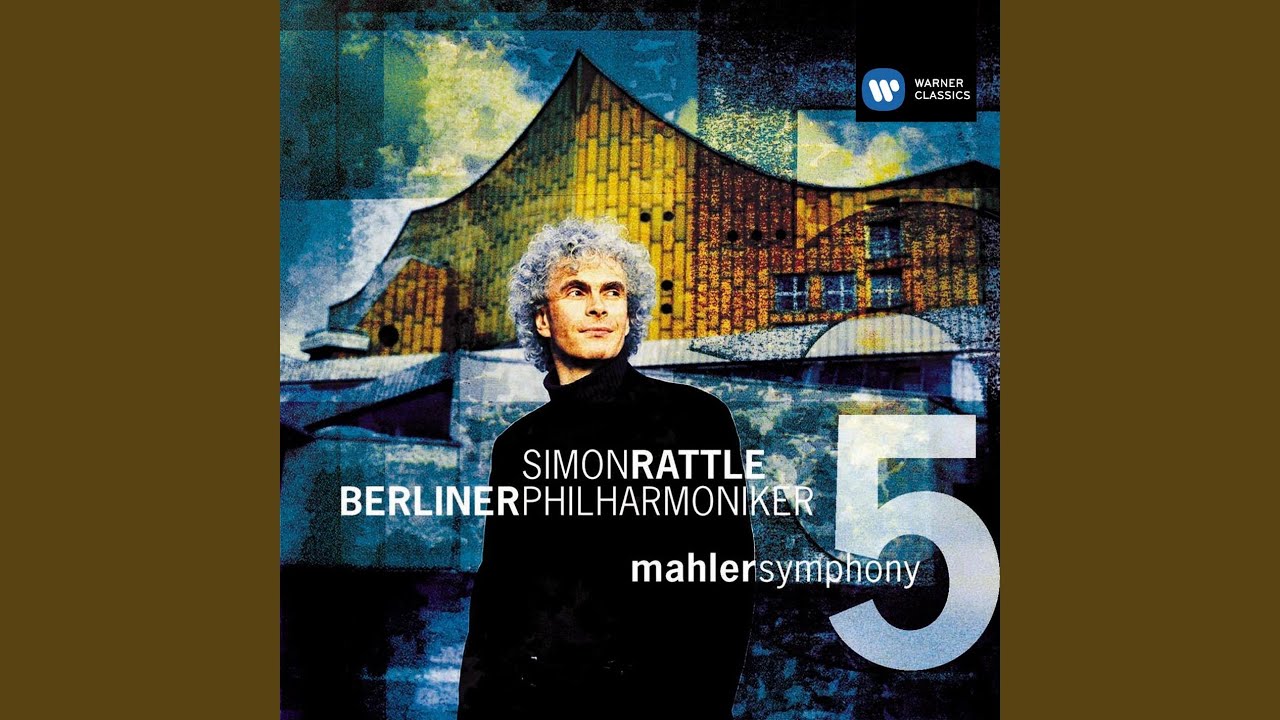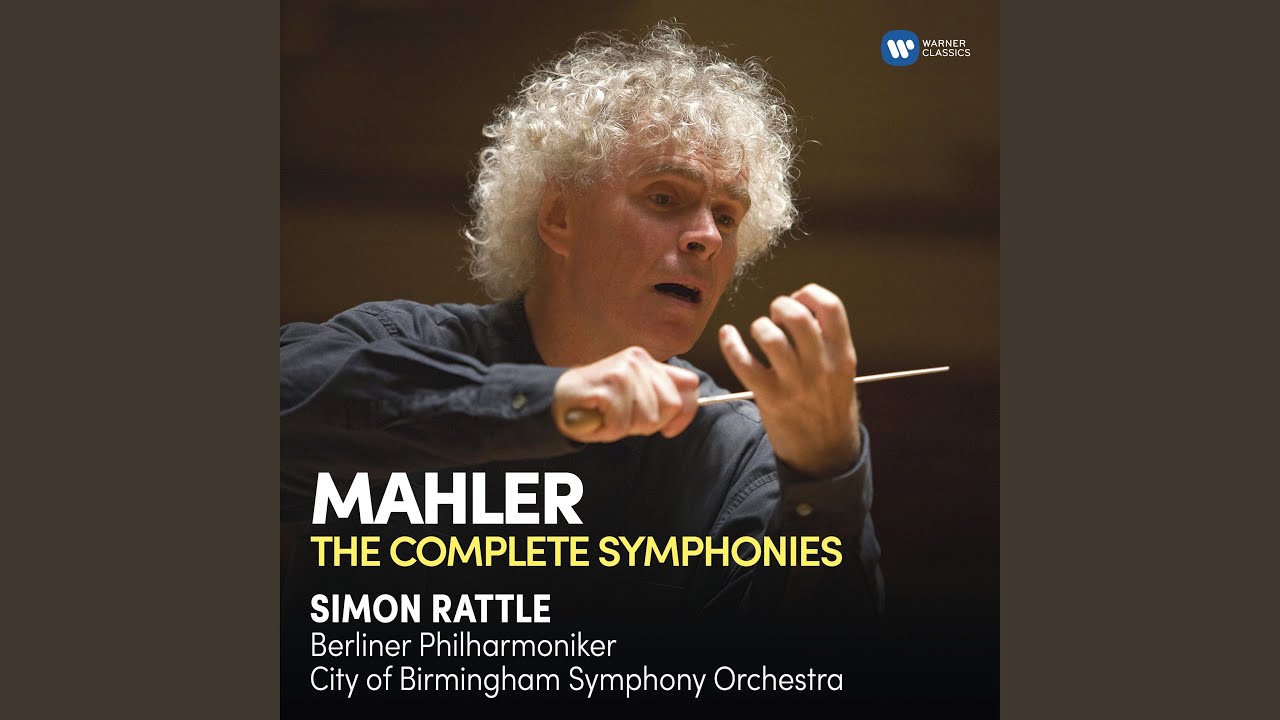サイモン・ラトル
マーラー交響曲第5番
曲目/
マーラー 交響曲 No.5 嬰ハ短調 (1902)
1. Trauermarsch. In gemessenem Schritt, Streng, Wie ein Kondukt (葬送行進曲,威厳のある歩調で,厳格に,葬列のように) 13:04
2. Sturmisch bewegt mit grosster Vehemenz (嵐のように激しく,一層大きな激しさで) 14:29
3. Scherzo (Kraftig, nicht zu schnell) (力強く,速すぎぬように) 16:59
4. Adagietto. Sehr langsam (とてもゆっくりと) 9:32
5. Rondo - Finale. Allegro (快速に生き生きと) 15:02
指揮/サイモン・ラトル
演奏/ベルリンフィルハーモニー管弦楽団
録音/2002/09/07-10 フィルハーモニー
P:ステファン・ジョンズ
BE/マイク・クレメンツ、グラハム・カービィ、アンディ・ビール
warner 0190295869175
この録音はラトルのベルリンフィル音楽監督就任初の記念演奏会の録音です。ラトルはEMIにおいて意識的にマーラーの交響曲全集を録音してはいなかったようで、ベルリンフィルの音楽監督に就任後に、この5番をはじめ、9番、10番を録音しています。まあ、若き日に第10番をボーンマス交響楽団と録音していますが、さすがにちよっとレベル的には全集として発売するには物足りないレベルのものだったのでしょう。音楽監督就任記念演奏会
の録音とあって、この演奏は映像でも残されています。
その映像でも確認できることですが、トランペット・ソロで開始される1楽章は、2002年より首席奏者に就任したタマーシュ・ヴァレンツァイ(b.1962、ハンガリー出身)の妙技が披露されています。彼は伝説のシカゴ響の首席奏者、アドルフ・ハ―セスにも師事していたという逸材です。さて、冒頭こそは大人しいもののすぐにラトルの本領が発揮されていきます。まるで高性能のオーケストラの出現を待っていたかのように、天下のベルリンフィルをこの任記念演奏会から思いっきりドライブしています。聴き進むにつれて、店舗を細かく動かし、それでいて切れ味鋭くそれまでのバーンスタインやテンシュテットの濃厚な表現とは違うさらりとした表現で演奏していきます。まあ、最初聴いた時はなんだこれはと違和感を覚えたものです。まあ、この記事を書くにあたって繰り返し聴くうちに少しは慣れて来ましたがね。そんな第1楽章です。
第2楽章も驚きの連続です。これが2000年代の新しいマーラーのアプローチかもしれません。ここでは、甘美に旋律を歌う部分と動的ダイナミズムを活かす部分が鮮やかにコントラストを成しています。テンポを目まぐるしく変え、例えば打楽器の強烈なアタック(後拍)をほんの少しタメたり遅らせたりする絶妙のリズム感でオーケストラを引っ張っています。こういうアプローチはそれまでのバーミンガム市交響楽団では出来ないものだったのでしょう。
CDで聴くぶんには気がつかないかもしれませんが、この楽章では珍しいアプローチを取っています。それが3楽章スケルツォのオブリガード・ホルンです。このオブリガード・ホルンを指揮者の横で、まるで協奏曲のように吹かせるのです。裏話があり、ラトルはベルリンフィル首席ホルン奏者のシュテファン・ドールにリハの前日に「3楽章のオブリガード・ホルンを指揮者の横で吹いて欲しい」と電話したそうです。この演奏会のDVDを観ると、2楽章が終わり1stホルンの場所に座っていたドールが立ち上がり、一旦舞台袖に行き再び指揮者の横へ出てきて、3楽章オブリガード・ホルンを立奏で演奏しているのが分かります。なんでも、マーラーの残された書簡の中にこういう形の演奏会をしたことがあるようで、ラトルはマーラーと指揮者ウィレム・メンゲルベルク(1871-1951)の往復書簡に基づいたアナリーゼでそれを再現したものでしょう。こういうのは映像が残っていて初めてその様子と効果がわかろうというものです。5楽章形式のこの曲の頂点をここに持って来ていて、曲を新芽リックに組み立てています。普段は第4楽章のアダージェットに目が行きがちのこの曲ですが、こういうアプローチにもラトルの解釈の斬新さが感じられます。
この楽章でもラトルの音楽はテンポを大きく動かしそのラトルにしっかりとついて行っているオーケストラはやはりすごいですなぁ。
ホルンが1人「前に出てきて吹く効果」というものは、録音だけのCDではなかなか分かり難い。やはり視覚的効果が大きい。しかし、この効果は生の演奏に接した際、素晴らしい効果を発揮している。
まず、ホルンの通常の位置と前に出てきて吹く際の音色の違いである。前に出てきて吹く方が、より生音を聴き取れ、圧倒的存在感を生む。また、「Schalltrichter auf!」の指示が頻繁に出てくるので、ホルンのベルを高々と上へ掲げて吹くその音色的・視覚的効果もある。
そしてメインのマーラー。まず耳に(目に)付いたのはベルリン・フィルの新時代を予感させるスター・プレーヤーの名技。トランペット・ソロで開始される1楽章は、2002年より首席奏者に就任したタマーシュ・ヴァレンツァイ(b.1962、ハンガリー出身)の名技が光る。。
きらりと輝くベルの刻印から、彼はウィーン・フィル元首席、ハンス・ガンシュ(b.1953)と同様、シャガールのロータリー・トランペットを使用しているのが確認された。元首席のコンラディン・グロート(b.1947、1974~1998年まで在籍)譲りの輝かしい音は、まさにベルリン・フィルのブラスセクションの証だ。
3楽章では首席ホルン奏者のシュテファン・ドール(b.1965)がステージ前に移動して演奏(画像下)。コンサートマスターの前に立って演奏するというスタイルは、マーラーと指揮者ウィレム・メンゲルベルク(1871-1951)の往復書簡に基づいただが、この辺りのパフォーマンスも中々ニクい。
そして、第4楽章です。まあ、この曲の聴かせどころですが、ラトルはいささか肩透かしを喰らわせるかのように、濃すぎず耽美に走らず、ひたすらアダージェットで演奏しています。そう、この楽章はアダージョではないんですなぁ。バーンスタインやアバド、小沢なんかは完全にアダージョで12分ほどかけて演奏していますが、ラトルは9分半で駆け抜けています。
第5楽章はやたら元気です。このろくおんについてしらべているとねこのラトルの交響曲第5番は音楽学者で国際グスタフ・マーラー協会副会長でもあるラインホルト・クビーク教授の手になるクリティカル・エディションを用いていることがわかりました。そういう意味でも、ラトルの演奏が一味違うマーラーになっている印象があることと関係があるのでしょう。なにしろ、ダイナミクスやアーティキュレーションなどの細かな校訂中心に、実に800箇所に及ぶ変更が加えられているそうです。まあ、そういう点でも異色の演奏ということが言えましょう。この楽章では弦セクションのアンサンブルの良さが際立っています。この時のコンサートマスターは安永徹氏が務めています。
リリース時には賛否両論のあった演奏ですが、従来のマーラーの第5番を聴いていた人にはやはり、カルチャーショックがあったのは当然と得ましょう。しかし、やがてこういう演奏がこの曲のスタンダードになる日が来るのではないでしょうか。