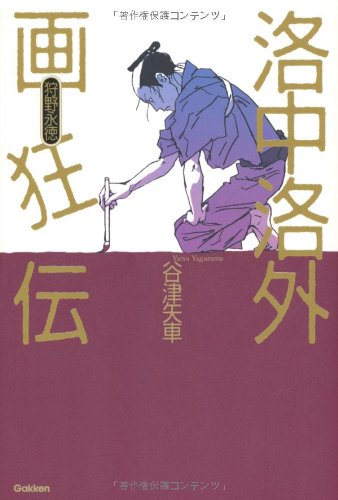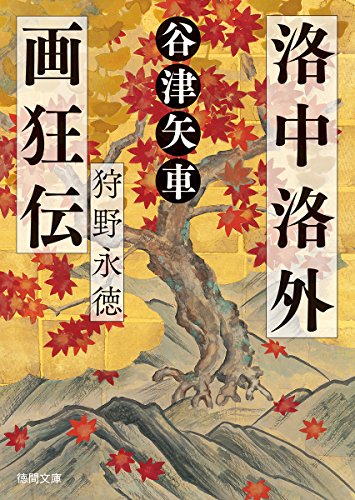洛中洛外画狂伝―狩野永徳
著者:谷津 矢車
出版:学研パプリッシング
「予の天下を描け」。将軍足利義輝からの依頼に狩野源四郎は苦悩していた。織田信長が勢力を伸ばし虎視眈々と京を狙う中、将軍はどのような天下を思い描いているのか--。手本を写すだけの修業に疑問を抱き、狩野派の枠を超えるべく研鑽を積んできた源四郎は、己のすべてをかけて、この難題に挑む! 国宝「洛中洛外図屏風」はいかにして描かれたのか。狩野永徳の闘いに迫る傑作絵師小説。---データベース---
最近になく一気読みをした作品です。この作品は、かの狩野永徳の「洛中洛外図屏風」の制作秘話であり、それは戦国時代に天下を狙う男たちの闘いの物語でもあります。NHKの大河も戦国武将を描くだけでなく、こういう文化人にもスポットを当てれば少しは違う視聴者を獲得できて、視聴率ももう少しアップするのではないでしょうかねぇ。
本作は、因習と対立しながらも、時の権力者たちとの接触を通じ、己の道を切り拓いていく狩野源四郎の成長物語です。個人的にも狩野永徳の名前こそ知っていましたが、どういう生涯を送ったかについては全く無知でした。この作品、調べたwikiに記載されていないところを見るとどこまで信憑性があるのかわかりませんが、室町末期から信長の台頭までを描いた時代に時の権力者にうまく取入り、時代の先を読む能力も優れていたことに気付かされます。まあ、そこには日乗という陰陽師が登場し、何かと永徳の水先案内人のような存在がいたことも留意しなければララないでしょう。この日乗、陰陽師でありながら後に僧としても活躍するのですが、この時代にキリスト教敗訴を掲げる朝山日乗を思わせます。多分史実とは異なるのでしょうが、唐突に登場するこの日常が永徳こと狩野源四郎の物語に幅を与えています。章立ては以下のようになっています。
目次
■プロローグ
1 軍鶏
2 錆色
3 魔境
4 競絵
5 業火
エピローグ
長編小説なので登場人物を整理すると次のようになります。
◆主な登場人物◆
狩野源四郎:狩野家若惣領で、後の狩野永徳
狩野松栄:源四郎の父で、狩野家惣領
狩野越前元信:源四郎の祖父で、松栄の父。狩野家総元締
狩野元秀:源四郎の弟
廉:土佐家の縁者の娘
福助:膠小屋の老人
平次:福助の孫
安:扇商の美玉屋の若主人
日乗:陰陽師で僧、日食を当てる
足利義藤:室町幕府十三代将軍で、後の義輝
松永弾正:三好長慶の家臣で、京の差配を任されている
宗養:連歌師
近衛前嗣:公家でありながら武術に通じる。関白左大臣で、後の前久
織田信長:尾張の領主
物語は上洛した織田信長と狩野源四郎の対面の場面から開始されます。そう、この物語は源四郎が室町幕府の最後の将軍足利義輝に県ジョゥするはずだった一幅の屏風「洛中洛外図」を信長に献上するシーンから始まるのです。そして、源四郎の口から、自身の半生と屏風に託した思いを語るという手法で開始されます。
天文十七年、狩野源四郎は六歳のとき、実物の蝶を捕まえて描いた絵のことで、父で師匠の松栄から手厳しく叱られた。参考にするのは粉本(手本帳)であり、実物を見て描くことは魔境に入ることであると、繰り返し小言をもらいます。この父との確執がこのストーリーの一つの柱とも言えます。その父との言い争いにより絵を描くことに倦んだ源四郎を祖父の元信が京の町に連れ出します。この元信こそ粉本を著した本人ですが、本信は源四郎にそれを押し付けません。早くから源四郎の才を見抜いていたのでしょう。
京の街中の辻の端っこで、賭け闘鶏をしているのに出くわして、はぐれ狼のような武者を思い起こさせる二羽の鶏の姿に興味をもつ。墨の持ち合わせのない源四郎は、鼻血を墨の代わりにして元信から渡された懐紙に、夢中で絵を描きます。そこへ、十人あまりの侍を従えて貴人の少年が闘鶏の見物にやってきます。闘鶏の勝負がつくと、少年は源四郎の鼻血に気付き話しかけてきます。そして、懐紙の上に血で描かれた鶏の姿を、「見事な絵ぞ」と褒めたのです。これが源四郎と足利義藤(義輝)の初めての出会いです。
源四郎の祖父狩野元信は優れた絵師であると同時に商売上手です。狩野派を画工集団としての基礎を築いた人物で、以後400年の長きに渡り狩野派全盛の時代の基礎を作った人物です。隠居後は、自分の作品をなぞる紛本を息子の松栄に描かせることで、狩野派の隆盛を支えます。その孫の源四郎は、それに飽き足らず、オリジナル作品に拘ります。紛本に執着する父松栄と源四郎の対立を軸に、もう一つの柱として、スポンサーとなる足利義輝との交流が描かれます。後に有名となる洛中洛外図のような作品は義輝みたいな依頼者があって可能なもの。本来の狩野家の生業は扇の絵を粉本によって大量生産することだったことがこの作品から伺い知れます。将軍家の衰退と新たな支配者の台頭、弱肉強食は絵師の世界でもあったのだと納得させられます。そして、ここに当時のもう一つの流派土佐派も登場し、その土佐家の娘が許嫁として狩野家に入ります。この小説で永徳の妻が廉だということを初めて知りました。土佐派と狩野派は、宮中や幕府の御用絵師、絵所預(えどころあずかり)を勤めた日本画の二大流派です。日本古来の大和絵を発展させた土佐派と、中国風の画法に大和絵の技法を融合させた狩野派は敵対関係ではなかったのですな。
さて、最初に永徳の事績が記録に現れるのは山科言継の日記『言継卿記』の天文21年1月29日(1552年2月23日)の条で、この日に狩野法眼(元信)が孫を連れて将軍・足利義輝に拝謁したことが記録されており、この「孫」が当時10歳(数え年)の永徳と推定されています。この小説でもそのシーンは描かれており、義輝が闘鶏の時の出来事を源四郎に問いただすシーンが描かれています。
この作品は、狩野源四郎と、足利義輝、松永弾正、織田信長ら京の町を統治し、天下に号令しようとする権力者たちとのやり取りを通して、戦国時代を鮮やかに描き出しています。そしてそこには、京の町に暮らす人びとの姿も源四郎の目に映ったままに織り込まれています。
この本では「洛中洛外図」の以前に元信との思い出を描いた作品も登場します。これは「洛外名所遊楽図屏風 四曲一双」のことわ指しているような気がしないでもありません。この作品は平成17年(2005年)7月、京都の古物商で発見されたもので、落款等はないが上杉本洛中洛外図と描写法が良く似ており、上杉本より少し前の作と推察されています。
そういう近年の成果までも取り入れた力作で、源四郎の人となりと「屏風」の制作秘話であり、それは戦国時代に天下を狙う男たちの闘いの物語でもあると言えるのではないでしょうか。まさに大河ドラマにふさわしい内容でしょう。さあ、NHKは動くでしょうか?
最近文庫本も出ています。