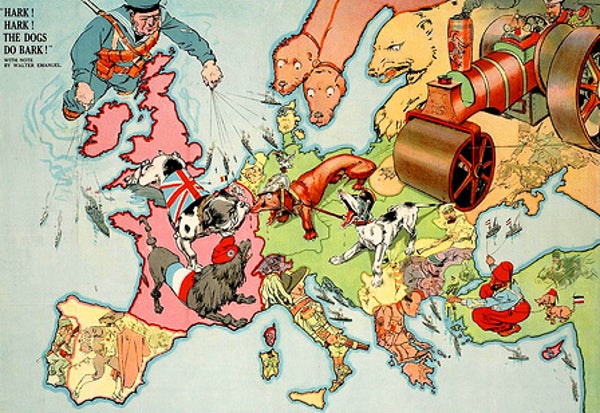毎年、年末に発表される「アイドル楽曲大賞」を紹介しつつ前年のアイドルについての話を書いています。
テレビという大衆メディアのお祭りであるNHK『紅白歌合戦』における「日本のアイドル」像はひとつの基準になるでしょう。
2025年に出演した現役アイドルは、
KAWAII LAB.から〈CANDY TUNE〉と〈FRUITS ZIPPER〉。
BMSGから〈BE:FIRST〉と〈HANA〉。
EBiDANから〈M!LK〉。
K-POPはHYBEから〈ILLIT〉と日本支社の〈&TEAM〉に、SM社の〈aespa〉。
旧ジャニーズの後継であるSTARTOからは〈King & Prince〉と〈SixTONES〉。TOBEから〈Number_i〉。
秋元康プロデュースを冠したチームは結成20周年記念でようやく出れた〈AKB48〉とついに坂道グループ最後の一組になった〈乃木坂46〉。
何となく基本大枠として各社/各グループから2チームずつ選んだ感じですね。一時期の日本の男性アイドルはジャニーズ、女性アイドルは秋元康プロデュースが枠を独占していた時代に比べるとバランスは良くなっています。
……これでも「最近のアイドルは全部同じに見える」と言うのなら、問題があるのは同じに見える人の方にあるし、ジャニーズと秋元康の悪口を言って「日本のアイドルは〇〇だ」と全てを語った気になっているような人はNHKが想定する大衆よりも文化水準が低いってことになる。
その出演者の中で、2025年に最も躍進したアイドルといえば、女性は〈HANA〉、男性は何と言っても〈M!LK〉になるでしょう。
25年3月発表の『イイじゃん』が〈aespa〉の『Whiplash』に似ているとK-POPファンに叩かれながらも「悪名は無名に勝る」とばかりに知名度が上がり、歌詞中の「今日ビジュイイじゃん」が大バズり。
続けて、10月発表の『好きすぎて滅!』もバズって一気にメインストリームへと駆け上り『紅白歌合戦』出演に至るまでの大衆的知名度も得ました。
NHKが25年の『紅白』に24年発表の『Whiplash』で〈aespa〉を呼んでいるのも〈M!LK〉の『イイじゃん』とセットで並べたかったのでしょう。直前にネトウヨが暴れたので〈aespa〉企画は無くなったみたいですが。(……暴れてるネトウヨも、それに反発して「日本のアイドルはお遊戯会」と暴れてる連中のどちらも「知」に対して不誠実。うんざりします)
〈M!LK〉はスターダストプロモーション社の男性アイドル部門EBiDAN所属で2014年結成。ポッと出ではなく十年以上の活動歴がありようやく地上に到達したチームです。各社/各グループから基本2組という枠なら、もし〈aespa〉が来なかった場合は同じ事務所で2015年結成の〈超ときめき♡宣伝部〉が出れたのだろうな。
とはいえ、エースである佐野勇斗と元メンバーの宮世琉弥は若手の主演級俳優として「テレビ」でも活躍していますので、逆にこれまで知名度が低かった方が不自然ではありました。理由はまあ…分かりますよね。ただ、旧ジャニーズ社への忖度もあったのでしょうが、テレビ局に代表されるマス向けメディア側が旧ジャニーズグループや秋元康プロデュース以外にも日本のアイドルがいる、という多様性を、複雑さを厭う大衆に媚びて均質化したフォーマットで提供するために無視してきたのもあるのでしょうし、テレビが提供するものの外に情報を自ら求めて行くことはない大衆がいての共犯関係。旧ジャニーズ社だけを悪者にするつもりはありません。
……少し前に時代劇のキャスティングには風土を感じさせる顔で選んでほしいという話を書きました。〈M!LK〉メンバーって時代劇顔だよな。『紅白』での坂本冬美とのステージの着物姿も話題になりましたが、三河岡崎の佐野勇斗は徳川家もの、薩摩と大隅の間にある霧島市出身の吉田仁人は幕末もので薩摩藩士、足利市出身の山中柔太朗も足利一門が似合いそう。伊勢の曽野舜太に、塩﨑太智は和歌山出身だけど河内っぽい。
風土を感じさせる顔って、アイドル界に大量に人材がプールされているのだから活用すれば良いのにな、なんて男女どちらのアイドルを見ていても思います。
「K-POPスゴイ。それに比べて日本のアイドルは芋だ」なんて言う人もいるけど、例えば、地方48グループでは農家の娘が農家の娘のままアイドルをしていたりしますが、それの何が悪いのだろう?
カルチャーに多様性ではなく、単一であることを求める感覚が私には分からない。
2025年は〈M!LK〉にとって元メンバーたち含め色々あった年でした。そうそう、女性アイドル〈ZOCX〉に猫猫猫はうとして加入したはうきも〈M!LK〉出身でしたね。
旧ジャニーズと坂道がアイドル枠を独占していた時代はファンの嫉妬を恐れて男女のアイドルの共演は避けられていましたが、今は積極的にTikTokを撮るなど交流を見せる方針になったのも良い変化だし、ジェンダーを越えて活動できるようになったのも良い変化です。
ここからは、女性アイドル楽曲を中心とした「第14回アイドル楽曲大賞2025」の上位20位までを見ていきます。
メジャーアイドル楽曲部門の上位20位までを。
1位. CYNHN『ノミニー』
2位. =LOVE『とくべチュ、して』
3位. CYNHN『息のしかた』
4位. 超ときめき♡宣伝部『超最強』
5位. AiScReam『愛♡スクリ~ム!』
6位. Perfume『巡ループ』
7位. いぎなり東北産『らゔ♡戦セーション』
8位. でんぱ組.inc『W.W.D ENDING』
9位. 清 竜人25『世界を愛せますように』
10位. 東京女子流『夏の密度』
11位. 私立恵比寿中学『SCHOOL DAYS』
12位. ≠ME『モブノデレラ』
13位. フィロソフィーのダンス『迷っちゃうわ』
14位. =LOVE『ラブソングに襲われる』
15位. 東京女子流『導火線、フラッシュバック』
16位. CiON『しましょ』
17位. ≒JOY『ブルーハワイレモン』
18位. lyrical school『朝の光』
19位. CYNHN『わるいこと』
20位. わーすた『わーるどすたんだーど』
1位は前年に続き〈CYNHN〉。3位にも入っているのでこの界隈を代表するチームとなったのでしょう。所属はディアステージ。
2位は〈=LOVE〉で、姉妹チームの〈≠ME〉〈≒JOY〉と併せて秋元康が後継者として認める指原莉乃のプロデュースするグループは一大勢力を形成しつつあります。
……木村ミサ率いるKAWAII LAB.グループと指原莉乃率いるイコール系グループという元アイドルの三〇代女性プロデューサーによる「カワイイ」対決が現在の「日本の女性アイドル」の状況です。
この二人より一世代上にはディアステージを率いる福島麻衣子やTokyo Pinkを率いる大森靖子、一世代下には〈HANA〉のちゃんみななどがいるわけですが、こうした女性プロデューサーたちの存在を透明化し無視して、秋元康だけで「日本の女性アイドル」を語ろうとするのは、ジェンダー規範に囚われた女性差別的な言動なんじゃないですかね。
一方で、〈Perfume〉の活動休止は別格としても、〈東京女子流〉、さらには〈フィロソフィーのダンス〉の解散は一時代の終わりを感じさせます。2025年には加えてWACKグループの全チーム解散/放出も渡辺淳之介の敗北宣言とともに話題になりました。〈BiSH〉を旗艦に2010年代後半のアイドル業界を引っ張ったWACKが全面再編に追い込まれ、25年年末には2010年代前半を引っ張った〈ももいろクローバーZ〉を旗艦とするスタプラでも複数チームの解散が同時発表され、事務所側社員人事も含めてグループの全面再編があるようで、2010年代とはアイドル周りの環境が激変しています。
〈CYNHN〉の所属するディアステでも、旗艦だった〈でんぱ組.inc〉が25年に解散すると最も人気のあるチームは「アキバ系」ではない外様の〈きゅるりんってしてみて〉になっていますから時代は変わりました。
こうした状況のなかで、2025年の「アイドル楽曲大賞」メジャーアイドル部門は「楽曲派」の好むタイプの曲とバズ狙いの曲が入り混じった上位層。
世界的に大バズしたのは5位の〈AiScReam〉による『愛♡スクリ~ム!』。
ここはライブアイドルではなく、2010年からアニメなどのメディアミックスで展開する『ラブライブ!』シリーズに出演していた声優によるステージから始まった声優アイドルですが、ライブアイドルを主に扱うランクにも入るほどの大バズでした。
ゆえに、『愛♡スクリ~ム!』が日本国外で「J-POPアイドル」とか「日本のアイドル」として紹介されているのを見かけるとなんだかモヤモヤします。声優アイドルはアイドルの派生ではなく声優からの派生なのでジャンルが違うし、属するカルチャーも違うのではないか、と。
ただ、日本のポップカルチャーの面白いところは、何か一つが流行ったらそれだけになるのではなく、マスとは異なる場所で、様々なジャンルが(ビジネスとして成り立つレベルで)並存して動いていることにあると私は思っています。
だからこそモノカルチャーではない、多様な表現をもっと知った上で、それから語ればいいのにな、なんて思います。
「アイドル楽曲大賞」とは別枠なのでここには載っていませんが、「ハロプロ楽曲大賞」で1位となった〈Juice=Juice〉の『盛れ!ミ・アモーレ』はステージの力でちゃんと(国内限定ではあるものの)バズった曲でした。
「日本にも口パクせずに踊りながら歌えるアイドルがいるんだ」なんて驚かれていましたが、〈Juice=Juice〉は〈モーニング娘。〉を旗艦チームとするHello! Projectグループ(通称:ハロプロ)所属で結成は2013年。十年以上の活動歴があります。
……「日本のアイドルは口パクばかり」なんて言う人もいますが「ばかり」ってのはどこの日本の話なんだろう?
続いて、インディーズ/地方アイドル楽曲部門の上位20位までを。
1位. タイトル未定『空』
2位. fishbowl『蒼霞』
3位. ラフ×ラフ『君ときゅんと♡』
4位. きのホ。『秋刀魚』
5位. Ringwanderung『LV』
6位. RAY『plasma』
7位. AQ『SKUMSCAMSCUM』
8位. 0番線と夜明け前『わたしは水になりたかった』
9位. ハルニシオン『ハルニシオン』
10位. CUBΣLIC『シュガビタ』
11位. ばってん少女隊『こっちみて星☆』
12位. RAY『おとぎ』
13位. RYUTist『Unknown Us』
14位. 美味しい曖昧『パフェクト』
15位. yosugala『コノユビトマレ』
16位. きのホ。『大問題』
17位. きゅるりんってしてみて『Special♡Spell』
17位. yosugala『何億分の1を』
19位. TEAM SHACHI『晴れ晴れ』
20位. AMEFURASSHI『Don't stop the music』
インディーズ/地方アイドル部門では、札幌拠点の〈タイトル未定〉が1位で、2位の〈fishbowl〉は静岡拠点。
「地下」の覇者であり良くも悪くも「地下」における話題の中心だった〈iLiFE!〉を旗艦とするHEROINESグループが上位に入らないのはこの界隈の相変わらずですが、「カワイイ」系に押されて弱体化している「楽曲派」のなかでリーダー的存在になりつつあるのが、京都拠点の古都レコード勢。〈きのホ。〉に続いて24年に活動開始した〈AQ〉も京都らしいカレッジチャート感があって良い。8位の〈0番線と夜明け前〉も京都拠点のチームです。
……ランキングから離れた余談になりますが、地方アイドルというと、K-POPアイドルの〈i-dle〉が25年10月に発表した『どうしよっかな』MVは、韓国では「日本の地方アイドル」と『ラブライブ!』的世界観は入り混じりこう見えているのか、という意味で面白い。
また、さらにアイドルからも離れますが、韓国で音楽チャートMelonの2025年年間10位とヒットした〈10CM〉の『너에게 닿기를』は、北海道を舞台とする少女マンガ『君に届け』アニメ版主題歌の韓国語カヴァーですが、「韓国人が郷愁を感じる田舎としての日本」という感覚は興味深い。
2020年代半ばに至ってようやくアイドルのテレビ出演枠が解放され、ジャニーズと秋元康プロデュースとK-POPのみで構成される時代が続いてきたテレビの音楽番組に、「地下」や「地方」からもテレビ「地上」波の音楽番組に出れるようになりました。
きっかけのひとつは、フジテレビで2024年に始まった公開オーディション「TIF×FNS歌謡祭コラボ企画」。24年に初の出演権を獲得したのは〈タイトル未定〉でしたが、25年は〈Devil ANTHEM.〉。ここも2014年結成ですから活動歴は十年以上でようやくです。
とはいえ、TBSの『SASUKE』出演権を賭けたやはり24年に始まった「アイドル予選会」もそうですが、1枠を巡る過酷な公開オーディションを勝ち抜いてようやくアイドルはテレビ「地上」波に出れるのですから狭き門は変わらない。ぽっと出の若い子がテレビに出てる、なんてことはそうはない。
で、もし私が「アイドル楽曲大賞」に投票するのならば、
バンドサウンドとして6位の〈RAY〉による『plasma』かな。
毎年、〈RAY〉は良いと書いているような気がしますが「インディーズとして」面白い。
クラブサウンドのダンス曲だと、こちらは入っていませんが〈Girls²〉の『LET ME DANCE』。
Y2Kブームなんてここ数年言われていますが、意外とこういう音の楽曲って出ていない。MVは日本国外での何度目かのギャル・ブームで軽くバズったけど日本国内にはあまりフィードバックされなかったな。
そういえば、アイドルではありませんが、子供服のキッズモデルたちによる企画〈KOGYARU〉がドイツで一時ヒップホップ部門1位になったり、ギャル系ファッション誌『egg』のモデルによる〈半熟卵っち〉などが世界的に25年になってからバズっていましたよね。
「男に媚びず、好きなものを好きと言える日本のギャル」というイメージは、日本ではあまり語られませんが相変わらず強い。
「楽曲派」界隈のランキングには入らないアイドルだと、最近、気になっているのは〈BLUEGOATS〉。
前身チームの〈The BANANA MONKEYS〉は悪名は無名に勝るの「炎上系」路線で避ける人も多かったし、2021年に〈BLUEGOATS〉に改編されてからも炎上覚悟の体当たり企画でYouTubeやTikTokの数字は稼いでも、音楽をやるライブアイドルとしての現場の動員には結びついていない印象でした。
しかし、今の路線の〈BLUEGOATS〉は、正直、他のロック系アイドルと比べてスキルが高いとは言えないかもしれないけれど、炎上に頼らずともライブアイドルとしてのパッションと歯車が嚙み合って勢いが出てきた痛快さがある。実際、勢いのあった頃のWACKの界隈にいた人たちがここに集まりつつあるような感触。
26年に期待するチームです。
現在のトレンドであるカワイイ系でもなく、「楽曲派」にも入れてもらえないロック系アイドルはどこも知名度を上げるのに苦労しています。ただ、元〈BiSH〉でソロとして25年の『紅白』にも出場したアイナ・ジ・エンドという存在がある。
K-POPアイドルの方が先に世界で知られるようになったため、日本のアイドルも歴史に反してK-POPの派生のように見られていた時期もありました。しかし、全く異なる進化を遂げてきたのが日本のアイドルというジャンルだ、と世界各国のミュージシャンや音楽ファンに知られ始めてきた2020年代半ば。
〈BABYMETAL〉の成功は知られていても、彼女たちが日本のアイドルにおける特異な存在ではなく、実は、ロックが日本のライブアイドルの本流であることが知られてくると、ロック畑のミュージシャンたちが日本のアイドルに接触するようになりました。
例えば、〈RAY〉の新曲『Bittersweet』は〈RIDE〉のマーク・ガードナーが楽曲プロデュース。
……個人的には〈RIDE〉の名前を久しぶりに目にしました。中学生の頃は好きでよく聴いていたので、この新曲をきっかけに当時の〈RIDE〉の曲を検索してみたらカセットテープにダビングしてウォークマンで聴きながら歩いていた情景まで思い出してきてノスタルジー。
そんな〈RIDE〉のマーク・ガードナーと〈RAY〉の内山結愛の対談(『音楽ナタリー』2025年10月15日付)より。
「ロックは年寄りの音楽」みたいなイメージを覆す存在として、若い女性がパフォーマンスする日本のライブアイドルを応援する空気はこれまでも日本のロック系ミュージシャンにはあり、楽曲プロデュースやバックバンドに付くなど珍しい話ではありませんでしたが、U.K.ロックを日本人が歌う面白さみたいなものが英国に逆流しているわけです。
"退屈な音楽に合わせてパフォーマンスをするグループがいっぱい"な現状に抵抗する象徴として期待するマーク・ガードナーの日本のアイドルに対する認識は、日本のアイドル楽曲を聴かない人たちには驚きをもって感じられるのではないでしょうか。特に「日本のアイドルは〇〇だ」と単純化して何かを語ったつもりになっているような人には。
再編後のWACKグループは拠点をロンドンに移すようですが、こうした空気に賭ける意図もあるのでしょう。ただ、〈WARGASM〉のサム・マトロックが楽曲プロデュースした〈ASP〉の『MAKE A MOVE』も曲としては良いけど数字として上手くいったとは言い難い。〈Bring Me The Horizon〉と〈BABYMETAL〉の『Kingslayer』との規模感の違いもあるとはいえ。
「日本のアイドル」とは何か? という話を、『楽曲派アイドルガイドブック』(2025年)に収録された〈RAY〉の内山結愛、〈XOXO EXTREAM〉の一色萌、〈メロン畑a go go〉の中村ソゼの三人へのインタビューから。

〈RAY〉のシューゲイズも〈XOXO EXTREAM〉のプログレも〈メロン畑a go go〉のロカビリー(にサイコなB級映画テイストを加えたサイコビリー)も、〈BABYMETAL〉のメタルや〈fruits Zipper〉の原宿カワイイ、「テレビ」で一時代を築いた〈モーニング娘。〉や〈AKB48〉。全部音楽ジャンルは違えども「アイドル」だし、楽器を持って演奏してもしなくても「アイドル」。その曖昧さを曖昧なまま楽しむジャンルなのでしょう。
逆に言えばアイドルとさえ名乗れば、どんな音楽ジャンルやパフォーマンスをしてもいいし、「(日本におけるカタカナ語としての)バンド」ともシームレスにジャンル移行できる。そして、「バンド」からも揃いの衣装で「アイドル」に変身できる。
ただ、そこに胡散臭い"チート"さを感じて受け容れられない人がいるのも分かります。私は音楽として実験的で面白いし、「バンド」よりもかえって自由を感じて興味が続いている。逆に言えば音楽の無い「アイドル」に興味は無い。
〈Fruits Zipper〉を旗艦とするKAWAII LAB.勢の標榜する「NEW KAWAII」から現在のトレンドを「カワイイ系」と表記していますが、当のアイドルたちは「キラキラ系」とも呼びます。まあ、確かに「カワイイ系」だとパフォーマンスの幅が狭まってしまうし、KAWAII LAB.にジャンルを代表されてしまいそう。「キラキラ系」の方がより広い概念を包括できそうではあります。
中村ソゼの"「面白い曲を演っている」という意味で楽曲派と呼ばれるのもうれしいけど、できれば"アイドル"として観てほしい"という感覚も知っておいてほしい。
1990年代の「アイドル冬の時代」を経て「アイドル」という言葉はどこか悪口のように使われてきました。「アイドルなんて(笑)」と冷笑するようなものだけでなく、「〇〇はアイドルを超えた。アーティストだ。」とか「〇〇はアイドルじゃない。アーティストだ」とか誰かを褒めるためにアイドルを下等なものとして見るような表現もそうです。
対して、「音楽として評価されるのもうれしいけど、アイドルとして観てほしい」という当事者からの言葉。
アイドルというものを低く見る人たちには、「アイドルはやらされている」という感覚が強いのだろうな。自分の意思で「アイドルというアート」をやっている当事者たちを無視して。アイドルの女性プロデューサーたちが透明化されて無視されるのも「男にやらされている」という思い込みの強さから来ているのだろうし。
そして、内山結愛の言う"「今どき冷笑はダサいよなあ」"は、彼女に限らず、色々なアイドルのインタビューやMCから聞くキーワード。
『楽曲派アイドル・ガイドブック』から「カワイイ系」のムーヴメントを作った一人であるヤマモトショウへのインタビューより。
ヤマモトショウはこの構造を演劇で説明するのですね。監督や脚本家の作劇したものを舞台上で演じる俳優としてのアイドル、と。
演劇で監督や脚本家に対し「おじさんが若い子に趣味を押し付けてる」みたいなことは言われないですよね。これも「アイドルはやらされている」という感覚の強さから来るのでしょう。アイドル本人の意思を無視して。
現在のアイドル業界は芸能界と違って(相対的に)移籍は自由ですから、アイドル自身に"私が歌いたかった曲"があるのならば歌いたい曲を歌っているグループに移籍すればいいし、運営側も良い人材を確保したいのならば音楽はもちろんとして良い"箱"としても提示しなければいけない競争原理が働く。……当然、どんな業界にも意識の低い人はいるでしょうが。
ヤマモトショウは故郷の静岡で地方アイドル〈fishbowl〉をプロデュースしています。これが彼が提示する"箱"ということになるのでしょう。
現実と虚構は切り分けて遊んだ方が良いと私は最近特に思う。応援はあっても、人生そのものを消費に換えて商品化しようとする「推し活」とか良くない。
現実と虚構を切り分けて遊べないからフェイクが現実を浸食していくのじゃないのかな。
リンクしてあるのは、sombrの『back to friends』。
2025年を代表する世界的な(本来の意味での)アイドルは男性だとsombrになるのでしょう。2005年生まれのシンガーソングライターな彼が24年12月に発表した『back to friends』は一年通してBillbordチャートに入り続ける大ヒット。
テレビという大衆メディアのお祭りであるNHK『紅白歌合戦』における「日本のアイドル」像はひとつの基準になるでしょう。
2025年に出演した現役アイドルは、
KAWAII LAB.から〈CANDY TUNE〉と〈FRUITS ZIPPER〉。
BMSGから〈BE:FIRST〉と〈HANA〉。
EBiDANから〈M!LK〉。
K-POPはHYBEから〈ILLIT〉と日本支社の〈&TEAM〉に、SM社の〈aespa〉。
旧ジャニーズの後継であるSTARTOからは〈King & Prince〉と〈SixTONES〉。TOBEから〈Number_i〉。
秋元康プロデュースを冠したチームは結成20周年記念でようやく出れた〈AKB48〉とついに坂道グループ最後の一組になった〈乃木坂46〉。
何となく基本大枠として各社/各グループから2チームずつ選んだ感じですね。一時期の日本の男性アイドルはジャニーズ、女性アイドルは秋元康プロデュースが枠を独占していた時代に比べるとバランスは良くなっています。
……これでも「最近のアイドルは全部同じに見える」と言うのなら、問題があるのは同じに見える人の方にあるし、ジャニーズと秋元康の悪口を言って「日本のアイドルは〇〇だ」と全てを語った気になっているような人はNHKが想定する大衆よりも文化水準が低いってことになる。
その出演者の中で、2025年に最も躍進したアイドルといえば、女性は〈HANA〉、男性は何と言っても〈M!LK〉になるでしょう。
25年3月発表の『イイじゃん』が〈aespa〉の『Whiplash』に似ているとK-POPファンに叩かれながらも「悪名は無名に勝る」とばかりに知名度が上がり、歌詞中の「今日ビジュイイじゃん」が大バズり。
続けて、10月発表の『好きすぎて滅!』もバズって一気にメインストリームへと駆け上り『紅白歌合戦』出演に至るまでの大衆的知名度も得ました。
NHKが25年の『紅白』に24年発表の『Whiplash』で〈aespa〉を呼んでいるのも〈M!LK〉の『イイじゃん』とセットで並べたかったのでしょう。直前にネトウヨが暴れたので〈aespa〉企画は無くなったみたいですが。(……暴れてるネトウヨも、それに反発して「日本のアイドルはお遊戯会」と暴れてる連中のどちらも「知」に対して不誠実。うんざりします)
〈M!LK〉はスターダストプロモーション社の男性アイドル部門EBiDAN所属で2014年結成。ポッと出ではなく十年以上の活動歴がありようやく地上に到達したチームです。各社/各グループから基本2組という枠なら、もし〈aespa〉が来なかった場合は同じ事務所で2015年結成の〈超ときめき♡宣伝部〉が出れたのだろうな。
とはいえ、エースである佐野勇斗と元メンバーの宮世琉弥は若手の主演級俳優として「テレビ」でも活躍していますので、逆にこれまで知名度が低かった方が不自然ではありました。理由はまあ…分かりますよね。ただ、旧ジャニーズ社への忖度もあったのでしょうが、テレビ局に代表されるマス向けメディア側が旧ジャニーズグループや秋元康プロデュース以外にも日本のアイドルがいる、という多様性を、複雑さを厭う大衆に媚びて均質化したフォーマットで提供するために無視してきたのもあるのでしょうし、テレビが提供するものの外に情報を自ら求めて行くことはない大衆がいての共犯関係。旧ジャニーズ社だけを悪者にするつもりはありません。
……少し前に時代劇のキャスティングには風土を感じさせる顔で選んでほしいという話を書きました。〈M!LK〉メンバーって時代劇顔だよな。『紅白』での坂本冬美とのステージの着物姿も話題になりましたが、三河岡崎の佐野勇斗は徳川家もの、薩摩と大隅の間にある霧島市出身の吉田仁人は幕末もので薩摩藩士、足利市出身の山中柔太朗も足利一門が似合いそう。伊勢の曽野舜太に、塩﨑太智は和歌山出身だけど河内っぽい。
風土を感じさせる顔って、アイドル界に大量に人材がプールされているのだから活用すれば良いのにな、なんて男女どちらのアイドルを見ていても思います。
「K-POPスゴイ。それに比べて日本のアイドルは芋だ」なんて言う人もいるけど、例えば、地方48グループでは農家の娘が農家の娘のままアイドルをしていたりしますが、それの何が悪いのだろう?
カルチャーに多様性ではなく、単一であることを求める感覚が私には分からない。
2025年は〈M!LK〉にとって元メンバーたち含め色々あった年でした。そうそう、女性アイドル〈ZOCX〉に猫猫猫はうとして加入したはうきも〈M!LK〉出身でしたね。
旧ジャニーズと坂道がアイドル枠を独占していた時代はファンの嫉妬を恐れて男女のアイドルの共演は避けられていましたが、今は積極的にTikTokを撮るなど交流を見せる方針になったのも良い変化だし、ジェンダーを越えて活動できるようになったのも良い変化です。
ここからは、女性アイドル楽曲を中心とした「第14回アイドル楽曲大賞2025」の上位20位までを見ていきます。
メジャーアイドル楽曲部門の上位20位までを。
1位. CYNHN『ノミニー』
2位. =LOVE『とくべチュ、して』
3位. CYNHN『息のしかた』
4位. 超ときめき♡宣伝部『超最強』
5位. AiScReam『愛♡スクリ~ム!』
6位. Perfume『巡ループ』
7位. いぎなり東北産『らゔ♡戦セーション』
8位. でんぱ組.inc『W.W.D ENDING』
9位. 清 竜人25『世界を愛せますように』
10位. 東京女子流『夏の密度』
11位. 私立恵比寿中学『SCHOOL DAYS』
12位. ≠ME『モブノデレラ』
13位. フィロソフィーのダンス『迷っちゃうわ』
14位. =LOVE『ラブソングに襲われる』
15位. 東京女子流『導火線、フラッシュバック』
16位. CiON『しましょ』
17位. ≒JOY『ブルーハワイレモン』
18位. lyrical school『朝の光』
19位. CYNHN『わるいこと』
20位. わーすた『わーるどすたんだーど』
1位は前年に続き〈CYNHN〉。3位にも入っているのでこの界隈を代表するチームとなったのでしょう。所属はディアステージ。
2位は〈=LOVE〉で、姉妹チームの〈≠ME〉〈≒JOY〉と併せて秋元康が後継者として認める指原莉乃のプロデュースするグループは一大勢力を形成しつつあります。
……木村ミサ率いるKAWAII LAB.グループと指原莉乃率いるイコール系グループという元アイドルの三〇代女性プロデューサーによる「カワイイ」対決が現在の「日本の女性アイドル」の状況です。
この二人より一世代上にはディアステージを率いる福島麻衣子やTokyo Pinkを率いる大森靖子、一世代下には〈HANA〉のちゃんみななどがいるわけですが、こうした女性プロデューサーたちの存在を透明化し無視して、秋元康だけで「日本の女性アイドル」を語ろうとするのは、ジェンダー規範に囚われた女性差別的な言動なんじゃないですかね。
一方で、〈Perfume〉の活動休止は別格としても、〈東京女子流〉、さらには〈フィロソフィーのダンス〉の解散は一時代の終わりを感じさせます。2025年には加えてWACKグループの全チーム解散/放出も渡辺淳之介の敗北宣言とともに話題になりました。〈BiSH〉を旗艦に2010年代後半のアイドル業界を引っ張ったWACKが全面再編に追い込まれ、25年年末には2010年代前半を引っ張った〈ももいろクローバーZ〉を旗艦とするスタプラでも複数チームの解散が同時発表され、事務所側社員人事も含めてグループの全面再編があるようで、2010年代とはアイドル周りの環境が激変しています。
〈CYNHN〉の所属するディアステでも、旗艦だった〈でんぱ組.inc〉が25年に解散すると最も人気のあるチームは「アキバ系」ではない外様の〈きゅるりんってしてみて〉になっていますから時代は変わりました。
こうした状況のなかで、2025年の「アイドル楽曲大賞」メジャーアイドル部門は「楽曲派」の好むタイプの曲とバズ狙いの曲が入り混じった上位層。
世界的に大バズしたのは5位の〈AiScReam〉による『愛♡スクリ~ム!』。
ここはライブアイドルではなく、2010年からアニメなどのメディアミックスで展開する『ラブライブ!』シリーズに出演していた声優によるステージから始まった声優アイドルですが、ライブアイドルを主に扱うランクにも入るほどの大バズでした。
ゆえに、『愛♡スクリ~ム!』が日本国外で「J-POPアイドル」とか「日本のアイドル」として紹介されているのを見かけるとなんだかモヤモヤします。声優アイドルはアイドルの派生ではなく声優からの派生なのでジャンルが違うし、属するカルチャーも違うのではないか、と。
ただ、日本のポップカルチャーの面白いところは、何か一つが流行ったらそれだけになるのではなく、マスとは異なる場所で、様々なジャンルが(ビジネスとして成り立つレベルで)並存して動いていることにあると私は思っています。
だからこそモノカルチャーではない、多様な表現をもっと知った上で、それから語ればいいのにな、なんて思います。
「アイドル楽曲大賞」とは別枠なのでここには載っていませんが、「ハロプロ楽曲大賞」で1位となった〈Juice=Juice〉の『盛れ!ミ・アモーレ』はステージの力でちゃんと(国内限定ではあるものの)バズった曲でした。
「日本にも口パクせずに踊りながら歌えるアイドルがいるんだ」なんて驚かれていましたが、〈Juice=Juice〉は〈モーニング娘。〉を旗艦チームとするHello! Projectグループ(通称:ハロプロ)所属で結成は2013年。十年以上の活動歴があります。
……「日本のアイドルは口パクばかり」なんて言う人もいますが「ばかり」ってのはどこの日本の話なんだろう?
続いて、インディーズ/地方アイドル楽曲部門の上位20位までを。
1位. タイトル未定『空』
2位. fishbowl『蒼霞』
3位. ラフ×ラフ『君ときゅんと♡』
4位. きのホ。『秋刀魚』
5位. Ringwanderung『LV』
6位. RAY『plasma』
7位. AQ『SKUMSCAMSCUM』
8位. 0番線と夜明け前『わたしは水になりたかった』
9位. ハルニシオン『ハルニシオン』
10位. CUBΣLIC『シュガビタ』
11位. ばってん少女隊『こっちみて星☆』
12位. RAY『おとぎ』
13位. RYUTist『Unknown Us』
14位. 美味しい曖昧『パフェクト』
15位. yosugala『コノユビトマレ』
16位. きのホ。『大問題』
17位. きゅるりんってしてみて『Special♡Spell』
17位. yosugala『何億分の1を』
19位. TEAM SHACHI『晴れ晴れ』
20位. AMEFURASSHI『Don't stop the music』
インディーズ/地方アイドル部門では、札幌拠点の〈タイトル未定〉が1位で、2位の〈fishbowl〉は静岡拠点。
「地下」の覇者であり良くも悪くも「地下」における話題の中心だった〈iLiFE!〉を旗艦とするHEROINESグループが上位に入らないのはこの界隈の相変わらずですが、「カワイイ」系に押されて弱体化している「楽曲派」のなかでリーダー的存在になりつつあるのが、京都拠点の古都レコード勢。〈きのホ。〉に続いて24年に活動開始した〈AQ〉も京都らしいカレッジチャート感があって良い。8位の〈0番線と夜明け前〉も京都拠点のチームです。
……ランキングから離れた余談になりますが、地方アイドルというと、K-POPアイドルの〈i-dle〉が25年10月に発表した『どうしよっかな』MVは、韓国では「日本の地方アイドル」と『ラブライブ!』的世界観は入り混じりこう見えているのか、という意味で面白い。
また、さらにアイドルからも離れますが、韓国で音楽チャートMelonの2025年年間10位とヒットした〈10CM〉の『너에게 닿기를』は、北海道を舞台とする少女マンガ『君に届け』アニメ版主題歌の韓国語カヴァーですが、「韓国人が郷愁を感じる田舎としての日本」という感覚は興味深い。
2020年代半ばに至ってようやくアイドルのテレビ出演枠が解放され、ジャニーズと秋元康プロデュースとK-POPのみで構成される時代が続いてきたテレビの音楽番組に、「地下」や「地方」からもテレビ「地上」波の音楽番組に出れるようになりました。
きっかけのひとつは、フジテレビで2024年に始まった公開オーディション「TIF×FNS歌謡祭コラボ企画」。24年に初の出演権を獲得したのは〈タイトル未定〉でしたが、25年は〈Devil ANTHEM.〉。ここも2014年結成ですから活動歴は十年以上でようやくです。
とはいえ、TBSの『SASUKE』出演権を賭けたやはり24年に始まった「アイドル予選会」もそうですが、1枠を巡る過酷な公開オーディションを勝ち抜いてようやくアイドルはテレビ「地上」波に出れるのですから狭き門は変わらない。ぽっと出の若い子がテレビに出てる、なんてことはそうはない。
で、もし私が「アイドル楽曲大賞」に投票するのならば、
バンドサウンドとして6位の〈RAY〉による『plasma』かな。
毎年、〈RAY〉は良いと書いているような気がしますが「インディーズとして」面白い。
クラブサウンドのダンス曲だと、こちらは入っていませんが〈Girls²〉の『LET ME DANCE』。
Y2Kブームなんてここ数年言われていますが、意外とこういう音の楽曲って出ていない。MVは日本国外での何度目かのギャル・ブームで軽くバズったけど日本国内にはあまりフィードバックされなかったな。
そういえば、アイドルではありませんが、子供服のキッズモデルたちによる企画〈KOGYARU〉がドイツで一時ヒップホップ部門1位になったり、ギャル系ファッション誌『egg』のモデルによる〈半熟卵っち〉などが世界的に25年になってからバズっていましたよね。
「男に媚びず、好きなものを好きと言える日本のギャル」というイメージは、日本ではあまり語られませんが相変わらず強い。
「楽曲派」界隈のランキングには入らないアイドルだと、最近、気になっているのは〈BLUEGOATS〉。
前身チームの〈The BANANA MONKEYS〉は悪名は無名に勝るの「炎上系」路線で避ける人も多かったし、2021年に〈BLUEGOATS〉に改編されてからも炎上覚悟の体当たり企画でYouTubeやTikTokの数字は稼いでも、音楽をやるライブアイドルとしての現場の動員には結びついていない印象でした。
しかし、今の路線の〈BLUEGOATS〉は、正直、他のロック系アイドルと比べてスキルが高いとは言えないかもしれないけれど、炎上に頼らずともライブアイドルとしてのパッションと歯車が嚙み合って勢いが出てきた痛快さがある。実際、勢いのあった頃のWACKの界隈にいた人たちがここに集まりつつあるような感触。
26年に期待するチームです。
現在のトレンドであるカワイイ系でもなく、「楽曲派」にも入れてもらえないロック系アイドルはどこも知名度を上げるのに苦労しています。ただ、元〈BiSH〉でソロとして25年の『紅白』にも出場したアイナ・ジ・エンドという存在がある。
K-POPアイドルの方が先に世界で知られるようになったため、日本のアイドルも歴史に反してK-POPの派生のように見られていた時期もありました。しかし、全く異なる進化を遂げてきたのが日本のアイドルというジャンルだ、と世界各国のミュージシャンや音楽ファンに知られ始めてきた2020年代半ば。
〈BABYMETAL〉の成功は知られていても、彼女たちが日本のアイドルにおける特異な存在ではなく、実は、ロックが日本のライブアイドルの本流であることが知られてくると、ロック畑のミュージシャンたちが日本のアイドルに接触するようになりました。
例えば、〈RAY〉の新曲『Bittersweet』は〈RIDE〉のマーク・ガードナーが楽曲プロデュース。
……個人的には〈RIDE〉の名前を久しぶりに目にしました。中学生の頃は好きでよく聴いていたので、この新曲をきっかけに当時の〈RIDE〉の曲を検索してみたらカセットテープにダビングしてウォークマンで聴きながら歩いていた情景まで思い出してきてノスタルジー。
そんな〈RIDE〉のマーク・ガードナーと〈RAY〉の内山結愛の対談(『音楽ナタリー』2025年10月15日付)より。
マーク 女の子たちによるダンスとパフォーマンスがシューゲイザーという音楽と結び付いている様子がとても新しくて、すぐに好きになりました。私は音楽とは「進化する必要があるもの」だと考えていて。正直な話、私はこれまで男性のシューゲイザーバンドがうつむいて演奏している光景を、飽きるほど見てきたんですよ(笑)。RAYが新しい発想で音楽を更新していこうとする姿勢こそ先進的で刺激的。とても素晴らしい活動をしていると思いましたね。日本でシューゲイザーと呼ばれる音楽ジャンルは、1980年代末から90年代前半頃の英国で流行した、靴でも見てる(Shoegaze)かのようにうつむき加減で演奏するサイケデリックなバンドサウンド。2025年には〈oasis〉の日本公演が話題になりましたが、90年代の〈oasis〉の大成功前夜のU.K.ロックが〈RIDE〉含め一まとめにされることもあります。
~(中略)~
今、退屈な音楽に合わせてパフォーマンスをするグループがいっぱいいる中、RAYのように誰も想像しなかったような新しい音楽の領域に踏み込むグループがいるのは素晴らしいことです。そして私もRAYを通じて、普段触れることのない新しい(アイドルの)世界に私も踏み込めたのは、とても魅力的な出来事でしたね。
~(中略)~
内山さん、RAYの皆さん、どうか今やっていることを続けていってください。アイドルとシューゲイザーという異なる要素を両立させて、突き詰めていこうとする姿勢は、とても刺激的で興味深いこと。RAYがこの先の活動を通じて、メインストリームの音楽にシューゲイザーを持ち込むことで、ポップミュージックはより面白いものになっていくはずです。その期待も込めて、とにかくがんばってほしいですね。
「ロックは年寄りの音楽」みたいなイメージを覆す存在として、若い女性がパフォーマンスする日本のライブアイドルを応援する空気はこれまでも日本のロック系ミュージシャンにはあり、楽曲プロデュースやバックバンドに付くなど珍しい話ではありませんでしたが、U.K.ロックを日本人が歌う面白さみたいなものが英国に逆流しているわけです。
"退屈な音楽に合わせてパフォーマンスをするグループがいっぱい"な現状に抵抗する象徴として期待するマーク・ガードナーの日本のアイドルに対する認識は、日本のアイドル楽曲を聴かない人たちには驚きをもって感じられるのではないでしょうか。特に「日本のアイドルは〇〇だ」と単純化して何かを語ったつもりになっているような人には。
再編後のWACKグループは拠点をロンドンに移すようですが、こうした空気に賭ける意図もあるのでしょう。ただ、〈WARGASM〉のサム・マトロックが楽曲プロデュースした〈ASP〉の『MAKE A MOVE』も曲としては良いけど数字として上手くいったとは言い難い。〈Bring Me The Horizon〉と〈BABYMETAL〉の『Kingslayer』との規模感の違いもあるとはいえ。
「日本のアイドル」とは何か? という話を、『楽曲派アイドルガイドブック』(2025年)に収録された〈RAY〉の内山結愛、〈XOXO EXTREAM〉の一色萌、〈メロン畑a go go〉の中村ソゼの三人へのインタビューから。

――すごくバカみたいな質問で恐縮なんですけど、アイドルってなんなんでしょう?「アイドル」とは音楽ジャンルではないのですね。
一同:「なんなんでしょう?」
――アイドルって音楽ジャンルの名前じゃないじゃないですか。ロックやヒップホップ、ジャズと並べるのはちょっとおかしい。
一色萌(以下、一色):たしかに、私たちのCDってレコード屋さんのどこの棚にあるのかわからなくなるときがありますよね(笑)。
――たとえば一色さんの所属するキスエク(XOXO EXTREAM)の場合、プレイヤーさんのキャラクターからアイドル棚に置かれがちだけど、サウンドのテイストで分類するなら、ロック棚ないしはサブジャンルのプログレッシブロック棚に置かれるはずですよね。なので「アイドルってなんだ?」と。
中村ソゼ(以下、中村):私がアイドルでいたいからアイドルなのかなあ?
一色:そういうことかもしれないですね。私、キスエクのサポートバンドに参加していただいているキーボディスト・諸田(英司)さんのre-in.Carnationでボーカリストもやっていて、そのバンドにはキスエクの小嶋りんもバイオリニストとして入っているんですけど、そのライブではアイドルと名乗ってないですから。
――そこではあくまでバンドマン?
一色:メンバーの半分はキスエクメンバーなんだけど、そうですね。でもキスエクのライブでキスエクの衣装を着て私が歌って、小嶋がバイオリンを弾いたら、それは私たちの中ではアイドルなんです。だからアイドルって、どういう気持ち、どういうスタンスでステージに立っているか次第で決まる存在なんだと思います。
――それこそSUPER EIGHTみたいに当たり前のように楽器を持つグループだって肩書きはやっぱりアイドルですもんね。
内山結愛(以下、内山):だからアイドルってチート的な存在なのかな? って思ってます。私たちRAYのやっているシューゲイザーでも、キスエクさんのプログレでも、ソゼちゃんのめろん畑a go goのサイコビリーでも、いろんな音楽ジャンルを自由に取り込めるし、楽器を持っていても持っていなくてもいい。そういう性格を上手く利用して活動している気がします。
〈RAY〉のシューゲイズも〈XOXO EXTREAM〉のプログレも〈メロン畑a go go〉のロカビリー(にサイコなB級映画テイストを加えたサイコビリー)も、〈BABYMETAL〉のメタルや〈fruits Zipper〉の原宿カワイイ、「テレビ」で一時代を築いた〈モーニング娘。〉や〈AKB48〉。全部音楽ジャンルは違えども「アイドル」だし、楽器を持って演奏してもしなくても「アイドル」。その曖昧さを曖昧なまま楽しむジャンルなのでしょう。
逆に言えばアイドルとさえ名乗れば、どんな音楽ジャンルやパフォーマンスをしてもいいし、「(日本におけるカタカナ語としての)バンド」ともシームレスにジャンル移行できる。そして、「バンド」からも揃いの衣装で「アイドル」に変身できる。
ただ、そこに胡散臭い"チート"さを感じて受け容れられない人がいるのも分かります。私は音楽として実験的で面白いし、「バンド」よりもかえって自由を感じて興味が続いている。逆に言えば音楽の無い「アイドル」に興味は無い。
――最後にちょっと話が変わっちゃうんですけど、この本では広義の"楽曲派"と呼ばれるアイドルをフィーチャーしていて、僕自身、ここまでけっこう無責任にこの言葉を使って来ちゃったんですけど、みなさん、その楽曲派と括られることについてどう思ってます?「アイドルとはなんなんでしょう?」の次の質問は、そのアイドルのなかでも「楽曲派とは何か?」という話。
内山:いい意味にせよ悪い意味にせよどう括られても別にいいかな、って思ってます。楽曲派って必ずしもいい意味ばかりじゃなくて、楽曲にこだわるアイドルや、その曲を聴いているファンのことを「楽曲派(笑)」って言う風潮もあるけど、私の周りにいるアイドルさんには「(笑)」が付いていない。本気で音楽に向き合っているグループさんしかいないし、RAYももちろんそのつもりですし。
――であれば、なおのこと「(笑)」付きで楽曲派を語る人にムカついたりしません?
内山:でも「今どき冷笑はダサいよなあ」とも思っていて、だから別にどう括られてもいいかな、って感じなんです。
一色:そもそも自分たちが楽曲派アイドルを目指して活動しているわけでもないから、あんまり気にならないっていうのもあると思います。
内山:うん。
一色:それに正直な話、楽曲派という括りってふわっとしていますよね?
――確かに最初の"アイドル"の話と一緒。音楽ジャンルの名前でもないし、ともすればマニアックなジャンルを指向する、ある一群のグループをざっくりと括った抽象的な言葉でありますね。
一色:そもそも"楽曲"自体はどんなグループにだってあるじゃないですか(笑)。
内山・中村:確かに(笑)。
一色:しかも今のアイドル楽曲ってどれもいいし、楽曲派に括られてはいないグループのメンバーさんやクリエイターさんも真剣に音楽に向き合っているし、実際どの曲も適当、おざなりではないから「楽曲派ってなんだろう?」ってなっちゃって。「そう括る人は"自分が推しているグループは特に曲がいい""曲に力を入れている"って認識しているのかな?」くらいのイメージで捉えています。
中村:演る側としてはそんなに強く意識してはないですよね。
――あくまで聴き手やメディアが使う便宜的な言葉って感じ?
中村:サイコビリーもシューゲイザーもプログレもそうだし、キラキラ系の楽曲も演れるのがアイドルなので。だから私たちは特定の音楽ジャンルのアイドルや、楽曲派のアイドルというよりもそれぞれのグループというジャンルを演っているアイドルという存在なんじゃないかな、って思ってます。「こういうジャンルの音楽のグループだから」という理由で応援してくれるのももちろんうれしいし、「面白い曲を演っている」という意味で楽曲派と呼ばれるのもうれしいけど、できれば"アイドル"として観てほしいな、っていう気持ちはあります。
〈Fruits Zipper〉を旗艦とするKAWAII LAB.勢の標榜する「NEW KAWAII」から現在のトレンドを「カワイイ系」と表記していますが、当のアイドルたちは「キラキラ系」とも呼びます。まあ、確かに「カワイイ系」だとパフォーマンスの幅が狭まってしまうし、KAWAII LAB.にジャンルを代表されてしまいそう。「キラキラ系」の方がより広い概念を包括できそうではあります。
中村ソゼの"「面白い曲を演っている」という意味で楽曲派と呼ばれるのもうれしいけど、できれば"アイドル"として観てほしい"という感覚も知っておいてほしい。
1990年代の「アイドル冬の時代」を経て「アイドル」という言葉はどこか悪口のように使われてきました。「アイドルなんて(笑)」と冷笑するようなものだけでなく、「〇〇はアイドルを超えた。アーティストだ。」とか「〇〇はアイドルじゃない。アーティストだ」とか誰かを褒めるためにアイドルを下等なものとして見るような表現もそうです。
対して、「音楽として評価されるのもうれしいけど、アイドルとして観てほしい」という当事者からの言葉。
アイドルというものを低く見る人たちには、「アイドルはやらされている」という感覚が強いのだろうな。自分の意思で「アイドルというアート」をやっている当事者たちを無視して。アイドルの女性プロデューサーたちが透明化されて無視されるのも「男にやらされている」という思い込みの強さから来ているのだろうし。
そして、内山結愛の言う"「今どき冷笑はダサいよなあ」"は、彼女に限らず、色々なアイドルのインタビューやMCから聞くキーワード。
『楽曲派アイドル・ガイドブック』から「カワイイ系」のムーヴメントを作った一人であるヤマモトショウへのインタビューより。
――となると、アイドルってもどかしい存在でもありますね。新曲のコンペに参加している子もいるんだろうけど、たいていの場合、自作曲ではないし、作家も選べないから、「私が歌いたかった曲を誰かが歌っている」みたいなことが起きかねない。アイドル楽曲について語ると、つい背後にいる「大人」と俗に称される運営プロデューサーや楽曲プロデューサーの趣味を若いパフォーマーに押し付けているのではないか? なんて話にもなります。
だからこそクリエイターや運営は、そんなことを思わせないほどにその子を魅せるための箱を責任を持って作らなきゃいけないんですよね。なんて言えばいいんだろう? 僕らは監督や脚本家でアイドルは作り上げた物語を演じてくれる俳優というイメージ。映画のセリフを聴いて「あ、これ俳優の〇〇さんがしゃべってる」って思われたらもう終わりじゃないですか。
~(中略)~
アイドルについても同じで、本名のその子ではなく、"ステージに立っている人"がいい曲を歌っていることに疑問を持たれないような設定を作っていくのが僕らの仕事なんです。ただ、これって芸能の世界では実は普通なんですよね。今はシンガーソングライターという存在が話をややこしくしてますけど(笑)。
ヤマモトショウはこの構造を演劇で説明するのですね。監督や脚本家の作劇したものを舞台上で演じる俳優としてのアイドル、と。
演劇で監督や脚本家に対し「おじさんが若い子に趣味を押し付けてる」みたいなことは言われないですよね。これも「アイドルはやらされている」という感覚の強さから来るのでしょう。アイドル本人の意思を無視して。
現在のアイドル業界は芸能界と違って(相対的に)移籍は自由ですから、アイドル自身に"私が歌いたかった曲"があるのならば歌いたい曲を歌っているグループに移籍すればいいし、運営側も良い人材を確保したいのならば音楽はもちろんとして良い"箱"としても提示しなければいけない競争原理が働く。……当然、どんな業界にも意識の低い人はいるでしょうが。
ヤマモトショウは故郷の静岡で地方アイドル〈fishbowl〉をプロデュースしています。これが彼が提示する"箱"ということになるのでしょう。
――ヤマモトさんのそのシンガーソングライター評、大好きなんですよ(笑)。誰もが詞も曲も書けて、ギターも歌も上手い椎名林檎みたいになれるわけではないだろう、という。今の時代、日本に限らず、フィクションをフィクションとして楽しめない人が多すぎるように思うのですね。ノンフィクションでドキュメンタリー「と見えるもの」こそがリアルで本物。多様な人の手を介して作られる「作り物」は偽物であるかのように語られ、冷笑される。
自分の言葉と音で自分の世界を100%表現できる人がいるのは事実だし、そういう人は天才だから目だつんだけど、そんな存在、めったにいないですよ。映画の話をするなら、それって、ドキュメンタリーですよね?
――自分の過去や現在について自分で綴って歌っているから。しかもそれがハイレベルだから、みんな憧れるし、自分で曲を作って歌うほうが優れているのでは? という幻想を抱く。
でも、多くの人の手によって作り上げられたフィクションにも名作はたくさんあるんだから、天才になれることを期待して生きるのもおかしな話ですよね。
――それって音楽の世界以外にも見られる傾向ですよね。マンガや絵本であれば絵を描く才能とお話を作る才能って別物のはずなんだけど……。
~(中略)~
音楽だってその思い込みをエポケーしてもいいはずですよね。「クリエイティブも表現もすべてひとりでやらなければ」という固定観念を外したほうがラクに活動できるし、いい作品ができるはずだよなあ、とは思っています。
――美空ひばりだって職業作家からもらった歌詞と曲を歌って名曲を生み出し続けていたわけだし。
そうそう、運営はクリエイターを探してくることやグループの宣伝についてがんばって、クリエイターはいい歌詞やいい曲をがんばって書いて、アイドルはがんばってその曲を魅力的に表現すれば十分戦えるはずですから。
現実と虚構は切り分けて遊んだ方が良いと私は最近特に思う。応援はあっても、人生そのものを消費に換えて商品化しようとする「推し活」とか良くない。
現実と虚構を切り分けて遊べないからフェイクが現実を浸食していくのじゃないのかな。
リンクしてあるのは、sombrの『back to friends』。
2025年を代表する世界的な(本来の意味での)アイドルは男性だとsombrになるのでしょう。2005年生まれのシンガーソングライターな彼が24年12月に発表した『back to friends』は一年通してBillbordチャートに入り続ける大ヒット。