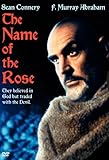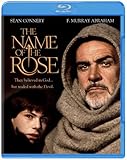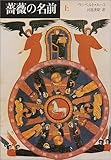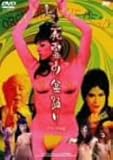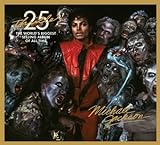突然ですが、労働基準法(以下、労基法)を読んでいこうと思います。
<はじめに>
一条ずつ読んでいきますが、何せ法学の知識はゼロです。
専門的なことは全然わかりません。
調べるにしてもネットが中心になり、上手に取捨選択できるかどうかわからないので、鵜呑みにしないでください。また、詳しい方がいらしたら教えてください。
私自身は労働争議を乗り越えてきたわけでもなく経験も乏しいですが、逆に、よく知っている人なら素通りするようなところで引っかかるでしょう。
これまで見たり聞いたりしてきたことを活かすのはもちろん、素人目線(?)を大事に進めていきたいです。
あと、今日はちょっと固めに書いてますが、今後はユルユルの軽いノリになると思います。
<動機>
私は今、とある中小企業に勤めていて、労働組合に入っています。
給料は低いですが、私の会社の労働条件はかなり良いです。
組合は、この規模の会社にしては強いです。
私はといえば、入社して組合に入るまで、「さぶろくきょうてい」が何かも知らず、「ちんあげ」とか「だんこう」とかその他諸々、全く何も知りませんでした。
組合に対しては偏った印象を抱いていて、特定の思想を持った人々の集団だと思っていました。
進められてちょっと入ってみたら違っていました。
私みたいな世間知らずは極端かもしれませんが、組合に入っていろいろやっていると、「どうしてこんなことも知らないまま働き始めてしまったんだろう」と思うことが多々あります。
まぁ、知ろうともせずなんとなく働き始めたのが悪いといえば悪いのですが、それにしても、小・中・高の生徒時代にもうちょっと教えてもらっていてもよかったのではないか、と思います。
労働三権というのは、団結権、団体交渉権、団体行動権です、などというのは習うわけですが、答案用紙には書けても全然身になってなかった。
そんな方は結構多いんじゃないでしょうか。
上司に「うちの会社には有給休暇制度はないよ」と言われたら、「ああ、そうなんですね」と納得していませんか(特に若い人)。
もちろんそんなのは労基法違反です。
じゃあ、もっと小さな個人事務所みたいなところに勤めていて、同じことを言われたら、どうですか。
「有休っていわゆる『会社』にだけあるものなのかな」…って思ってしまうかも?
そんなことはなく、やっぱり労基法違反です。
そういう「当たり前」をもっと早くから学んでおけばよかった。今からでも勉強しておきたい。
そう思ったので始めてみます。
で、労基法ってけっこう長いので、ぼちぼちペースでやっていきます。
なお、条文は、厚労省の労働基準法のページから引用します。
ウィキソースはこちら↓
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95
条文引用しても著作権侵害にはならないんだって、ウィキソースの一番下に書いてありました。
そこを読むまで「条文に著作権あるのかな?」なんて考えもしなかったけれど(笑)、いろいろ難しい世の中ですね。
----------
まずは、労働基準法がいつできたか。
上記のページにアクセスしてみると、「○労働基準法」とあって、右側に、