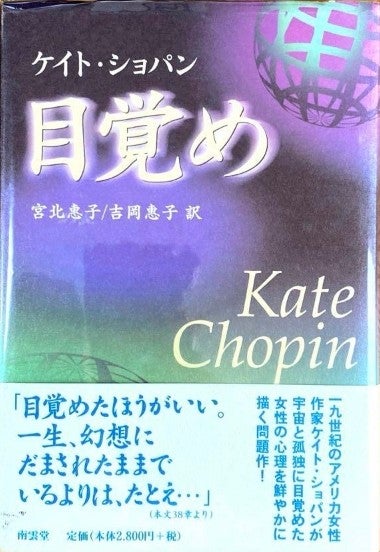樋口一葉 (1872~1996)

樋口一葉(明治5年/1872年5月2日生~明治29年/1996年11月23日没)の小説はいずれも中短篇で、19歳の最初の短篇「闇桜」(「武蔵野」明治25年/1892年3月)から出世作となった第12作「大つごもり」(「文學界」明治27年/1894年12月)と森鷗外・幸田露伴・斎籐緑雨の合評「三人冗語」で空前の大絶讚を博した第13作「たけくらべ」(「文學界」明治28年/1895年1月~明治29年/1896年1月断続連載、「文芸倶楽部」明治29年4月・一括掲載)を経て、結核の悪化から病没半年前の最後の短篇小説となった「われから」(「文藝倶楽部」明治29年/1896年5月)まで22篇しかありません。明治20年代にはまだ一般の文章を始め小説も文語体(和漢混交体)が主流だったので、口語体の作品は初子を授かった新婚女性の一人称で書かれた第19作「この子」(「日本乃家庭」1896年1月)だけなのもあって、一葉の小説はやはり文語体で書かれた日記・書簡とともに、現在の読者には親しみづらく、口語訳が行われたりもしています。しかし一葉の小説は明治20年代~大正期までの文語詩などよりはずっと平易で、助詞を替えればそのまま口語体に移行できるようなものです。
一葉は没落した貧困士族の長女で、兄が二人いましたが、夭逝した長兄と素行不良のため事実上勘当されていた次兄を置き、借財を残して急死した父の跡目を継いで、17歳で母や妹たちの生活を背負う樋口家の戸主になりました。父が膨大な借財を残して死んだため、元々両家同士の契約だった婚約者との縁談も破談になりました。一葉の父は長女の学才を見込んで早くから出来る限りの教育を受けさせていたため、一葉は下町庶民の子女のための和歌の私塾を生業として生計を立てるも十分な収入を得られず、さらに文筆で家計を補おうと小説家を目指して習作を重ね、「東京朝日新聞」専属作家の半井桃水(1861~1926)を訪ねて師事するとともに、桃水主宰の文芸誌「武蔵野」に最初の短篇「闇桜」を発表します。しかし一葉の初期短篇小説は注目されず、女弟子を何人も持ち文壇の色男と持て囃されていた桃水の愛人の一人と噂され軽んじられていた期間が、主流文芸誌「文學界」に発表された2年半後の短篇第12作「大つごもり」までかかりました。一葉が今日では忘れられた流行作家・半井桃水に惹かれていなかったのは、一葉を表敬訪問に訪れた斎藤緑雨の印象を没後発表された日記に、優男の桃水より気骨のある魅力的な男性、と記していることでも明らかです。第12作「大つごもり」(明治27年/1894年12月)に次いで、一葉の名声を決定的にした第13作の中篇小説「たけくらべ」の執筆から、病状悪化によって筆が執れなくなり、最後の短篇となった第22作「われから」(明治29年/1896年5月)執筆までの一葉晩年の創作時期は「奇跡の14か月」とも呼ばれています。一葉の中短篇の逸品は貧困階級の女性を描いた「大つごもり」、子供の世界を描いた「たけくらべ」、また心中小説「にごりえ」(「文藝倶楽部」明治28年/1895年9月)の3作が上げられるでしょうが、一年間(明治28年/1895年1月~明治29年/1896年1月、断続掲載)をかけて「文學界」に連載された中篇小説「たけくらべ」こそ一葉生涯の名作にして、おそらく明治以降の日本文学が唯一世界に誇れる作品と思えます。世界の文学史上でも類を見ない着眼点と完成度を誇る、とんでもない大傑作です。千年に及ぶ日本文学が生んだ独創は、『源氏物語』と「たけくらべ」だけかもしれません。しかし着想の独創性と卓越した芸術的完成度において、「たけくらべ」は明治時代の文学にあってあまりに孤立した傑作と見なされがちです。そこでこの小文では、比較文学というほど大それた意図ではなく、「たけくらべ」という作品、そして樋口一葉という作家について、思いつく限りの小説や作家と照らし合わせてみようと思います。

中篇小説「たけくらべ」の設定やあらすじはよく知られている通りで、およそ従来の文学作品では描かれることのなかった、思春期前後の下町庶民の子供たちの世界を、子供たち自身の視点から描いた作品です。舞台は吉原の裏手で、遊女を姉に持つ少女・美登利と、僧侶の息子の少年・信如が幼なじみの少年少女たちとともに子供時代ならではの年中行事を楽しみつつ淡い恋心をい抱きあいますが、その恋はすれ違いに終って実らず、結末では美登利の登楼(水揚げ)が暗示されるとともに、信如は家を継いで出家します。信如・美登利がおたがいを慕いながら、またそれぞれの家庭環境の違いによる別れが刻々と迫りながら、折々に会う機会も徐々に失っていく焦燥を抱えつつ、恋心を打ち明ける契機は決して訪れない後半は、あくまで作者が自意識の稀薄な子供たちの視点で淡々と客観的に叙述を進めるだけに、これ以上の悲しみはないほどです。鷗外、露伴、緑雨といった明治時代最高の文学者が最大の絶讚合評を贈ったのも頷けます。こんな小説は「たけくらべ」以前にはなく、そして「たけくらべ」以後にもないのです。夭逝前の1年半にようやく才能が認められた一葉には生前刊行の作品集はなく、没後すぐに全集が刊行されて遺族の経済的苦境を救うロングセラーとなりました。また「たけくらべ」は一葉肉筆原稿の写真版を本文に、生前の一葉を知る文学者たちの回想・解説を添えて昭和17年(1942年)に『真筆版たけくらべ』として単行本化もされるほど愛読される国民的作品になりましたが、生涯を貧困にあえいだ一葉の遺影が、没後110年を経て紙幣の肖像画に採用されるとは無神経にもほどがある皮肉です。

大人になっては失われてしまう子供時代ならではの世界が、子供たちの集団的視点から書かれた文学作品には、ヴァレリー・ラルボー(1881~1957)の1918年の連作短篇集『幼さごころ (Enfantines)』がありますが、フランス的な観察と回想で描かれた印象の強いものです。また映画では「子供の世界を子供の視点から描いた、画期的映画史的作品」として小津安二郎(1903~1963)の『大人の見る繪本 生れてはみたけれど』(松竹, 1932)、ジャン・ヴィゴ(1905~1934)の『新学期・操行ゼロ (Zéro de conduite: Jeunes diables au collège)』(フランス, 1934)がよく上げられますが、「映画の父」D・W・グリフィス(1875~1948)が短篇映画時代にニューヨークの下町の不良少年少女たちの姿を、映画創始期ならではの、ヌーヴェル・ヴァーグに50年先立つ即興演出とロケーション撮影で描いた「ピッグ横丁の銃士たち (The Musketeers of Pig Alley)」(1912年)こそが、小津やヴィゴに先立つものでしょう。

David Wark Griffith - Musketeers of Pig Alley (Biograph, 1912, B&W, Silent, 18mins)
西洋社会において「児童」の概念は19世紀後半にようやく児童教育者たちによって発見(!)されたもので、それまでは子供服という概念すらなく、子供たちは大人の服装をそのまま縮小されたものを着せられていました。子供は主に労働力において、単に「未熟な人間」として扱われていたのです。アジア圏でも識字階級以上の生活をしている社会では同様で、子供が子供に合わせた着やすく動きやすい服を母親の仕立てで着せていたのはむしろ庶民階級で行われていましたが、そうした庶民階級は独自の文化こそあっても文学や美術を始めとする芸術の担い手ではなく、せいぜい職人にとどまっていました。日本の庶民階級でも趣味的な和歌や俳諧、琴や三味線が教養として推奨されていましたし、また江戸時代には中国由来の伝奇小説の伝統や日本固有の恋愛文芸の流れがありましたが、それはあくまで大人による大人のための、大人の世界を描いたものでした。歴史学者・津田左右吉(1873~1961)の日本文学思想史『文学に現はれたる我が国民思想の研究』(大正6年/1917年~大正10年/1921年)は平安朝から江戸時代までの文学史を「貴族文学の時代」「武家文学の時代」「平民文学の時代」と分けていますし、国文学者・折口信夫(1887~1953)が長年の研究から『日本文学の発生序説』(昭和22年/1947年)でまとめ上げた平安朝以前から昭和文学までの見取り図は津田よりもっと複雑で精緻ですが(例えば堀辰雄を愛した折口は、大正~昭和初期の「新感覚派」を王朝文学への回帰と見ていました)、折口の膨大な論考を整理して日本文学史を理解するにも、津田左右吉の「貴族文学の時代」「武家文学の時代」「平民文学の時代」というという文学史観は有効です。
英文学に学んだ夏目漱石(1867~1916)の『三四郎』(明治41年/1908年)の画期性は「新時代の青年の青春」を、大学に進学したばかりの未熟な主人公の視点から描いたことにありました。あくまで国立大学(旧制高校)に進学できる財力と知的エリートに限定された環境下の青年にとどまる限界はありましたが、それは二葉亭四迷(1864~1909)の処女作にしてロシア文学に学んだ明治初の意識的な口語体(言文一致)小説『浮雲』(明治20年/1887年~明治24年/1891年、未完)の、就職するもすぐに免職された青年の苦悩を描いた先例をずっと普遍的な内容に洗練させたものでもありました。それまで子供から直に大人になるしかなかった社会構造の日本にあって、明治にして初めて日本の青年(ただし学力・財力ともにエリート階級にある青年ですが)には、モラトリアムという青春時代が選べるようになったのです。『三四郎』に感化されて森鷗外(1862~1922)が書いた『青年』(明治43年/1910年)はドイツ文学に学んだ鷗外ならではの屈折があり、『浮雲』『三四郎』『青年』は明治を代表する文学者それぞれの、それまでの日本文学になかった青春文学と目せます。のちに批評家・中村光夫(1911~1988)が大反響を呼んだ長篇文学論『風俗小説論』(昭和25年/1950年)で着目した作品で、当時すでに忘れ去られていた、尾崎紅葉門下生の小栗風葉(1875~1926)が二葉亭四迷が訳したツルゲーネフの『うき草 (ルージン)』(1857年)の感化から日本版翻案的に描いたベストセラー大作『青春』(明治38年/1905年~明治39年/1906年)を含めてもよく、風葉の『青春』と偶然類似した、日本語訳では当初伏せ字だらけで刊行されたミハエル・アルツィバーシェフ(1878~1927)のセンセーショナルな国際的ベストセラー大作『サーニン』(1907年)同様、中村光夫は風葉の『青春』、青年世代の刹那的快楽主義を差して「サーニズム」という造語まで生んだアルツィバーシェフの『サーニン』を、文学を目指して一過性の風俗小説にとどまった作品として、大衆受けする現代小説の多くもまた風葉やアルツィバーシェフの轍を踏んでいると批判しています。
しかし一葉より年長、かつ知的エリートだった二葉亭、漱石、鷗外ですら描くことができたのはせいぜい大学生以上のエリート青年像でした。漱石の中篇「坊つちやん」(「ホトトギス」明治39年/1906年)には語り手の新任中学教師の眼を通して四国の田舎町の子供たちの姿が描かれますが、むしろ「たけくらべ」の発展は「坊つちやん」で描かれた子供たちの姿にあるとも思えます。ただし「坊つちやん」執筆当時の漱石は大学の英文科講師だったので、漱石自身が27歳の明治28年(1895年)の一年間、中学教師として赴任したことがある愛媛県時代の思い出を10年後にイギリスの滑稽小説風にデフォルメした趣味的作品が前年の第一長篇『吾輩は猫である』に続く「坊つちやん」だったと見なす方がよく、『吾輩は猫である』も「坊つちやん」も明治以降の日本文学には珍しい風刺的ユーモア小説の名作ですが、「坊つちやん」の翌年に大学講師を退任して文筆一本になってからの作品とは創作姿勢が異なります。そこでいよいよ樋口一葉が23歳の明治28年(1895年)に一年を費やして執筆した「たけくらべ」の突出した先進性と、類を見ない着想、その達成が際立ちます。森鷗外がドイツ留学から帰国後の27歳(明治23年/1890年)で発表した短篇処女作「舞姫」は、海外留学と異国(西洋)女性との恋愛という、やはり鷗外以前には題材そのものが日本文学には存在しなかったものですが、逆に海外留学や国際結婚が珍しいことではなくなった現在では(「舞姫」の当時は、佐藤春夫の証言の通り、大きなカルチャー・ショックでしたでしょうが)、鷗外が書かなくてもいずれ日本文学に現れたテーマとも言えます。
24歳で夭逝した一葉は婚約者側からの婚約破棄のため生涯未婚で、パトロンを得ることもその内妻(または外妾)となることもなく、当然子供も持ちませんでした。一葉が生業としていた和歌の私塾には、女性の教養として「たけくらべ」のヒロイン・美登利と同年輩の少女たちが生徒として出入りしていたでしょう。10代半ば~せいぜい17、8歳までが女性の婚期の限界とされていた時代です。17歳で一家を背負うことになり結婚もできなかった一葉にとっては、父親の急死とともに突然少女時代が打ち切られた思いがあったでしょう。「たけくらべ」に投影された一葉の創作力の源泉はそこにあり、おそらく生計のために短篇小説を書き出してから3年の習作期間の間、一葉の胸中にはそのテーマがずっと秘められていたはずです。「たけくらべ」の一葉の独創は、西洋文学に触れる機会のなかった一葉が知るべくもなかった同時代のアメリカ作家、ケイト・ショパンやスティーヴン・クレインを連想させます。

元々文学少女でしたが6児の母にして未亡人となり、30代後半から本格的に創作を始めたケイト・ショパンは、アメリカでも人気の高かったモーパッサン流のローカル短篇作家として地元セントルイスの地方新聞・雑誌で人気を博すも、離婚した男に恋する30代未亡人をヒロインにアルコール依存症、情事、離婚を描いた第一長篇『過ち (At Fault)』は出版社の拒絶によって自費出版でしか発表できず、短篇集3冊は好評に迎えられながら、結婚と不倫を経たヒロインの自立と性的・内面的解放を描いた第二長篇『目覚め (The Awakening)』は不道徳を極めた女性像を肯定的に描いた作品として悪評を浴びてショパンの作家生命を絶つことになり、以降ケイト・ショパン作品が画期的な芸術性を備えたアメリカ初のフェミニズム小説と再評価されるまで1970年代までかかりました。今日『目覚め』は建国以来250年におよぶアメリカ文学史でも五指に上げられる最重要小説(おそらくアメリカ小説三大古典『緋文字』『白鯨』『ハックルベリー・フィンの冒険』に次ぎ、女性作家の小説としては『心は孤独な狩人』や『賢い血』と並び、『黄金の杯』『アメリカの悲劇』『バビット』『グレート・ギャッツビー』や『響きと怒り』『U.S.A.』、『眠りと呼ばん』『地上より永遠に』『見えない人間』『キャッチ22』『J.R.』『重力の虹』などに拮抗するかそれ以上の作品として!)とされており、日本語訳も3度(杉崎和子訳・牧神社1977年、瀧田佳子訳・荒地出版社1995年、宮北惠子/吉岡惠子訳・南雲堂1999年)に渡って刊行されていますがいずれも少部数・絶版の稀覯書になっていますので、現代文学の転換を告げる特異点をなす古典としてスティーヴン・クレインの「街の女マギー」と並び、文庫版の新訳が望まれます。もっともショパンの作品はシチュエーションに捻りがありオチの効いたモーパッサン流の短篇小説(4巻分、全96篇)の方が面白く、成人女性の自立と精神的・性的充足を追究した野心作の長篇2作はわかりやすい面白さに欠けるので、代表的な短篇選集2巻ないし1巻と長篇2作(第一長篇『過ち』はまだ未訳です)で本格的な再紹介がされるのが理想です。
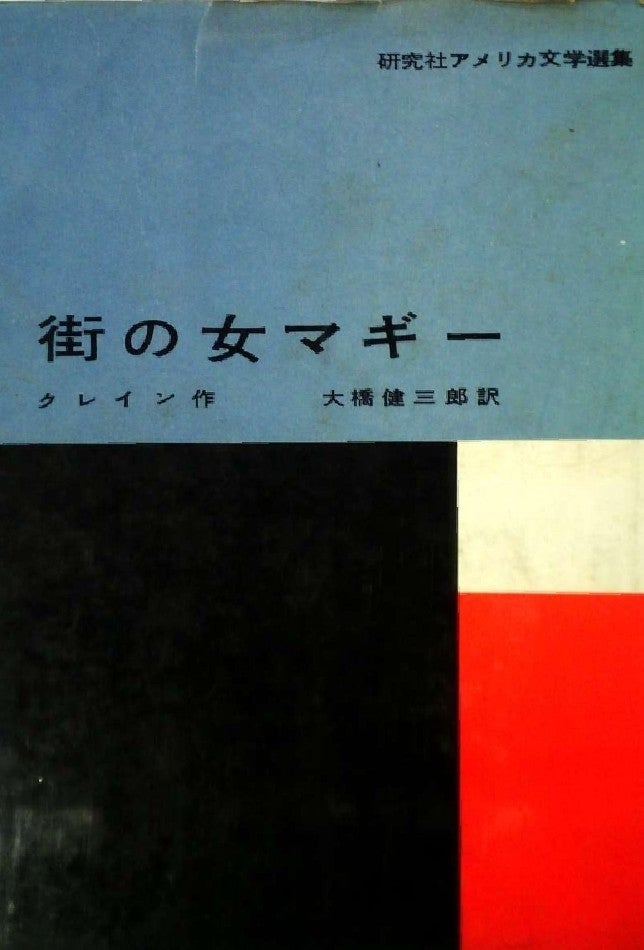
28歳で夭逝したスティーヴン・クレインは早くから作家を志し、ニュージャージーの大学在学中に完成するも、出版社からことごとく断られ匿名で自費出版した、ニューヨークの下町に暮らす少年少女たちの生態と街娼に身を落とすヒロインを描いた21歳の自費出版中篇処女作「街の女マギー」はまったく売れなかったばかりか、ヨーロッパ文学とは異なる印象主義リアリズムが理解されるまでシャーウッド・アンダーソンやヘミングウェイらがその手法を継ぐ没後30年あまり真価が認められませんでした。南北戦争に従軍した一兵卒の極限状況下の肉体的・精神的危機を描いた第二中篇「勇気の赤い勲章」(旧邦題「赤い武功章」「赤い武勇章」、映画化題『勇者の赤いバッジ』)もまたリアリズムと印象主義手法の混交する手法で、自然主義時代の当時のアメリカ小説の潮流からは賛否両論を呼びながらベストセラーを記録する出世作となり、20世紀にはアメリカ文学の古典と目されるようになりました。クレインの代表作はいずれも短く、中篇小説6作が主要作品となりますが、その不安定で多義的な作風ゆえに、いずれも1920年代以降のモダニズム時代のアメリカ小説、また1960年代以降のポスト・モダン文学を予告した先駆的存在と見なされています。
おそらく樋口一葉は、世界文学的にはケイト・ショパンとスティーヴン・クレインの中間にあり、着想に優れながら若すぎる学生作家としてデビューしたためリアリズム手法によるドラマチックな小説構成に手腕が届かず、印象主義的な描写の累積による限定的な小説作法にとどまったクレインより成熟し、晩熟で人生経験を積み、具体的な想像力に富んで女性作家としての限界に挑んだショパンほどの広がりはないとしても、「たけくらべ」「にごりえ」を頂点とする晩年10篇の中短篇において、その創作の芸術的達成と完全な発露ではショパンやクレインの傑作を凌駕します。一葉は日本の同世代文学者・北村透谷(1868~1894)ほど意識的に封建的道徳に反逆した革新的な天才ではなかったでしょう。しかし十分な芸術的完成に達した作品を生めなかった透谷に対して、晩年2年間の一葉の作品は最高の文学的手腕で庶民、そして庶民階級の子供の悲しみに同化し、美しい率直さによって小説化したものです。その観察力と共感力は比類なく、なかんずく「たけくらべ」は時代も国境も越えています。千年、あるいは四千年ののちに明治~令和までの日本文学と文化的背景が忘れられても「たけくらべ」、そして一葉という女性の存在は、紫式部作『源氏物語』と同等か、それ以上に伝承されていくという戦慄さえ放っているのです。