牧村憲一、藤井丈司、柴那典『渋谷音楽図鑑』☆
渋谷で生まれた都市音楽の歴史を、まさにその時代を作り上げてきた歴史の生き証人である、生まれも育ちも渋谷のプロデューサー牧村憲一氏が語り、解説した素晴らしき名著です☆
三人の著者名が記載されてますが、基本的には牧村氏による渋谷都市音楽史を巡る回顧録がメインで(牧村氏の語りを柴氏が書き下ろし)、後半に藤井氏と柴氏が対談に登場し、主に藤井氏による、具体的な都市音楽の楽曲分析解説の講義がメインとなっていく構成です☆
ちょうど前に牧村氏が書かれた、ここでもレビューを書いたあの大名著『「ヒットソング」の作りかた 大滝詠一と日本のポップスの開拓者たち』にさらに肉付けして、具体的な渋谷都市音楽の歴史書として書かれたような、こちらも紛れも無い名著です☆
https://ameblo.jp/erroy3911/entry-12242129118.html
まずは、東京オリンピックが渋谷の街並みを変え、1960年代には文化的に最も栄えていた新宿から、1970年代に入ると渋谷が文化の中心になっていきますが、西武の堤清二の都市計画とパルコの増田通二の文化戦略が、何もなかった渋谷に新しい繁華街を作って、同時に文化を作り、育て、最先端の文化的な街としての地盤を、いかに産業的に形成していったかの歴史が語られていきます☆
と同時に、渋谷ジャンジャンのような小劇場や、BYGのようなライブハウス、またはミュージシャンの交流の場でもあったヤマハ渋谷店や、牧村氏が在籍した早稲田大学グリークラブ、または桑沢デザイン研究所や青山学院大学といった場所から、後の都市型ポップスを牽引する逸材が多数輩出されており、いかに重要な文化拠点であったかについても書かれています☆
これは、単なる都市音楽の本ではないので、それを生み出した都市や文化拠点の歴史、その産業&流通の歴史など、つまり”渋谷の地下水脈”からその成り立ちが語られていく、まさに渋谷の歴史書として始まります☆
そこに、その時代に、渋谷で都市音楽がどのように生まれ、ムーブメントが拡がっていったかが、牧村氏個人の生き証人としての具体的な回顧録を織り交ぜて書かれています☆
だから歴史書と言っても、よくある歴史を研究している学者が書いた、客観的考察とデータ的裏付けに終始しているような、どこか俯瞰的で距離感があり過ぎる学術的歴史書のつまらなさや曖昧さを遥かに超えた、歴史の生き証人によるドキュメント的な辿り方が成されている実にリアルな歴史書です☆
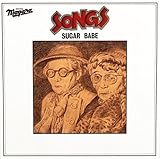 | SONGS -40th Anniversary Ultimate Edition- 3,024円 Amazon |
この中で、牧村氏がプロデュース他で尽力されたシュガー・ベイブ、山下達郎氏のファーストアルバム、竹内まりやさんのファースト、大貫妙子さんのヨーロピアン3部作の話は、何回読んでも個人的に感慨深いです☆
この話は牧村氏の前著『「ヒットソング」の作りかた』にもっと詳しく書かれてましたが、それでも読む度に個人的には興奮します☆
だって、自分は達郎さんやまりやさん、大貫さんの音楽を聴いてなかったら、果たして日本のポップスを聴いてたかどうかわからないからです☆
 | CIRCUS TOWN (サーカス・タウン) 2,469円 Amazon |
回想的に書きますと、70年代後期の学生時代に知った達郎さんの音楽を聴いて、自分は日本のポップスに俄然興味を持ちました☆
女性シンガーソングライターも、吉田美奈子さんと竹内まりやさんと大貫妙子さんの存在によって、俄然注目度が高くなりました☆
三人ともが、達郎さんと関係ある人たちというのも大きかったと思いますね☆
牧村氏は日本のフォークにも関わってられますが、自分は当時流行のフォークもニューミュージックもあんまり興味がなく、この頃ヒット曲を出していた人で興味を持ったのはChar氏と原田真二氏ぐらいでした☆
歌謡曲もヒット曲も大して興味ない、フォークやニューミュージックも共感出来ない、洋楽ポップスにもビートルズやカーペンターズとかに当時違和感があり、となると、もうポップス音楽に興味持てない状況ですが、しかし洋楽にはジャズやクロスオーバーやAORがあり、邦楽には達郎さんがいたことが何より救いでした☆
70年代のまだ売れてない頃の達郎さんの楽曲は、当時の自分の気持ちの代弁者だと勝手に思ってました☆(それを達郎さんが売れ出してからよく聴いていました☆)
自分にはフォークやニューミュージック、ビートルズやロック、パンク以上に、70年代の達郎さんやAORの人たちが、世界や人間についての本質を歌っていると思えたのでした☆(今もそう思っています☆)
もちろん達郎さんもAORの人たちも基本メッセージソングの人たちでは全くないです☆
そういう曲もたまにありますが、そういうたまに作る珍しい楽曲に本質があると思ってるわけではないのです☆
メッセージソングでも何でもない、シティミュージックやAORとしてのポップスの名曲が、どうにも世界や人間の本質を歌っているように思えるのです☆
 | インディアン・サマー(紙ジャケット仕様) 2,700円 Amazon |
自分にとって、たぶん唯一の青春ソングに思える、達郎さんがプロデュース&アレンジした、マザーグースの『貿易風にさらされて』EPバージョンというのは、本当に特別な名曲だと思っています☆(牧村氏関連ではないですが☆)
もちろんこちらも何かのメッセージソング的だったりは全然しません☆
でも今でも、自分の唯一の青春ソングってやつじゃないか、とどうにも思えるんですよね☆
しかもマザーグースのアルバムに収録されている同じ曲(アルバムバージョン)には特に感じ入るものがあまりないのに、達郎さんのアレンジ&プロデュースによるEP盤になると、まるで魔法にかかったような途轍もない感慨深さに様変わりしてしまっている曲なんですよね☆
特に最初のイントロが、全てを語っているような感慨深さで、まるで達郎さんの音楽要素の中で最も聴きたかった超メロウで浮遊的な儚さのフレーズを、ど頭から聴かされたような衝撃を(初めて聴いた時に)受けましたね☆
結局世に言う青春ソングには、全く青春を感じないか、他人事にしか思えないので、自分に青春なんてなかった、とも思うんですが、それでも『貿易風にさらされて』EPバージョンにだけは特別なものを感じるのです☆
と、かなり話が脱線しましたが、だからその70年代後期の達郎さんのソロ活動初期の仕事を大きくサポートしていた牧村氏の仕事というか感性によって、自分はなんとか日本のポップスを好きになれたんだなとも思えるわけですので、その辺りの牧村氏の回顧録はついつい何度も読み返してしまいますね☆
この基本線というか土台を、達郎さんと牧村さんが作ってくれなかったら、たぶん日本のポップスを自分は聴いてなかったと思いますのでね☆
その後の80年代に入ってからも、自分が邦楽でメインに聴いていたのは、清水靖晃氏が率いたマライア系や達郎さん(&達郎さんのMOONレーベルのAORミュージシャン)でしたが、やはりYMO系や、牧村氏が携わっていた大貫妙子さんや、竹内まりやさんにEPOさん、細野晴臣さんのノンスタンダードレーベル、とか、ムーンライダースや鈴木さえ子さんや立花ハジメ氏他などなどを、そのままリアルタイムでよく聴いてましたので、この時代の牧村氏の回想にもかなり愛着が湧きますな☆
この時代、原宿セントラルアパートに、これらのアーティストを盛り立てる牧村氏他のクリエイターが集結しており、80年代のYMO系や都市音楽系のアートディレクションや宣伝その他が、ほとんど原宿セントラルアパートという一つの建物の中で出来上がってしまうシステムになっていたという回想話は実に興味深いですね☆
80年代の日本の都市音楽には、様々なアイデアが次から次へと飛び出してきて、それを追いかけてるだけでも楽しかったですが、それらの多くが、原宿セントラルアパートという一つの場所、まるで映画の撮影所システムかスタジオシステムのようなところから生まれていたというのは、本当に歴史的に貴重な回想だと思います☆
その後の渋谷系となる、牧村氏が発見しデビューさせたフリッパーズ・ギターも聴いてましたな☆
渋谷系は、自分は基本的にピチカートファイヴやオリジナルラブ、U.F.O.(United Future Organization)他などがメインで、よくLiveやイベントに行ってましたが、牧村氏が大きく携わっていたフリッパーズ・ギターのファーストはジャケの洒落っぽさも好きでしたが、やはり楽曲が見事にネオアコっぽくて良かったですな☆
 | Three Cheers for our side ~海へ行くつもりじゃなかった 2,621円 Amazon |
ネオアコは80年代の真ん中頃に、ロータス・イーターズやペイル・ファウンテンズ、トレーシー・ソーン、ザ・スタイル・カウンシル他なんかが個人的には一番好きでよく聴いており、日本でネオアコというと、それまでムーンライダースや彼らが尽力した水族館レーベルのミュージシャンたちという印象があったんですが、フリッパーズ・ギターのネオアコには当時のピチカートと似た空気感が漂い、なんだか次の時代のネオアコって感じがしましたね、当時☆
1989年末から90年代初頭にかけてのこの時期、流行りのイカ天とかのバンドブームや、大量発生した安っぽいシンセ音のポップスが苦手で、ワールドミュージック日本代表だった清水靖晃氏や、ピチカートとかフリッパーが好きでしたが、この自分のリスナーとしての流れと牧村氏のプロデュースの流れがだいたい同じなのも、なんか偶然ではない必然を感じますな☆
やはり自分は『サーカスタウン』で達郎さんの方向性を決めた牧村氏の作ってきた日本のポップスの道のりを、リスナーとして歩いてきたんだなと思いますね☆
ピチカートやフリッパーと一緒に、あの頃、達郎さんのファースト『サーカスタウン』を引っ張りだしてよく聴いていたのも、やはり偶然ではない気がしてきますね☆
また80年代中期によく聴いていたサロン・ミュージックの吉田仁氏が、フリッパーズ・ギターのプロデュースをされていたことも、何というか音楽的必然という感じでいいですね☆
その後フリッパーズ・ギターはかなりの人気となりますが、そこから解散へと至るまでのドキュメントが、プロデューサーの牧村氏の目線からリアルに語られ、トラットリア・レーベルの発足、躍進に牧村氏が尽力していく様なども語られていて、こちらも貴重な歴史的回想だと思いますね☆(ちなみにトラットリア・レーベルで、実は当時自分が一番興味を持ったのは、デス渋谷系と言われた中原昌也氏のノイズ系・暴力温泉芸者でしたな☆)
さて後半は、対談形式ではありますが、基本的に藤井丈司氏が講師となって、はっぴいえんどや達郎さん、またはフリッパーズ・ギターやオザケン、コーネリアスなどの日本の都市音楽の名曲の、コード進行やシンコペーションなどの特異点から具体的に楽曲の魅力を分析した解説が、譜面まで掲載されて語られています☆
この藤井氏による具体的な分析、解説はかなり素晴らしくて面白いです☆
やはり都市音楽というのはコード進行の転調の魅力というのが大きいというのは強く思います☆
個人的には、その都市音楽の転調の魅力を変態的なまでの転調芸術にまで露骨に高めてしまったのがスティーリー・ダンだと思うし、クロスオーバーミュージック(特にデオダート他のブラジリアン・クロスオーバー)やAORの魅力もやはり転調にあるなとよく思います☆
 | Aja Amazon |
そのスティーリー・ダンの転調芸術の影響を受けているキリンジや冨田ラボ、または北園みなみや流線形、Lampなどが21世紀の都市音楽の要になり、そこに渋谷系のアシッドジャズムーブメントの影響も加味されて、NulbarichやSuchmos、WONKなどに都市型音楽が流れていくことは、極めて必然的なことだと思いますね☆
 | SHIPBUILDING 2,366円 Amazon |
 | TOKYO SNIPER 2,520円 Amazon |
これも、あくまで極めて個人的には、ですが、都市音楽のアクロバティックな転調を聴いていると、自分はどうしても、世界や世の中は一筋縄の通常コード進行通りには行かない、
人間というものも、人生だって、決まりきったよくあるパターンのコード進行では進まない、
という、世界の表と裏、人間の表層と暗部、またはその合間にある隠れた世界の実像や、隠れた人間の超微妙すぎる微粒子のような感慨(またはエモーション)や、世界や人間の流動性を、あくまで音楽的に掬い取って表現している楽曲という気がしてしまうんですな、昔から☆
だから先にも書いたように、達郎さんやスティーリー・ダン、またはAOR他の都市音楽こそが、「人間や世界の本質を表現している」ように思え、70年代の達郎さんの楽曲が自分の気持ちを代弁してくれているように思ったのかもしれませんね☆
メッセージソングを聴いても、昔から胡散臭いと思ってしまうのは、その単純なシンプルさが、結局は大資本をバックにしたビジネスに利用されていたり、ただのわかりやすさ故の大きなビジネスになっているだけだったりするな、という欺瞞をよく思ったからです☆
そのシンプルなメッセージが偏向的な政治や思想に利用されてしまう胡散臭さが無批判で流通してしまう傾向もあり、昔からどうしてもこれには大きな違和感を持ちますな☆
それはつまり大衆化、または大衆煽動に音楽を利用するというものでしょうから☆
藤井丈司氏が対談の中で、80年代真ん中ぐらいで都市型ポップスが失速してしまったことについて、
「都市型ポップスが持っていた少年性やファンタジーが失われて、大衆のものとなり、土着のものになっていく。それが71年から81年の10年間で起こった変化」
と言われていますが、これは都市型ポップスの栄枯盛衰を一発で語った名言だと思います☆
藤井氏が上記で言われている変化を、自分は達郎さんの『RIDE ON TIME』までと、次の大ブレイクアルバム『FOR YOU』の間に明確に感じました☆
『FOR YOU』を聴いた時、たった一年で大衆化してしまったと思ったし、少年性というのはちょっとわかりませんが、ファンタジーが失われてしまったというのは明確に感じました☆(でも今はこのアルバム好きになりましたが☆)
 | RIDE ON TIME (ライド・オン・タイム) 2,469円 Amazon |
 | FOR YOU (フォー・ユー) 2,469円 Amazon |
先に書いたマザーグースの『貿易風にさらされて』は、それで言うと、都市型ポップスの少年性(または少女性)とファンタジーが最もメロウに充満した曲だから、自分にとっての唯一の青春ソングに思えるのかもしれません☆
たぶん、ここで過去に「1978年の世代」ということに拘って、色々と書いてきたのも、この藤井氏の名言と深く関係があると思います☆
1978年は、都市型ポップスにファンタジーが充満していたように思いますね☆
しかも、70年代のドロドロ感すら一気に脱して、都市型ポップス特有のファンタジーが弾けて全開になっていました☆
しかし80年代に入って都市型ポップスが大衆化していくと、どんどん土着化して詰まらなくなり、流行自体下火となりましたが、やはりファンタジーが無くなっていったということだと思いますね☆
それで言うと、角松敏生氏のセカンドアルバムまでにはファンタジーが明確に感じられたのに、サードアルバム以降は大衆音楽に思えた、というのも思い出しました☆
それで、まだディスコ・ブギー系やブラコンにファンタジーを持っていた角松氏の弟子格・ジャドーズに期待したということも昔ありましたな☆
80年代真ん中ぐらいで一旦都市型ポップスの流行が終わったのに、90年代に渋谷系という形で、また都市型ポップスが復活したのは、都市型ポップスがピチカートファイヴやフリッパーズ・ギターやオリジナルラブなどによって、少年性やファンタジーを取り戻したからかもしれません☆
フリッパーズ・ギターの『恋とマシンガン』にはスウィングジャズのコードが使われていて、謂わばパンクとジャズを融合させたネオアコをやっていたと藤井氏に分析されていますが、このパンク性という意味では、ピチカートやオリラブにもポストパンクの影や、パンク性を当時感じましたね☆
ピチカートなら、小西康陽氏の歌詞に、死滅したパンクスの、その生き残りによる鎮魂歌(レクイエム)のようなものが感じられましたし、オリラブはメジャーデビュー前に、渋谷クワトロでやったお披露目ライブの演奏が、まさにパンクとジャズとロカビリーのかなりワイルドな融合というか、ぶつかり合いのような凄いものでした☆
そして、そこに都市型ポップスの少年性やファンタジーがダイレクトに出ていました☆
 | ベリッシマ 2,592円 Amazon |
また90年代末から21世紀にかけて、終わっていく渋谷系に代わって、キリンジや冨田ラボ、流線形やLamp、多和田えみ他がイノセントなまでに少年性とファンタジーに満ちたシティミュージックを再興し(しかしこの本では21世紀に入ってからのこのムーブメントには全く触れられていないのがとても残念☆)その後北園みなみやNulbarich、Suchmos、WONKなどの、都市型ポップスが生まれてきたのも、謂わば都市型ポップスを絶えず少年性やファンタジーによって、大衆化から浄化し続けている変遷故ということなのかもしれませんな☆(でもSuchmosはあまりに大衆化を今や余儀なくされているのが心配ですが☆)
また海外でグラミー賞だって可能性あるNao Yoshiokaや、フランスのブギー系レーベルからデビューした、すでにあちらではプロフェッショナルとすら思われているT-GROOVEなども都市型ポップスの可能性が感じられる人たちですな☆
藤井氏が、オザケンとコーネリアスの二人は、それぞれソロになってから全く対極的な楽曲制作を行っているという優れた分析をされていますが、やはりオザケンもコーネリアスも、時代がどうとか今の若者がどうとかのマーケティング的な発想ではなく、それぞれ自身の少年性やファンタジーを完全に真空パックして、それをそれぞれ全く対極的な方向に向けて勝手に好きなようにやってきたからその天才性が顕現して、一つのムーブメントの中心になったと思いますけどね☆
牧村氏はそのことがよくわかってらっしゃって、コーネリアスのプロデュースにおいても、ある時期からご自身の発想を入れないようにしようとされていたようですが、それで良かったんじゃないでしょうかね☆
それによってコーネリアスは、少年性やファンタジーを完全真空パック出来たわけですから☆
今はこういう時代だの、今の若者はこうだから、というありがちなマーケティングから細野さんや達郎さん、フリッパーズ・ギターが生まれたとは思えませんし、そういうマーケティング思考が大衆化による土着化を招くというか、そもそもその発想自体が、大衆化や土着化への拘泥をハナから前提にしているような発想だと思いますね☆
対談の終盤で牧村氏が、今やってる渋谷の再開発は、あれは再開発ではなく破壊作業をしているようなもので、ハナからサロンを元々資格のある人に与えようとする発想であり、逆にそんな再開発に反対するような人が勝手に集まった方がいいと言われてますが、まあ仮に新たなサロンがそこに生まれるにしても、やはりこの「勝手に集まる」ことが重要だと思いますね☆
それ無くして、大衆化や土着化に繋がる(というかハナから前提になっている)マーケティング思考をやっても、まあそれをJPOPのような、大衆化や土着化がハナから前提というか最終目的になっているようなものに対してなら有効でしょうが、こと都市型ポップスにおいてはちょっと本末顛倒だと思いますな☆
やはりこの本は、かなりの名著ですね☆
 | 渋谷音楽図鑑 Amazon |

