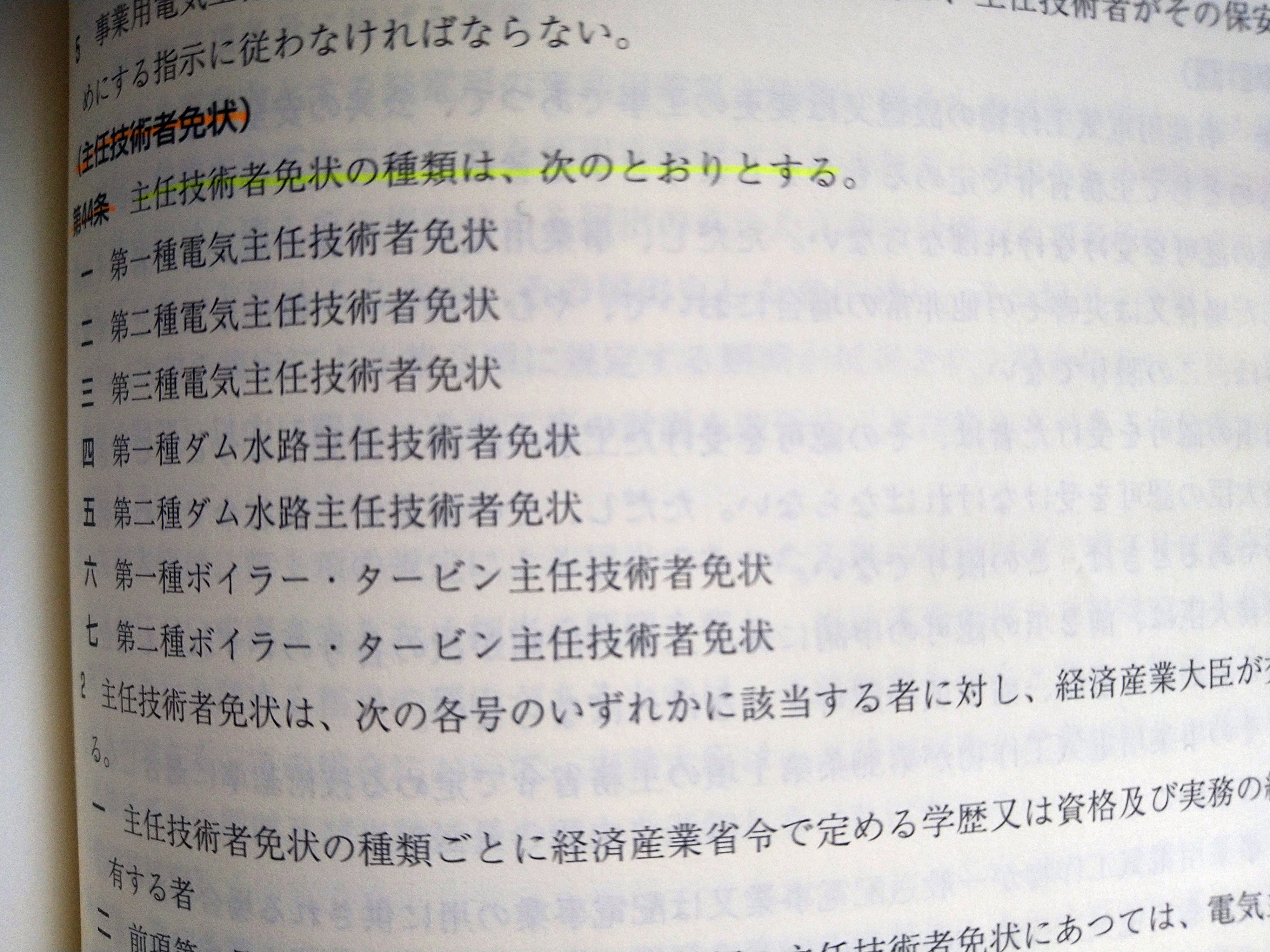電磁砲44です。
今回はボイラー・タービン主任技術者の労働災害について考えてみたいと思います。
日本人ならば憲法において労働の義務が定義されているため、よほどのことがない限りどこかの職場に属していることになりますが、その労働において災害が発生してしまってはいけません。労働安全教育を少しでも受けたことのある方ならわかると思いますが、「朝家を出たそのままの姿で、家に帰ってくる」ことが大変重要であるという教育を受けますよね。まぁ、当然の事です。
その労働災害ですが、当然ですが職場により発生する災害が変わってきます。建設業なら「転落」や「落下物」、電気業なら「感電」、事務職では「腰痛」や「腱鞘炎」。それぞれの業界に応じた災害があります。我々が労働する際には、このことを強く意識しておく必要があります。意識しておくことで、労災を未然に防ぐことも可能となります。
労働災害とは
厚生労働省の用語解説で「労働災害」が出てきます。
これによると・・・
「労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、業務 上の疾病及び死亡をいう。ただし、業務上の疾病であっても、遅発性のもの(疾病の発生が、事故、災害などの 突発的なものによるものでなく、緩慢に進行して発生した疾病をいう。例えば、じん肺、鉛中毒症、振動障害 などがある。)、食中毒及び伝染病は除く。
なお、通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。」
とあります。
また、わかりやすい解説によりますと・・・
「労働者が仕事や通勤が原因で、負傷したり、病気になったり、亡くなったりすることをいいます。労災が発生した場合、労働者は労災保険から補償を受けることができます。
一方、会社には、従業員が労災申請をする際の「手助け」と「証明」をすることが法律で義務付けられています。また、労災事故が発生したにも関わらず、労働基準監督署長への報告を怠ると、労災隠しとして処罰される可能性もあります。このような事態を防ぐためにも、労災が発生した時の正しい対応方法を知っておくことが重要です。」
会社においては労働災害が発生した場合は隠蔽せず、手助けしないといけないってことなんですね。
では、ボイラー・タービン主任技術者が関係する労働災害とはどのようなものなのか、見ていきましょう。
1、やけど
一つ目は「やけど」です。やけどと一言で言っても手の甲から顔に負うものまで様々で、さらに重症度も違います。ボイラー・タービン主任技術者はどうしても蒸気を扱う必要があり、やけどは1番身近な労働災害と言ってもいいでしょう。
対応策としては、「蒸気出口の正面に立たない」だったり、「牛革の作業手袋着用」と言ったことがあげられます。また、熱いバルブに触っただけでもやけどする可能性もあるため、温度確認は重要となります。特に肌を出すような服装は極力控えます。
2、転落
二つ目は「転落」です。どうしても作業環境が高所になったり、転落しやすい場所となることが多く、負いやすい労災の一つです。
対応策としては、必ず「安全帯」をつけましょう。この4・5年でフルハーネス型安全帯の着用が義務付けられた職場も少なくないと思われますが、自分の身は自分で守るという認識が重要です。
先日も、建設現場の鉄骨が落下し、作業員が亡くなる痛ましい事故が発生しました。
この状況については色々あって詳しくわからないのですが、このような悲惨な事故が二度と起きてはいけないと私は思っています。
3、感電
三つ目は「感電」です。タービン発電機周りは電気盤もあり、電気主任技術者と連携して作業することが大切です。また、ボイラー・タービン主任技術者が年次停電作業に従事することもよくあることだと思います。15ミリアンペアで心室細動と呼ばれる、心臓の細かい痙攣が起こるレベルに達します。また、このくらいの電流値となると、体の自由も効かなくなり、通電している対象物を離すことができなくなります。結果、長い間心臓を電流が流れるため、災害としては非常に危険なものの一つです。
対応策としては、電圧レベルに応じた保護具の使用や汗の処理、検電等を行うことで不用意な感電は防ぐことが可能です。とはいえ、高圧や特別高圧になると、接触していなくても感電してしまうこともあるので、細心の注意が必要です。
4、引き込まれ
四つ目は、引き込まれ事故です。ボイラー・タービン主任技術者が最も接しやすい状況と言っても良いでしょう。
ボイラーは運転している時はたいてい正圧で運転していますが、運転停止して温度が下がると負圧となることがあります。そのためにボイラー・タービン主任技術者は、水抜き前にエア抜き弁を開放し、ボイラー内部の圧力を大気圧にする作業を必ず行います。岩手県野田村で次のような事故がありました。2chの過去スレです。
https://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1468655439/
負圧になったボイラードラムの入り口を開けたときにボイラードラムに吸い込まれ外傷性ショックで死亡しています。
このような事故を防ぐためには、必ず点検前にはエア抜弁を開放する、ドラムの入り口に留め具を付ける等の措置が考えられます。
5、巻き込まれ
五つ目に、モーター等の回転体に袖等が巻き込まれることがあります。ボイラー等の設備はポンプ(モーター)等の回転体を多く使用するため、服などが巻き込まれて大きな怪我をすることがあります。
これを防止するためには、袖等はガムテープ等で回転体と接触しないようにする、腕まくり等をしないなどがあります。
まとめ
幸いにも私の周りでは労働災害で亡くなった方はいらっしゃいませんが、指が一本なかったり、私自体、背中を足場に強打し、しばらく背中が痛かったことがあります。
このような労働災害を極力減らすために、次の事に注意しましょう。
① 手順を守りましょう
② 保護具は面倒でもつけましょう
③ 疲れているときは休みましょう
(労働災害は疲れているときに発生しやすいということも言わ
れることがあります)
④ しっかり食事をとり、体調を整えましょう
⑤ 安全衛生教育を行いましょう
⑥ KY活動をしよう
⑦ リスクアセスメントを実施しよう
⑧ 作業しやすい服装を心がけよう
他にもありますが、このようなことに気を付けるだけでも労働災害を減らすことは可能です。
さていかがでしたか、人間が作業する場合どうしても不安全行動が起こることがあります。でも、それは可能な限り減らすことはできます。不安全行動が労働災害を生み出すといっても過言ではありません。労働災害で人がなくなることがない業界になってほしいと思っています。
いかがでしたか、いいね押してもらえると励みになります。
関連記事