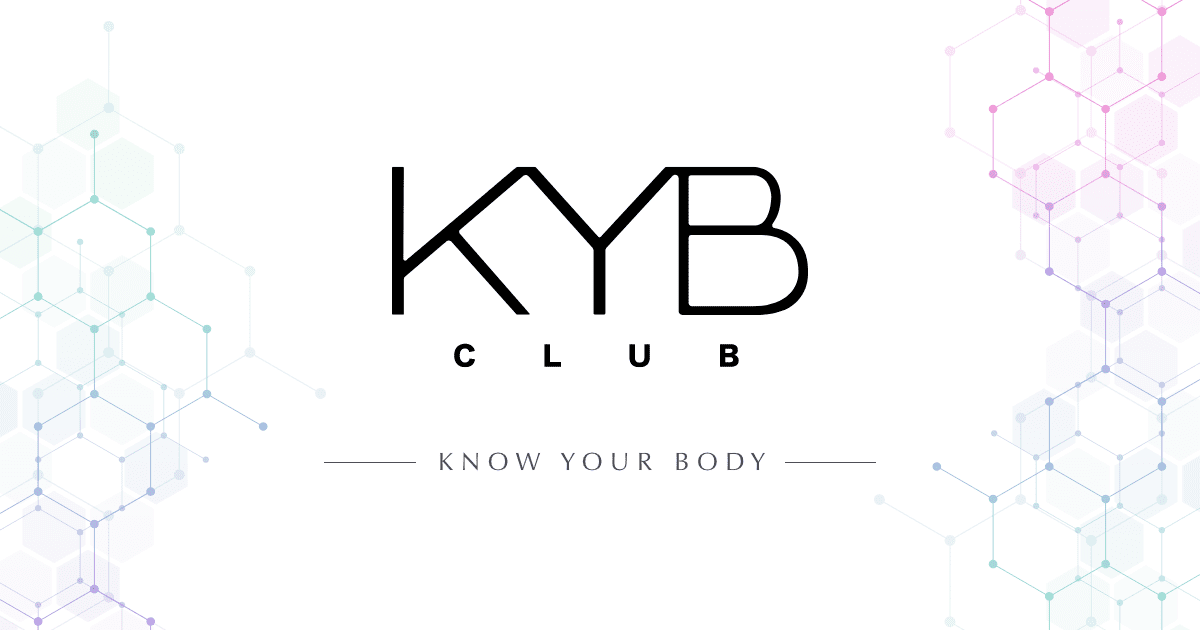自己流の当てずっぽうで補う、のは危険
「補うなら、客観的な栄養状態の評価に基づいて」
なんですが…
自己流でないまでも、「病院で診てもらっているから安心」と言えるんでしょうか?
決して医療を否定しているわけではありません…でもこと栄養改善に関しては、うーん?ということも。
癌の方には多い貧血。
どうしても癌治療の方が優先で、病院では「まぁこれぐらいなら大丈夫ですよ」と貧血は軽く見られがち。
でも貧血は、全身の細胞の酸欠状態…。ミトコンドリアは酸素がないとエネルギーを産生することもままなりません。
体は、大きな負担を強いられているんですよね。
詳しくはこちら
↓
そして「じゃあ、貧血を治療しましょう」となって、処方されるのは、鉄剤。
吸収も悪く、むきだしで、胃腸の負担にもなりやしく、活性酸素も発生させやすい「非ヘム鉄の鉄剤」。
吐き気やムカつき、便秘など胃腸障害を我慢しながらも、貧血を治すために、とがんばって続けている方も…。
中には、ヘモグロビンが低すぎるからと、鉄の静脈注射(点滴)の治療をするケースも…。
この鉄の静脈注射。本来の鉄代謝とは全く違った不自然なルートで鉄がダイレクトに血中に入ってくる…体内では一体どんな反応が起こっているんでしょう?
こういった非生理的な形で体内に入ってくる鉄というのは、活性酸素を発生させ、様々な弊害を生みます。
一方、わたしたちの分子栄養学で、鉄を補う場合、使うのは「ヘム鉄」。
レバーや赤身肉の中に含まれる鉄と同じポルフィリン環に包まれた化学構造を持つ鉄で、非ヘム鉄のようにむきだしではないので、吸収阻害を受けにくく、胃腸障害も起こりにくいヘム鉄。
吸収率は、非ヘム鉄の約6倍。
こんなに吸収率はいいのに、鉄過剰にはなりません。
なぜでしょう?
レバーや赤身肉をガンガンとり続けたとしても、鉄の充足はあっても、鉄過剰にはならないですよね?
それは、わたしたちの体には、口からとったヘム鉄に関しては、鉄が足りていなければ腸管から積極的に吸収する、逆に鉄が足りている時には便と一緒に排出する、といった絶妙な調整機能が備わっているから。
つまり、自然界に存在する食品と同じ化学構造を持つものを至適量入れておいて、「いってらっしゃ〜い 」 と、あとは体におまかせ。
」 と、あとは体におまかせ。
そうすれば、体が勝手に代謝して、必要な分だけ必要なところで利用してくれる。
逆に余分なものは排出してくれる。
なんともシンプル、かつ合理的。
これはわたしたちの分子栄養学では基本中の基本。
↓
でも「ヘム鉄」ならなんでもいいわけではありません。
同じ「ヘム鉄」と表記されていても、中身は分子栄養学で扱うものとはまったく別物。ネットやドラッグストアなど巷にあふれるサプリに関しては一切責任とれません、あしからず。
詳しくはこちら
↓
そもそも、貧血は鉄不足だけが原因ではありません。
たんぱく質、亜鉛、ビタミンB群が不足しても貧血になるし、造血に関わるホルモンを作る腎機能が落ちていても貧血になります。
どこかで溶血があっても貧血になるし、貯蔵鉄のフェリチンがたくさんあったとしても、体内でうまく利用できない「鉄の利用障害」があれば、貧血のような症状が。
つまり、ヘモグロビンの数値だけを見て「鉄」を補うのは早計なわけで…。
☑ 貯蔵鉄のフェリチンがどれぐらいあるのか?
☑ 血清鉄はどれぐらいあるのか?
☑ 体内で鉄を運ぶトラックはどれぐらいあるのか?
☑ 貧血に関わる栄養素の欠損はないか?
こういったことも見ていかないと、鉄が体内でどのように代謝され使われているか、なぜ貧血の症状が出ているのか、貧血の全体像は見えてきません。
しかし、保険診療では、こういった概念はありません。
特に癌は炎症性疾患。この炎症によりフェリチンにはマスクがかかったりするので、その辺りを他の項目も併せて、慎重に見ていかなければいけません。
ヘモグロビンだって、低たんぱくになりがちな癌患者さんの場合、血液濃縮により、見かけ上いい感じの数値に落ち着いてしまい、本来ある貧血が隠されてしまうことも…。
病院での診察時に、このように栄養状態を正しく評価し、様々な原因を探った上で、対処してもらっていますか?
多くの癌患者さんであふれる病院での診察室では、時間も限られ、あくまで癌治療に関するお話が中心。
保険診療の限られた血液検査結果をサラッと説明はしてもらうけれど…。
やっている抗がん剤治療、放射線治療が続行可能かどうかを見ているだけで、実は
栄養欠損のサイン
がたくさん見えているのに「H」や「L」がついてなければ「問題なし」。
↑ほんとに大丈夫かな? 
いまいち、自分の栄養状態にはどんな問題があって、何が足りていなくて、どう対処していけばいいのか、よくわからない。
うーーん🤔
もや。
もやもや。。。
もやもやもや。。。

これって「病院あるある」ではないでしょうか?
やはり、癌治療はあくまで癌を消すことが最優先。
決して、医療を否定するわけではありませんが、病院まかせにしていると、どうしても栄養状態はおざなりになりがち。
だからと言ってそのままでは、栄養欠損はどんどん進んでしまい、結果的には肝心な癌治療さえもとどこおってしまう、それだけは避けたいですよね…。
だからこそ、栄養改善の専門家の力を借りながら、医療と連携しながら、そして自分たちで知識を身につけながら
自分の体は、自分で守っていかなくては
結局のところ、それが、「癌に負けない体」を作る一番の近道だと思いますね。
お問合せフォームからもお気軽にどうぞ(*^_^*)
乳がんステージ4
わたしの乳がん治療
・2021年10月 右乳癌ステージ2B
腫瘍径 1.8cm ER100% PR100% Her2(-) Ki67 30% 核異形度3 ルミナルB 腋窩リンパ節転移 2ヵ所
・2021年12月 放射線治療
・2022年 1月 ホルモン療法開始
・2022年 6月 PET 乳腺、腋窩リンパの腫瘍は消失も肝臓2ヶ所、肺、肋骨に転移が判明→乳癌ステージ4
・2022年 8月 免疫療法開始
・2022年 2月 PET 肝臓2ヶ所は縮小
・2022年 3月 肋骨のみ放射線治療
・2022年 3月 肺、肋骨に追加の免疫処置
・2023年 9月 PET 肝臓、肋骨は消失、肺は縮小も第5腰椎に新たな骨転移
・2023年 11月 第5腰椎骨転移にラジオ波治療
・2023年 12月 免疫療法にて再発予防の処置開始
栄養療法に支えられ、元気に乳がん闘病中 ![]()
乳がん転移予防、乳がん再発予防ために
ご自分の栄養状態を「正しく」知りましょうね。