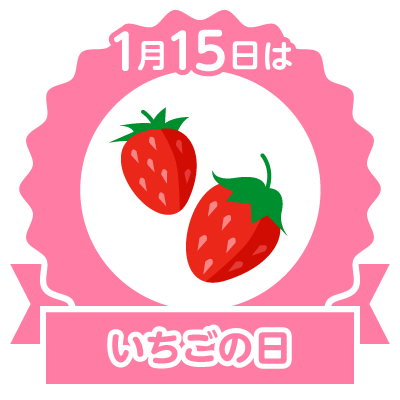「廃藩置県で旧国は廃止された」と思っている人がいますけど、間違いです。
律令制の「国」、いわゆる旧国は、江戸時代にはすでに行政区画としての実態はまったくなく、単なる地域区分に過ぎなくなっていました。
「藩」の領域というのは、国とは必ずしも関係なく分けられていました。従って、藩を廃止しても、国を廃止する必要は全くないのです。
廃藩置県というのは、藩をそのまんま県に置き換えただけで、それこそ数百という県ができたわけです、それが明治のあいだに目まぐるしく合併、合併を繰り返して、だんだん現在の形に近づいたわけですが。
その間、明治政府の公文書では、地域を表す「国名」が依然として使われていたんです。
たとえば鉄道の施設計画書をつくるとき、地名を示すためには、国名が正式文書にも使用されていました。
県名は使えません。五年語、十年後にもそこが同じ県名である保証は全くないからです。
だから、鉄道の建設計画書には「武蔵国〇〇郡から、相模国××群まで、線路を建設する」といったように、国名が堂々と使われていたんです。
江戸時代には、大名旗本の肩書(柳沢出羽守、とか)に使われるくらいで、実質意味がなかった「国」が、明治になっていきなり実際に地域単位として使用され始めたわけです。
国鉄では、日本中に同じ名前の駅が二つあってはまずいので、後からできたほうの駅名には「国名」をつけます。日本中に同じ地名なんかいくらでもありますから、この例は数え切れないほどあります。
羽後本荘の近所には「羽後亀田」という駅がありますね。見たことありますか、映画「砂の器」(松本清張原作)。
丹波哲郎と森田健作の刑事コンビが冒頭で降り立った駅です。殺人事件の被害者が東北弁で「カメダ」と口にしていた、という証言をもとに捜査に来たのですが、空振りに終わる。
駅名に「羽後」がついているので分かるように、カメダなんて名前の土地は全国にいっぱいあるんで、頭に国名をつけて区別するわけですね。
東北地方のカメダをいくら探しても手掛かりがなかったのに、実は意外なところに、それは島根県の出雲地方も東北弁に似たイントネーションだった、そこにカメダがー?っていうミステリーなんだけどさ。それはさておき。
同時に陸奥は「陸奥(青森)陸中(岩手)、陸前(宮城)、磐城、岩代(福島)」と五つに分かれました。
また、北海道には明治になってから「渡島・胆振・日高・後志・北見・千島・石狩・天塩・十勝・釧路・根室」という国名ができています。北海道の駅名にこれらが頭についていたら、それは「国名」なんです。
東京にだって「武蔵境」や「武蔵溝の口」「武蔵小杉」があります(あ、これは神奈川かな)。他所に「サカイ」や「コスギ」があったので、区別しているんです。
現在でも、新しい駅ができたとき他所と名前がカブれば、国名がアタマにつくことがあります。「武蔵浦和」なんて結構最近できた駅です(これはさすがに、いかがなもんかと思ったけどね)。
「国名」は、昔の名残でも思い出でもなく、制度上も廃止されずに、現役で生きているからです。