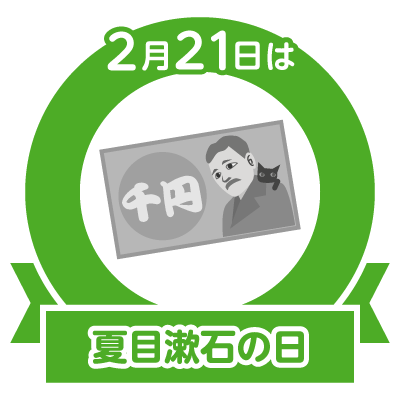「鎖国」時代には、実は四つの窓があった、というのは、現在では普通に言われています。
なぜ、江戸幕府は、薩摩と対馬と松前という三つの藩にだけ、事実上、海外貿易することを許したのか?
もちろん、密貿易ではありません。「公認」と「黙認」の中間くらい、でしょうか。

幕府は長崎によるオランダ、中国との貿易以外は、国家との正規の貿易を認めていませんが、これは建前です。実際には、周辺諸国と何の交易もせずに済むもんではないんです。海には壁を立てられません。
そこで例外を三つ許したわけです、
まず対馬の宗氏、これは朝鮮との外交関係を仲介しており、そのための方便として朝鮮国王の臣下となり(もちろん幕府の諒解のもとです)、儀礼的な貿関係を結んでいました。対馬は、日本なのか朝鮮なのか、曖昧な位置です。
松前藩が取引していたのはあくまでアイヌ相手であり、そのアイヌがロシアと交易していたので、現実はロシアと松前藩が交易しているわけです。アイヌというのは松前の領民のようでもありそうでないようでもあり、だからロシアと私貿易をしても大目に見られた。日本人なのかどうなのか、曖昧な位置です。

薩摩は、琉球を征服し、これを支配することを幕府に認めさせました。ところでこの琉球は形式上は独立国で、明と朝貢関係を結んでいました、つまり中国と堂々と貿易していたわけです。琉球は、日本なのか中国の子分の独立国なのか、曖昧な地位です。
幕府が薩摩に許しているのは、琉球を支配することです、貿易して宜しいなんて公認はしません。貿易しているのはあくまで薩摩人ではなく琉球人です。明(中国)のほうも、自分たちは琉球という国と交易しているつもりでいます。
なんでこんなことを許すかといえば、薩摩は日本の端の生産性の低い土地で、国内の農業だけではとてもやってけない、地の利を利用して交易で儲けて、はじめて成立する国なんです。だからお目こぼしせざるを得ない。

世の中に誤解している人が多いですけど、薩摩というのは江戸時代の大名のなかで、いちばん幕府から贔屓されて優遇されてきた特別な藩なんです。こいつらが本気で叛乱してきたら面倒で仕方ないから、さまざまな特例を認めています。
それに、薩摩が本気で衰退したら、幕府としても困るんです。日本の端のほうの弱った土地に、外国が攻め込んできたらあっというまに占領され、日本全体が征服される足がかりになる。だから、辺境諸侯にはある程度の特権を与えて自衛力を保持してくれないと、日本が困る。
これは、対馬も蝦夷地も同じです。ほとんどコメが取れない辺境の地を放置したら、そこから外国が侵入してきてあっという間に日本全部が危うくなる。だから、宗氏にも松前氏にも、事実上の交易を許して、力を蓄えさせることを許しているんです。

「鎖国」っていうのは、国内に流通経済が浸透すること防ぎ、幕藩体制を守るために必要な策といえます。大名を貧乏にさせるためではありません。武家政権ってのは国内の農業生産だけで自給自足するのに相応しい政権です。商業に手を出しすぎると、武士の政権は必ず弱体化します。そのための「鎖国」(カッコ付き)です。

しかし、言うほど簡単なことではありません。外国は、どんなに見ないフリをしていても、やっぱりあるんですよ。完全に国を閉ざすことは不可能だし、本気でやったら窒息死します。「アソビ」つまり緩衝地帯を作っておかなければ、危ないんですよ。