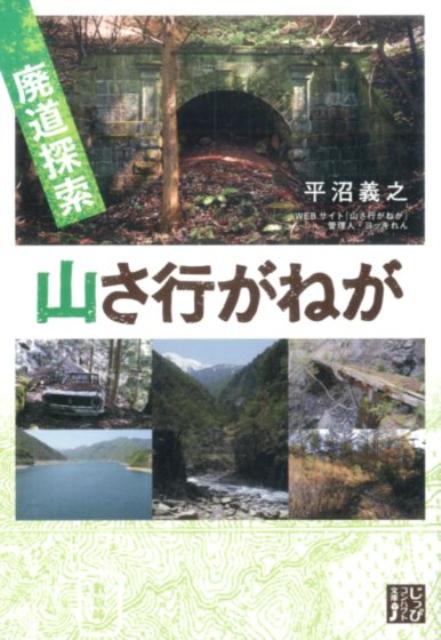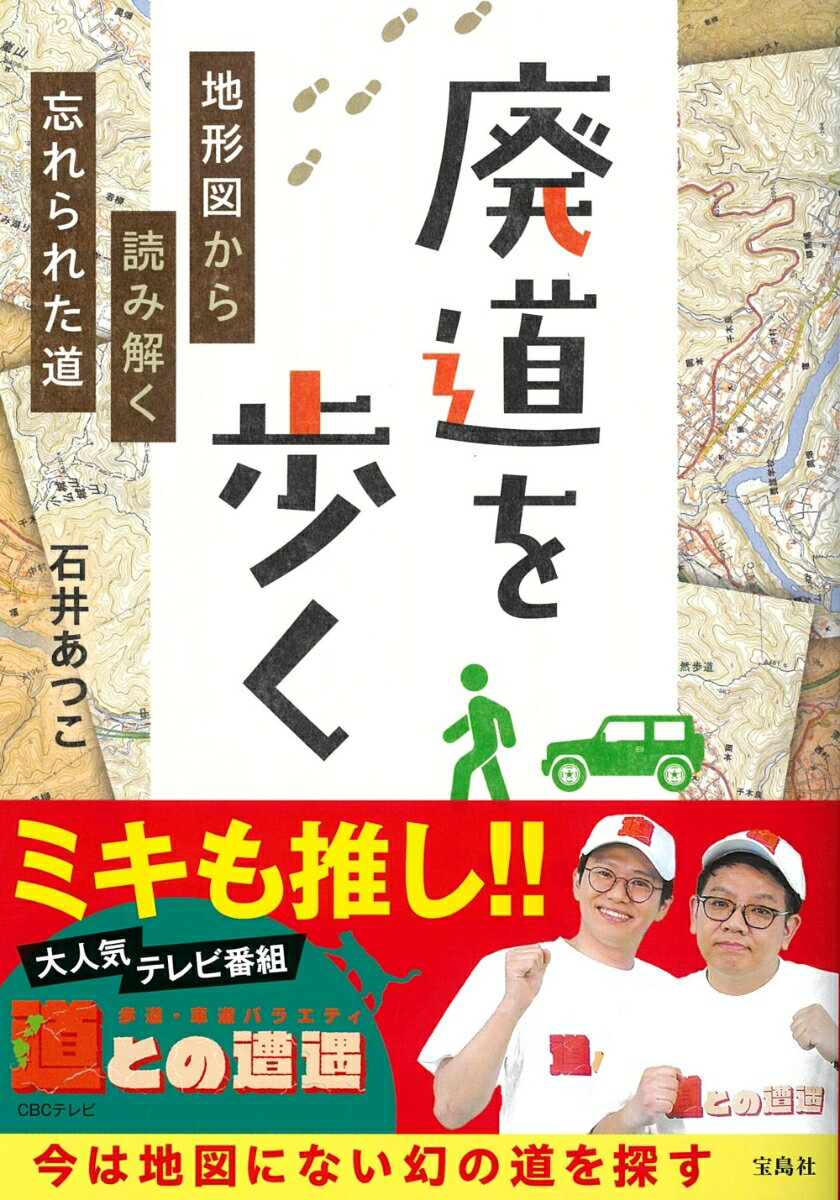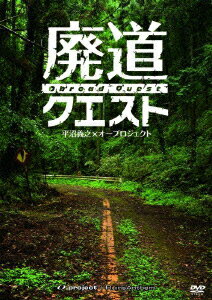この古道は踏跡が全く無く、道形も消失していたり見えにくかったりするので忠実に辿るのが難しいです。地形図に描かれた山道とも経路が異なっており、山慣れた人でないと道迷いの危険があると思われます。ネット上に情報も皆無なので十分注意が必要です。
現在の国道293号は越床峠をトンネルで越えているが、この道は1995年に開通した樺崎バイパス。
それ以前はトンネル坑口あたりから南へ回り込んで、巨大な切通しで通り抜けていた。ここが今の越床峠となっている。
そして、車両が通行できる最初の道は1895年、今のトンネルより少し南の山中に素掘り隧道が掘られ、ここを通っていた。
城好きになって間もない2019年3月に、ワタシはこの旧道、旧々道とまとめて見物に来ていた😂
少なくともこの当時、尾根から東側の道形も隧道もハッキリ残っていた。
さて、明治より昔、この峠道はどこを通っていたか…
なんてことは考えることもなく忘却界へと葬り去っていたのだが…
(電子国土webの図上に筆者作図)
この図は、4年前に訪問した隧道のある旧々道と、今回下った古道の経路を描いたもの。
例によってGPSログではなく一部は記憶に頼って描いたので、不正確なことをお許し願いたい。
この日、樺崎城、赤見駒場城と続けて訪問し越床峠の方に向かって下山途中、最高点になる山神山を通過し下った鞍部で、こんな場所に出会ってしまった😮
ここ、隧道より前の越床峠じゃないか…?⚡️
そして、その傍らに土や岩が盛られ、てっぺんに石龕…
見れば、東西両側から、つづら折れの道のようなものが登ってきている😮
峠の西側を俯瞰。東側は撮るの忘れた😂
地形図にもそれらしい道が描かれていたので、これが往年のトレイルと決めつけて、車を置いた西の方への近回りを兼ねて下ってみた。
このトレイルはネット上に情報が全く無く、ここを通過したらしい記録などでも悉くスルーされてた。完全に忘れ去られている…🥺
道形は消えたり現れたりしながら、広い谷の底ちかく、地形図に描かれたのとはだいぶ違うところをを通っている。
少し下ったココなんか、雄大な左カーブを描いていてカッコいい✨
標高150メートルあたりで沢から北に離れてゆくように見えたが、経路はハッキリしなくなるしヤブも深くなってきたので、そのまま沢を少し下り、右側がヤブのない植林地に変わったところでトラバースしてゆくと、ふたたび道形に出会った。
このあたりは、ほぼ地形図に描かれた経路を進んでいるようだ。
まるで城の横堀のように、外側の築堤との間に深く凹んだ道😮
そして、広場のような平坦な場所に出ると、ついには立派な踏跡が現れる。
だがこれを辿ってゆくと民家の庭に出てしまうので、引き返して広場のもう少し奥へ。
地形図の経路あたりに小さな掘割状が走っていて、これが古道の続きだろう。
しばらくす進むとヤブの中に突っ込むが、道形は見えるので怯まずに進むと、こんな立派な掘割に変わる😮
土が柔らかくて歩きにくいが進んでゆくと、庚申塔などが並ぶ車道端に出た。
近くに小さな説明板が掛かっていた。
それによると、ここは間違いなく車道ができる前の越床峠道で、入口には百庚申塔があり現在も95基が残っているとのこと。
遺構と思われるものは多くの部分が消えかけ、横堀状のところも薬研堀みたく見える断面になっているところを見ると、道幅はせいぜい2〜3メートルといったところだろう。
峠ちかくは曲線も勾配もきつく、とても車両では通行できなそうな道形を見た限りでは、明治よりも前の徒歩道なのだろう。
このルートは道なき山の経験豊富な人には楽しいだろうが、かなりの部分で道形が消失していたりヤブに埋もれたりしているので、迷いやすい。
赤見駒場城あたりに登るのにショートカット出来そうに見えるが、単独で歩くのは止めた方が良いだろう。
★越床峠古道
栃木県足利市樺崎、佐野市赤見町
足利側の入口に百庚申塔、峠に石龕あり。経路はほぼ消失、かなりの部分が地理院地図の山道とも不一致。下マップのピンは足利側の入口。
(2025年6月18日 記)