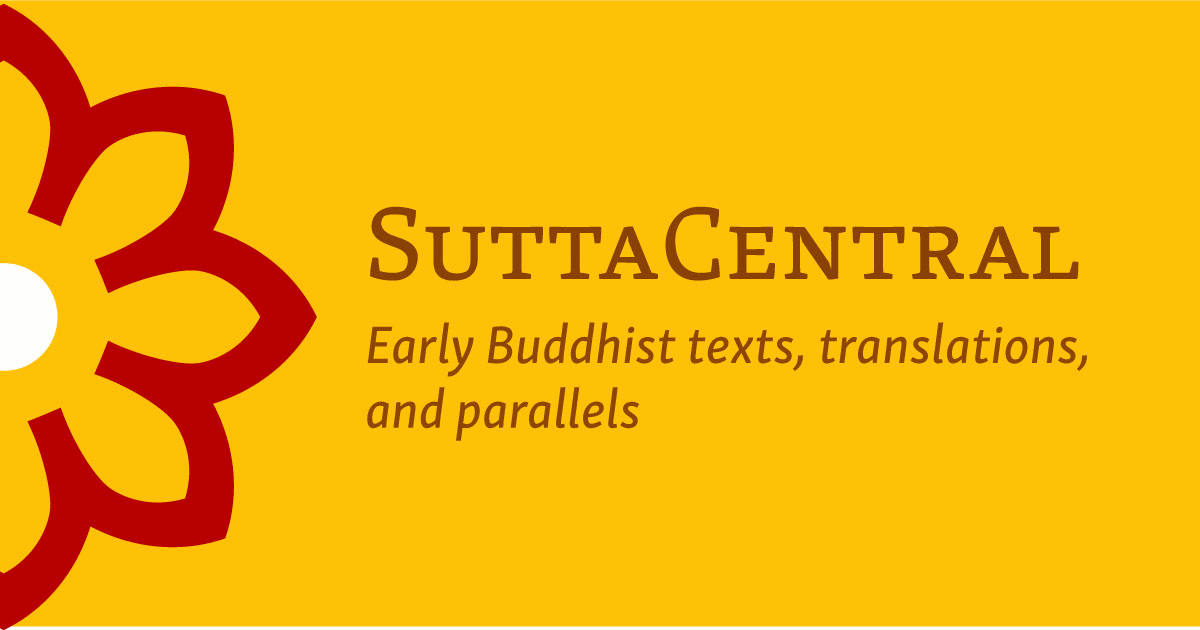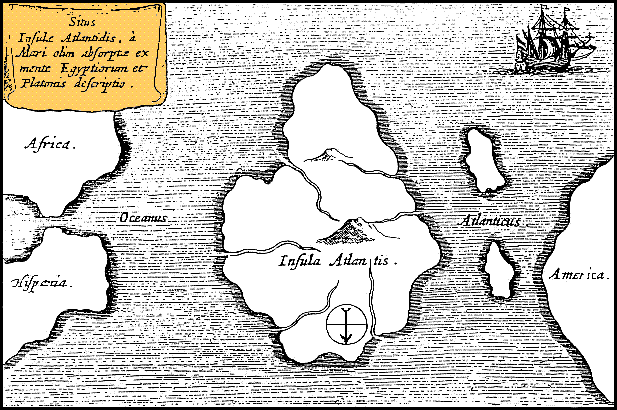占星術師のDee Nakagawa(ディー・ナカガワ)です。
電話占いヴェルニで電話鑑定してます。
原宿占い館塔里木(タリム)で対人鑑定しております。
Zoom鑑定始めました。
安倍元総理の死去で浮き上がってきた統一教会問題。
個人的には統一教会については問題を起こしている団体という印象だけで、詳細は興味がなかったんです。
ですので今も問題が継続し、これだけ政治家達と癒着しているのは驚きです。
今の他の宗教法人がどれだけ政治と癒着しているかというのは、表に出ないでしょうが千差万別。
逆に反政府反政治で、癒着とは逆に政治勢力を嫌い距離を取っている団体も少なくない。
宗教と政治。
もともと宗教の始まりはスピリチュアルとも同じ「秘教、ミスティシズム」にあります。
その宗派がメジャーとして政府と国民に認知されるかされないかの違いが、宗教とスピリチュアルの違い。
スピリチュアルで反社会性が強いとカルトと認識される感じですよね。
スピリチュアル団体のソシオパスみたいな感じでしょうか。
宗教システム、教義の中身が人の精神に与える影響と、国の支配層側の認知はほぼ関係無いと思います。
統一教会も日本政府に持てた影響力は政治力の提携とカネが主力だったようですし。
もしも仮定として、
仮に神や仏といわれる人間を超えた何かが実在するなら、人間社会のさらに上の階級がこの世に存在することになります。
神なので人間全部より上な訳です。
上級国民達を支配する支配者より上の精神的人間がこの世に存在する構図になる。
ですので支配側は根本的には宗教を潰したがる。
支配側に認知されるほど、それは国家より下の宗教と認識される団体なので、逆に宗教性は希薄になります。
宗教とは常時存続危機にさらされる、危ない領域なのです。
同時に今の多くのカルト団体は、自分たちは支配側の被害者とも主張する訳で、宗教業界は混迷し複雑怪奇になっています。
私が興味あるのは、正確にミスティシズムを追求しようとするタイプの宗教です。
そんな中、私は仏教は興味深く感じてきました。
自分の知っている宗教の中でも最古に近く、社会的な権力構造との結びつきはお釈迦様の存命時から強かったので取り上げてみたいんです。
教祖のゴータマ・シッダールタ(お釈迦様の事)は、キャラクターもカリスマそのもので強烈です。
彼は仏教の組織化を上手にやりました。
ゴータマの人生については教典類に比べ情報が少なく、没前を記録したパーリ語教典というのがあり、これ以外にはそれほど参考になる文献は無いかと思います。
「パーリ語教典」は興味深く面白い。
パーリ語教典関係は、
日本語訳は詳細に訳していらっしゃると思いますが、ニュアンス的にお釈迦様に気を使い過ぎかと思うこともあります。
ここだと英文ですが良い感じ。
ゴータマ・シッタールダの個性は、私たちが一般的に考えている「文武両道、優秀で繊細な優しい元王子様」とは違うと思います。
この教典から私が受けるゴータマの印象は、普通ではない強靭で強引なメンタルの持ち主です。
それをコントロールできる賢い地頭と意思もありました。
時に救世主というより、修行をサボらせない軍事教官や将軍といった方がハマる時もあると思います。
彼の精神的強靭さは修業時代から入滅まで一貫しています。
連想するのは、19世紀のG・I・グルジェフです。
グルジェフの伝説はゴータマ・シッダールタより時代が近くリアルで印象が強いのですが、20世紀の誰もが感服したグルジェフであってもゴータマの力強さには敵わないと思うんです。
まずゴータマ・シッダールタはコーラサ国のカピラヴァストゥで王子として生まれたのですが、29歳で彼が出家し、お陰で結局彼の家は滅びています。
また母親のマーラーはゴータマを生んで7日後に死去しています。
悟って後、早いうちにマガタ国のビンビサーラ王とコーサラ国のプラセーナジット王に支援され、ビンビサーラから貰ったラージャグリハの竹林精舎は活動拠点にもしました。
しかし晩年その2人の王は息子に殺され、コーサラ国はゴータマのシャカ国を破壊し滅ぼします。
マガタ国のラージャグリハでは、ゴータマを支援した善良なビンビサーラ王を王座欲しさに幽閉し餓死させた極道息子のアジャータサットヴァ王を、ゴータマは弟子認定したりしています。
アジャータサットヴァ王はゴータマ・シッダールタの遺骨の一部も貰ったくせに、ゴータマの気に入っていたヴァイシャリを、ゴータマから聞き出したヴァイシャリの詳細情報とノウハウを参考にしてゴータマの死後に滅ぼしました。最低ですね。
そしてそのアジャータサットヴァ王もまた息子に殺されています。
時代のひどさもありますが、ゴータマ・シッダールタ自身も別に穏便な人ではなく、むしろ私には誰も逆らえないタイプのカリスマだったように思えます。
彼が影響した災厄で死んだ人もいる。
これだけの運命を生きるとこの世にも人生にもウンザリしそうです。
ゴータマ自身は出家時からこの世に期待を持つような人ではなかったと思いますが、他者への支配性は最初から最後まで一貫し非常に強いまま。
おそらくグルジェフ以上に本質的な力強さに溢れていた印象を受けます。
本物の宗教性がもたらす「力」の一側面です。
ゴータマは生まれた時から王子であるだけでなく「天上天下唯我独尊」でした。
彼の時代に、どの分野でも彼以上は存在しない人だったのです。
人類史上の最高傑作。
成人し出家するまでは、王国内で敵わない望みはなかったでしょう。
高等な教育も受けたと同時に、毎日を酒池肉林に過ごし大人になった訳です。
彼の場合、セクシャルなタントラとかに近いものは生まれた環境的にあったかもしれませんし、出家後は感覚的な喜びも一貫して否定し続けています。
彼の人生に無かった負の要素、死、老化、病、争いにむしろ執着し、ストイックに自分に負荷をかける修行に向かいました。
修行しすぎて瘦せ衰え死にかけた時にスジャータにお粥を貰い命をつないで悟ったというのは良い感じのおとぎ話です。
私は実際に90年代にインド南部で痩せこけたサドゥー(修行僧)にはお会いしたことはあります。
痩せこけても眼力とかエネルギーは強烈でした。
悟るための修業は、ゴータマにはハマったのではないかと思います。
ゴータマのような人たちの傾向として基本、修行に惹かれる性向がある。
似た事例として、例えばヨルダンでイエス・キリストは福音書にあるように、荒野に出て40日間飲まず食わずで過ごしました。
こんなことをすると様々なものが見えるでしょう。
全てが自分自身と神にまつわる世界。
荒野だと自己生存に関してはストレスしかなく、自己の外部に期待できるものはありません。
そういう場所に長時間自分の意志で存在すると、人間の意識はやりようによっては結晶化を起こします。
結晶化で得られるものは何かというと、肉体の死後も存続するエネルギー身体の形成。
通常人間が死んでも脳の完全停止までのタイムに臨死体験は得られるようです。
その後はやはりエネルギー体は解体され、あると教えられたかもしれない魂の多くは実際には消え去る。
なぜなら死後も存続可能な纏まりのあるエネルギー身体を、その人の寿命内で形成できていない。
ですので輪廻転生と言っても、それは良心に基づく正確な身体形成が上手く行った数少ない魂に限るということはグルジェフは主張していますし、釈迦の説法も非常に近いものを感じます。
現代の私たちのほとんどは“死ぬ時に後悔しないように”という事で、様々な希望を死去までのタイムラインで実行することが人生だと教えられています。
しかしながら実際の死に際して、後悔とか満足とか吟味するゆとりを持てる可能性は何パーセントくらい有るでしょうか?
内部と外部の大量の情報と感情の逆転交換が起こり、それに翻弄されるのが通常の死です。
そういった事をゴータマにしろ、マハヴィーラにしろ、イエスにしろ、グルジェフにしろ、様々に言い方を変えアプローチし続けたと思います。
聖書は“塵は元あった地に返り、霊はこれを下さった神に返る”と言いますが、その為の諸条件が無ければ宗教的なシステムもワークも必要ないはず。
ですのでこういう宗教的荒行には強い魅力があるのです。
映画でも修行中のサタンの誘惑、実在した柱頭修行聖者シメオンの伝説をルイス・ブニュエル監督がシュールに描いていたり。
「砂漠のシモン」
宗教の本質である神秘主義の指向性とは神意識との合一、仏教的に言うと「悟り」に向かう方向性。
こういうことを人生で本気で求める人自体が極少数です。
人間が知らない重要事項を人間に伝えようとすると、様々なリスクが降りかかります。
キリストは十字架で一度殺されたし、あるムスリムの聖者は「私は神だ」と口走り、生きたまま手足を切断され殺されました。
まるで現代のISISです。
古代宗教が伝えた「良心」から切り離されるほど、人間の世界は現在のように異常な世界になります。
科学や環境の発展は未来にあるのかもしれませんが、人間の内部の可能性の答えは未来でなく古代にある訳です。
人間達の特性を理解していたゴータマは、悟った後は特に何かをしようとは思っていなかったようです。
実際に意識の爆発を経験していくと、自分も世の中もどうでもよくなる傾向はあります。
執着心が減ったり無くなったり。
ゴータマの教え方については、パーリ語教典でも出て来るのが例えば中部21の「鋸喩経」で、
「盗賊に手足を切り落とされた時であっても、心を乱すことなく、怒りのこころを抱かないように実践せよ。目の前で比丘尼が棒で打たれたり襲われたり刃物で刺されても、心を動かしたりあれこれ思うな」などと言っている。
執着心の極端な減少ありきで可能になる事ですが、ゴータマの教典での弟子へのアドバイスとしては「“自分の心は動じない”と念じろ!」というもの。
弟子にしてみれば強引さは半端ない人だったのではないかと思います。
ゴータマはブラフマンから、「人間達に真理を教えてくれ」と懇願されたので教え始めたと言われています。
ブラフマン=ブラフマチャリア、つまり梵天からの逆らえない強いインスピレーションがあったと現代的に解釈すれば理解しやすいですが、ゴータマの理性的には人間に教える事がどれくらい難しい(というより無理な)話か、完全に分かっていました。
「中部26 聖求経」“聖なる追い求めの経”みたいな意味の経の中、ブラフマンとの対話でこう言っています。
困苦して我證得せる所も
今また何ぞ説くべけん
貪・瞋に悩まされたる人々は
此法を悟ること易からず
これ世流に逆らひ至微にして
甚深・難見・微細なれば
欲に著し黒闇に覆はれし者は見るを得ず
上記の英文とも比較して意訳すると、
「自分ですら悟るのにさんざん苦労した。
他人に分からせられる訳がない。
欲や憎しみにまみれた連中には無理だ。
これは世の中の流れに逆らう、深く精妙な真理なのだ」
とブラフマンに応えている。
この時点で、悟りで世間と関わることは最初から放棄していた訳です。
結局ブラフマンに懇願され聞き入れましたが、真理をどう伝えるかは全ての聖者の最重要課題。
基本的に人間は自分が聞きたい事しか聞き入れません。
悟りという分からないものを修行して手に入れようとさせるのはどうしたら良いのか?
釈迦としては妥協を受け入れると同時に、戦略も考え続けなければならなかったのではないかと思います。
こうした事情から、上記の『マガタ国のビンビサーラ王とコーサラ国のプラセーナジット王の支援』に繋がるのですが、政治と宗教の結びつきの歴史は古く、パーリ後の“聖求経”でもゴータマはしきりに“聖なる”を繰り返します。
来れも日本語訳だから“聖なる”ですが、基本的には“高貴な品性を持った生まれ”とでも言う階級的な意味に繋がるとしか思えない個所もあるので、読んでいくうちに混乱するところもあります。
ゴータマ自身の高貴さもアピールし、王達に感銘を与え教えを広める基盤を確保しています。
“高貴な(聖なる)者の為の教え”であれば高貴ではない人達も生まれます。
力と繋がると早速区別、差別が出来ている感じがするんです。
現実問題やむを得ないのかもしれません。そうしないと仏教がその後の5千年間に抱える膨大な仏教徒達に対しての影響力を維持してこれなかったのでしょうし。
もう一点お釈迦様の人種関連で、釈迦族がアーリア人だという事を唱える方もいます。
こちらの方も書かれております。
マックス・ミューラーによるとゴータマはアーリア人という事になります。
アーリア人=アトランティス人説もあります。
釈迦の教えはどこから来たのでしょう?
そのインドに侵入した少数民族だった高貴なアーリア人は後に、ヒットラーの「ゲルマン民族は高貴なアーリア人」幻想に繋がりました。
釈迦は膨大過ぎてブログの字数内で纏まりません。
今回はとりあえずこの辺で。