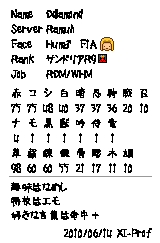下品、横柄、野蛮。キャリオットはそういう男だった。目覚めたキャリオットは全ての点でムーンの好みとかけ離れていた。
豚鬼を一斬りで葬り去った男の周りに村の衆が賞賛しながら群がった。男は当然のことの如く平然と受け止め、先程来から繰り返しているあの言葉「俺は征服王のキャリオットだ。」と一声吠えた。
「有難く思うがいい。この村は今日から私の統治下に置くことにする。征服王キャリオットの偉大な第一歩がこの地で始まるのだ。」
村人は、何のことやらわからずにぽかんとした。
「あのぉ。それで、この村で何をしたらいいんじゃろうか。」
気の利いたものが恐る恐るお伺いをたてた。
「まずは飯だ!最高のものを持ってこい!」
そういうと、男はずんずんと村の中に入っていった。村人達はざわめきながら男の後に続いた。村人は皆、立て続けに起こる珍事に戸惑っていた。
ムーンは豚鬼の返り血を全身に浴びて硬直したまま、ユピト老他数名に抱えられて村に帰った。とにかくひどい臭気で吐きそうなのを我慢するのが精一杯だった。ムーンは服を全部着替えて全身を洗い流すことだけを切に願った。
ムーンはよろめきながら井戸端に転がり込み、破り捨てるような勢いで服を脱ぎ、冷たい水を頭からかぶった。それでもムーンが理性的な思考を取り戻すのにはしばらく時間がかかった。
その間もキャリオットは平然としていた。血なまぐさい臭いに馴れているのか鈍感なのか、おそらくその両方なのだろう。キャリオットは行き当たりばったりの家の中にづけづけと入り込み、食卓に腰かけた。
「5分待つ。とりあえずなにか口に入るものを持ってこい。」
その家はムーニエ老と奥方の家であった。ムーニエ老は魔術に失敗して一時失神したが、村のものに支えられて意識を取り戻していた。
「何日も寝ておったから腹が減っとるのも仕方なかろう。かゆでも作ってお上げなさい。」ムーニエ老はおどおどする奥さんに優しく言った。家の周りには人垣が出来ていた。村人は目覚めた男を見てあれやこれやとひそひそ話をしていた。話をまとめたのはムーニエ老であった。
「皆の衆にもいろいろ言いいたいことはあるじゃろうが、ここは一つわしの話を聞いてくれんか。
あの男が何を考えとるかわしにはわからん。もしかしたら村にとって迷惑なよそものなのかもしれん。じゃが、わしらはあの男に助けられた。恩を仇で返したくない。今日だけはわしに免じて、村の客分扱いしてやってくれんか。」
ざわめきはあったが、大勢はムーニエ老に賛成であった。村人のほとんどが無防備に昏睡するキャリオットの面倒を見ている。みんなの心にはもう、捨て難い愛着がついていた。
たった今まで前後不覚に寝入っていた若者が、しかもたった一人で”村を支配する”というのはあまりにも現実味がなさすぎて、大方は腹も立たなかった。口には出さなくても、やんちゃな孫を見るようなほほえましさを感じている者も少なくなかった筈である。その程度の暴言で憤慨するような青臭い者はこの夢使いの村にはいない。ここは老人の村なのである。
少しづつでも美味しいものがあれば持ち寄るようにとみんなで相談しあって、老人達はそれぞれの家へ散った。元来、老人は人をもてなすのが好きなものである。相手が誰であろうと、もてなすとなったら浮き浮きしてくるのを止められない。歳を取ると何事にも薄れていく感動を、若い者は眩しい位に感じてくれる。自分ではとうに味わえなくなった悦びを若い者に与えることで共有出来るように思えるのであろう。
男は湯で絞った布を渡され、おざなりに体を拭いた。ズボンも返り血をたっぷり浴びていたが、着替えるより飯が先だと取り合わなかった。押し問答をしているうちにあちこちから食べ物が集まった。なんの打ち合わせも無かったが、御馳走が見つからなかった家からは秘蔵の食器が提出された。質素な生活をしていても、村人全員が持ち寄ると大層な御馳走になるものである。合わせると、ここが地の果ての村とは思えない食卓になった。
好奇心がまだ旺盛な女達が即席のくじを引き、代表に決まった女3人が鼻高々に盆を持ってキャリオットの前に揃えた。
「なんだ、これは。」
自信満々の村人にはキャリオットの不機嫌さが理解できなかった。キャリオットは手拭いを絞った手桶をひっくり返して女達に突き出した。
「とりあえず、これ一杯酒を汲んでこい!飯も手を抜くんじゃないぞ!俺は征服王キャリオットだ、ままごとみたいな器でちまちま飯が食えるか!」
女は慌てて飛んで帰り、まだ血なまぐさい臭いの残る手桶にワインをなみなみついで持ち帰った。
男は桶を受け取るとそれを一気に飲み干した。普通人なら混倒してしまう程の量を流し込んでもキャリオットは平然としていた。
村人達は再度額を突き合わせて相談した。この男が果たして何を求めているのか理論的に説明出来るものはいなかったが、素直に現象だけを追うと”質より量”と主張しているようにしか思えなかった。そこまでしたらいくらなんでも礼を失するのではないかと反対する者もいたが、麦がゆは飼葉桶に盛られた。それが村で一番大きい器だったのだ。
キャリオットはこれまた満足げに飼葉桶に顔を突っ込んで、塩味だけの麦がゆをむさぼるように食った。その食欲たるやまさに馬並みであった。その姿は老人達がとうに忘れた食べることの悦びそのものであった。村人達はその健啖ぶりをほれぼれと眺めた。
「なにをぼーっと見ている。おまえらもやらんのか。」
キャリオットは口の中に大量の飯を詰め込んだまま、戸口で見守る村人達に声を掛けた。
「飯は大人数で食った方がうまい。ほれ、そこらにうまそうなものがいくらもあるだろう。」
村人はますますキャリオットの性格がわからなくなった。征服王と大上段に切り出した男がこんなに気さくでいいのだろうか。この男は食卓に誘っておいて無理難題を吹っ掛ける魂胆なのではと勘ぐるのはむしろ当然と言えた。しかし、村人の何人かはキャリオットに触発されて何十年かぶりに蘇った食欲に抗い切れず、食卓についた。
「食え。」キャリオットは手を止めずに素っけなく指示した。目の前に並んでいるのは鮭の卵の塩漬け、砂糖菓子、珍しい果物といった普段は滅多に口に出来ないものばかりである。キャリオットはそういうものにはほとんど手をつけず、もっぱら穀物関係ばかりを食いあさっていた。
「これを、私達が頂いてよろしい訳で?」
「自分達の食い物を遠慮する奴があるか。」男は事もなげに言った。「ちまちました食い物は、食が細った年寄りが食うのが丁度いいんだ。」男は豪快に飼葉桶を抱えて食い続けている。
それからは水が流れるように事が運んでいった。キャリオットはテーブルに就いた老人達に一人ずつ名前を聞いた。その態度は相変わらずの大上段で横柄な口ぶりであったが、先程来の不機嫌さはなくなっていた。腹の中に納まるものが納まったのですっかり機嫌を良くしたらしい。
食卓を囲んだ老人達は恐る恐る料理に手をつけた。その様子を見てキャリオットはいらいらし、歳をとっても男は男、覚悟を決めたら堂々としろとどやしつけた。やり玉に上げられた老人は目を白黒させて驚き慌てた。その様子がおかしくてキャリオットは吹き出した。それに釣られて戸口から様子を伺っていた者の何人かが笑い、キャリオットはますます高笑いした。キャリオットは実に気持ちよく高らかに笑う。
笑いは伝染し、食卓は急に和やかな雰囲気になった。やじ馬からまた何人かが顔を出して、仲間に入ってもいいだろうかとお伺いを立てた。いいもなにも椅子はあまっている、足りなくなったらどこかから持ってこい、テーブルが足りなきゃどこかから持ってこい、それでも足りなきゃ青天上でやればいい、キャリオットは飼葉桶を抱えて立ち上がった。
「今日は祭りだ、征服王キャリオットが御当地にいらっしゃった記念の祭りだ。」
お調子者がはやしたてると、キャリオットはまたもや腹の底から高笑いした。やじ馬の壁は決壊した。村人はわらわらと部屋に入り、自分の入るスペースを確保しだした。ワインをなみなみとついだ手桶が村人の中を周り、集められた食料が見る間に空っぽになった。
男の何人かはすっかり出来上がって、女達に酒と料理の追加を命じた。状況に馴れたのは女も同じで、口々に不平をこぼし始めた。今一時で冬の食料を食いつぶしてしまう気か、もってこいと言われたってそんなに沢山重くてはこべやしない、あんた自分の足があるんなら自分で持ってくりゃいいだろうと。
言い争いを耳にしたキャリオットは話の間に割って入った。
「酒蔵に案内しろ俺が持ってくる」
女にがたがた言われているのは男が男の仕事をしとらんからだ馬鹿者と吠えて、老婆を引きずって行き、ワインの樽を二つ肩と脇に抱えて帰ってきた。
キャリオットは戦士にしては小柄な体つきであるが、胸から肩にかけての筋肉は見事であった。こけおどしの贅肉など全く無く、鋼の様に引き締まった実用的な体型を維持していた。一樽抱えるのに二人がかりの重量がある樽を支えた姿は芸術的と評せる程美しかった。
村人達はキャリオットの雄姿を称えて拍手喝采を送った。キャリオットは目に見えて有頂天になっていった。
「だいたいだな・・・」キャリオットは抱えてきた樽の一つに腰を下ろして演説をぶち始めた。
「男というのは偉いのだ。何故偉いかというと女より優れているからだ。だから男は自分より劣っている女を助ける義務と権利があるのだ、わかるか?男が偉いというのは男が女を護るから偉いのだ、女一人護れない男が偉い訳があるか。かくいう俺は征服王だ。王様だ。偉いのだ。貴様らの誰より偉いのだ。それは貴様らの誰より強いから貴様らの王足り得るのだ。だから俺は日夜修行の旅をしている。俺より強い奴がいるならばそいつの方が俺より偉いからそいつが王様なわけだが、俺は未だかつて俺より強い奴にお目にかかったためしが無い。だから今んところ俺が王様なわけだ、わかるな皆の衆。」
訳がわかったものはほとんどいなかったが、その口調は歯切れが良くて壮快であり、男達は”男が偉い”という一節が、女には”女を護る”と言う一節がなんとなく心地よかったので、口々に賞賛の声が上がった。
さらに気分を良くしたキャリオットは、樽に片足を掛けて立ち上がり、腰の剣帯に吊るされた長剣をすらりと抜いて構えた。
「みろ、これが俺の愛刀だ。」その剣はつい今しがた豚鬼を一刀両断に斬って捨てたとは思えぬ輝きを放っていた。
村で鍛冶屋をやっている老人が人垣の頭を越えて走りより、食いつくような視線で長剣を眺め回した。
「これはなんじゃ」
老人はため息混じりに呟いた。
「こんな剣、見たことが無いぞ。長剣のような格好はしておるがこりゃ全くの別もんじゃ。」
キャリオットはにやっと笑う。
「わかるか、老人。」
「ああ、わかるとも」老人は興奮していた。
「材料はただの鉄じゃないな、こんな滑らかな表に仕上げるには相当な打ち出しがいる。しかも歯は別の金属がはまっておる、凝った作りじゃ。こんな作り方をした剣は見たことが無い。何処で手に入れた、作ったのは誰じゃ。」
キャリオットはちっちと舌を鳴らして食いつきそうに身を乗り出す老人を制した。
「これは俺の親父の形見らしい、親父が何処で手に入れたかわからんが、物心ついた頃には俺のものになっていた。ま、つまり俺は親の顔すら知らんのだな。
だからこの剣は俺の親父そのものってわけだ。俺も長いこと旅をしているがこれと同じものは見たことが無い。
こいつをよーく見てみな、そう、この波紋のような紋様を、吸い込まれそうなくらい妖しいだろう。そこらのなまくら剣と一緒にしてもらっちゃ困るぜ。
俺にいわせりゃそこらの剣は金槌みたいなもんだ。力任せにひっぱたいて切り込むなんざ野蛮人の仕業よ。こいつはな、引いて斬るのさ。おまえさんの首なんか軽く引いただけですっぽり胴体と泣き別れだぜ。」
キャリオットは軽やかに剣を振り上げた。
「おおいやめてくれ、切れ味は先刻見せてもらったよ。」
キャリオットはまたもや高笑いを上げた。
「ところでこの剣、こんな見事なものなんだからさぞかし凄い名前があるんだろうね。」 観衆から声が掛かった。
「名前、名前か。そんなもの考えたこともなかったぞ。」
キャリオットから笑顔が消えた。真剣に考え込んでいる。同時に二つのことが考えられないタイプの男なのだ。考え込むと周りが見えなくなってしまう。しかも、考え事が得意なタイプでも無いらしい。
「コンクリエーター(征服王)。そうだ、それがいい。」
誰ともなく声が上がった。キャリオットは頭を上げた。
「よし、貰った!コンクリエーター。今日から貴様の名前はコンクリエーターだ!」
キャリオットは剣を高々と差しあげた。座は最高に盛り上がった。ムーンがこのらんちき騒ぎに現れたのは丁度その頃だった。