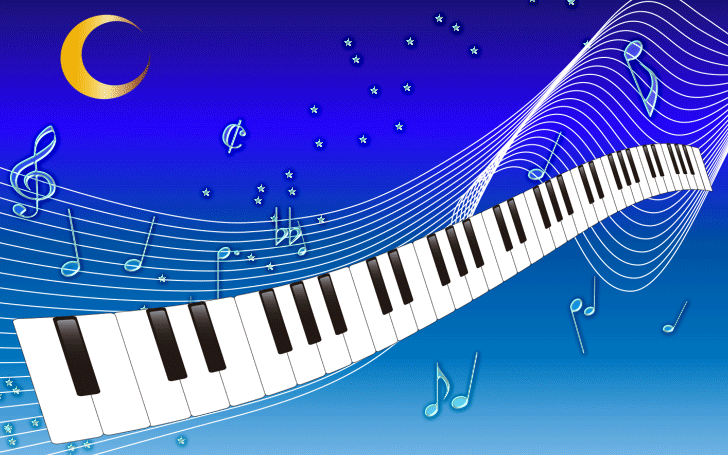仕事でパソコンを使っていて「タイピングがもっと早ければ仕事も早く終わるのになー」と思ったことはありませんか?
速く打とうと練習してみたけど、あまり速くならなかったという方も多いのではないでしょうか。
でも大丈夫!きっと今までは練習方法が間違っていただけです。
タイピングは正しい方法で練習すれば誰でも速くすることができますよ!
そこで今回は、イータイピング検定特級の私が考えた「タイピングを速くするための合理的な方法」をご紹介します。
ホームポジションを身につける
ホームポジションとは、タイピングを行う際に指を置く基本位置のことです。
まず左手人差し指を「F」に置き、そこから中指・薬指・小指をD,S,Aと置きます。
同様に右手の人差し指は「J」に置き、そこから中指・薬指・小指をK,L,;と置きます。
その状態から、各指を縦方向に動かしながら文字入力をしていくイメージですね。
(出典:ちびむずドリル小学生)
なぜホームポジションが大事かというと、タイピングを速くするためにもっとも重要なのが「指の記憶」だからです。
タイピングが速い人は、頭で考えながら指を動かしているわけではなく、指の記憶によって反射的に指を動かしています。
ピアノを弾く人がよく「指が覚えている」なんて言いますが、それと同じイメージですね。
指の記憶は「この単語を打つときはこの指をこう動かす」ということを繰り返していくうちに定着するのですが、ホームポジションをまもらずに毎回違う指で打っていては一向に指の記憶が定着しません。
また、手元を見ずにキー入力する「ブラインドタッチ」を習得する際にも必須となりますので、ホームポジションは必ず身につけましょう。
母音に特化して練習する
母音とは、日本語でいうと「アイウエオ=aiueo」の5音のことを指します。
日本語は「子音」+「母音」で成り立っていますので、日本語の文章をローマ字入力する際には約半分が母音ということになりますね。
(例.タイピング練習⇒Taipingurensyuu)
ですので、文章の半分を占めている母音の入力スピードを速くすれば、文章全体の入力スピードも速くなるということがいえます。
母音に特化した練習をする際には、下記のタイピング練習サイトで公開されている「50音タイピング」がオススメです。
特定の単語をひたすら練習する
タイピング練習をする際、いろいろな単語や長文を打って練習されている方が多いですが、そのような「浅く広く」練習する方法ではなかなかタイピングは速くなりません。
タイピング練習で大事なのは「狭く深く」。
すなわち、同じ単語や文章を何度も練習して指に覚えさせることなのです。
「その方法じゃ、練習した単語しか速く打てるようにならないんじゃないの?」と思うかもしれませんが、大丈夫です。
ひとつの単語を速く打てるようになると、似たようなスペルの単語も速く打てるようになってきます。
例.「練習:rensyuu」が速く打てるようになると
⇒編集:hensyuu
⇒先週:sensyuu
⇒演習:ensyuu
⇒連中:rentyuu
・・・なども速く打てるようになる。
さらに、速く打てる単語が増えてくると、それらを部分的に組み合わせた単語も速く打てるようになってきます。
例.「練習:rensyuu」と「大会:taikai」が速く打てるようになると
⇒回収:kaisyuu
⇒集会:syuukai
⇒大衆:taisyuu
⇒醜態:syuutai
・・・なども速く打てるようになる。
このように、速く打てる単語のバリエーションが増えていくことで、最終的にあらゆる文章の入力が速くなっていくのです。
ブラインドタッチをできるようにする
ブライドタッチとは、キーボードを見ずにタイピングを行う技術のことです。
タイピングを速くしたい方にとってブラインドタッチの習得は必須となります。
なぜかというと、キーボードを見ながら文字を入力する場合「タイピングスピードの限界=キーボードを目で追えるスピード」になってしまうからです。
当然、人間の目はそんなに早く動きませんから、タイピングもそれなりのスピードまでしか速くなりません。
ではどうすればブラインドタッチができるようになるのかというと、これもやはり「狭く深く」練習することが重要となります。
特定の単語をひたすら指に覚えさせ、ブラインドタッチで打てる単語を少しずつ増やしていきましょう。
すると、それらを部分的に組み合わせた単語や似たようなスペルの単語もブラインドタッチできるようになり、最終的にはあらゆる文章がブラインドタッチできるようなる・・・というわけです。
なおブラインドタッチができれば、常に画面を見ながらタイピングができるので入力ミスに気付きやすいというメリットもあります。