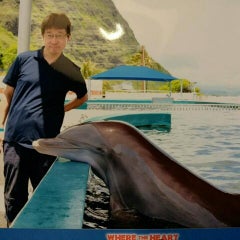江戸時代のキーワードを一つ問われたら、皆さんはなんと答えますか?自分は『鎖国』と答えます。この『鎖国』という政策ですが、良くも悪くもこの政策のお陰で日本独自の文化が発展したんじゃないかと思います。漢方医学も例外ではないと思います。
江戸時代に活躍した漢方家として私が直ぐに思い出せるのは原南陽(はらなんよう/乙字湯)、本間棗軒(ほんまそうけん/連珠飲)、華岡青州(はなおかせいしゅう/十味敗毒散)の三人です。
本間棗軒は漢方医学を原南陽から蘭方医学を華岡青州から学びました。なので原南陽と華岡青州は本間棗軒を通して知り合いだったかもしれませんね。
さて、この華岡青州は外科医として有名ですが、吉益南涯(よしますなんがい)に古方を学んだとのことで、十味敗毒散という漢方薬も創製しています。
これは明代の医書の「万病回春(まんびょうかいしゅん)」に収載されていた荊防敗毒散より[前胡]、[薄荷]、[連翹]、[枳実]、[金銀花]を除いて[桜皮]を加えたものです。選択のポイントの一つとしては患部に化膿を伴うかあるいは繰り返す場合に適応するようです。
構成生薬は、
茯苓4.0 桔梗3.5 柴胡3.5 川芎3.5
防風3.5 桜皮3.5 甘草2.0 荊芥2.0 独活2.0 生姜1.0です。
適応症状は、
①化膿性皮膚疾患、急性皮膚疾患の初期
②蕁麻疹、湿疹、にきび、水虫
本方は自分が前のお店に勤務していた時に一緒だった女性スタッフがにきびの治療薬として「清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)」が効かなくなったので十味敗毒湯に転方した(←恐らく証が変わったのでしょうね)という話を記憶していて、十味敗毒湯はにきびの治療薬として記憶の片隅にありました。
和漢薬方意辞典によれば、
◎廱瘡及び諸ぞう腫、初期増寒(憎寒?)壮熱、疼痛を治す。
◎炎症性疾患の初期、なお発赤・腫脹・疼痛・熱感等の熱証の存在する時期にもちいる。湿証の化膿の初期から中期にも用いられるが、進行して陰証に陥ったものには適応しない。
◎皮膚病には連翹を加える。散発性の小丘疹がポツポツとあり、先端が化膿する傾向のものに良い。便秘傾向があれは必ず大黄を加える。
◎小柴胡湯証で特に解毒・排膿作用を必要とするものに用い、体質改善にも有効である。必ずしも胸脇苦満を要しない。掌蹠膿疱症の70%に有効との報告がある。
◎清上防風湯・治頭瘡一方は本方より熱証が強い。
との記載がありました。
また私がいつも参照している漢方関連書籍では、『浅田宗伯(←同じく江戸時代の漢方家、浅田飴にその名を残しています)が[桜皮]を[樸樕]に代えた方剤が十味敗毒湯です。』という記述もあります。その本では本方を十味敗毒散として紹介しています。うちのお店にある、一般用漢方薬の十味敗毒湯(クラシエ薬品)は華岡青州の処方(つまり、十味敗毒散)に準拠しています。
調べたところ、[桜皮]を用いるのが「十味敗毒散/華岡青州」で[樸樕/浅田宗伯]を用いるのが「十味敗毒湯」みたいです。
江戸時代に活躍した漢方家として私が直ぐに思い出せるのは原南陽(はらなんよう/乙字湯)、本間棗軒(ほんまそうけん/連珠飲)、華岡青州(はなおかせいしゅう/十味敗毒散)の三人です。
本間棗軒は漢方医学を原南陽から蘭方医学を華岡青州から学びました。なので原南陽と華岡青州は本間棗軒を通して知り合いだったかもしれませんね。
さて、この華岡青州は外科医として有名ですが、吉益南涯(よしますなんがい)に古方を学んだとのことで、十味敗毒散という漢方薬も創製しています。
これは明代の医書の「万病回春(まんびょうかいしゅん)」に収載されていた荊防敗毒散より[前胡]、[薄荷]、[連翹]、[枳実]、[金銀花]を除いて[桜皮]を加えたものです。選択のポイントの一つとしては患部に化膿を伴うかあるいは繰り返す場合に適応するようです。
構成生薬は、
茯苓4.0 桔梗3.5 柴胡3.5 川芎3.5
防風3.5 桜皮3.5 甘草2.0 荊芥2.0 独活2.0 生姜1.0です。
適応症状は、
①化膿性皮膚疾患、急性皮膚疾患の初期
②蕁麻疹、湿疹、にきび、水虫
本方は自分が前のお店に勤務していた時に一緒だった女性スタッフがにきびの治療薬として「清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)」が効かなくなったので十味敗毒湯に転方した(←恐らく証が変わったのでしょうね)という話を記憶していて、十味敗毒湯はにきびの治療薬として記憶の片隅にありました。
和漢薬方意辞典によれば、
◎廱瘡及び諸ぞう腫、初期増寒(憎寒?)壮熱、疼痛を治す。
◎炎症性疾患の初期、なお発赤・腫脹・疼痛・熱感等の熱証の存在する時期にもちいる。湿証の化膿の初期から中期にも用いられるが、進行して陰証に陥ったものには適応しない。
◎皮膚病には連翹を加える。散発性の小丘疹がポツポツとあり、先端が化膿する傾向のものに良い。便秘傾向があれは必ず大黄を加える。
◎小柴胡湯証で特に解毒・排膿作用を必要とするものに用い、体質改善にも有効である。必ずしも胸脇苦満を要しない。掌蹠膿疱症の70%に有効との報告がある。
◎清上防風湯・治頭瘡一方は本方より熱証が強い。
との記載がありました。
また私がいつも参照している漢方関連書籍では、『浅田宗伯(←同じく江戸時代の漢方家、浅田飴にその名を残しています)が[桜皮]を[樸樕]に代えた方剤が十味敗毒湯です。』という記述もあります。その本では本方を十味敗毒散として紹介しています。うちのお店にある、一般用漢方薬の十味敗毒湯(クラシエ薬品)は華岡青州の処方(つまり、十味敗毒散)に準拠しています。
調べたところ、[桜皮]を用いるのが「十味敗毒散/華岡青州」で[樸樕/浅田宗伯]を用いるのが「十味敗毒湯」みたいです。
AD