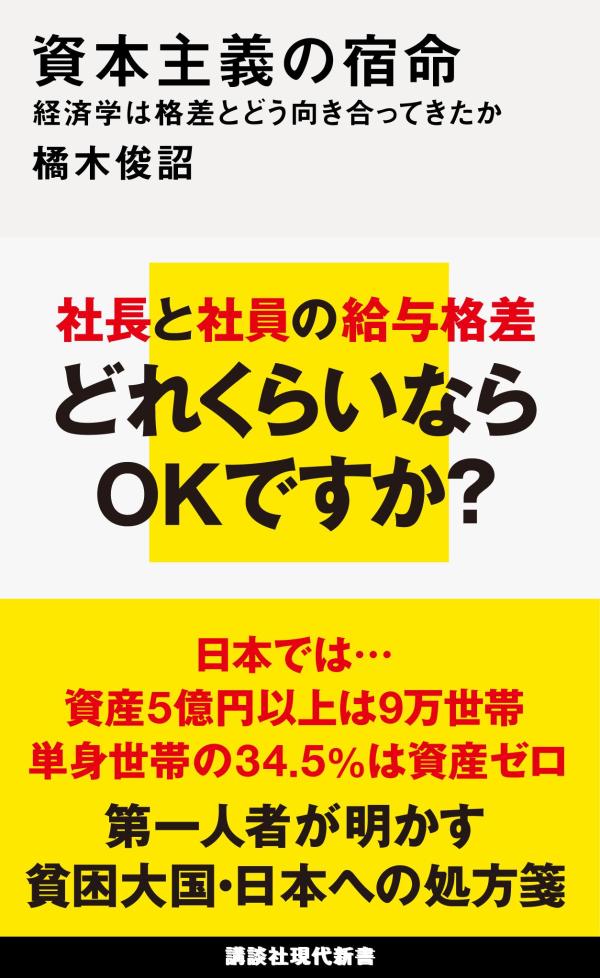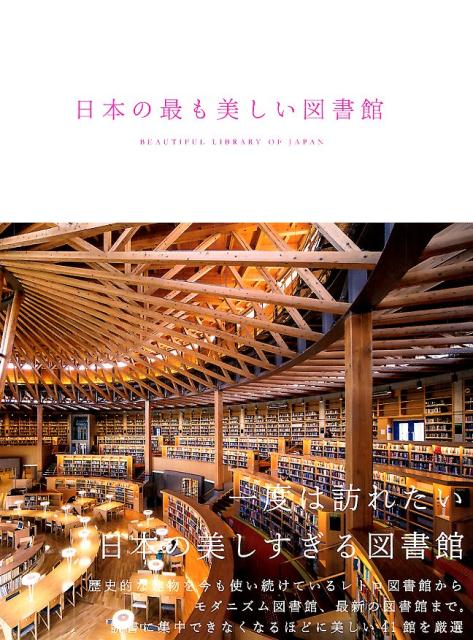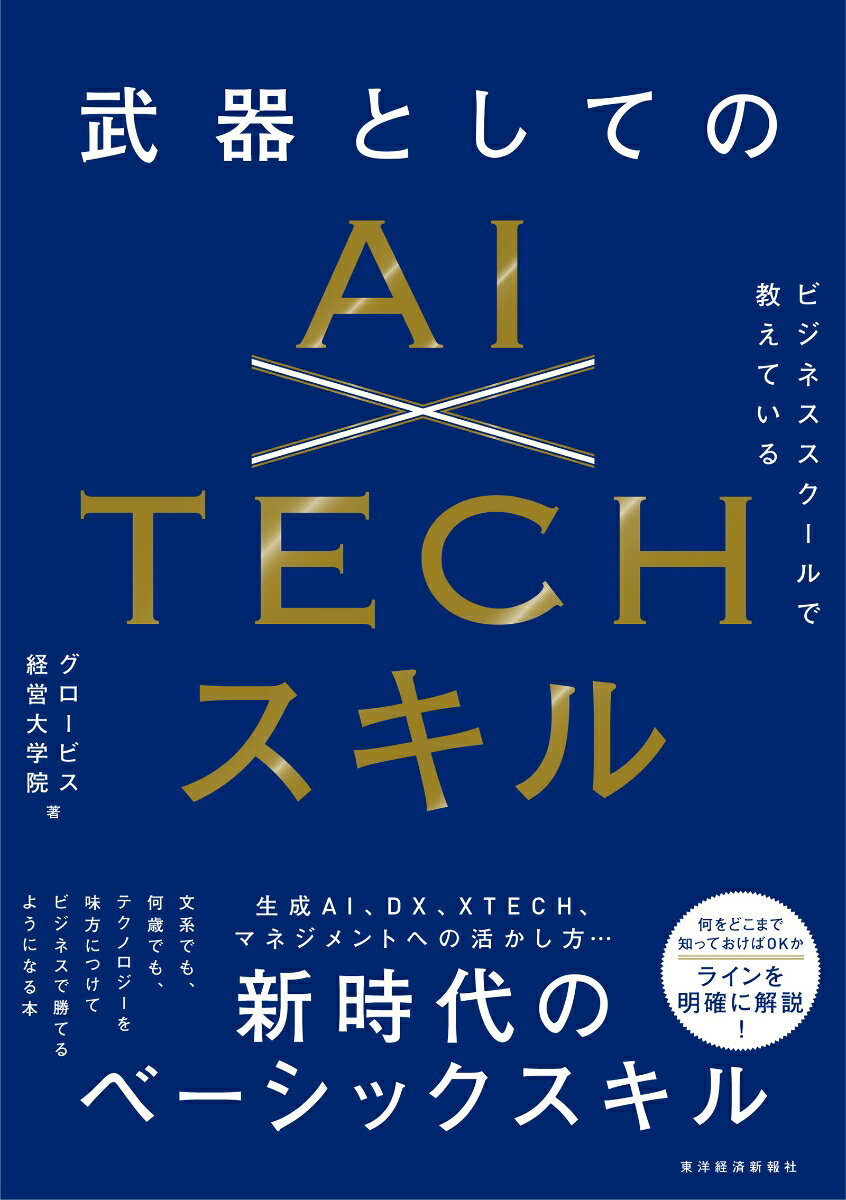マインドフルネス系の本に近いのですが、グロービスの先生が書かれたとのことで興味深く、手に取りました。
セルフコンパッションの説明は下記の通り。
セルフコンパッション(self-compassion)とは、自己に対して思いやりや優しさを持つ態度を指します。困難な状況や失敗に直面したときに、自己批判ではなく、自分をいたわり、理解しようとする姿勢を大切にすることです。セルフコンパッションには以下の3つの要素が含まれます。
1. 自分への優しさ(Self-Kindness):失敗や過ちに直面したとき、自分を厳しく批判するのではなく、温かく受け入れること。
2. 共通の人間性(Common Humanity):自分の苦しみや困難は、他人も経験するものであり、誰もが完璧でないことを理解すること。
3. マインドフルネス(Mindfulness):自分の感情や苦しみをありのままに観察し、否定するのではなく、その感情を受け入れること。
セルフコンパッションを高めることで、ストレスや不安の軽減、精神的なレジリエンスの向上などの効果が期待できます。