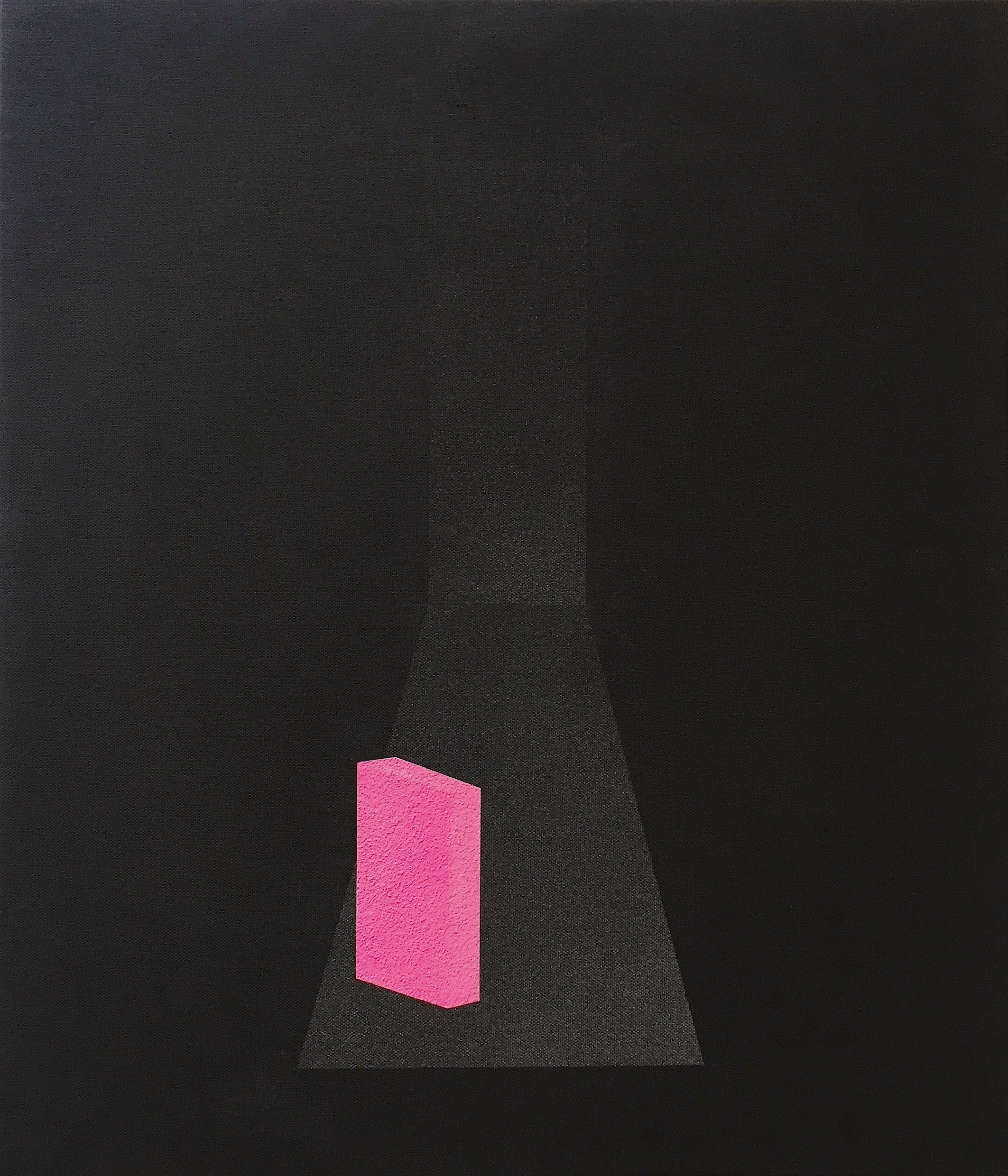小動物とエクリ
note ⇄ memo
最新の記事
カレンダー
プロフィール
2025-04-17 01:46:41
ペラッペラの単なる人間管理?
テーマ:note ⇄ memo
はじめにーー目的に抗する〈自由〉
自由は目的に抵抗する。自由は目的を拒み、目的を逃れ、目的を超える。人間が自由であるための重要な要素の一つは、人間が目的に縛られないことであり、目的に抗するところにこそ人間の自由がある。
私たちは目的なる語なしで何かを考えることができなくなっている。
第一部 哲学の役割ーーコロナ危機と民主主義
「生存以外にいかなる価値をもたない社会とはいったい何なのか?」(ジョルジョ・アガンベン『私たちはどこにいるのか?ーー政治としてのエピデミック』
自分で問いを立てる
哲学というものを勉強すると、世の中に溢れている紋切り型の考え方から距離を取れるーー僕はそんな風に考えています。
世の中には或る問題、論点についてのパターン化された答えが溢れかえっています。
あらかじめ用意されたテンプレに身を置かざるを得ないのは、自分なりにその事柄について問いを立てる営みが省かれているからです。
だから先ほど述べた、すごく遠くにある関心事というのは、研究においても大切だと思います。
ものすごく遠くにあるボンヤリした関心事とものすごく近くにある課題を大切にする。その間のことはなかなか思うようにはならないと分かっておく。
アガンベンはコロナ危機において「例外状態」が人々によって進んで受け入れられつつあることに危機感を抱いたわけです。
言い換えれば、テロリズムが我々の自由を脅かしているのだから、自由を守るために、我々は自分たちの自由が制限される緊急事態を受け入れねばならない、と。
このような論法に対するアガンベンの問題提起さ極めてシンプルです。自由を守るために自由を制限しなければならないーーそんな矛盾が受け入れられるだろうか、というものです。
そもそもそうやって制限された自由は、結局、元に戻らないのではないか。
アガンベンによれば、この「伝染病の発明」は権利制限を拡張する理想的な口実を提供しています。
それは我々が緊急事態において生きることに慣れてしまっているということに他なりません。
我々が意見を交わし合うことの重要性はどれだけ強調しても強調しすぎることはありません。
けれども、意見が飛び交う中で、実は忘れられている営みがあるのではないか。それは問うことであり、考えることです。意見を述べることと、問うたり考えたりすることは別です。
意見を表明すると、それに対する強い賛成と強い反対が集まりやすいので、そこから更にその事柄について考えるのが難しくなってしまうのです。
意見を述べるにとどまって問うことがなされないならば、我々は倫理と政治について考えるべきであった何かについて考えずにすませることになってしまうのではないでしょうか。
三つの論点(1)ーー生存のみに価値を置く社会
誰もいつまで続くか分からないこのような生き方に慣れてしまった国で、人間の関係はどうなってしまうのだろうか?そして生存以外にいかなる価値ももたない社会とはいったい何なのか?
アガンベンは人間が生きるということと、人間がただ生存しているということを区別しているのです。その上で、ただ生存するということを何よりも最優先するのならば、人間が生きていると言えるために必要な何かが蔑ろにされはしないかと指摘しているのです。
「剥き出しの生ーー剥き出しの生を失うことへの恐怖ーーは人間たちを結びつけるものではない。人間たちの目を見えなくさせ、彼らを互いに分離するものである」
我々は「剥き出しの生」のみを価値として認めるに至っており、その結果、それを失うことを恐怖しているというわけです。
三つの論点(2)ーー死者の権利
先の引用文では、死者が葬儀の権利をもたないと指摘されています。
権利は決して生きている者だけが欲することのできる権利ではない、と。
隣人愛の思想が踏みにじられつつあるという感触がアガンベンにはある。
これはある種の保守主義的な態度表明と言って良いでしょう。
保守主義
つまりここに垣間見られる思想の背後には、ただ単に生存していること、生命として存続していることよりも価値のあるものの存在が想定されているのです。
敢えて言うならば、それは人間が人間として歴史の中で培ってきた文化であり、たとえば宗教などはその表現の一つであると言えるでしょう。
教会こそは、単なる生存には還元できない、人間が人間として歴史の中で培ってきた文化の価値の守り手ではなかったのか、というわけです。
これまでに人間が築きあげてきた価値への敬意なくして政治など可能でしょうか。そこに残るのは、「今」しかない、ペラッペラの単なる人間管理だけではないでしょうか。まさしく、「倫理的そして政治的な諸々の帰結について問うこと」が求められていると言わねばなりません。
考えることの危機と哲学すること
ものを考えるということはしばしば危険と隣り合わせであり、もしかしたら、何事かを考えていると言えるのは、考えることの危険に向き合った時であるとすら言えるかもしれません。
社会の虻としてーー哲学者の役割
虻は嫌われます。アガンベンも世界中の研究者に嫌われました。
三つの論点(3)ーー移動の自由の制限
自由とは移動の自由に他なりません。
支配の条件
自由に移動ができる限り、暴力だけで相手を支配することはできないのです。
ルソーの自然状態論
もし私が或る場所で苦しめられるなら、ほかの場所へ移るのをだれが妨げるだろうか。(ルソー『人間不平等起源論』
つまり、自然状態では支配の関係が成立しない。
所有関係が移動を様々な意味で妨げることがあるのかもしれない。だとしても、移動の自由か支配と服従から逃れる可能性の根本であることに変わりはありません。
日本国憲法における移動の自由
大雑把なことを言うならば、先にも指摘した通り、移動の自由の制限こそが人間にとって最も苦しい罰になることに、社会がだんだんと気づいていったということなのかもしれません。
殉教者と教会の役割
「身体的な生の経験と精神的な生の経験はつねに、互いに分離できないしたかで一つにまとまっていたが、私たちはそれを、一方の純粋に生物学的な実体と、他方の情感的・文化的な生とに分割してしまった」
アガンベンはそこで前提とされている「純粋に生物学的な実体」へと人間の生が還元されることを断固として拒否しているわけです。
改めて三権分立について
権力は権力によってのみ阻止され、しかも同時に侵害されずにすむという考えがあるというのです。(アレント『革命について』)
たとえば、行政権が行きすぎてしまった時、立法権や司法権によって、それを阻止することが可能である。
三つの権力の均衡によるチェック・アンド・バランスこそが、各権力の横暴の阻止と、その健全な行使に資する。
現在は行政権が非常に強くなっている時代です。コロナ危機でそれはより顕著となりました。アガンベンはそのことに危機感を抱いています。
第二部 不要不急と民主主義ーー目的、手段、遊び
「目的とはまさに手段を正当化するもののことであり、それが目的の定義にほかならない」
(ハンナ・アレント『人間の条件』)
必要と目的
必要と言われるものは何かのために必要なのであって、必要が言われる時には常に目的が想定されている。目的とは、それの「ために」と言い得る何かを指している。必要であるものは何かのために必要であるのだから、その意味で、必要の概念は目的の概念と切り離せません。
消費と浪費
贅沢を享受することを「浪費」と呼ぶならば、人間はまさしく浪費を通じて、豊かさを感じ、充実感を得てきたのです。
遊びについて
遊びは目的に従属する行為、哲学的な用語で硬く言えば、合目的な活動から逃れるものに他なりません。そして、合目的性を逃れることは少しも不真面目であることを意味しません。遊びは真剣に行われるものであるし、ゆとりとしての遊びは活動がうまく行われるために欠かせないものです。
政治と行政管理
逆説的な言い方をすれば、必要を超え出て、目的からはみ出す活動は、目的に奉仕する限りで、目的に抵触しない限りで認められる。
遊びとしての政治とプラトン
それは不真面目に振る舞うということではなくて、そうやって遊びを楽しむことこそが「真剣な事柄」であるというのです。
たとえば、戦争に関することは真剣な仕事であり、それは平和のために、うまくなされなければならないと考えられています。しかし事実は、戦争のうちには真の意味の遊び(パイディアー)も、わたしたちにとって言うに足るだけの人間形成(パイディアー)も現に含まれてもいませんし、将来もないでしょう。しかし、わたしたちの主張からすれば、この人間形成こそ、わたしたちにとってもっとも真剣なことなのです。ですから、各人は、平和な生活をできるだけ長く、できるだけ善く過ごさなければならないのです。では、正しい生き方とは何でしょうか。ひとは一種の遊びを楽しみながら、つまり、犠牲を捧げたり歌ったり踊ったりしながら、生を過ごすべきではないでしょうか。そうすれば、神の加護をわが身にうけることができますし、敵を防ぎ、戦っては勝利を収めることができるのです(プラトン「法律」森進一他訳、岩波文庫、下巻、一九九三年、五七~五八ページ[803DIE])。
人間形成こそが僕らにとって最も真剣なことである。ところが、戦争には少しもその真剣なことがない。つまりプラトンは遊びと真剣を分けるのではなくて、真剣に遊ぶことの重要性を説いている。
ここで語られているのは市民の義務としての戦争参加であり、つまり市民の政治的義務が問題にされていると考えておいてください。
遊びはここで、手段と目的の関係を無効化するものとして捉えられていることになります。
プラトンは心底真面目に「遊びにあふれた政治」を考えたのだとアガンベンは力説しています。
社会運動が楽しくてはダメなのか
目的に縛られてしまうこともある。けれども、運動に携わりながら、自由を感じることが間違いなくあったのだと思います。
目的合理性だけにとらわれ、遊びを全く失った社会運動のようなものがあったら、それは恐ろしいものではないでしょうか。それはあらゆる手段とあらゆる犠牲を正当化する運動に他なりません。
現在の言論環境の圧力に負けて、その区別に対して見て見ぬふりをするようなことがあってはならないと思います。
運動に携わる中に自分にとっての自由の経験があったことは確かであり、それはささやかな政治参加ではありましたが、とても大切で貴重な経験でした。
問題は、あらゆるものが目的合理性に還元されてしまう事態に警戒することです。
人間が自由に行為すれば、そこには同意や共感だけでなく、不同意や反感も生まれるでしょう。そうすれば対話や調整が必要になります。
その活動は単に奉仕する活動ではないがゆえに、目的のための犠牲を正当化しない活動です。言い換えれば、目的から自由である活動を忘れた時、人間は目的のためにあらゆる手段とあらゆる犠牲とを正当化するようになります。
目的のために手段や犠牲を正当化するという論理から離れることができる限りで、人間は自由である。
【質疑応答】
1 コロナ危機と自由の関係について
他者の身体というのは抑止力をもつ。僕が重いと言ったのも、この抑止力のことではないかと思います。だから遠慮もあるし、気遣いもある。
1 責任について
真剣な遊びとしての政治は、それこそ、目的を理由にして責任逃れをすることのない政治です。
『目的への抵抗』より引用、抜粋。
2025-04-10 23:52:32
自分の連続性や同一性に回収できない事柄
テーマ:note ⇄ memo
◾️脳梗塞以前と以後
「私」が〈こんなことが自分の身体やその周囲に起きている〉と知覚、認識したとしても、その認識はきっと間違っているはずだ、と思わざるをえなかった。
むずかしいのは経験をした自分が同じ自分として連続しているという確信が持てないからだと思うのです。この期間の時間かまったく別の時間として感じられる。時間が飛んでしまっている。
とは、以前の自分の意識を復元し、つまり再び仮構して、それに心身を適合させるということかもしれませんが、するとこの期間(まだまだ続いているのですが)に起こった決定的な体験を覆い隠してしまうような感じがします。
端的に怖い。山本さんの質問に答えるとすれば、変容というか、いちばんの違いは、脳梗塞の前と後ではもはや同じ「私」ではありえない、同じ「私」であると感じるのはそれ自体が錯誤なのではないか、間違っている、いや、いけないことなのではないか?そんな感覚的な抵抗があります。
■何かが手に絵を描かせた
ところが気の持ちようで、どんな小さなことでもできるようになると奇跡のように嬉しく感じるともいえるのです。
工夫すれば何か道が見つかるだろう、絵具がなくてもケチャップをこぼすだけでも絵は描ける。
いままで脳が「自分の」と思い込んでいた身体をいかに間違って歪曲して認識していたかをはっきり悟らされます。リハビリで教わったのはこのことでした。身体の諸部分は連携していて、その身体諸部分の連携した動きは、脳との回路が切断あるいは弱くなっても、身体にプログラムされて回路として残されている。いわば身体が覚えている。
身体はいわばメディウムです。それがもっている特性、プログラムを知って、それを脳に改めて回路として実装しなければならない。
意識が離れている、自分で自分についていけない。
おそらく脳を含めて身体が自発的に活動を生成させていくのを、意識が追いかけて観察しながら、後付けでそのプロセスを自分がやったと、自分が指令したと理解している。つまり後付けで自分の指令を組み立てている。自分がやった、作ったという感覚は遅れてくる。そのズレが強烈に感じられるんですね。しかし入院しているうちに、いままでもそうだったんじゃないか、という感じもしてきました。創作という行為にはこういう認識の遅れがあるものですから。だから、文章を書こうと、絵を描こうと、自分がつくったかどうかという感覚はあんまり関係がなくなってしまった。描くたびに自分の体が描き上げた絵に驚いている。
いずれにせよ病気になると身体が自分のものでない感覚は強くなりますよね。
たとえば「コリント人への手紙」に従えば、自分の身体は自分のものではない。身体は主によって与えられた、いわば住まい、神の宮、神殿であって、そしてそれを歩かせ話させ動かすのは自分ではない、宮にもともとすまう精霊だというわけです。与えられた神殿をつねに浄らかにし、精霊の働きを持つ。やがて起こるその働きを認め、自分の意志としてそれに従っていく。
自分がこれを作ったんだ、というその自分が来る前に、すでに行為が先行している。そのとき自分はまだいなかったんだから、それを自分がやったと言えるとしたら、それを位置づける主体が一緒に、いや後から遅れて生成してきた、からであって、その順番をひっくり返し、後からきたはずの自分がやった、俺がつくった、みたいに言うのは、相当ずるくないか?と感じますね。漁夫の利みたいですね。
そうですね。主体は最初からそこにいたかのように振る舞って、いいとこ取りをしているわけですからね。
いいとこ取りをしておいて、後から「これは僕がやったんだ、すごいでしょう」と得意顔で言うようなものですね。でも大切なのは、誰がではなく、それができたということでしょう。
■「エコロジー」から考える
現実には、自分の意識だけでなく、無意識や自分で必ずしも統御できない身体、さらには身体を通じて外部から入ってくる各種の知覚や変化が混然一体となって、文章なり絵画なりが生成されているはずです。でも、環境が私を通してさせているとも言えるような、思考や行動が生成されるそうした過程をうまく記述する言葉や論理を私たちはまだ持っていないのかもしれない。そこで、「誰々がつくった」とか「私が書いた」とつい言ってしまう。近代の作者という見方や著作権をめぐる法体系はそのような思考法に基づいてできていることもあり、ともすると私たちはなかなかその枠組みの外にあるような思考をしにくい。
「エコロジー」という言葉をつくった生物学者のエルンスト・ヘッケルは、ある生き物が周りにあるあらゆるものとどんな関係を結んでいるのか、その総体を見ましょう、そうしなければ、この生き物に何ができて、何ができないのか、どのように生きているのかを把握できない、と考えて、その関係の総体を考える「エコロジー」(ヘッケルが示したドイツ語ではOccologic)という学問を提唱しました。この原義を踏まえて言うと、人間の思考や行動が生成される過程を人間の意識や主体と呼ばれるものを中心に考えるのではなく、周囲の環境と人間が織りなす関係の総体から考えようとする、というわけです。これが「エコロジカル」な見方というときの含意でした。
岡崎さんの心と身体の連携が失われ、それがリハビリによって再構築されていく過程で生じた「勝手に手が描いた」という感覚は、「エコロジカル」な認識に通じているのではないかと思うのですね。
■「自然」や「霊」の正体
そこで、一見話が飛ぶようですが、岡﨑さんが四月に催されたトークイベントで語っていらしたヒルマ・アフ・クリントについてお話しいただけないでしょうか。クリントは「勝手に手が描く」ことを方法にまで高め、それによって画期的な抽象絵画を制作したと言えるからです。
クレーは自然そのものを再現するのではなくて、自然そのものが作品をつくりだすと考えることができた人です。だから彼らは自分の仕事を個人表現とは思っていない。自分たちはむしろ媒介で、自然の原理が力を発揮して何かをつくるときの媒介に自分がなっているんだと考えていた」と語っておいででした。
また、これはもとの文脈を確認していないのですが、クリントが四人の女性画家と結成した「ファイブ」というグループのメンバーと行っていた降霊術で、霊がこう告げたというのですね。
「知というものは、感覚でもなければ、知性でもなく、感情でもない。それは自分という存在のいちばん深いところにあるものだ。つまり、自分の霊という知である」と。この「金」を探求する思想や運動は、当時「スピリチュアリズム」と呼ばれていました。「霊」とか「スピリチュアリズム」と言えば、オカルトと言われるわけですが、岡﨑さんはト1クイベントでスピリチュア
それがリハビリによって再構築されていく過程で生じた「勝手に手が描いた」という感覚は、「エコロジカル」な認識に通じているのではないかと思うのですね。
■「自然」や「霊」の正体
そこで、一見話が飛ぶようですが、岡﨑さんが四月に催されたトークイベントで語っていらしたヒルマ・アフ・クリントについてお話しいただけないでしょうか。クリントは「勝手に手が描く」ことを方法にまで高め、それによって画期的な抽象絵画を制作したと言えるからです。
彼女は、自然科学に強い関心を抱く一方、ヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキーやルドルフ・シュタイナーの神智学に傾倒し、降霊会にも参加したりしながら抽象絵画の制作に向かっていきます。
「クリントやモンドリアン、クレーは自然そのものを再現するのではなくて、自然そのものが作品をつくりだすと考えることができた人です。だから彼らは自分の仕事を個人表現とは思っていない。自分たちはむしろ媒介で、自然の原理が力を発揮して何かをつくるときの媒介に自分がなっているんだと考えていた」と語っておいででした。
「知というものは、感覚でもなければ、知性でもなく、感情でもない。それは自分という存在のいちばん深いところにあるものだ。つまり、自分の霊という知である」と。この「霊」を探求する思想や運動は、当時「スピリチュアリズム」と呼ばれていました。「霊」とか「スピリチュアリズム」と言えば、オカルトと言われるわけですが、岡﨑さんはトークイベントでスピリチュアリズムは「(当時の)新しい科学と矛盾するものではなかった」とおっしゃっていましたね。そして「科学とスピリチュアリズムの共通項は、誰かが何かを考える、主体的に考える、という精神のはたらきが世界と対立してあって、その精神が主観的に考えることと客観的な世界が分離するという考え方が両方ともにない、ということです」とも。
つまり、クリントをはじめとするいち早く抽象絵画を制作しはじめた芸術家たちは、自分たちを「媒介」として作品をつくりだす「自然」や「霊」の正体に、言ってみれば科学的に辿りつこうとしていた。あるいは、それらを自分に「降ろして」芸術を生み出そうとしていた。
「エコロジカル」なものの見方で視野に入れたいのも、ここで「自然」や「霊」と呼ばれるものかもしれません。ある人がこれまで身を置いた環境のなかで経験してきたことのすべて、他者と取り結んできた関係や経験の総体が何かその人にしかないものとして蓄積していて、それらの関係の網の目のようなものが、その人の心身に痕跡として宿っている。
そこから私たちは何か「霊感」とも呼ばれるきっかけを得て、絵を描いたり、文章を書いたり、発言や行動をしたりしている。そんなふうに見ています。
■ペルフェッティのリハビリ理論
彼が提唱し実践してきた認知運動療法と呼ばれるものは、まさに人間の身体行為はそれをとりまく環境、事物とのネットワークとして成立している、と考える理論でした。
身体運動とは、同じ身体部位が、そのつど他のさまざまな身体部位と必ず連動して、特定の機能、働きをもった行為を生み出している。この働きは身体だけで完結しているわけでなく、さまざまな道具、事物、環境との応答、関係によってそのつど、固有な運動回路を作り出している。
つまりそれぞれの身体部位はその都度、別の働きに連動し、そのとき脳も異なる運動イメージ、形状イメージに結びつけて、その同じ身体部位を捉えている。生成変化する可塑性、多義性を持っている。いわば、環境との関わり、機能、働きによって、そのつど別の連動=身体のネットワークが組織され、身体イメージ=意味も可変的に組織されていく。それに応じて脳自体も同じように無数のネットワーク、回路の重なりとして組織されているというわけですね。
その部位の運動はもともと複数のネットワークとそのつど協働していたわけで、その損傷した箇所を含む多層的なネットワークの全体はまだ残っている。だから損傷を補って、ネットワークを再建させることはできる。こうしたネットワークと離れて個別の運動を考えることは抽象化された理念にすぎないときっとペルフェッティは言ったでしょう。
その統合された運動イメージを脳がはっきり持っていて、身体が受け取ってくる情報を収集し編成している。その過程を再編成することがリハビリでいちばん肝要だとペルフェッティは考える。
◾️神殿としての身体
その運動が「目的」をもって運動しているとするための、あるいは目的に沿っていると受け止める「意志」が発生してはじめて、その運動は自分がしていると理解できる。その動いている身体は自分のものだと把握できる。認知科学で運動主体感(sense of agency)、あるいは身体所有感(sence of ownership)と呼ばれている問題ですね。それが生成するにはネットワークというよりは、もう少し強い規範性をもったorderというか、特定の状態を要請する命令あるいは命令によって発生した秩序である、とみなされる場面が不可避になりますね。
その現れている違いを受け入れなければならない。それを受け入れ、偶然ではなく必然としていく能動性が生じないと行動ははじまらない。その能動性は、たとえば雨であるという、もしかしたら忌避したい現実をたんに否定するのではなく、受け入れ、超えていく、つまり反対に、いままでの主体、たとえば晴れにしか向いていなかった主体のあり方を修正し、作り替えていく能力、決断を含んだ能動性ですね。するとこの改変はいままでの自分の単なる延長ではできないわけですからなんらかの力がいままでの主体にとっては未知であった他から働いているとみなされなければならない。それを仮に精霊の働きと呼んでもいいでしょう。それは身体にもともと(まさにネットワークとして)あったけれど、ただ認めていなかったのか、外から到来したのか、は決定する必要はない。いままでは自覚されなかった、発現していなかったということです。ネットワークなら身体の内と外はつながっているはずですから。大事なのはその自覚が新たな意志として、そしてその意志を備えた主体として生成する、ということでしょう。それが生成しなければならない。病になって、いままで自分が持っていたと思い込んでいた身体のイメージは間違っていた。身体を自分のものとして使用していた、指令=命令が否定され、切断されたわけですけれど、◎リハビリというのはこのいままでの、自分と思い込んでいた身体像(イメージ)、そして思い込みに支配されていた主体自体を新しく再建しないとなりたたない。先ほどもいいましたが福音書では「神殿」という語に特別な意味が担わされているように思えます。
神殿が身体だとすれば、たしかに身体は外部の世界、環境と交流、交通し、さまざまな物質、情報が集まる場になっていた。そしてそこで交換される言葉やあるいは貨幣というモノが観念として、往々にして、この場の使用を支配し、占拠してしまってもいた。この支配をいちど打ち払う必要がある。
自分たちの身体も同じく媒体として与えられた神殿として考えていいのではないか?そこを支配していた古い、社会に適応していた主体が無効になったとき、再び、その場が言葉を語りはじめ、活動をはじめる。それが精霊の働きだと。その働きを認める新しい「私という主体」は遅れてやってくる。つまり、この身体は自分のものではない、預かっているだけである、そしてこの身体のリハビリは自分のために行なっているのではない、という発想は、ずいぶん気持ちを楽にしてくれました。精霊は身体を動かし、私はそれを私に先立つ「私」の意志として受け入れ、認める、自分のものとしてインストールする。つまり「私」自身があらたにインストールされる。
■ヒルマ・アフ・クリントの転回
自身の作品群を精細に記録し整理していたパウル・クレー(クリントより一七歳年下です)をはるかに凌ぎます。つまりクリントは自分の仕事を普遍的かつ客観的な研究成果として扱っている。
発表を控えたのは、その仕事が当時の社会に理解されうるとは考えず、また当時の社会で認知されたいとも望んでいなかったからでしょう。
世俗的な枠内での評価を得ることは彼女の仕事の普遍性を歪め、世間の評価の水準に合わせること、妥協することを意味していた。だからクリントは彼女が獲得していた地位を捨てることも服わなかった。比べればシュタイナーは啓蒙家であって、世間の水準に合わせて階梯をつくって徐々にそれを上げていくことを考えていた。彼はその戦略で世間の人気をいわば獲得した。これがシュタイナーがクリントに世間に発表するのはまだ早いと助言した理由でしょう。
けれどクリントはその世俗的な枠内での評価を超えたところで普遍性を持つと確信していた。残された膨大な数の彼女のノートをみると彼女の探求の深さは驚くべきものですが、下地には自然科学の深い知識と洞察があったことがわかります。ところで一八世紀後半以降、芸術と自然科学を結ぶ出発点となっていたのはゲーテの仕事でした。ゲーテの仕事を通過していたか、いないかはその後の芸術を理解する上で大きな違いです。ゲーテは自然の変化生成、そのつど特殊な形態として現れる現象の多様性、つねに同一には現れない特殊を構造として把握しました。同じく、それまで主観的現象として扱われていた個々人の知覚作用を客観的構造として基礎づけた。ゲーテによって、内的現象=経験の通約不能な特殊、そして一回性として現れる外的現象の特殊が、方法的に普遍として結びついたわけです。
二つめは構造的に理解されたとたんに、知覚されえない世界、つまり聴こえない、見えない世界の広がり、可能な世界の実在性に気付かされることになる。それを一つめに折り返せば、生成変化しつづけ静止した像をもたない世界を可能にしている原理、力こそを捉えることに当然、関心は移行します。
クリントの仕事はこうしたゲーテ以来の思考の流れでみれば王道であり、クレーの仕事もそれに連なります。一方、私たちの知覚条件を変えれば、まったく異なった世界像が現れることは客観的事実として顕微鏡や望遠鏡、高速度で移動する機関車、写真、レントゲンなどなどの装置によって、あるいは阿片などの薬物によって、すでに広く経験されはじめていました。
自然科学におけるパラダイムシフトは一九世紀末には広く浸透していましたが、芸術表現にはその転換はすぐには落とし込められていなかった。『抽象の力』でとりあげたように、抽象表現が現れたのはこの転換に応答していたとおおよそは見てもいいでしょうが、本質的にその核心を理解し徹底して探求できたのは傑出してヒルマ・アフ・クリントしかいない、と僕は考えています。クリントに先行し、彼女が参照したとみられる芸術作品があまり見出せないことが彼女の仕事を唐突かつ突出したものと感じさせますが、クリントの自然科学への深い知識、理解がそれを助けたのは確かです。それを知っていれば彼女の仕事が現れるのは決して唐突ではない。問題はこの認識上の転換は、社会的に制度化された、芸術表現の枠組みには位置づけにくい性格をもっていたことにあった。
◾️スピリチュアリズムと科学
クリントの転回で大事なのはクリントが視覚的なイメージを対象として写して描くのではなく、形象が生成するプロセス、そのとき働く力自体を、描くというプロセスで把捉しようとしたことだと思えます。描くという行為自体が、自然界で形象が生成するプロセスそのものを準えていて、それを体現している。彼女がこうした仕事に没頭しはじめた時期、クリントの母親が視覚を失い、クリントは盲目となった母親の介護のために王立美術院の自分のスタジオから離れることになったとも言われています。こうした経験も彼女の転回に影響を与えたのかもしれません。いずれにせよ絵を描くことは、視覚的イメージを対象として描くのではない、形象を生成させる力それじたいを、描くプロセスとして体現、実践することになった。そのとき形象を生成させる力はもはや画家個人の主体に属すものではありえません。自然力じたいが描く行為のなかに移し替えられている、と感じられるはずです。自然界で形象が生まれることと絵を描くことは同じ力に沿った出来事になった。このプロセスにおいて、表現主体としての画家が対象=主題を選び、それを表現するというモデルは捨て去られなくてはならない。シアンセ(降霊会)への参加はこの自然科学におけるパラダイムシフトを実装するために必要な過程だったのかもしれません。当時のスピリチュアリズムの関心は新しい科学が探求しつつあった関心領域とかなり重なり合うものがあった。たとえばクリントが降霊会などに入り込んでいったのは、フロイトが精神分析の理論を展開していた時期であって、「無意識」の活動が認知されはじめた時期と重なっています。他の科学の分野でも、重力や電磁気、さらには放射線、また視覚像としては捉えることのできない運動イメージなど、私たちの感覚器官によっては直接的には把握できない力への関心、探求が盛んになっていた。クリントより五歳年下のマリー・キュリーが放射線の活動、ラジオアクティビティを発見した時期とクリントが抽象表現へ転回したのは同時期でした。キュリー夫妻は一九〇三年にノーベル物理学賞を受賞し、マリーは女性初の受賞者となります、さらに一一年にはマリー・キュリーは単独でノーベル化学賞も受賞しています。ストックホルムの目と鼻の先に住んでいたわけですから、クリントは当然キュリーの実績を知っていました。いずれにせよ、いままで知覚では捉えることができなかった力が自然現象、そして私たちの身体、感覚に影響を与えている、あるいは支配しているという考えは「新しい科学」的認識としてすでに世界中で共有されていました。柳宗悦の最初の書物『科学と人生』(一九一一年)はその例です。そこでスピリチュアリズムは新しい科学として理解されていました。彼が民藝に見出した工人がその主体的な意志によらず、無心に事物を作り出してしまうことへの驚きは明らかに、「新しい科学」に見出した思想的関心から、まっすぐに引き出されたものでした。つまりクリントと柳はほぼ同時代に同じ問題群を共有していたということですね。が、どちらかというと柳の立ち位置はシュタイナーに近かった。何かを認知し世俗的社会に再着地、再登録する翻訳者、啓蒙家だった。クリントは自分より一歳年上で、そしてゲーテの研究からキャリアをスタートさせていたシュタイナーの理解力、知性を信頼していたけれど、一方で彼の世俗的、政治的振る舞いを見限ってもいたのは確かです。ところでクリントが降霊術的方法で即興的、自動描出的なドローイングを集中的に制作していたのは数年のことで、後には、霊的な閃きで元のヴィジョンは得ていた(と彼女が記しています)としても、その閃きをクリントは受け入れた上でそれをきちっと構成した画面に仕上げ、さらに理知的に分析し構造化したノートを作成しています。ですからクリントにとって後期の作品ももとより個人表現ではありませんが、大事なのは、その自分が得た経験、調査を冷静に観察、分析し説明する主体が成立していることです。霊的な閃きからイメージが自動的に生成する、と書くと誤解もされやすいですが、そこで観察される現象は、自分自身に起こったことだとしても、いわば自然現象のようなものであって、それを別の主体が観察し構造的に認識している。現在の社会に認知されえないが、必ずこの認識は普遍たりうると確信できたのはその観察する主体の成立に支えられていたからだと思います。
リハビリ概念の限界
かつて脳が作りあげていた、いまは壊れてしまった、かつての「私」でなく、大袈裟にいえば、それに代わる「私」を、すくなくとも新しい回路を、新たに脳が組織することができるかどうか。一旦は外にある事物として、自分から切り離されてしまった身体から学び直すという過程を今、してやっているわけです。
一般にリハビリというと、この病気になる前の状態へ回復する、というモデルでつい考えられがちですが、実際に渦中に入ると、これは何か、元にはもう戻れない。未知のものを学ぶ学習過程といった方がむしろ希望がもてる気がします。
その意味でいえば、ヒルマ・アフ・クリントも自分自身の身体をメディウムつまり媒体、霊媒にして獲得された認識から学び、それを理路をもって整合させうる主体を立ち上げることができたのだとも言えるかもしれません。
が、それはいままでの社会化され制度化された「私」ではありえなかった。その連統性が維持されていたなら、その経験を受け止めることができない、破縦してしまう、ということも知っていた。既成の美術史に表現者としての自分を認めさせ登録したいなどとは望むはずがない。それに位置づけられえないから、いったん主体をアノニマスのメディウムに落とす必要があった。むしろ反対に、こうしてクリントが構築した新しい主体=体系にもとづいて、あらゆる芸術作品が理解され直されなければならない。実際それはできるのです、それくらいの強い体系性をクリントの仕事はもっている。
医療としてみればリハビリとは患者の外的な属性、社会と関係づけられた同一性をなるべくいままで通りの一貫性を保って、制度に再接続すること、復帰させることが目的なのだと思います。日常生活を患者が自立してできるようになるということは、患者と対応する周囲、社会のほうからすれば、周囲がなるべく大きく変化することなく、安定的に患者とつきあっていくことができるようになる、という意味となります。いずれにせよ、リハビリはいままでの患者と社会との関係をなるべく変化させず持続させることが前提にされる。リハビリの過程には、入試や各種免許のような評価、試験が不可避的に伴います。その評価に応じて、制度に、その患者への社会的対応を安定的に位置付けていこうとする。介護保険を得るためにはむしろ障碍があるときちんと認められた方が有利であったり、一方で装具などの補助具は、回復見込みの
みの限界を見極めた上でその障碍があっても生活できるよう製作されます。
いいかえれば装具は障碍をある程度、固定的なものとみなして作られる。いずれにせよ恢復とは社会との安定的な関係の恢復であり、制度的にはかつての位置づけへの再登録あるいはその復元を意味している。患者の周囲からみればそれが望まれているのは当然ですが。しかし患者からすると、患者は元の形での社会との関係を復元することではなく、それはそもそも脳の一部は欠損してしまい不可能なのですから、新しく身体との関係を構築する、そのことによって社会との関係、世界との関係も新たに作り直すとポジティブに考えたほうが救いがもてる。恢復という言葉に違和感があるのは、いままで通りの自分そして、従来の世界との関係に戻す、近づけるというニュアンスがあるからなんですね。別の新たな自分を立ち上げる可能性、自己の可塑性は終わりの形が見えない。それが形になってきたとしたら、世界の方も同じままではなくなっているはずです。ネットワークが再組成されるわけですから。つまり同じ世界に戻るのではない。前の世界はもう失われているのだから、また世界と関係をもてるとするならば、私だけでなく、世界も変わっていなければならない。
「リハビリテーション」という言葉は、漢語で言えば「適応」という意味でしたね。つまり、元の状態に戻すことが含意されている。でも、患者からすれば、身体の変化に伴って意識も変わらざるを得ない。病気以前の「元の状態」に戻すのではなく、病気以後の変化した状態を受けて、改めて生成される、自分を再構築する、と捉えた方が事の次第からいってもいっそう適切だし、結果的にはハッピーなのではないかと思います。
◾️新たな主体をいかに創生するか
実際に新しい自分を創生したり、再構築したりするのは大変困難なことです。ボードレールは恢復期という概念を提示し、美術史では晩期様式(late style)といわれますが、大病を通り抜けた芸術家が大きくスタイルを変えた例が多く知られています。ゴヤ、あるいはクレーやマティスにしても、再起不能と診断されるような大病に冒された後で、病気になる前の身体では思いつかなかったような絵を描きました。ドガやモネだって病になった身体でしか作れないような新しい形式の作品を残した。そういう知識があったことは励みにはなりました。そもそも芸術作品とは特定の物質条件に依存せず、物質性を含めた基盤となる条件、状況が変わっても、その変化に応じて、方法、技術、形式をフレキシブルに変容させていくものだった。新しいものの創造はこの条件の変化からむしろ引き出される。長年、芸術教育に関わってきて、そんな風にも教えてきました。[可塑性」という概念でそれを説明してきたのですが、脳梗塞後の恢復を語るときのもっとも大事な概念が同じく脳の「可塑性」でした。ですから「僕が本当のアーティストであるかどうかは、この病の後もアーティストとして作品を作り続けられるかどうかで試されるんです」なんてリハビリの先生たちに言ったりしていました(笑)。大風呂敷を広げて自分にプレッシャーを与えて、リハビリをさぼれなくして頑張ったわけです(笑)。脳梗塞から再起したことで知られる最大の画家は、その脳梗塞がどの程度の重さであったかはともかく、北斎ですが、そもそも彼はひとたび自分のスタイルが完成しルーティン化すると、自分の名とともに他の画家に売ってしまい、名を変更し引っ越しするということを生涯繰り返していました。いずれにせよ、昔から芸術には、あらかじめ統御された身体や精神を一度、解体し、その後、新たな主体をいかに組成させるかこそが核心に含まれていたのだと思います。
ひとたび統合性を失なった世界のなかで、あるいは世界との関係が切断、解体されたあとに、なお新たな主体が生成してくる、その主体が生成するそのプロセスが実験的に賭けられていたのではないかと改めて考えなおしています。
主体が生成し移行していくプロセスが記述のプロセスに重ねられていたのではと。
林檎という存在に対して、たくさんの異なる印象、さまざまな感覚があるのではない(一つの物質的客体に対して、無数の主観的印象があるのではない)。林檎それ自体があるのと同様に、それぞれの感覚はそれぞれが客観的事実としての権利を持って、そこにあるということです」と書かれていました。
このような状態とペソアが考えた無数に変化してゆく「私」のあり方は、私にはパラレルに見えたりもします。つまり、ペソアは統一された不変の主体などというものはない、と言い、岡﨑さんは感覚は一つのイデアに収斂するものではなく、無数の感覚がそれぞれ客観的事実としてある、と書いている。思い起こせば、岡﨑さんは『ルネサンス経験の条件」(文春学藝ライブラリー)でも、ルネサンス絵画は遠近法を確立し、一つの消失点に向けて、統一された絵画空間を成立させた、と言われてきたけれども、いやいやそんなことはなくて、◎ルネサンスの画家たちは常に絵画の平面は見られるたびに分裂し、解体することを知っていて、絵画を見る者の主体を劇的に変容させるために絵画を制作していた、と論じていました。
しかし、先ほど岡崎さんが言及されたリハビリ制度をはじめ、「制度」と呼ばれるものは、感覚や現象を一つのイデアの反映と見立てて、人やものに対しても「〇〇は〇〇である」と一つの定義や変わらないアイデンティティを与えることで機能しています。私たちの使っている、あるいは使わされているといってもいい「言語」そのものが、「制度」の最たるものと言えるでしょう。ところが、私たちは生きていると、「制度」からはみ出たり、齟齬を来すことが常にあって、そこに葛藤や衝突が生まれます。こうした制度とうまく付き合ったり、つくりかえたりするには、どうするとよいでしょう。
制度に助けられリハビリをしているわけですが、そのリハビリの前提として、制度との葛藤があるわけですね。僕は自信をもっていうことはできませんが、障碍を持っている側がそれを障碍として固定的に扱おうとする制度の評価、予測を裏切るかたちでなんらかの成長、生成を示していかないと、制度との新たな関係を作れないような気がしています。(少なくとも患者側から見て)制度側も一緒に変化させることができて、はじめて再適応、リハビリがなりたつ。
でないと個々の患者の問題は解決されないですよね。ネットワークの問題なのですから。
しかし、この葛藤はそもそも可塑性が発現する条件でもありますね。脳は脳梗塞を受けた後が、いちばん活性化されます。そのとき脳の可塑性が最大限に現れるといわれています。そのとき脳のなかで何が起こっているかというと、たしかに「感覚のエデン」で書いたように、脳は脳内で発現する、すべての感覚、情報を受け容れようとする。健康なときは何かを認識したり、行動したりする際は、非常に効率よく特定の回路だけを使って処理していたわけですが、
その基幹の回路が破壊されてしまったので、その欠損を補ってなんとか回路を確保しようと、周囲の路地のような回路、いや脳内すべての神経細胞が活性化するのだと説明されます。いままでやっていたことをしようとしても動かない、どこをどう使っていいかわからないために脳がフル活動する、いいかえれば大混乱、パニックになる。それこそ小指一本、薬指一本を動かそうとして、全身使って身悶える、肝心のことはできず、身体の別の部位が動く、さまざまな代償動作が現れます。リハビリはものすごく疲れるものなのです。目眩が起こり、頭がふらふらしてくる。要するに頭が疲れるのです。ところが不思議なのは脳で活性化するのは身体機能に関わる部分だけではないようなんですね。
脳の「可塑性」のポジティブな面を拾っていえば、こんな不思議なことも現れます。けれど、ほとんどはパニック状態であってメンタルも浮き沈みが激しく、とくに鬱のときは行き場がない。それを「エデン(楽園)」とはとてもではないが言いがたい。つまり可塑性とは、治る可能性そのものでもなく、治らないと状態を固定することでもない。破壊の別の側面ですよね。
■可塑性は教えられるか
「可塑性」といえば、「プラスティシティ(plasticity)」の訳語でした。その語義は「柔らかくして形をつくる」「固定する」というわけです。これだと、せっかく可塑的に変化したとしても、やがて固定するというイメージにもなる。でもそれだと、脳のもつ働きからズレてしまう。そこで彼は、「ライブワイヤード(live-wired)」という言葉を提案しています。
つまり、脳の神経細胞は絶えず配線を組み替え、ずっと変化していくものだというわけですね。
リハビリに関わる点で、もうひとつ興味深かったのは、日頃から繰り返し行っている思考や行動をする際は、脳に効率のよい回路がすでにできているので、ほとんど意識せずともそうした思考や行動をとれるのだという話です。この場合、脳はほとんど学習をしていない。配線の組み替えをせずとも対応できるわけです。脳が学習するのは、不意打ちをされたときだというのですね。予期せぬこと、言い換えれば、まだ神経細胞がそれに応じる回路を十分備えていない状態です。
岡崎さんは産業革命以後の近代社会では、生産システムが常に変わっていくので、それを構成する「市民」は、自分で自分を変えていける可塑性を備えなければならないと指摘していました。
■メタ学習のコツ
このように常に壊れつづけ、つくりなおされつづけている。そんな状況を前にすると、教師をはじめとして多くの人は不安、怖れなどネガティブな感情に呑み込まれてしまいます。主体の連続性や不変性、同一性が確保されないからでしょう。「破壊即創造」などというけれど、創造を教えるのはもちろんですが、破壊を教えるのもむずかしいんですね。
認識、知覚を入れ替える、つまり学び方を学ぶ、メタ学習です。このメタ学習にも、いま方法といったけれど、方法や形式があればいいけれど、それは固定したものとしてはありえない。
もしコツがあるとすれば、何かを能動的、積極的に作ろうとする主体をいったん棚にあげ、忘れるということでしょうか。そして、よく見ること、聞くこと、感じることです。これは受動的ではなく反対に能動的に見る、能動的に聞く、能動的に感じる。いままで何度も見ていたものから、まったく気づかなかったことが発見されるまで見る、聞く、感じる。つまり何かが発見されるまで待つ。◎発見とは見る人間の態度の変更、依拠していた認識枠、技術枠が変換されることとも言えます。いままで見ていた対象からいままで見ていなかった何かが発見されるわけですから。創造することは発見することと同意だということです。
こうした発見を導くためにその記事ではアッサンブラージュ、比例-比喩、サイバネティックスという方法を提示しています。三つとも作ることと作品を見たり聞いたり感受することの区別は消え、融合してしまいます。多くの人は、ひたすら主体的に目的論的にものを作る、作らなければならないという強迫観念に縛られていますから、既得され前提とされている、自分の連続性や同一性に回収できない事柄を受け入れるのが困難になるのですね。すでに学んできたもの、既得の認識枠、技術枠をいったん手放し、無効とみなすことに、ときに自分が死んでしまうような恐怖を感じます。けれど、なにかを創作する場面、また芸術教育の現場では、自分をいったん棚にあげておいたほうがうまくいく。何かを発見し、システムを再構築するフィードバックはうまく作動する。重要なのは、先行する強く一貫した、作ろうとする意志よりも、見ることであり、聞くこと、触ること、感受することです。いわば素材、メディウムの声をよく聞くこと。そこに示されたオーダーに従う、つまり「乞わんに従う」ということですが、そのとき制作意図、意志はメディウムの側にあって、そこに開示される。「精霊がメディウムに降り立つ」ともいっていい気がします(ベイトソンがいいそうですが)。私たち作家は、そのメディウムの教え、精霊の教えをフイードバックして、新しい主体として、後からシステムをインストールしなおす。それを作ったと了解できる主体は後から作られるんですね。
脳梗塞で倒れ、入院したとき、そもそも主体の持続性や連続性など確保も保証もされていません。そんな主体などいったん括弧に入れられ、強制的に棚上げされてしまいますね。あるいは社会的事象、行為、認識全体の一貫性、統合性を支えていたシステム自体が機能しなくなったとき、そのシステムに彩りながら、このジステムをどうすれば改変できるのか、入れ替えられるのか、というと「ノイラートの船」みたいな思考演習になるけれど、ところが、われわれが、もうその船から放り出されてしまっていたとするならば、だいぶ答えは異なる。船の外、海の只中は確かな支えもなく、まったく不安定な動きしかできないけれど、なんと、私の身体は沈むことなく、浮いている!いわば発見はこの状態を体験し、担保するところからはじまるのだと思います。
システムは自らに与えられている目的が正しいのかそうでないのか、あるいはシステム自体の善悪の判断をすることはできない。危機があろうとなかろうと、システムの外に立って、システムの目的やシステムそれ自体を検証する。また、必要とあらば、新しい目的を設定したり、システムそのものを作り直す。人が好むと好まざるとにかかわらず、複数の人間が集まってなにかをする場所では、そうした発想が常に必要なのだと思います。
いまの世界の状況はどう見ても、非常事態であり緊急事態でしょう、可塑性という概念は啓蒙主義の生まれた十八世紀に普及しましたが、そのとき以上の状況でしょう。
■「遊び」の必要性
現在の深刻な事態を前にして、この言葉を持ち出すと、眉をひそめられるかもしれませんが、可塑性を身に付けるためには、もっと「遊び」が必要なのではないかと考えています。
「遊び」には、何かの役に立つといった実利や目的がない。むしろ「遊び」では、そうした有用さを脇に置いておき、いま自分が置かれた状況で、その場や自分にどんな状態が出てきてしまうのかを探って試行錯誤する。試行錯誤には、うまくいくことだけでなく、うまくいかないこと、失敗も含まれる。
「遊び」とは、むしろそんなふうに探る過程自体に喜びや楽しみを感じる行為と言えるでしょうか。目的に最短距離で向かおうとするというよりは、なにが起きてしまうか、自分が思ってもいなかったような状態になることを試す営みと言いましょうか。結果として、世界にはそうした潜在性があるという次第にも気がついたり、考えたりするきっかけになると思うのです。
危機的な状況においては、事前に想定された問題への対処に長けた制度だけでは太刀打ちするのが難しいケースも多いかと思います。というよりも、事前に想定していた範囲に収まっていないからこそ危機にもなるわけです。そうした制度も必要だし時に有効だとして、他方では、いま述べた目的なき「遊び」から生まれる思考や行動が必要とされる場面もあろうかと思うのですね。
大きくは山本さんの考えに賛成ですが、「遊び」という一つの言葉だけにまとめてしまうのは、ためらいがあります。というのは極端に言えば、人を殺すのも、戦争ですら「遊び」と言えてしまいますから。確かに自分では最初は気が進まないことでも「遊び」として身を投じると、そのうち熱中し、その「遊び」を楽しく感じられるように主体が変容するかもしれません。けれど、このメカニズムは既存のシステムに迎合させる仕掛けとして、すでに使われてもいますね。受験勉強でも戦争でも何でも「遊び」だと考えれば楽しいよ、と。
たしかに、状況との組み合わせや言葉の使いようによっては、ただの現状肯定にもなりかねませんね。
重要なのは、迂回にみえること、無駄にみえることを、あえて引き受けるということだと思います。それが「遊び」というのだとしたら、それを余剰の「遊び」とみなしているのは、システムの側ですよね。しかし引き受ける側はそれを「遊び」としては受け取っていない、真剣そのもの、回避できないものとして受け取っている。そうでないとその行為はきちんと行われないし、作動しませんね。真剣に受け取るには、それを無駄、非効率だとみなす判断をしている主体なり、システムに依拠することをいったん放棄しなければならない。したがって既存のシステムに順応させるメカニズムとして「遊び」が利用されるのには警戒しなければならない。大事なのは、システムとの整合性に依らず、それが、いままで排除してきたものに真剣に目をむける、それに向けて身心の体制を組み替え、入れ替えていくことができるか、どうかということですが。それは一般化できない極めて特殊なもの、主観的、個人的な事柄にすぎないと看做されかねないものだけれと、それをのっぴきならない、より普遍的なメッセージとして受け取れるかどうかに関わっている、そういう面があると思います。
◾️坂田一男と漱石の経験
結局、可塑性とは、世界を物理的に破壊するような暴力ではなく、脳が自分自身の脳を破壊するような暴力を受け容れて、それを積極性、能動性に転化できるかどうかにかかっているのだと思います。
その暴力を受け入れ、自らの意志へ組み込むことができるかどうか、新しいシステムとして組成、蘇生できるかどうかが可塑性ということですよね。自分の思い込み、既得の概念を破壊し、修正することは反省や内省からもたらされるとされていますが、けれど反省や内省では自分は破壊されない。力はシステムの外から働きかけるから有効だったわけで。
不意打ちされたとき、それまでの経験から脳に生じた既存の回路だけでは間に合わず、自分で自分をつくり変える過程が始まる。そういえば、プラトンとアリストテレスは師弟揃って「哲学は驚きから始まる」と言い、ドウルーズが「思考は不法侵入から始まる」と書いていたのも思い出されます。「なんだこれは」という驚きがあるからこそ、対象が見知らぬものに感じられて、それを知ろうとする探究が始まる、というわけです。
。坂田は今見ている世界にそれが崩壊する様を同時に重ねてみていた。それを絵画の構造に実装したことが彼の仕事の偉大さです。
目の前の世界は全部仮の姿であり、仮象であると捉えるという感覚は、しかし大正時代に仕事をはじめた坂田の世代の芸術家にけっこう共有されていた感覚だと思います。そしてその感覚は第一次世界大戦、日本では関東大震災によって現実的に裏打ちされました。僕の読み方が正しいかどうかはわかりませんが、その意味で僕はその時代に先行していた漱石を大事だと考えてきましたし、強く影響を受けてもいます。 。坂田は今見ている世界にそれが崩壊する様を同時に重ねてみていた。それを絵画の構造に実装したことが彼の仕事の偉大さです。
目の前の世界は全部仮の姿であり、仮象であると捉えるという感覚は、しかし大正時代に仕事をはじめた坂田の世代の芸術家にけっこう共有されていた感覚だと思います。そしてその感覚は第一次世界大戦、日本では関東大震災によって現実的に裏打ちされました。
僕の読み方が正しいかどうかはわかりませんが、その意味で僕はその時代に先行していた漱石を大事だと考えてきましたし、強く影響を受けてもいます。
世界の姿は確率的なものであって決して安定しない、主体と客体、主観と客観の区分は固定されず、つねに揺れ動いている。
つまりFとfの配分を安定的に行うことができるポジションはありうるのか?当然のことながら漱石はそんなスタティックな区分はできるはずないと知っていたと思います。一方で創作に対して、理論というものはむしろ幻惑的に働くものですね。理論を通して再度、当該の作品を眺めるとまったく異なる像が現れてくるように感じることがある。いや、そういう幻惑的な揺らぎ(作品像の変容)を文学の読書経験がもたらすから、それを定位しようと理論は書かれるのかも知れませんが、実際は理論によって揺らぎは大きくなることがあるし、その変容を起こすことを目指して批評が書かれることさえある。つまりそれを読むというプロセス、あるいはそれを書くというプロセスにおいて、理論と創作が生起させることはかなり重なっている。
そんなふうにして、文字を読んだ結果、自分の心身になにかが起きるのを味わう。文章の書きぶりと読み手の組み合わせによっては、そこに言葉で記された出来事が、本当はつくりものであるにもかかわらず、読み手の脳裡では、あたかも本当に生じたことであるかのように感じられる。これが幻惑です。文学作品を読む人は、片時、幻惑されて、何かが揺らいで、また現実に戻ってくる。作品を受けとる立場について言えば、このような幻惑をもたらす経験をどのように受け容れたり、捉え返したりするかが、醍醐味と言いましょうか、創作に触れる面白さの源泉ですね。先ほどの話につなげると、予期せぬからこその不意打ちであるわけですが、それにしても不意打ちされるためには、幻惑をもたらすものに対して、自分を開いておくのも肝心な条件かと思いました。
■思考することと創造すること
絵を描くことでむしろ、知っていたはずの絵の見方がかわること、忘れていた作品がふいに思い起こされることが面白い、それが起こらないと作品ができたという実感がしないのですね。このエッセイはほぼ絵を描きながら、想起した通り思考した通り、のプロセスで書いたものですから、書き始めるときは安定した視点があるわけではない。ところが書いているうちにまとまってきて、最後にはなんとなくオチがつく。とりあえず適切な用語が思い浮かばないのでオチといっておきます。これは絵画や彫刻を制作するプロセスで起こっていることとほぼ同じに感じます。様々なことを想起しながら、さらに、それらが想起させる問題群に配慮しながら、作品を作っていく。このように、いわば考えをまとめていくプロセスとしてしか作品はできないし決まらない、ただし僕の場合ですけれど。同様な作用はエッセイを書くときにも起こった。想起されるのは芸術のことばかりではなく、対象を問わない。大袈裟ですが結局はこの世界のすべてに思考が及んでいく。それが可能であるという意味で開かれているとも言えます。けれど同時にこれは個人の身体、脳に生起した思考にすぎないとも言える。としても、そこで生成した何らかの想念いわば世界像は、客観的な対象、客体=オブジェクトとしての抵抗感をもっている。否定しようとするとモノとしての抵抗が起こる。これは作品と同じですね。つまり思考することは、それが脳の中に回路を組織するということだとしても、抵抗を持った何かの像を造形する、という意味において、物質的に造形することとまったく同じである。何かを造形する、創る行為に平行し、見ること、想起すること、思考することが、同時に生起しているというか。
人間が同時に行っている、異なるカテゴリーの行為は、実はそれぞれ一つのカテゴリー、項目として固定されていない。それらは互いに影響を与え合って絶えず動いている。その影響関係が構造として一定の安定をもつならば、それぞれの項目が項目として扱われるのが可能になること、いわば一つの像として扱われうるようになるといえるのかな。世界は不安定でますます危機的な様相を帯びていますが、自らの身心そして行為がそもそも相互に分裂した複数のカテゴリーの不安定、可動的、可塑的なネットワークで組織されていたのであれば、危機は心身にもともと確率的に埋め込まれていたということになるかもしれませんね。こんな解釈をしても、日々の困難は変わりませんが、リハビリという決して安定に達することのないプロセスをつづける意味、アーティストをつづける意味は確認できたような気がします。(6月10日、岡崎氏宅にて収録)
芸術史の逆撫で
ーーハロルド・ゼーマンを継ぐ
田中純
問題はそれがいかなるあらたなパースペクティヴを「芸術史」という「歴史」に対して切り開くかである。「切り」「開く」ーーつまり、それさいままでの歴史叙述を切開し、その内部構造を暴き出すようなものであるべきだ。
すなわち、「独身者機械」や「総合芸術作品」といったオブセッションの展示は、オリジナルな芸術作品よりもむしろ、小説中の描写にもとづく実作や模型・複製の制作によって行なわれたのだ。◎芸術作品という「もの」それ自体よりも、「態度」と呼ばれた制作活動のプロセスこそが展示対象の核心であった「態度が形になるとき」展以来のゼーマンの一貫した姿勢である。これが所蔵コレクションという美術館の制度的優位性に対する対抗戦略であったことは明白だろう。芸術史、とくに美術史の書き換えは、美術館という制度を「逆撫で」することを必要としたのである。
ゼーマンによる「もうひとつの芸術史」としての展覧会は、もとより網羅的な歴史を意図するものではなく、ゼーマン自身の出自や関心を反映して地域的にも限定されている。それはこれらの展覧会が彼自身の「個人的神話学」にもとづく「オブセッション」の産物だったからであろう。逆に言えば、制度としての美術館に根を下ろした美術史を書き換えるために、ゼーマンは徹底して個的なオブセッションの神話学を必要としたのだ。そのとき、「もうひとつの芸術史」は展覧会というかたちで空間化され、カフカの処刑機械のように、作家や思想家のオブセッションは物体と化して可視的なものになる。そのようにして実体化された理念の配置された展示会場という一種のエネルギー場が「もうひとつの芸術史」を観客に伝達するのである。
「総合芸術作品」という理念は、個的・集団的生の総体と芸術作品とが一体化する究極のユートピアをめぐるオブセッションにほかならない。その意味では、言うまでもなく、ゼーマンの展覧会自体がそのようなユートピアを志向している。
ゼーマンによる「もうひとつの芸術史」は展覧会という形態を取る限り、つねに暫定的でその場限りである。展示物に模型を積極的に採用するのは、そこで重要なのが「もの」それ自体ではなく、媒体としての模型を通じて経験されるオブセッションのエネルギーだからであり、そのような経験は必然的に鑑賞者それぞれに異なっていて、物質的・客観的には確定できぬ、エフェメラルなものにとどまらざるをえない。
ベンヤミンが「閃光」に譬えた「過去のイメージ」を想起してもよい。オブセッションを核とする「もうひとつの芸術史」において重要なのは、実現したもの、達成されたものではなく、本質的に未完成にとどまる志向性であり、そこに注ぎ込まれた、そこから発散するエネルギーである。ゼーマンは美術館という近代的な制度のエッジを際立たせるようにして、非美術館的な、ということはすなわち、美術というジャンルだけには限定されない「もうひとつの芸術史」を展覧会として、美術館の「際」で試行したのだ、という言い方もできるかもしれない。それは美術館も美術史も否定はしていない。むしろ、それらを支持体として、そこにオルタナティヴな「もうひとつの」、ありえたかもしれない可能性を現出させるのが、彼のキュレーションだったのである。
ボリス・グロイスは『アート・パワー』で次のように述べているーー
「アート・ドキュメンテーションは、アート・スペースのなかで芸術のメディウムを用いることによって、生そのものを指し示そうと試みる。言い換えれば、純粋な活動、純粋な実践、いわば芸術の生を、直接現前させるのではなく、指し示そうとするのである。ここでの芸術は生の形式をとり、芸術作品は非芸術に、すなわちこの生の形式の単なる記録となる。芸術はここで生政治的なものになる、と言うこともできるだろう。なぜなら、芸術はさまざまな芸術的手法を用いて生それ自体をある純粋な活動として作り出し、記録しはじめているからである。そして事実、アート・ドキュメンテーションが芸術形式として成立可能になったのは、生そのものが技術的、芸術的な造形の対象となった、今日の生政治時代の状況下においてのみのことだ。」(『アート・パワー』、石田圭子ほか訳、現代企画室、二〇一七年、九三九四頁)
グロイスにとって「生政治」とはまず第一に所与の時代状況であるが、生政治的芸術は権力による生政治に対する対抗的な活動をおもに意味しているととらえてよい。ゼーマンはさまざまな手法を駆使して、グロイスが言う「アート・ドキュメンテーション」こそを展覧会として組織してきたのであり、そこで問題だったのは芸術のこの対抗的な生政治的次元だったと言えるのではないだろうか。「総合芸術作品」が重要なテーマとなるのもそのためである。グロイスは「今日の生政治時代」なるものにおいては、生物と人工物の差異は可視的な自明なものではなく、アート・ドキュメンテーションを通じて人工物もまた生きたもの、自然なものになりうると言うーー「つまるところアート・ドキュメンテーションとは、人工物に生あるものを、技術的な実践に生き生きした活動をもたらす技法なのである。それは生芸術であり、同時に生政治でもあるのだ」。ゼーマンが一連の展覧会で模索していたものとは、このような生芸術による対抗的生政治の可能性であったように思われる。
グロイスのこうした指摘を補助線とするとき、ゼーマンにとってクラヴェルが重要な存在であった理由の一端が明らかになる。まず第一に、クラヴェルと彼を取り巻く時代環境には、「独身者機械」「真理の山」「総合芸術作品」という、ゼーマンによる三つの大きな企画展のテーマが集約されている。
「もうひとつの芸術史」を書くために必要なのは、過去からのかすかな「さざめき」を聴き取り、過ぎ去ってしまったもののわずかな「かげ」の移ろいをすばやく捕らえることなのかもしれない。そのような「かげ」と「さざめき」がすなわち、「危機のしるし」だからである。それはまた、ヴァールブルクという「歴史の地震計」が身をもって経験した歴史的時間の変調でもあった。ハラルド・ゼーマンが「個人的神話」や「オブセッションの美術館」といった発想で取り組んだ芸術史の書き換えを継承する
ーーしかし現代の生政治的状況に対応してよりいっそう繊細なーー「歴史の逆撫で」の戦略が模索されなければならない。
『文學界』10月号【特集】もうひとつの芸術史 岡崎乾二郎×山本貴光より引用、抜粋。
2025-04-07 01:11:40
思考は〈外〉からやって来て〈外〉に帰っていく ②
テーマ:note ⇄ memo
芸術作品としての生
Ⅰ
ドゥルーズ
言語学者とは正反対の立場をとったフーコーの目から見ると、言語ですら平衡とはほど遠いシステムだったわけですからね。
フーコーの思考は絶えず次元数を増していきながら、けっして個々の次元が前の次元に含まれることはなかった。
Ⅱ
ドゥルーズ
ようするに、歴史とは私たち自身から引き離すものであり、私たちが自己を思考するために乗り越え、突き抜けなければならないものが、この歴史にほかならない。ポール・ヴェーヌがいうように、時間とも永遠とも対立するものとして、私たちの現在があるのです。
Ⅲ
ドゥルーズ
思考するということは危険に満ちた行為なのだ、とフーコー当人も明言しています。
思考するとは、まず〈見ること〉であり、〈語ること〉であるわけですが、ただしそれには条件がある。つまり目に物が拘泥するのをやめて「可視性」に達し、言語が単語や文に拘泥するのをやめて言表に達していなければならないのです。これがアルシーヴとしての思考です。つぎに、思考するとは能動的になることです。つまり力の関係を張りめぐらすこと。そのためには力の関係がたんなる暴力に還元されるのではなく、行動をめぐる行動、つまり「示唆する、帰納する、転用する、むずかしく、あるいはやさしくする、拡大したり制限をもうけたりする、ある程度まで可能にする」といった行為を構成するということを理解していなければならない。これが戦略としての思考です。
主体として生存するのではなく、芸術作品として生存すること。この最後の段階が審美的思考です。
Ⅳ
ドゥルーズーー考古学や系譜学は、一種の地質学でもあるのです。
考古学はアルシーヴであり、アルシーヴは視覚の部分と聴覚の部分をもつ。
物をとりあげるのは、そこから可視性を抽出しなければならないからです。
ある時代における〈言表可能なもの〉とは言語の体制のことであり、この体制がさまざまな内属的変化によってひとつの均質システムから別の均質システムへと飛躍的な移行をとげる(体系言語は常に不均衡の状態にある)。
そして、〈見ること〉と〈言うこと〉が分離され、〈見ること〉と〈言うこと〉が隔たりと還元不可能な距離によって引き離されているという事実は、ごく単純につぎのような意味をもっているのです。つまり、認識の(というよりもむしろ「知」の)問題は、照応関係に訴えたところで解決できるものではないし、符号関係をもちだしてもどうにもならないということ。〈見ること〉と〈言うこと〉を交錯させ、織り合わせる理由は別のところにもとめなければならないのです。アルシーヴが大規模な断層につらぬかれ、断層の片側には〈可視的なもの〉の形態を、反対側には〈言表可能なもの〉の形態を配分し、この両者は還元不可能である、そう表現すればいいでしょうか。〈可視的なもの〉と〈言表可能なもの〉を縫い合わせ、両者の溝を埋める糸は、形態の外の、もうひとつ別の次元にあるからです。
V
ドゥルーズーー権力は知の諸形態の間隙をすりぬける、あるいはその下をくぐりぬける無形の要素にほかなりません。
権力とは力であり、力の関係であって、形態ではない。
そして権力の焦点に「対峙する」抵抗の拠点に訴えようにも、肝心の抵抗は何に由来するのかわからない。そこでフーコーは考える。一線を越え、さらには力の関係を乗り越えていくにはどうしたらいいのか、と。あるいは、権力を握っていても、権力に服従する立場にあっても、とにかく権力と顔をつきあわせていくしかないのか?
それは力をたわめるのにも似た操作であり
ある特定の力が他の諸力を触発するかわりに、力自体が触発を受けるようにしむける操作です。つまり、「襞」。これがフーコーのいう力と自己の関係なのです。つまり抵抗し、すがたを消し、生や死を逆用して権力に対抗すべく、自己との関係によって力の関係を「二重化する」こと。フーコーによると、この操作を考案したのは古代ギリシア人でした。
主体化がおこなわれるごとに、権力が主体化のプロセスを回収し、力の関係に服従させようとつとめたとしても、主体化のプロセス自体は常に息をふくかえし、かぎりなく新たな様態を産みつづけるわけだから、このプロセスはなおさら可変的なものになるのです。
主体化は「人称」ともいっさい関係をもたない。
主体化とは、個人にも集団にかかわるし、(一日のうちのある時間、大河の流れ、そよぐ風、生命といった)〈事件〉を性格づけることもある個体化なのです。それは強度の様態であって人称的主体ではない。それなくしては知を超えることも、権利に抵抗することもできないような特殊性の次元。フーコーはギリシアとキリスト教世界における生存の様態を分析し、それがどのようにして知のなかに入り込み、どのようにして権力と妥協の関係を結ぶのか、明らかにしています。しかし、生存の様態それ自体は知や権力とは違う性質をもっているのです。
フーコーが最大の関心をよせた対象はギリシア人への回帰ではなく、「いまの私たち」なのです。
私たちにはみずからを「自己」として成立させる手段があるのか、そして、ニーチェふうにいうなら、知と権力を超えた、じゅうぶんに「審美的」な方法があるのだろうか?
Ⅶ
「人間の死」
ドゥルーズ
フーコーは人間を信じていない。つまり人権を信じていないのだ。
人間の死は形態と力の問題です。
Ⅷ
偉大な書き手においては、文体はかならず生の様式になりえている。文体とは断じて個人的なものではなく、生の可能性を、生存の様態を考えだすことなのです。
「ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール」一九八六年八月ニ十三日
聞き手ーーディディエ・エリボン
フーコーの肖像
ドゥルーズ
過激な肉体の運動には危険がつきまとうものだということは誰もが認めるでしょうが、思考もまた、息が詰まるほど過激な運動であることに変わりはないのです。思考がはじまると、生と死が、そして理性と狂気がせめぎあう線との対決が不可避となり、この線が思考する者を引きずっていくのです。
〈近いもの〉と〈遠いもの〉が死と狂気のなかで反転し、転倒するありさまに魅力を感じていたのです。
フーコーにとっては現象学よりも認識論のほうが好ましいわけですが、それは、個々の歴史的形成に応じて変化する「知」のなかに狂気がとらえられる、そんな認識論なのです。
狂気の思考は狂気の体験とは違って、あくまでも思考の体験なのです。
主体化の様態は断じて主体への回帰ではなく、新たな創造をうながす断絶の線だった。つまり主体化の様態とは、知と権力を対象としたこれまでの関係に変化をもたらす新たな探求だったのです。
思考は生の問題でした。生そのものだったと言ってもいい。
私たちと主体化との関係、そして私たちがみずからを主体として成立させるときの方法が重要なのです。いつの時代でも思考することは実験することと同じなのです。思考とは解釈ではなく実験なのです。
歴史は実験ではない。歴史とは、歴史ではとらえきれないことの実験を可能にする、ほとんど否定的ともいえる条件の総体であるにすぎないのです。
それから、ブランショの場合と同様、フーコーでも「誰か(on)」の分析が促進されます。
つまり三人称ですが、分析の対象にすべきなのはまさにこの三人称だということ。〈誰か〉が語り、〈誰か〉が見て、〈誰か〉が死んでいく。つまり複数の主体が存在するのてす。主体とは〈可視的なもの〉の塵のなかを舞う微粒子であり、匿名性のつぶやきのなかに置かれた可動性の場のことです。主体はいつも微分の様相を呈する。主体は誰かが語り、誰かが見る行為の密度のなかで生まれ、そこで消滅していく。
これは、いわばジュルジュ・バタイユと正反対の考え方で、汚名に塗れた人を規定するのは悪における過剰ではなく、語源学の見地からみてふつうの人やありふれた人が、隣人の苦情とか警察の出頭命令、あるいは訴訟沙汰といった三面記事的な事情によってふいに日の当たる場所に引き出されたとき、汚名に塗れた人になるという……。つまり権力との対決を強いられ、何かを語り、みずからの姿を人目にさらすことを命じられた人間。
汚名に塗れた人になること。これかフーコーの夢だった。
そして、権力と衝突することは現代人(つまり汚名に塗れた人)の宿命であり、私たちが見たり語ったりするような圧力をかけてくるのは、ほかでもない権力なのだ、と自分に言い聞かせるわけです。
たぶんフーコーはなんとしてもこの一線を越えて線の向こう側に足をのばし、知と権力の複合体よりもさらに遠いところまで行かなければならないと感じていたのでしょう。
ライプニッツと同じように、「沖に投げ出された」わけです。
〈外〉はいかなる内界よりも近いものだということにもなる。そしてそこから〈近いもの〉と〈遠いもの〉が絶えず反転しあう関係が生まれるのです。思考は内部からやって来るわけではありませんが、かといって外界が出現する可能性を拡張するわけではない。思考は〈外〉からやって来て、〈外〉に帰っていく。思考は〈外〉に挑むことによって成立する。〈外〉の線は私たちの分身であり、分身の他者性をともなっている。
知と権力を超えたところに、「システム」の第三の側面があり、第三の要素があるということ……。これが極限に達すると、そこでは死と自殺の区別すらつかないような加速が実現することになるのです。
可能なかぎり、そしてできるだけ遠くまで見越して、線を生の技芸につくりかえること。線に挑みながら、もう一方では逃走し、わが身の保全をはかるにはどうすればいいのか?この問いが提起されたとき、フーコーが頻繁にとりあげた主題が表面に出てきます。つまり、線を折り畳めようになり、生きうる帯域を成立させてそこに住まい、挑み、支えを見出し、息をつく必要がある。ようするに思考を可能にしなければならないという切迫した問題。線の上で、線とともに生きられるようにするため、線を折り曲げること。
フーコーには〈外〉があり、〈外〉の線を折り畳んだ襞があって、さらに〈外〉の存在としての人間的現実がある。
類似は表面的なものにとどまると考えるべきだと思います。フーコーには現象学的意味での「経験」がなく、常に複数の知と複数の権力があらかじめ存在し、これが〈外〉の線にみずからの限界を見出し、〈外〉の線上で消えていくことになる。
覚醒状態で世界を生きるには世界を折り畳まなければならない、そしてすべてが一度に与えられるわけではない、と説明しています。
自己にたいして作用するとき、その力によってできる襞。それから私たちと真理との関係において真理によってつくられる折り目。そして最後に究極の折り曲げとして出てくるのが〈外〉の線自体の襞であり、これが「待機の内在性」を成立させるわけです。
つまり他人を統率する資格をもつのは十全な自己抑制に達した者にかぎられるのです。自己にかぶせるかたちで力を折り畳むことにより、そして力を自己との関係のなかに注ぎ込むことによって、ギリシア人は主体化を発明したのです。
だから、もっともすぐれた人間は自分自身に向けて権力を行使する者だということになります。
ギリシア人は美学的な存在の様態を発明した。それが主体化なのです。つまり線を湾曲させ、線は線自体にもどり、力は力自体を触発するようにしむけること。そうすれば、私たちは他の方法では生きられないものを生きるための手段を手に入れることができる。フーコーが主張しているのは、生存を「様態」や「芸術」に変えないかぎり、私たちは死や狂気を回避できないということです。
主体などありはせず、主体性の生産が存在するにすぎないわけですからね。主体性とは、時期が熟したとき、まさに主体がないからこそ生産しなければならないものなのです。そして私たちが知と権力の段階を乗り越えていれば、すでに主体性生産の時期は熟したことになる。新たな問いを提起するよう私たちに圧力をかけるのは、そうした知と権力にほかならないわけですからね。それ以前には新たな問いを提起することは不可能だった。
主体化、つまり〈外〉の線を折り畳む操作は、たんに保身にはげみ、難を避ける方法だと考えてはならない。それどころか、主体化こそ、線に挑み、線をまたぐ唯一の方法なのです。
主体化とは、生存の様態を、あるいは生の様式を生産することにほかならないのです。
プロセスとしての主体化は一種の個体化であり、個体化は個人的であっても集団的であってもいいし、一個人についておこなわれても、多数についておこなわれてもいい。
フーコーのいう様態には、たしかに主体なき個体化が含まれている。これがもっとも重要なポイントでしょう。それに熱情も、熱情の状態も、おそらく主体化の場合と同じで、〈外〉の線を折り畳み、生きうる線につくりかえ、呼吸する手段を身につけるという意味なのではないか。
フーコーの定義によると、司祭的権力は「個体化をおこなう」権力です。
真理は、真理を発見するための方法を前提するのではなく、真理を欲するための方式と手続きとプロセスを前提するということです。
さらに私たちの手元にある主体化や個体化のプロセスを介して、私たちは自分にふさわしい真理をいつでも手に入れることができる。
はっきりしているのは、フーコーにおける人間の死という主題であり、この主題とニーチェ的超人とのつながりでしょう。なぜなら、人間の諸力だけでは、人間がそのなかに住まう支配的形態をつくりあげることはできないからです。
くどいようですが、主体化とは、けっして主体の成立などではなく、生存の様態を創造することなのです。
聞き手ーークレール・パルネ、一九八六年
Ⅳ 哲学
媒介者
つまり軟弱な、反動の時代が来たわけです。
問うべきは、「ただなか」では何がおこるのかということだったからです。そしてこれとまったく同じことが物理的な運動にも当てはまる。
運動はスポーツや慣習のレベルで変化する。
新しいスポーツ(波乗り、ウィンドサーフィン、ハンググライダーなど)は、すべて、もとからあった波に同化していくタイプのスポーツなのです。出発点としての起源はすたれ、いかにして軌道に乗るのかということが問題になってくるのです。
そしていま、永遠不変の価値の代役をつとめているのが人権です。つまり権利国家をはじめ、誰がみても抽象的としか思えない観念が幅をきかせているのです。そしてこうしたものの名において、あらゆる思考が阻止され、運動にもとづく分析がことごとく遮断されてしまうわけです。けれども、抑圧が恐ろしいものになるのは、それが運動をさまたげるからであって、永遠不変のものを傷つけるからではないということは、はっきりさせておいたほうがいい。そして不毛の時代が来ると、哲学は「……について」の反省に逃避していく……。
そこで哲学は永遠不変のものや歴史的なるものについて反省し、自分から運動をおこす能力を失ってしまうのです。
哲学書は反省するのではなく創造する人間だ
哲学者は創造をおこなうのであって、反省するのではないのです。
ベルクソンは思考の自己運動をとりあげた先駆者のひとりなのです。
知性の運動を与えられた概念を構築しなければならないのです。
このことを実感させてくれる実験室たりうるのはひとり映画だけです。それは運動と時間が映像自体の構成要素になったからにほかなりません。
映画の第一段階は映像の自己運動にある。
主人公がなんらかの状況にいて反応をおこす、そして主人公は常にしかるべき反応をするのだと思いこまないかぎり感覚=運動の図式は成り立たないのです。
むろん、運動は映像にあらわれつづけるわけですが、そこには純粋な視覚的・聴覚的状況が出現し、〈映像=時間〉を解き放つことになる。重要なのはもはや運動ではにい。運動は指標として現前するにすぎなくなるのです。
〈映像=時間〉とは、前と後がつながった継起を意味するのではありません。
〈映像=時間〉は時間の内部に生起することと混同されてはならない。〈映像=時間〉とは、新たにあらわれた共存や系列化や変換の形態なのですから……。
パイこね変換
私にとって興味深いのは、芸術と科学と哲学の関係です。
科学の真の目標は関数を創造することだし、芸術の真の目標は感覚世界の集合体を創造すること、そして哲学は概念の創造をめざす。
とにかく大雑把な項目を三つもうければ(関数、集合体、概念)、項目相互間の反響と共振の問題を定式化することができます。
「パイこね変換」
ひとつの正方形をとりあげ、それを引き延ばして長方形にする。そしてこの長方形をふたつの部分に切り分け、その一方をもう一方に重ねあわせる。こうして得られた正方形をふたたび引き延ばすことによって、どんどん正方形を変形していく。いわゆる混捏操作です。
線と線のあいだの干渉は相互の監視や反省に属する事柄ではないということです。
独自の運動をおこすことが重要なのです。誰も始める者がいなければ誰も動かない。また、干渉はたんなる交換とも違って、すべては贈与と捕獲によっておこなわれるのです。
もっとも重要なのは媒介者です。創造とは媒介者のことなのです。媒介者がなければ作品はありえない。
そして媒介者は系列をなす。純然たる空想の産物でもかまわないから、とにかくひとつの系列をつくることができなければおしまいです。私には自分を表現するために媒介者が必要だし、媒介者のほうも私がいなければけっして自己を表現することはできない。
人びとを作り話の現行犯でとらえるということは、人民成立の運動を把握するのと同じことです。人民ははじめから存在するものではない。ある意味では、人民とは欠落しているもののことにほかならないのです。
パレスチナ人は、自分の土地から退去させられた瞬間から、抵抗運動をおこなうかぎりにおいて、人民成立のプロセスに入るのです。
つまり、真理とは、はじめから存在するがゆえに発見すればことたりうるというものではなく、個々の分野で創造されなければならないと考えるわけですが、これは自明なことです。
「真理は創造される」と述べることは、真理の生産はなんらかの素材を変容させる一連の操作と、文字どおりの歪曲をおこなう一連の作業とを経由するものだということを意味します。フェリックス・ガタリと私の共同作業を例にとるなら、私たちはたがいに相手を歪曲しあう偽作者になったといえる。つまり私たちのうちの一方が、相手の提案した概念を自己流に解釈しなおすのです。こうしてふたつの項をもつ反映系列が形成される。
真なるものを産むにいたる〈偽なるものの潜在力〉。それが媒介者なのです……。
左翼には媒介者が必要だ
説得することはそれほど重要ではなく、クリアな話し方をすることがもとめられるのです。クリアな話し方とは、状況のみならず問題自体の「与件」をつきつけるということです。別の条件のもとでは見えなかったものが見えるようにすること。
左派の役割は、政権を担当しようとそうでなかろうと、とにかく右派がなんとしても隠蔽しようとするタイプの問題をあらわにするところにあるわけです。
左派に必要なのは人びとにものを考えてもらうことらだからです。
模倣者たちの陰謀
「無名作家の不在には気づかない」
模倣者は模倣者同士で模倣しあっている。だからこそ模倣者はひろく世に受け入れられるし、お手本よりもうまいという印象を与えるのもそのせいなのです。
「いまの社会はあまりにも空虚な残忍性に毒された社会である。残忍性とは、他人の人格を侵害しに行くことだ」
「残忍性は幼児性のあらわれだ、と私は固く信じている。現代の芸術は日ましに幼児的なものになっていく」ロッセリーニ
カップルもこれまでだ
押さえつけようとする力は、人びとが考えを述べるのをさまたげるのではなく、逆に考えを述べることを強要する。いまもとめられているのは、言うべきことが何もないという喜び、そして何も言わずにすませる権利です。
いわゆる意味というものは、文をよびさます興味のことにほかならない。
植民地のオイディプス
ジャーナリストが文学を征服した。
本は、本以外のところでくりひろけられた活動や体験や意図や目的の報告にすぎなくなる。つまり本自体がただの記録になってしまうわけです。
こうして本は「副次化」され、マーケティングの様相を帯びてくる。
文学の死があるとしたら、それは虐殺によるものだ
文字文学と視聴覚表現のどちらかが選択されるというのではないのです。創造をおこなう力(これは視聴覚表現にも文学にも含まれている)と、家畜化を推進する権力のあいだで選択がおこなわれるのです。
創造の可能性はそれぞれの表現様態によって大きな違いをみせるとはいえ、市場と迎合の、つまり「市場向け生産」の文化空間の成立に一丸となって抵抗しなければならない点で、あらゆる創造の可能性はたがいに通じあう面をもっているのです。
テニス界のプロレタリア
スタイル(文体)とは、文学の概念で、シンタクスのことを指します。
ようするにスタイルとは新しいものだということを証明しているのではないかと思いますが……。
新しいスタイルは、新しい「離れ業」を意味するのではなく、姿勢の連鎖を意味しているのです。
エイズと世界戦略
エイズは、ストレスと自己免疫という二極の中間に位置づけられる。
戦争勃発の危険は、特定の外敵が侵略行為をおこす可能性から生まれるとはかぎらない、自国の防衛反応が暴走したり、崩壊したりする場合にも戦争がおこりうるというのです(だからこそ核戦力の抑制が重要な問題となる)。
創造とはいくつもの不可能事のあいだをぬってみずからの道を切り開くことだと考えなければならない……。
創造者とは、独自の不可能事をつくりだし、それと同時に可能性をつくりだす人のことです。
大地を離脱しようというのではありません。そうではなくて、大地のあり方を左右する液体や気体の法則をつくりだすことによって、なおさら大地に密着していこうというのです。ジャン・ルノワール
真理とは実際に生存を産み出すことです。真理は頭のなかにあるのではなく、現に存在するもののことなのです。作家は現実の肉体を送り出す。
作者のナルシシズムが醜悪なのは、影にはナルシシズムがありえないからです。
「オートル・ジュナル」第八号、一九八五年十月
聞き手ーーアントワーヌ・デュロール、クレール・パルネ
哲学について
ドゥルーズ
哲学は伝達をおこなうのではないし、静観的でも、反省的でもない。常に新たな概念を創造しつづける点で、哲学はその本性からして創造的だし、革命的なものになりうるのです。
概念には、概念以外にもふたつの次元が含まれている、つまり知覚対象と情動の次元が含まれていると思うからです。私の関心をひくのはこのことであって、イマージュそのものではないのです。知覚対象とは知覚のことではない。知覚を経験した人間が死んだ後も生き残る複数の感覚とその諸関連の束が知覚対象なのです(この場合、人間は以前とは別のものになる)。
生成変化を乱したくなければ、動きすぎないようにこころがけなければならないのです。
「放浪の民とは、動かない人たちのことである。旅立つことを拒むからこそ、彼らは放浪の民になるのだ」というのがそれです。
トインビー
難問を切り抜けるにはいかにして運動をおこしたらいいのか、いかにして壁を突き破るのかということが問題になるのです。難問を切り抜けるには動きすぎない、しゃべりすぎない、ということが必要なのではないか。つまり、誤った運動を避け、記憶が消えてしまった場所にじっとしているべきなのではないか。
空白ではなくて、定数外の流動的な追憶が過剰なまでに増殖し、それをどこに置き、どこに位置づけたらいいのかわからなくなる状態(そんなこともあったな。でも、あれはいつだったのだろう?)こうした追憶は、どうあつかったらいいのかわからない。余分の追憶だからです。
人間の生涯で面白いのは、いま説明したふたつの状態、つまり健忘症と記憶過剰なのです。
哲学における文体とは、概念の運動のことです。文体とは、国語にヴァリエーションを与えること、変化をもたらすことであり、また、言語全体がひとつの「外」に向けて傾斜した状態を指しています。
文章を書くのは生命を与えるためであり、生命が閉じ込められているところから生命を解き放ってやるため、そして逃走線を引くためなのです。そうするためには言語が等質の体系であってはならない。言語は、均衡を失ったものとして、絶えず不均質の状態に置かれていなければならない。文体は言語のなかに潜在力の差異をうがち、そうした差異と差異のあいだを何かが通過し、何かがおこりうる、そして言語自体から閃光が走り、語を取り囲む暗闇のなかにあった、それまでは存在すらほとんど気づかれることのなかった実体を、私たちに見させたり、考えたりさせるのです。
自分が個人であるのかどうか、私たちにはまったく確信がもてない。
意見のレベルでは、誰もが同じような話し方をするものだし、「私」を名乗って、自分はひとりの個人だと思い込む。
けれども、私たちは、そのことに確信がもてないし、個人というのはけっして的確な概念ではないはずです。
記号は生の様態や生存の可能性を表示している。
しかし、芸術家は、枯渇した生活に満足することも、個人的な生活に満足することもできない。自分の自我や自分の記憶や自分の病では文章は書けないからです。書くという行為のなかでは、生命に手を加えて、個人を超える何かに作りかえる、そして生命を閉じ込めるものから生命を解き放ってやろうという企てがある。芸術家や哲学者は、健康状態がすぐれなかったり、からだが弱かったり、均衡がとれていなかったりすることが多いでしょう?
創造とは、伝達することではなく、耐久力をもつことです。記号と〈事件〉と生命と生気論のあいだには、深い関係がある。
死んでいくのは有機体のほうであって、生命は死ぬことがない。
妄想は〈現実界〉のなかでその効力を発揮するものだし、私たちの目から見ても、現実界以外の要素は存在しなかった。だから、想像界も象徴界も、誤ったカテゴリーだと思ったのです。
「内在性」
ドゥルーズ
抽象によって説明されるものなど何ひとつ存在しないのであって、抽象のほうこそ説明されなければならないのです。普遍概念など存在しないし、外在的概念も存在しない、さらに「一なるもの」も、主体(そして客体)も、また理性も存在しない。あるのはプロセスだけです。そして、こうしたプロセスは具体的な「多様体」のなかで発動するのだから、何かが実際に生起する場となる真の環境は多様体なのです。内在性の場を満たしているのは、多数の多様体ですが、それは多数の部族が砂漠に住みついても砂漠は砂漠であることをやめないのと少し似てます。そして内在性の場とは、構成してつくりあげなければならないものであり、だからこそ内在性とは構成主義なのだし、局所決定できる多様体のひとつひとつが平面上の一圏域のようなものになる。あらゆるプロセスは内在性の平面上の、局所決定できる特定の多様体のなかで生まれます。統合、主体化、合理化、集中化なとはいかなる特権ももたない。
そして、実際に解釈がおこなわれるときは、かならず、欠如していると仮定されたものが引き合いに出されるのです。
とにかく超越性の視点を据えてみた場合に、内在性の平面の作成がさまたげられるとかならずあらわれてくるのが欠如の現象なのです。すべてのプロセスは生成変化であり、生成変化は、その結末となる成果によって評価されるのではなく、その流れの質とその持続の力に照らし合わせたうえで評価されます。
普遍概念など存在せず、あるのは個別性だけ。概念は普遍的なものではなく、ひとつひとつの個別性が、ほかの個別性の近隣にまで延びているような、個別性の集合なのです。
大地とは、脱領土化された大地であって、途方もない大地の運動と重なる脱領土化のプロセスから切り離すことができない。こうしたものが、たがいに相手を延長し合う個別性の集合であり、そのままで「リート」という〈事件〉を指し示すひとつの概念となっているのです。
いくつもの多様体がこの平面を満たし、個別性がつながりあい、プロセスあるいは生成変化が展開して、強度が高まったり、低くなったりするのです。
私は、哲学は多様体の論理であると考えています(この点にかんしては、自分はミシェル・セールに近いと感じますね)。概念を創造するとは、平面上にひとつの圏域をつくりあげること、すでに存在していた圏域にもうひとつ圏域をつけ加え、新しい圏域を探索し、欠如を埋めることなのです。概念とは、線や曲線をいくつも組み合わせ、統合したものです。概念が絶えず入れ替わらなければならないのは、ほかでもない内在性の平面が圏域ごとに構成され、少しずつ、局所的につくられているからなのです。
概念には、独自の潜在力としての反復というものがある。ひとつの圏域を別の圏域に接続するのが、この反復なのです。
ですから、内在性の平面はひとつしかないのに、すべての概念が局所的だという、あなたの印象は正しいことになります。
私にとって、反省のかわりにはなるのは構築作業です。そして伝達のかわりになるのは一種の表現主義です。
思考のイマージュとは、方法のことを指しているのではなくて、なにかもっと深いものがあって、それが常に前提としてある、つまり座標計とダイナミズムと方向決定の体系があるという意味です。
有無を言わせぬほど強力な制約に応じて、思考のイマージュは変容するのではないか?
概念の創造を導くのは思考のイマージュです。
イマージュの問題にあらわれているのは、モデルではないし、手引きですらなく、ひとつの指向対象、絶えずおこなうべき異種交配であり、それは具体的にいうと脳について知られていることと一致するのです。
フーコーの方法は、あらゆる普遍概念を破棄して、さまざまな多様体のなかに生起する、常に個別であることをやめないプロセスをあらわにしてくれます。
たとえ新たな知や権力を産むことになったとしても、とにかくつくりあけられた知や確立した権力の周辺部で、さまざまな個人や共同体が主体として成立するときの操作を指しているのです。
主体は、高揚の状態からも嘆きのなかからも生まれてくる。フーコーは、いま、私たちの現代社会で輪郭をあらわしてきた主体化の動きに魅惑されてきました。いま現に主体化をつくりだしているのは、どのような現代的プロセスなのかという問題。ですから、フーコーにおける主体への回帰が語られるのは、フーコーの提起する問題がまったく見えていないからです。
国家と人権は相互補完的なふたつの機能だといえるのです。
ノマドが私たちの関心を強くそそったわけは、ノマドはひとつの生成変化であり、歴史の一部分ではないからてす。
社会的領野は、あちこちで逃走の水漏れをおこしているのです。
パレスチナ難民は「反時代者」として中東にあり、領土の問題を最高度に高めています。非=権利国家で重要なのは、どうしてもノマド的にならざるをえない解放のプロセスの性質です。
襞を無限に増大させるのがバロックであり、エル・グレコの絵画やベルリーニの彫刻を見ればわかるように、知覚対象と情動による非=哲学的理解への道を開いていくれるのも、バロックなのです。
「マガジン・リテレール」第二五七号、一九八八年九月
聞き手ーーレーモン・ベルール、フランソワ・エヴァルト
ライプニッツについて
ドゥルーズ
類似だけが差異を示すという命題と、類似を示すのは差異たけだという命題は、はっきり区別して考えなければならないのです。一方では複数の事物相互間の類似が優先され、もう一方では個々の事物が差異をもち、まず自分自身との差異を示す。複数の直線はたがいに類似してますが、複数の襞は相違をあらわし、個々の襞も差異化する傾向にあるのです。
襞とは「差異生成の要因」であり、「微分=差異化」のことなのです。概念にはふたつの種類がある。つまり普遍相と個別相を区別しなければならないのです。襞の概念は常に個別的です。相違を示し、分岐をおこしながら変容していかなりかぎり、地歩を固めることができないのです。
つまり数千年の単位の時間は永続性ではなく、純粋状態の時間なのであり、その内実は柔軟性なのだということが明らかになるわけです。そして一見したところ不動だと思われたものがくりひろげる不断の運動ほど、強い当惑をまねくものはありません。ライプニッツなら、無数の微粒子が襞をなして舞っている、と表現するでしょうね。
ーーあなたの本が明らかにしているのは、襞の概念を磨きあげることにより、ライプニッツの哲学が哲学以外のさまざまな現実に接続され、それに照明を当てることができるのはどうしてか、そしてモナドが絵画作品と彫刻作品に、さらには建築や文学作品にもつながっているのはどうしてなのか、ということです。
ドゥルーズ
ひとつひとつの魂や主体(モナド)は完全に閉じられていて、そこには出口も窓もない。
こうして世界はひとつひとつの魂のなかに畳みこまれながらも、その襞は魂によって相違をみせる。襞の一部分に側面から光がさしているからです。
私は、バロック建築やバロックの「インテリア」、そしてバロック的光線がまさにそのとおりだということを明らかにしようとつとめているわけです。
事物が新しいかたちで折り畳まれる場合のあり方を考慮するならば、これは私たち現代人の状況にも当てはまる。
現代の社会生活では、窓と外部のシステムにかわって、閉じられた部屋と情報表のつながりが支配的になりつつある。つまり世界を見るとうよりも、世界を読むようになったわけです。あらゆる組成を巻き込んだ社会の「形態学」が成り立つばかりか、都市計画や国土開発のレベルにもバロックが作用をおよぼしているのです。建築はいつの時代でも一個の政治だったし、新しい建築はかならず革命的な力を必要とする。
「物質は組成である……」。この種の命題をどのように規定したらいいのでしょうか。
ドゥルーズーーいまでも数学や関数理論の特権的対象でありつづけているものに「変曲」があります。物質は種子からなるのではなく、先にいくほど小さくなる襞からなっているのだと述べるライプニッツの仮説には、粒子と力の物理学がひとつの意味を与えてくれます。
動物は一定数の刺激に反応したり、ほとんど反応しないこともあるけれども、刺激そのものは広大な自然の暗い底にさしてくるかすかな光となるということを証明しているのです。
ライプニッツ以前にも科学と芸術の世界では襞は知られていた。しかし、ライプニッツは襞を無限にまで高めることにより、襞を「解き放った」最初の思想家だということに変わりはありません。同様にして、バロックは、襞が無限に拡大し、あらゆる限界を超えるようになった最初の時代なのです。
「事件を定着させる」とき、メディアは何をつかんでいるのでしょうか。
ドゥルーズ
まず、メディアが最初と最後を見せるにたいして、〈事件〉のほうは、たとえ短時間のものでも、さらには瞬間的なものでも、かならず持続を示すという違いがあります。そしてメディアが派手なスペクタクルをもとめるのにたいして、〈事件〉のほうはロスタイムと不可分の関係にある。これは〈事件〉の前後にロスタイムがありということですらなくて、ロスタイムは〈事件〉そのもののなかにあるということなのです。
どんなにありふれた〈事件〉でも私たちを見者に変えるにたいして、メディアのほうは私たちを単に受動的なだけの見物人に変え、最悪の場合には私たちを覗き魔に変えてしまうのです。グレートフィゼンによると、あらゆる〈事件〉は、いわば何もおこらない時間のなかにある、ということになります。ところが、まったく予測のつかない〈事件〉にも気の遠くなるような待機が含まれているということは忘れがちです。〈事件〉をとらえることができるのは芸術であってメディアではない。たとえば映画は〈事件〉をとらえます。
述辞が〈事件〉であるならば、主辞(主体)は何であるべきか?バロックの銘文にもこれとよく似たものがありますよね。
私は点というものが好きになれないし、定点をさだめる(ポイントをおさえる)ことは愚劣だと考えています。ふたつの点のあいだに線があるのではなく、線が何本も交差したところに点があるわけですからね。線は規則的ではありえない。そして点は線の〈変曲〉であるにすぎないのです。だから重要なのは始まりと終わりではなく、〈あいだ〉の部分なのだということにもなる。事物の思考は〈あいだ〉に芽生え、そこで育っていくわけで、じっくり見据えなければならないものは、この〈あいだ〉にあるのだし、襞も〈あいだ〉にあらわれてくるのです。だからこそ、多線状の集合体は折り返しや交差や曲折をもちうるのだし、これがあればこそ哲学と哲学史、そして一般の歴史学、さらには科学と芸術が通じあうことになるわけです。
哲学は肉声による歌とは違う真の歌であり、哲学には音楽と同じような、運動をとらえる感覚がそなわっているということです。
ライプニッツによって哲学は和音の生産となった。
音楽に哲学をかぶせるのではなく、哲学に音楽をかぶせるのでもない。これはやはり折り畳みの操作だと考えたほうがいいでしょう。
ブーレーズがマラルメを相手におこなったように「襞にそって襞を」折り畳むことが必要なのです。
「リベラシオン」一九八八年九月ニ十二日
聞き手ーーロベール・マジオリ
レダ・ベンスマイアへの手紙(スピノザについて)
つまり、哲学には哲学的理解と同様、非=哲学的理解が必要なのです。
スピノザには、むしろ文体がないかに思われるのに、どうしてそのスピノザをとりあげるのか。じつをいうと、「文体がない」とされた書き手は要注意人物なのです。すでにプルーストが指摘しているように、「文体がない」書き手はすぐれた文筆家であることが多いからです。
ここまでは概念の見地から語ってきた、しかしこれから先は文体を変えて、直観と直接性にもとづく純粋な知覚対象によって語るだろう、と。
「未来」第五三号、一九八九年
V 政治
管理と生成変化
ドゥルーズーー私が興味をもっていたのは、代理=表象というよりも、むしろ集団による創造のほうでした。
実際に利用する人がいればこそ、法が政治に変容するわけですからね。
〈反時代的なもの〉の普遍性とは、いったい何のことを指しているのてしょうか。
ドゥルーズ
「非歴史の雲」がなければ重要なことは何ひとつ起こらない、と述べたのはニーチェでした。
歴史は実験ではない。歴史とは、歴史ではとらえきれないことを実験できるようにする、ほとんど否定的とすらいえる条件の総体であるにすぎないのです。
実験そのものは歴史に属する事柄ではないのです。
生成変化は歴史とは違う。
「生成変化」をとげるためには、つまり新しいものを創造するためには、こうした条件に背を向けなければならないのです。ニーチェが〈反時代的なもの〉と呼んだのはこのことにほかならない。
人間の唯一の可能性は革命的生成変化にある。
私たちの観点からすると、社会というものはその矛盾よりも、むしろ逃走線によって規定されるということ。
『千のプラトー』にはもうひとつ別の方向があります。それは、矛盾よりも逃走線を好んで検討するだけではなく、階級よりもマイノリティを検討の対象にするということです。それから第三の方向は「戦争機械」のあり方をさぐるというもの。
資本主義には普遍的なものがひとつしかありません。市場です。普遍的な国家が存在しないのは普遍的な市場が存在するからにほかならない。すべての国家はこうした市場が集中する焦点であり、その証券取引所があるにすぎないのです。そして市場とは、普遍化や均質化をおこなうものではなく、富と貧困を産み出す途方もない工房なのです。
集団がどのように変質し、どのようにして歴史にのみこまれてしまうのか、という問題が、不断の「気づかい」を強いてくるのです。
従来はプロレタリアが自覚をもちさえすればよかった。しかしいまの私たちには、そんなプロレタリア像は無縁なものとなってしまいました。
マイノリティのほうがマジョリティより数が多いこともありうるからです。マジョリティを規定するのは適合を強いてくるモデルです。
マイノリティにはモデルがない。マイノリティは生成変化であり、プロセスであるわけですからね。マジョリティに該当する人はひとりもいないということもありうるでしょう。
こうしたマイナー性とメジャー性が共存しうるのは、両者が同一平面上で生きられるのてはないからです。
芸術とは抵抗するもののことです。死に抵抗し、束縛にも、汚名や恥辱にも抵抗するのです。
ユートピアというのは適切な概念ではありません。むしろ人民と芸術の双方に共通した「仮構作用」があるべきだと考えるてしょう。
いまでもなお、コミュニズムは成り立つのでしょうか。コミュニケーション社会が到来したいま、コミュニズムは従来ほどユートピア的ではなくなったのかもしれません。
ドゥルーズ
フーコーは、規律社会とは私たちがそこから脱却しようとしている社会であり、規律社会はもはや私たちとは無縁だということを述べた先駆者のひとりなのです。私たちは管理社会に足を踏み入れている。管理社会は監禁によって機能するのではなく、不断の管理と瞬時に成り立つコミュニケーションによって動かされている。
学校改革を推進するかに見せかけながら、実際には学校制度の解体が進んでいるのです。
機械をほんの一部分として取り込んだ集合的アレンジメントを分析しなければならないのです。
重要になってくるのは、管理をのがれるための非=コミュニケーションの空洞や断続器をつくりあげることだろうと思います。
主体化のプロセスにはたしかに反抗の自発性があるのです。そこにはいわゆる「主体」への回帰などありはしないのです。つまり義務と権力と知をそなえた審級が回帰することはありえないのです。
〈内〉と〈外〉のはざまに展開する可逆的で恒常的な運動のリミットをなし、〈内〉と〈外〉をへだてる膜となるのが、ほかならぬ脳だからです。
主体化も〈事件〉も脳も、私にはどうも同じものだと思えてならない。世界の存在を信じることが、じつは私たちにいちばん欠けていることなのです。私たちは完全に世界を見失ってしまった。
世界の存在を信じるとは、小さなものでいいから、とにかく管理の手を逃れる〈事件〉をひきおこしたり、あるいは面積や体積が小さくてもかまわないから、とにかく新しい時空間を発生させたりすることでもある。
抵抗する能力はどれだけのものか、あるいは逆に管理への服従はどのようなものなのかということは、具体的にこころみのレベルで判断される。人民〈と〉大衆が同時に必要なのです。
「前未来」創刊号、一九九八〇年春
聞き手ーートニ・ネグリ
追伸ーー管理社会について
Ⅰ. 沿革
規律社会のモデルは、目的と機能がまったく違った(つまり生産を組織化するというよりも生産の一部を徴収し、生を管理するというよりも死の決定をくだす)君主制社会の後を受けたものである。
こうして規律社会にとってかわろうとしているのが管理社会にほかならないのである。
Ⅱ. 論理
工場というものは、みずからの内的諸力を平衡点にいたらせ、生産の水準を最高に、しかし給与の水準は最低にとどめる組織体だった。ところが管理社会になると、今度は企業が工場にとってかわる。
企業も教育も奉仕活動も、すべて同じひとつの変動が示す準安定の共存状態であり、変動そのものは普遍的な歪曲装置としてはたらくからである。
規律社会にはふたつの極がある。ひとつは個人を表示する署名であり、もうひとつは群れにおける個人の位置を表示する数や登録番号である。つまり規律にとっては、個人と群れのあいだには両立不可能性などありはしなかったし、権力は、群れの形成と個人の形成を同時におこなっていたのだった。ようするに権力は、権力行使の対象となる人びとを組織体にまとめあげ、組織体に所属する各成員の個別性を型にはめるのである。
規律型人間がエネルギーを作り出す非連続の生産者だったのにたいし、管理型人間は波状運動をする傾向が強く、軌道を描き、連続性の束の上に身を置いている。
それぞれの社会に機械のタイプを対応させることは容易だ。しかしそれは機械が決定権をにぎっているというからではなく、機械を産み出し、機械を使う能力をそなえた社会形態を表現するのが機械であるからにすぎない。
現在の資本主義は過剰生産の資本主義である。
いまの資本主義が売ろうとしているのはサービスであり、買おうとしているのは株式なのだ。これはもはや生産をめざす資本主義ではなく、製品を、つまり販売や市場をめざす資本主義なのである。
人間は監禁される人間であることをやめ、借金を背負う人間となった。しかし資本主義が、人類の四分の三は極度の貧困にあるという状態を、みずからの常数として保存しておいたというのも、やはり事実なのである。
管理が直面せざるをえない問題は、境界線の消散ばかりではない。スラム街のゲットーの人口爆発もまた、切迫した問題なのである。
Ⅲ. プログラム
学校の体制では、さまざまな平常点の形態と、生涯教育の学校への影響が表面化し、これと見合うかたちで大学では研究が放棄され、あらゆる就学段階に「企業」が入り込んでくる。
これは俗にいわれるような個性尊重への接近をあらわしているのではなく、分割不可能な、あるいは数値的身体に、管理の対象となる「可分性」の素材を置きかえているにすぎないのだ。企業の体制では、古い工場の形態とは縁を切った、金銭と製品と人間にたいする新たな取りあつかいがあらわれる。
もっとも重要な問題のひとつは労働組合の無能性にかかわるものである。
「オートル・ジュルナル」創刊号、一九九〇年五月
訳者あとがき
対話とは、一個独立した人格としてあるふたりの人間が起点となって見解のやりとりがおこなわれることではなく、両者の「あいだ」で、おのおのが自分以外のものになる生成変化によって成り立つ。
公共の場にありながらも、公共ならざるものでありつづけるための戦略と言えばいいだろうか。
本書の原題は《Pourparlers》、直訳すれば『均衡』である。「均衡」という語の意味するところは、ドゥルーズ自身の序文で述べているとおり、ある力が外部から侵入してきたとき、その力を内側に折り曲げ、自己との戦いをくりひろげるということだ。したがって、外部の力として把握されたメディアへの対応を実践してみせる本書のタイトルは、素直に『均衡』と訳すべきだったのかもしれない。
一九九二年三月
宮林 寛
『記号と事件1972-1990年の対話』ジル・ドゥルーズ/著、宮林 寛/訳より引用、抜粋。