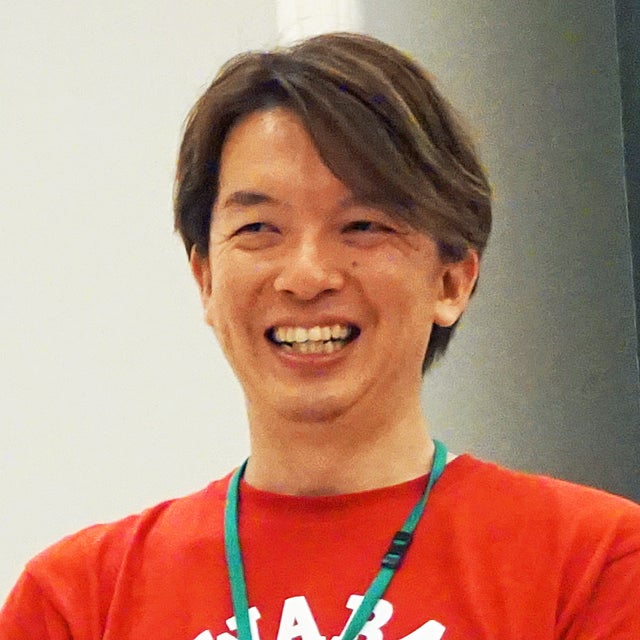「ニッポン城めぐり」運営ブログ
全国3,000城をめぐる位置情報(GPS)スタンプラリーアプリ「ニッポン城めぐり」公式ブログ。開発裏話や城の話などアプリをより楽しめる情報を発信中!
プロフィール
テーマ
最新の記事
カレンダー
月別
ブックマーク
攻城の種類(兵糧攻め/乾渇攻め)
テーマ:城と歴史の話自分が小学生だったころ、確か1学年6クラスくらいあったと思うので、40人×6クラス×6学年=約1500人ほど生徒がいたことになります。給食の時間には廊下や教室がてんやわんやしていた記憶がありますが、いくら子供とはいえ、1日の食糧消費量![]() はたいへんなもんです。
はたいへんなもんです。
これを籠城戦にあてはめるとその大変さがわかります。保存技術も未発達な時代、毎日肉体労働する大人が何千人も籠もる城の食糧消費量は想像を絶します。よって、「籠城できる期間」というのはおのずから限られてきます。
その弱みにつけ込むのが「兵糧攻め/乾渇(かつえ)攻め」です。これは文字通り、城の周りに付城 を築くなどして厳重に包囲し、水食糧が尽きるのをひたすら待つ作戦です。
軍の構成が半士半農だった頃、城を囲むにしても農繁期にはそそくさと引き揚げなければならなかったものが、兵農分離が進んで包囲する側が長期間戦争に従事できる時代になると、兵の損耗が少ない「兵糧攻め」が増加していきます。
特に豊臣秀吉はそのスペシャリストであることは良く知られていますが、播磨三木城 、因幡鳥取城 はその代表例ですね。秀吉の言葉を借りれば、「三木の干殺し、鳥取の渇殺し、太刀も刀もいらず」だそうです(余裕のコメント(ノ゚ο゚)ノ)。
「兵糧攻め」の場合、城主が切腹して城兵は助けられる、というケースが一般的で、多少の餓死者は出るものの、圧倒的に戦死者が少ないのが特徴です。なので、ある意味すごく平和的![]() とも言えます。
とも言えます。
「乾渇攻め」についても「兵糧攻め」とほぼ同じプロセスをたどり、以前ブログで取り上げた白米伝説 のようなつよがり伝説も生まれてくるのですが、「兵糧攻め」と違うのは、“補充される可能性がある”点です。
米は外部からの援助がないと増えませんが、水は雨が降れば一時的にしのげるのと、枯れない井戸やわき水などの水源があれば、ほぼ無限に補充可能なのです。
そんなこともあって、「乾渇攻め」をしてもまったく効果があがらなかった、という事例もしばしば見受けられます。「兵糧攻め/乾渇攻め」されたら最後、籠城する方は降伏あるのみと思いきや、実際そうとも言えないようです。
とはいえ、そんな水源すら破壊してしまう攻城法もあるので、それについてはまた次回取り上げることとしましょう![]()