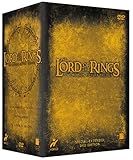アンリ・ル・シダネル展
で見た「閉じられた鎧戸〔ジェルブロワ〕」(1932年)という作品。
鎧戸からうっすら灯りの漏れる窓の様子が描かれているのですけれど、
我ながら誠に唐突だなとは思いつつも「こりゃ、サウロンの目のようだな…」と思ったのですね。
だいたいサウロンと聞いてぴんと来る方がどれほどおいでかとも思いますが、
トールキンの「指輪物語」、というより視覚的なことを言ってますから
映画「ロード・オブ・ザ・リング」に出てくるダークサイドの王の名前でありまして、
中つ国(middle earth)の一角に位置するモルドールという、
常に暗雲垂れ込めた王国に立つ高い塔の上でサーチライトのように光る目だけの存在、
それがサウロンでありますね。
ル・シダネルには申し訳ないながら、思い出してしまったものはしょうがない。
そこで改めて映画「ロード・オブ・ザ・リング」を見てみることにしたという。
DVDのSpecial extended editionという代物で、「旅の仲間」208分、「二つの塔」223分、
「王の帰還」250分とただでさえ長いのに全3部作で681分(つうことは11時間21分)にもなるという長尺。
もうおなか一杯というくらいですが、これを一気見で見てしまいましたですよ。
ところで全編を見終えてふと思いましたのは、邪悪なパワーを持った「指輪」の処分が
なぜフロド・バギンズ(イライジャ・ウッド)に託されることになってしまったのかということなんですね。
ここで誠に勝手な思いつきをつらつら記していきますけれど、
この物語がお好きな方には「何と異端な!」と思えるものかもしれませんのでご注意を。
といいつつ、広くそう考えられているのを知らないだけなのかもではありますが…。
魔法使いのガンダルフ(イアン・マッケラン)の呼びかけで、
指輪がサウロンの手に渡ることを恐れるエルフ、ドワーフ、人間といった各種族の代表が集まります。
そこで誰に指輪を葬り去る役を委ねるかということになりますが、
結局のところガンダルフはホビットという小人族の若者フロドに託すことにするわけですね。
これは、ホビットがおよそ戦闘力のない平和なのんびりした種族であるのに対して、
それ以外の種族の場合にはどの種族であっても
指輪のパワーを利用して中つ国の覇権を握ろうとするような行動に出てしまうかわからない、
そうなれば中つ国全体が暗雲に閉ざされてしまう、そうした可能性があるからでしょう。
では、フロドが指輪の邪悪さに負けて、指輪を我が物としてしまう可能性は考えられなかったでしょうか。
指輪をモルドールの火山に投げ込んで葬り去るという旅の途中で、幾度も幾度もフロドは
指輪の誘惑に負けそうになりますね。
最後の最後になっても危うい状態が続くわけですが、
これを何とか振り払って、時には相棒のサムの手を借りながら克服して…
とまあ、この辺りがビルドゥングス・ロマン的な感動に繋がるのかもしれません。
が、とりわけフロドができた人物かといえば他の登場人物に比べれば、
子供も同然(ホビットだからというばかりでなく)。
そこで考えが及んでしまうのは、ガンダルフとしては
指輪の魔力に負けてしまってもいちばん世の中に害のない人物を選んだとしか
言いようがないわけですね。
つまり、フロドが指輪の処分に最適の人物であったわけではなく、
他に任せる者がいないからというネガティヴ・チョイスに他ならない。
まあ、ここまではもしかしたらどなたのご意見とも一致するところかもしれません。
では、ネガティヴ・チョイスであるにしても、
安心してフロドの旅を見ていられるかというとそんなことはないわけで、
ガンダルフには、ホビットには組織的軍事力もなく、たとえ指輪を我が物としてしまったとしても、
ぜいぜい元の保有者である伯父ビルボのように隠し持つか、
悪くしても執着のあまりゴラムという醜い姿になってしまった
スメアゴルのようになってしまうかというくらいなものという考えがあったのではないかと。
スメアゴルも元々はホビットだったわけで、持ってる間指輪を偏愛するものの
それを使って世界制覇をもくろむようなことはなかった。
つまり、指輪の魔力に負けても世界を大きく騒がせる可能性が少ないのはホビットに預けること、
それがこの場合はフロドに託すということになったわけですね。
ガンダルフとしては、大なる犠牲(中つ国の混乱)を免れるために
小なる犠牲(フロドの危険)は止むを得ないと考えていたのではないかと。
さらにいういと、ガンダルフはフロドの旅が本当はうまくいかないことも想定して
布石を打っていたのではないかとも思えるのですが、
それが再三再四現れれるゴラムなのではと思ったり。
塔から落ちても、地下洞窟で落ちても結局無事であったガンダルフなればこそ、
断崖絶壁から落下してよもやもう現れまいと思われたゴラムを再登場させるくらいなことは
お茶の子であったわけですね。
ちと都合よ過ぎの解釈かもですが、
本当に最後の最後でゴラムが現れなかったら指輪は葬れなかったとも言えますし。
最終的には指輪が葬れればベストですけれど、
そうでなくともフロドかゴラムが隠し持ってしまうならそれも次善ということですね。
ただ、そうであるなら最初からゴラムに指輪を与えてしまえばそれでお終いではないかとも言えますが、
それではゴラムを指輪が持っていることを知る機会のある者が多々生じてしまい、
指輪を追ってゴラムを探す輩が現れないとも限らない。
指輪が葬られないとするなら、最終局面でもって誰の手に渡ったのか分からないまま、
指輪共々姿を隠してしまうということになる必要がありますね。
最初は「旅の仲間」と威勢よく出掛けた一隊は、やがてフロドとサムだけの行動に移りますけれど、
後になってフロドが一人で旅を続けたものと思ったガンダルフが、
サムも一緒であると知ったときの微妙な表情をご記憶の方もおいでかと。
その後ガンダルフはひと言「サムも一緒。それなら安心」みたいなことを言いますが、
ガンダルフにとっては思惑違いだったろうなあと見えましたですねえ。
…とまあ、物語全てに敷衍された点で合理的な考えになっていたかどうかはともかく、
こうも考えられるかなと思ったまでということはありますよ。