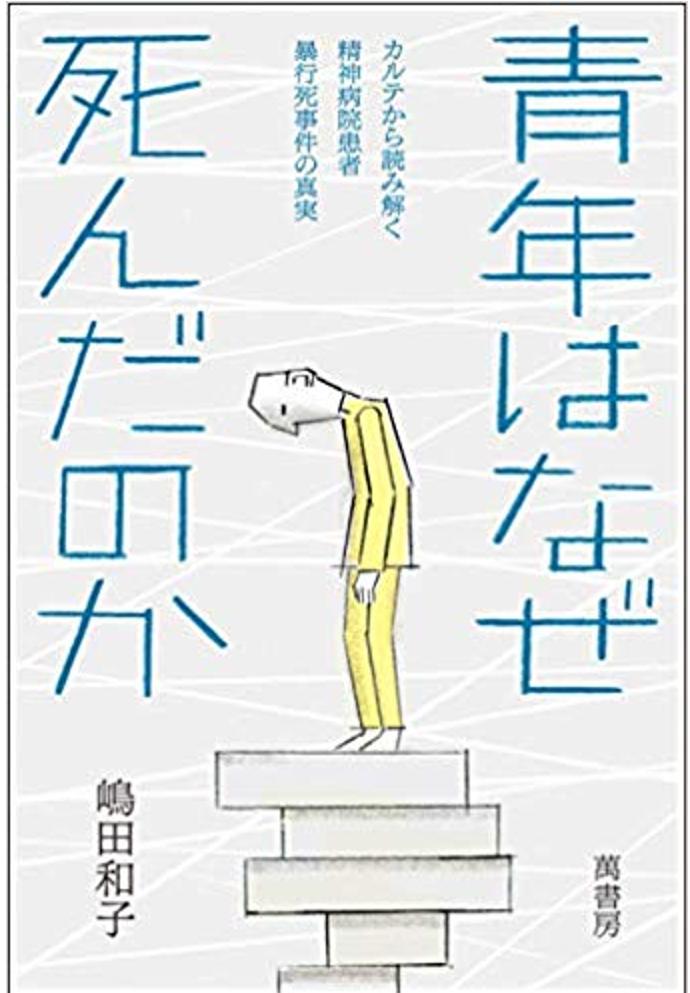チョロちゃんが小学3年生になった時に特別支援学級の担任が男の先生に変わりました。
地元の小学校では交流学級の担任は毎年変わりますが、特別支援学級の先生はあまり変わることがないと思っていました。
新しい特別支援学級の先生は2年生の時に交流学級の担任の先生だった人で、穏やかな先生でした。
絵がとっても上手で二年生の時に子ども達の似顔絵をそれぞれの自由帳に書いてくれたりしていました。
3、4年生(中学年)は一般的にギャング世代と言われる学年だそうで、丁度「9歳の壁」の時期でもあります。
この頃のチョロちゃんは未だ食べられないものがたくさんあって野菜が好きではありませんでした。
それで、担任の先生が土いじり~初めは汚い(汚れる)と言って消極的な参加でしたが~ということで、野菜を作ることに挑戦させてくれて、土を耕したり植えたりしていました。
校長先生が池をキレイにしたい。ということで、自らどぶさらいのようなことまでして池の水も入れ替えたりした時も、チョロちゃんにお声がかかって一緒に作業をしていました。
…とはいえ、勉強(学習)の方も確りとしてくれました。
理数系が好きなチョロちゃんに合わせて色々な実験をさせてくれたり、工作や将棋等も教えてくれて楽しみながら勉強ができました。
落ち着きがなかったり、多動が酷かったりというのはだいぶ落ち着いてきていましたが、人から攻撃されると我慢することができなかったし、衝動性は未だありました。
年に一度、医師の診察(と言っても名前だけの様子伺いと顔合わせ)を受けていましたが、毎回薬の話をされました。
わたしは子どもに「向精神薬」を飲ませない。
と宣言していたのですが一応聞くことになっている。
という事でした。
担任の先生が変わったことは結果的にチョロちゃんにとってはよいことだったと思います。
当時、自閉症の子どもは変化に弱い(対応がし難い)と言われていたので、できるだけ変化のない生活を…と言われていましたが幼児期はともかく、この頃のチョロちゃん自身はそこまで拘ることもなく、特に崩れることもなく過ごしていました![]()
元々、薬を飲ませて何とかするという事にずっと違和感もあり、まして「脳に作用する薬」なんて怖くて飲ませられません。
色々な人を見ていて感じたのは、周りの専門家(?)の意見ばかりを聞き入れて神経質になってしまうとそれが子どもにも伝わって返ってよくないのではないかなぁ~ということ。
わたしは結構アバウトでじゃじゃ馬で猪突猛進型でADHDの傾向のある子どもだったですが、今でも多少はそういうところがあって割とスパッと決断したり切り替えたりします。
チョロちゃんが小さい頃(小学中学年位まで)はよく参加していた研修会・勉強会・相談会では薬の話も出ていましたし、それを何とも思わずに飲ませている方もいたのですが、わたしは全く関わりませんでした。
後にこのブログがきっかけで知り合ったお母さんが教えてくれた「かこさんのブログ 」
こういう事を本当にわかって飲ませている親が一体どれほどいるでしょう?
コロナ禍でわかった(わたしにとっては再確認した)事は、医師は本当の事を言わないし、実際にコロナそのものやワクチンについて本当に理解している人はとっても少ないという事でした。
実際にわたし自身がワクチンを打たない理由の一つに基礎疾患(過去にリウマチ予備軍と診断されあちこちが腫れていた)があり、免疫系の疾患がある人には特にこのワクチンは避けるべきものだという事がわかっていましたが、ある内科医は「新型コロナワクチンはmRNAワクチンでこれまでのものとは違うので、基礎疾患がある人にとってむしろ安全」だと言い切りました。
mRNAワクチンが安全?
もう突っ込みどころが多過ぎて何も言いませんでした。←本気で言っていたので。
向精神薬に関してもかなりいい加減な処方だと思っています。
何十年もその処方箋を書いている医師が本当の怖さを知らない訳がなく、その場凌ぎで〜授業に集中できる、落ち着いていられる〜飲ませて取り敢えず勉強ができるようにして落ち着いたら減薬する。という流れの様でした。
当然の事乍ら、薬に頼らなくても成長と共に落ち着いてくるし、身体を使って親子でアレコレこれしたら治る所も出てきます。
その時その時の必要に応じて子ども自身がする事を邪魔しないで後方支援、援護射撃よろしくしっかり見守り困った時に支える。という立ち位置でいれば子どもは安心して自由に伸び伸び育っていきます。
誰かの意見。
ではなく子ども自身の育つ力を信じて。
当時はもう暫くアレコレが続きますが、それも通過点でしかないのだとわかっていれば何とかなってしまうものです。
元々ズボラでいい加減な所があるのでそれも良い方に作用したと思います。
肩の力を抜いて今日も楽しく過ごしましょう![]()
凸凹発達の子育てを頑張っているお母さんへ
新しい一日が始まりました![]()
今日も一緒に子育てを楽しみましょう![]()