白州正子さんや多くの文人も
鮎の解禁を待ちわびたという
創業400年「京都平野屋」さんが有名です。


武者小路千家三代の画
一番左が八歳の頃の若宗匠
千宗屋さんの仏画です。
私も茶事で一度
ご一緒させて頂きましたが、
待合から本席の趣向の
読み取り方はほんまにエグい。
まぁ八歳から神童ですわ。
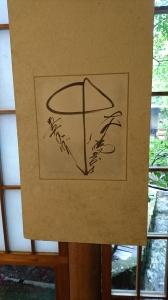
大川橋蔵さん、美空ひばりさん
もともと平野屋さんは
京都火伏の神として知られている愛宕神社の門前町、嵯峨鳥居本にある鮎問屋として
始まりました。
この世木の鮎は世木村、現在の日吉町で
6月1日から9月30日まで、夏のかせぎとして
漁が行われておりました。
投網で一網打尽が早そうですが、
傷がつきますから、ヒッカケ漁や
友釣りなどが主流のようです。
鮎を獲るアユトリさんから、
鮎を運ぶアユモチさんに
引き継いで、

平野屋女将 井上典子さん

中には炭を塗り込め暗くする工夫を
計50~70匹を入れ計27kmを
7時間山道をアユモチ桶に鮎を入れて、
鮎が心地よい様に揺らしながら
鮎を運んだそうです。

平野屋鮎の生簀
貴重な鮎を運ぶのに
かなり熟練を要したようです。
途中2~3Kmごとに新鮮な冷たい水を
鮎桶に補給しながら
慎重に慎重を期して運んだそうです。
そして一日置かれて、
鮎のストレスを取ってから
祇園祭で賑わう
祇園や先斗町の高級料理屋さんで
旬の鮎料理が振舞われたという事です。

平野屋鮎

茶店の菓子「志んこ」も有名。
抹茶、白、ニッキ
茶の湯と同じように、京都に育まれた鮎文化。
茶席に登場する鮎を見かけたときには
ぜひこんな鮎の流れを思い出してみると
さらに楽しくなると思います。
夏の京都に行かれたら
平野屋さんに寄って白州さんを
想うのも乙ですわ。

