
経済史の始まりはアダム・スミス。不況のときこそ、自由と資本主義の大切さを見直そう!
http://ameblo.jp/channelcrara/entry-11805740787.html
この後の世界の経済学の流れを大根切りにしてみます

アダム・スミスの後は・・いわゆる古典派経済学
ジャン・バティスト・セイ(1767~1832・フランス)
「供給はそれ自身の需要を創出する。」セイの法則
その後、第1次大戦を経て、1930年代は大不況の時代に
1929年に始まった世界大恐慌後、世界中の工業国が長く深刻な不況に悩まされていました。
1929.10.24「暗黒の木曜日」
ニューヨーク ウオール街の群衆
ケインジアン登場(ケインズの考え方を継ぐ経済学者)
「資本主義経済は市場メカニズムにまかせた場合に総需要が不足することがあり、放っておくと、大量の失業が出たままになってしまう」と説いたのがイギリスのジョン・メイナード・ケインズでした。
人々の貨幣に対する過大な需要が失業の原因とも
「人々が月を欲するために失業が発生する」
ジョン・メイナード・ケインズ(1883~1946・イギリス)
ケインジアンの「大きな政府」へ
その後、第2次大戦を経て、アメリカ始め西側諸国ではケインジアンが経済学の中心となり未曾有の経済成長を遂げるのです。
日本のケインズ政策は
政府が道路やダム、港湾、コンビナートを造る「公共事業」で経済を活性化させるインフラストラクチャーの整備
北欧や西欧では
福祉の充実の為に政府支出を増やす「福祉型」
アメリカ
多様な財政政策のなかで
特に目立ったのは世界中に軍隊を展開して最新鋭の兵器を投入する「軍事型」
★建設資材や人材が不足していると言われる中日本も防衛支出を増やすケインズ政策を取ることもできますね。
田中秀臣先生ブログ■[経済]財政政策ならば防衛支出を増やす方が望ましいのではないか?(田中秀臣、飯田泰之、原田泰諸氏の主張再考)

引用:『不況は人災です!』(松尾匡・筑摩書房)
読みやすくお薦めです
その後、第2次大戦を経て、アメリカ始め西側諸国ではケインジアンが経済学の中心となり未曾有の経済成長を遂げるのです。
日本のケインズ政策は
政府が道路やダム、港湾、コンビナートを造る「公共事業」で経済を活性化させるインフラストラクチャーの整備
北欧や西欧では
福祉の充実の為に政府支出を増やす「福祉型」
アメリカ
多様な財政政策のなかで
特に目立ったのは世界中に軍隊を展開して最新鋭の兵器を投入する「軍事型」
★建設資材や人材が不足していると言われる中日本も防衛支出を増やすケインズ政策を取ることもできますね。
田中秀臣先生ブログ
■[経済]財政政策ならば防衛支出を増やす方が望ましいのではないか?(田中秀臣、飯田泰之、原田泰諸氏の主張再考)
http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20130104#p4
ミルトン・フリードマン(1912~2006・アメリカ)
⇒ともに当てはまらない事態に直面したのです不況対策としての需要拡大政策も万能ではない
人々の意表をついてやったらしばらくは効果があるかもしれないが、人々がその結果として生じるインフレを想定するようになってしまえば効果がなくなる。
規制緩和をして技術革新を進め、供給能力を高めよう
再び「小さな政府」へ
アメリカのレーガン大統領、イギリスのサッチャー首相、日本の中曽根首相などが規制緩和や民営化、財政削減などを進めました。
新しいケインズ理論の登場
1990年代以降の日本の平成長期不況で、世界は戦後初めてデフレの時代を経験しました。
価格や賃金が下がらないから均衡しないとするケインズ主義も
市場に任せれば価格や賃金も下がり均衡するという新しい古典派も
人々の意表をついてやったらしばらくは効果があるかもしれないが、人々がその結果として生じるインフレを想定するようになってしまえば効果がなくなる。
規制緩和をして技術革新を進め、供給能力を高めよう
再び「小さな政府」へ
アメリカのレーガン大統領、イギリスのサッチャー首相、日本の中曽根首相などが規制緩和や民営化、財政削減などを進めました。
新しいケインズ理論の登場
1990年代以降の日本の平成長期不況で、世界は戦後初めてデフレの時代を経験しました。
価格や賃金が下がらないから均衡しないとするケインズ主義も
市場に任せれば価格や賃金も下がり均衡するという新しい古典派も

引用:『不況は人災です!』(松尾匡・筑摩書房)
読みやすくお薦めです

- 不況は人災です! みんなで元気になる経済学・入門(双書Zero)/筑摩書房
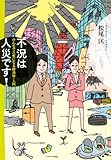
- ¥1,728
- Amazon.co.jp
経済学はその時の状況に応じて、過去の学問・研究を踏襲しながらも、時には大きく変化をし続けているのですね。
続きは
 へ・・・
へ・・・■誰でもわかる経済学~田中秀臣~【チャンネルくらら】再生リスト
「フリードマンって悪い人なの?」「似非ケインジアンに続く」
ちょっと難しい経済学が動画で分かるシリーズ、お薦めです

今日の動画はコチラ
■じょねらじ(確)平成26年4月号 第4回 上念司 倉山満 桜林美佐【チャンネルくらら】
★チャンネルくららは皆さまのサポーター寄付のみで運営しております。1口千円から、今月のサポーター特典をご購入頂けます

今月の特典は、「倉山・上念・桜林」3人でちょっとメディアリテラシーを語る動画です。





