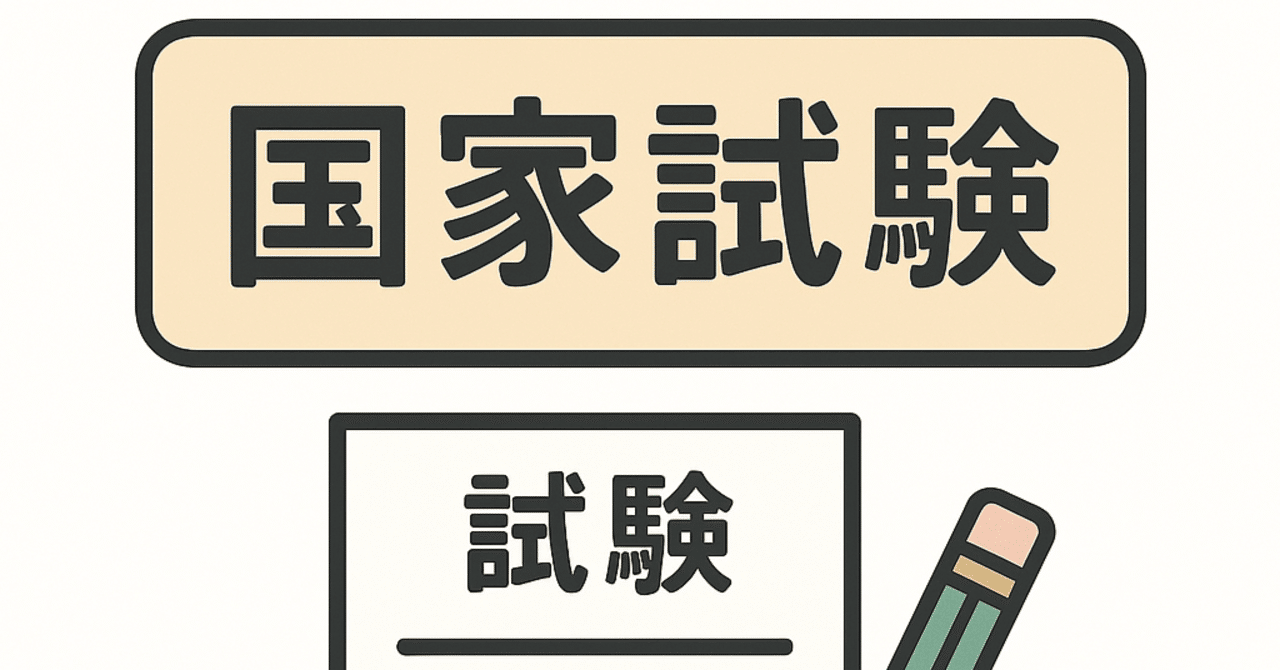皆さん、「俯瞰(ふかん)」という言葉をご存じですか?
意味は 「高い位置から見下ろすように、物事全体を広く見渡すこと」 です。
仕事で全体を見渡す視点、つまり俯瞰することを意識できていますか?
これは経営者、中間管理職、ベテラン、新人…すべての立場に欠かせないスキルです。
目的を忘れていませんか?
日々の経営課題や業務トラブルに追われていると、本来の目的を忘れてしまいがちです。
その場の問題は解決できても、全体を俯瞰せずに対処すると、別の問題が次々と発生し、気づけば日々に疲弊してしまう…。
先日お伝えした「プロジェクトマネジメント」ともつながりますが、俯瞰スキルを持って全体を見ながら仕事を進めることが、結局は成果につながるのです。
ケース:商社の物流トラブル
例として、商社で車部品を顧客に納入する場面を考えてみましょう。
物流トラブルが発生し、新たにトラックをチャーターして追加費用を支払い、顧客納期を守らなければならなくなったケースです。
コロナ禍以降、ドライバー不足で実際によく起きている問題です。
中堅社員のよくある対応
-
追加費用を払う判断ができない
-
上司に相談したいが連絡がつかない
-
夕方ようやく指示を仰いだが、手配が遅れてチャーター便は明後日になる
-
結果、納期遅延で顧客に迷惑 → 始末書を書くことに
費用もかかり、信用も失い、ダブルパンチ…。これは実際に多くの企業で起きている現実です。
俯瞰的に考えれば?
そもそもの目的は「部品販売で利益を上げ、顧客と長期的な信頼関係を築くこと」ですよね。
であれば、この場合は 追加費用を払ってでも納期を守る のが王道です。
そのために普段から俯瞰し、上司と「利益が出る範囲なら追加費用は自分で判断して良い」といった 権限移譲を取り決めておく ことが重要です。
正社員はアルバイトではありません。給与をいただいている以上、自分で判断し、リスクを取る覚悟が必要です。
まとめ
今回のケースは中堅社員や新人にありがちな例でした。
次回以降は、経営者や管理職がどう俯瞰するべきかも掘り下げていきますね。
本日もお読みいただきありがとうございました!